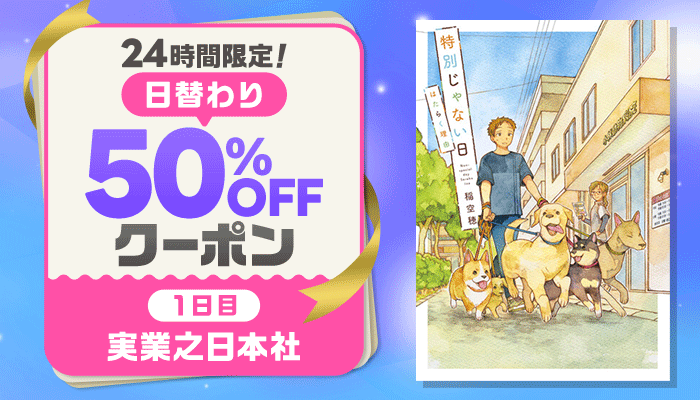インドのイロハ(特に政経)が一気に分かる1冊です。
2023/10/30 21:22
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:広島の中日ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイトルで『インド』と言い切っている通り、インドという国の基礎・イロハが当書を読めば一気に分かります。
中でも、インドの政治経済について詳しく著されています。紙幅が比較的厚いですが、読みやすい文章で書かれているので、短時間で読み切れます。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
これからのインドの発展について、興味深く読むことができました。グローバルサウスの代表としての位置が、わかりました。
ゆくゆくは世界1位の経済大国に?
2024/06/05 13:36
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
カースト制度という仕組みから成り立ってるように思えるインド社会を、経済面、とくにIT産業の強さの理由という面から、そしてアメリカ、中国といった大国との外交の面から解説してくれる本
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ニッキー - この投稿者のレビュー一覧を見る
特に最近は、人口や国際的発言力など、インドの存在感が増してきました。相違現在のインドを知るのに最適なコンパクトな一冊です。
投稿元:
レビューを見る
人口世界一、GDPは世界第5位。新興国のリーダーとも見られるインドの政治、経済、ビジネス、社会、外交戦略をわかりやすく解説。
投稿元:
レビューを見る
インド―グローバル・サウスの超大国 (中公新書 2770)
インドの1 人当たりの所得はいまだに年2200ドル(28万6000 円。1ドル130 円として計算、以下同) 程度で世界139位にすぎず、貧困と格差問題は深刻である。経済成長の反面、地域間、男女間、カースト間、宗教間で格差が縮小せず、大気や水質の汚染も深刻である。インドの農村を実際に訪れてみれば庶民の苦しい生活折情は容易に見てとれる。
そもそも多様性に富んだインドという国を「インドとはこのような国だ」という断定的な表現で表すこと自体、無理である。インドは地方によって政治も経済も文化も大きく異なる。また一口に「インド人」といっても、宗教、言語、出身地、カーストなどによって大きく異なる。
インドの多様性は、インドを流れる時間についても言える。敵千年の歴史とともに「悠久の国」と言われるインドでは、「変わらないインド」と「変わるインド」が况在しており、この国には様々な「時」が流れている。インドの農村を訪間した人の多くは、彼らの生活が依然として変わっていないことを感じるであろう。同様に、数千年の歴史を持つインドのカースト制度が、わずか30年ばかりの経済成長とともになくなるわけでもない。実際、欧米や日本での極端な報道を、多くのインド人やインドに永く住んでいる日本人は、冷やかな目で見ている。
第1章 多様性のインド— 世界最大の民主主義国家
インドでは、広大な国土に、異なる言語を活し、異なる宗教を信じ、異なるカーストに属する14億人の国民が、お互いを離重しながら、一つの国に暮らしている。
インド人は、「出身地、言語、宗教、カースト」という4 つのアイデンティティで規定される。
インドには連邦レベルの公用語であるヒンディー語以外に、州レベルで21の公用語が認められており、英語も政府公用語として使われている。インドの紙幣には、表而にヒンディー語と英語、裏面には15の言葉で金額が書かれている。北インドでは、サンスクリット語を祖語とするヒンディー語やベンガル語などが母語であるのに対し、南インドではタミル語などドラヴィダ系言語が話されていて、両者の言語は全く異なる。
ある程度の教育を受けたインド人は、自分の母語以外に、公用語であるヒンディー語と英語を話すことができる。このような環境で育ったインド人が欧米のグローバル企業で活躍しやすいことは、十分に理解できる。
インドの北部は、農業が盛んなことが特徴で、インド最大の穀倉地帯のハリャナ州も北部に位置している。一方、 デリー首都圏はスズキの合弁工埸もあって、 自動車産業の集積地と
なっており、デリー近郊のグルガオン( グルグラム) は在留邦人がインドで最も多い。北インドは一般的に教育水準は低く、保守的である
東部の中心は西ベンガル州である。同州は1911年まで植民地インドの首都であったコルカタを擁していることもあって学問、文化・芸術が盛んであり、ノーベル賞受賞者も輩出している。しかし西ベンガル州は1977 年から34年間にわたって、インド共産党が政権を担っていたため、ビジネスは停滞気味である。
西部��、商業の中心である。インドの財閥の多くは、西部を拠点とするマルワリ、グジャラティ、パンジャビ、パ—ルシーなどのコミュニティに属している。このマルワリ、グジャラティ、パンジャビというのは、 カースト名ではなく、一族の「出身地」を意味する。西部最大の州であるマハラシュトラ州の州都ムンバイは金融と商業の中心で、中央銀行であるインド準備銀行やムンバイ証券取引所があるほか、「ボリウッド」と呼ばれるように映画産業の中心地でもある。
南部(南インド) は、インドで最も教育水準が高く、北インドより治安もいい。南インドに居住するドラヴィダ人は、そもそもインド全体に住んでいたが、アーリア人の侵略により南インドに追いやられた歴史がある。南インドの人たちは北インドに対する反感、あるいはコンプレックスがある。
1947 年の独立に際して、多くのイスラム教徒は東西パキスタン(現在のバングラデシュとパキスタン) に移り住んだこともあってインドではヒンドゥー教徒の人口が圧倒的に多いが、ヒンドゥー教徒によるイスラム教徒の抑圧は、欧米を中心にしばしば問題視されてきた。
4つの階層制度を、インド人は「カースト」ではなく、「ヴァルナ(四種姓) 」と呼ぶ。そして、この4つの階層の下に、「ダリット(またはアウトカースト、不可触民) 」と「アディヴァシ 先住民) 」と呼ばれる二つの最下層が存在する。
この4 つのヴァルナとその下のダリットの集団は、「ジャーティ」と呼ばれる多数の集団に細分化されている。インドではこのジャーティが、長年にわたって世襲的な職業に結びつけられてきた。そしてジャーティの職業を代々継承するため、婚姻関係も伝統的に同じジャ—ティ間で結ばれてきた。そのため、都市でも農村でも異なるカースト間の婚姻は奨励されず、とりわけ農村部ではいまだにそれが顕著である。
ジャーティの敬は3000以上にも及ぶとされ、それぞれの職は同じジャ—ティに属していても、異なるジャーティ間で上下関係がある。例えば、バラモンに属する人々の中でも、聖職者のジャーティの方が教師のジャーティよりも地位が上といった感じである。
インドでは、 高級官僚や学者、ITエンジニアなどの知的エリートは、 上位カースト、とりわけバラモンが圧倒的に多い。一方、インドの財閥にバラモンはきわめて少なく、商業カーストのヴァイシャが中心である。
多様なバックグラウンドを持つ人々が共存するインドは、世界最大の民主主義国でもある。IT大国インドらしく、総選挙では9億人の投票者か電子投票を行い、投票最終日の翌日には結果が判明する。
モディ首相は勤勉なことで知られ、年間1日の休みもとらずに、早韌から深夜まで仕事に没頭している。部下にも自己規律を守って期待された成果を上げることを厳しく要求する。類まれな演説の名手であるモディ首相は、アイパッドの愛用者で、フェイスブックやツイッターなどのソーシャルメディアを使いこなすことでも知られている。
モディ首相は、彼の支持者によって「第二のサルダ—ル・パテル」とも呼ばれている。サルダ—ル・パテルはインドの初代内相として強権を発揮し、インド独立時に500以上あった藩王国を統一インドに帰狷させた功紐で知られ、地元グジャラート州では英雄的存在である。
第2章 モディ政権下のインド経済
モディ政権が発足した14年の段階では、インドの名目GDPは世界第10位であったが、その後8 年間で5 カ国を抜いたことになる。さらに、22年の物価水準を考慮した購買力平価に基づくGDPの国別ランキングでは、インドはドイツと日本を上回る世界第3位となっている。
世界最大の人口を抱えるインドの強みは、巨大な中間層の存在である。日系企業のインドへの高い関心の背景には、インドの膨大な中間層の購買力への期待があることは言うまでもない。
インド経済のもう一つの強みは、基本的に内需主導で、海外との貿易に影響されにくいことである。2008 年から09年にかけての世界不況の時もそうであったように、現在のような世界的な不景気の状態においては、インド経済の底堅さが目立つ。
インドにおける製造業育成の最も大きな課題の一つに、インフラ未整備が挙げられる。電力供給の不足や道路整備の遅れなど、問題はいまだに山積みで、モディ政権の努力にもかかわらず、公共事業の遅れや予算超過などは日常茶飯事である。
労働者の生産性の低さも問題である。インドでは職業訓練施設が不足しているため、未熟練労働者が多い。
また「IT大国」であるはずのインドでは、大半の未熟練労働者にはデジタル・スキルが欠如している。
インドは17世紀には世界のGDPの27%、18世紀には23%を占めていた。しかしそれが1820年には16%に低下し、その後英国の植民地支配下で、長期低落傾向を余儀なくされた。1947 年にインド連邦として独立した時点では、 国民の大多敖が貧困ラインを下回る惨状であった。
製造業は国営企業(ないし財閥を中心に育成する) というのが当時のインド政府の方針で、この「混合経済」と言われる政策によって、社会主義の平等と資本主義による活力の両方のメリットを享受することを期待されていた。また工業化に重点をおいていたため、農業部門の育成や初等・中等教育による人的資源開発は軽視された。
1960年代後半から70年代に入ると、「混合経済」による保護主義的な政策は行き詰まりが顕著となり、インディラ・ガンディー首相は世界銀行や米国に支援を求めた。しかし、当時の米国は中東と関係の近いパキスタンをインドよりも重視していたため、結局支援は受けられなかった。このことに失望したインディラ・ガンディーは、ソ連に接近していった。
インドの非同盟中立外交は今でも継承されているが、インディラ・ガンデー首相の時代のインドは、非同盟中立と言いつつ、実際にはソ連寄りの国であった。インディラ・ガンディーは、
69年には商業銀行を国冇化したほか、非効率な社会主義的経済理営を推し進めていった。
こうして社会主義化の傾向を深めていったインド経済は、停滞を余儀なくされた。1980年代後半にはラジブ・ガンディー政権によってその修正が試みられたものの、うまくいかなかった。その結果、1947年の独立時から90年までのインドの成長率は、年平均3.5%程度にとどまり、 これは「ヒンドゥー・レート・オブ・グロース」と呼ばれた。
1991年7月、インドの経済自由化がついに着手されることとなった。90年8 月に始まつた湾岸戦争の影響で原油価格が高騰し、中東の出稼ぎ労働者からの送金が途絶えて、91年7月インドは2 週間分の輸入決済分の外貨しか手元になくなり、深刻な外貨危機に陥った。
当時のナラシンハ・ラオ首相とマンモハン・シン蔵相は、国際通貨基金と世界銀行の融資と引き換えに、彼らが主導する「構造調整プログラム」を実行する形で「新経済政策(NEP) 」に着手した。
一連の経済自由化政策は成功し、インドの経済成長率は上向き始めた。その哭綃は国際的にも評価され、IMF経済支援を受けて経済改革を行った途上国の中でも、インドは最も成功した例であると言われるようになった。
2014年に始まったモディ政権の主な実績は、 インフラ整備、投資環境の改善、汚職撲滅の3つに要約することができる。この中でもとりわけ評価に値するのは、インフラ整備の推進である。
第3章 経済の担い手ー主要財閥、注目の産業
インドの大半の財閥は、マルワリ、グジャラティ、パンジャビ、パールシ— のいずれかのコミュニティに属しており、とりわけ「インドのユダヤ人」とも言われるマルワリのコミュ二ティに属する財閥が長らく牛耳ってきた。
マルワリ系の中では最大であったビルラ財閥と、パールシー(イランから移住したゾロアスター教徒) のタタ財閥、そしてグジャラティのリライアンス財閥の三大財閥は、外資企業との合弁や提携、海外でのビジネス展開などによって生き残り、その後のインド経済の拡大とともに急成長を遂げた。
タタ財閥は、汚職をしないクリーンな体質でも知られており、売上の一部を社会に寄付するなど社会貢献にもきわめて熱心である。インド最高峰の大学の一つであるインド科学技術大学院もタタが設立している。タタ財閥は従業貝を家族の一員のように扱うことで評判で、コロナ禍でも解屈を行わなか
った。
中国が「世界の工場」であるとしたらインドは「世界のオフィス」である。
インドでIT産業が発展した理由はいくつかある。第一に、インド人自体の素養がソフトウェア開発に向いていた。その昔ゼロが発見されたのも、天才数学者ラマヌジャンを生んだのもインドであったことからわかるように、インド人は観念的なことに秀でていて、大量生産よりも一品生産を得意とし、自由でフレキシブルな仕事文化を好む。こういった才能がIT産業で一気に開花した。
第二に、インド政府が早くから高等教育を奨励して、優秀な人材が理工系へ進学する傾向にあったことが、多くの1 丁エンジニアの輩出に結びついた。多言語国家のため、教育に英語が用いられ、知識層は英語が当たり前に話せるというのも幸いした。
第三に、インド政府のIT振興策も功を奏した。IT産業への税制優遇処置やソフトウェア・テクノ ロジーパークの設立などにおいて、政府が果たしてきた役割は評価に値する。
第四に、いたずらにハイテク技術を追うのではなく、安い労賃を活かして口 —エンドの顧客向けソフト開発を行い輪出するIT企業の戦略も正しかった。優秀な人材をこれだけ大量に低コストで使える国はインド以外にないため、得意とするローエンドの下請でライバルがほぼいない状態を築いたのは正解であった。
第五に、米国との半日の時差も有利に働いた。米国の夜間にインドでデータ処理などの作業がなされていることが米国企業で重宝がられた。米国の夕方までにインドに依頼しておけば、朝には出来上がっているため、時間の無駄がないのである。
第六に、米国の業界にインド人が大量に働いており、彼らが米国企業とのパイプを強化し、米国のIT産業の仕事文化をインドに輸入したことも幸いした。
インドIT産業は、世界的な不況の影響も受けにくい。不況になると、欧米の多くの企業が小務や業務の合理化のためにIT投資を行ったり、ハックオフィスの一部をそのままインドへ移したりするからである。
インドのIT企業の多くは、バンガロールに本社を構えている。その理由として、気候が温暖であることに加え、他の地域から入ってくる人たちに寛大で自由な空気があったこと、軍事産業が盛んであったため、科学技術の人材が蓄積していることなどがあった。これらの理由は米カリフォルニア州とも共通しており、バンガロールは「インドのシリコンバレー」として世界中に知られている。
IT産業に続いて注目されているのは、ジェネリック(後発薬) を主体とする医薬品産業である。2020年度のインドの医薬品の年間売り上げは423億ドル(5 兆4990 億円)に及んだ。
欧米の医薬品メーカーがインドでビジネスを行うメリットは、いくつかある。第一は、医薬品製造コストの安さである。インドの労働コストは先進国の6 分の1程度であり、医薬品製造設備についても、機器や建設コストは先進国に比べると4 割も下回る。
第二に、臨床試験やケミカル・サービスのコストも非常に安く抑えられる。生産コストの削減だけでなく研究開発費の増大を抑制するためにも、巨大な人口を背景とした臨床就験デ—タ収集に優位性を持つインドは先進国企業にとって重要である。失うものの少ない貧困層は治験に積極的に参加してくれるし、 彼らの多くが薬を飲んだことがないことも、 治験において利点となっている。
第三に、インドは国際的な化学合成技術と品質管理技術を持っている。米食品医薬品局が米国外で認知している医薬品製造工場の数はインドが最も多い。それに加えて、人材面の豊富さも挙げられる。インドでは化学を専攻した人材の数が米国の6倍に及ぶ。
最後に、他国にはない価値を提供できることもインドの強みである。インドの医薬品企業は研究から製造までを一貫して請け負う研究製造業務受託サービスを強化している。米国では製造化の部分のみを、吹州では医薬中間体(原料から原薬になるまでの途中の化合物) のみを受託する企業が多く、インドのように.一貫請負をする企業はない。
第4章 人口大国—若い人口構成、人材の宝庫
国連の推計によると、2021年から41年の20年間に、インドの人口の2人に一人が労働人口となり、インドの「人口ボーナス期」は2040年代前半から後半まで続くが、40年代後半には「人口オーナス期」に入る。これは、40年代後半になって、ようやく生産年齢人口の従属人口に対する比率が減少に転じることを意味する。
日本や韓国、台湾、中国といった東アジア諸国が「人口ボ— ナス期」に高い経済成長率を実現できたのは、生産年齢人口に対して十分な雇用創出が、製造業を中心になされたことか大きい。この「人口ボーナス期」を東アジア諸国と同じように冇効に活かすことは、インドの純済発展にとってきわめて重要である。製造業はとりわけ雇用吸収力が大きいため、モディ首相が「メイク・イン・インディア」「自立したインド」と題して国内の製造業育成に力を入れているのも、そうした理由によるところが大き
インドの人口抑制政策は1950年代から導人されてきたが、その道のりは平坦でなかった。1976 年から77年、当時のインディラ・ガンディ—首相と次男サンジヤイ・ガンディーが弥制的に避妊手術を推し進め、それまでの3倍に及ぶ800 万人が避妊手術を受け、うち600万人の男性がパイプカット手術を受けた。数値目標達成のために当局にはノルマが課せられ、警官が貧しい人々を捕えて、強制的に避妊手術を受けさせることさえまかり通った。
これは国民の反感を買い、1977年の総選挙における与党の大敗にもつながった。その結果、直接的な人口抑制政策はインドの政治で触れられにくく、タブーに近い問題となった。
こうしたことから、インドでは人口を抑制するために避妊を推し進めるのではなく、女性の教育や保健政策といった間接的な効果にゆだねるやり力が一般的となった。
近年政治問題化しているのは、宗教間の出生率格差である。イスラム教徒の出生率はヒンドゥー教徒と比べて相対的に高く、このことがヒンドゥー教徒を支持母体とする与党BJPにとって、懸念材料となっている
インドの高等教育制度は、初代首相ネルーの志のもと、理科系を柱として急速に整備されてきた。大学の数の増加とともに大学の「民主化」も進み、大学進学比率は現在では1割近くまで増加した。
インドの大学生は、おしなべて真面目で勉強に前向きである。授業の出席率が75%に満たないと卒業試験を受けられない大学も多く、日本と違ってアルバイトに精を出す学生はほとんどいない。
このように、最優秀の理系人材の水準が高いインドであるが、課題も多い。第一に、高等教育の急速な拡大にともなう質の低下がある。
第二に、国内の需要に対して、満足のいく水準の理工系学生が不足気味である。
第三に、学生の就職難の問題が広がっている。
第四に、インド政府内の教育の優先順位の低さも問題である。
第五に、研究水準にも課題がある。優秀な人材の宝庫のインドだが、此界の大学ランキングでは、インドの大学のランクはおしなべて低い。これは、インドの国公立大学では教員の給与水準が政府によって規定されているため低く、研究費も少ないため、 優秀な教員は海外の大学や国内の民間企業や研究所へとられてしまう結果である。
第六に、産学協同が不足している。インドの地埸企業は、おしなべて最先端の研究開発に前向きでない。TCSやインフォシスなど、地場のIT大手は基本的に欧米の下請業務に特化しているし、医薬品メーカーも後発薬の開発が主体であるため、新薬開発には積極的でない。
インド人にとって最も望ましい留学先は、言うまでもなく米国である。2022 年度に、インド人向けの米国の高校や大学で学ぶ学生ビザの発給数が約10
万件となり、中国を上回ってインドは国別トップとなった。米国以外にも英国、オーストラリ���、ニュージーランド、カナダ、シンガポールなどの英語圏諸国では、インド人制学生の比率がとりわけ高い。
モディ首相は、インドで始まり世界中に広まったヨガを2016年にユネスコ無形文化遺産に登録し、インドの「ソフトパワー」として使うことを本格的に始めた。自らも毎日早朝ヨガを行っているモディ首相は、6 月21日を国連の「国際ヨガの日」として定め、毎年この日に各国で一大イベントが行われている。
インドのヨガは、元来エクササイズのような肉体的なものではなく、ヒンドゥー教に根差した精神的なものであった。インドのヨガはこうした精神的なものであり、今日一般的な肉体的ヨガが世界に広まったのは、アイアンガーが前後、著名ヴァイオリニス卜のメンユ—イソによって英国に紹介されたのが一つの契機であった。
第5章 成長の陰にー貧困と格差、環境
インドの宗教の中で低カースト眉からの改宗比率が圧倒的に高いのは、仏教徒である。彼らはインドで「新仏教徒」と呼ばれていて、地域的にはインドのほぼ中央に位脸するマハラシュトラ州ナグプールやその周辺に最も多く居住している。
仏教への集団改宗を最初に主導したのは、不可触民の英雄ビームラーオ・アンベードカルであった。差別の温床となっているカースト制度自体を根絶すべきであるとアンベードカルと「カースト制度自体は認めるものの、カーストによる差別は認めない」という見解 を持つ国父マハトマ・ガンディーと対立し、1956年10月に50万人に及ぶダリットとともに自ら仏教に改宗した。これが、仏救がほぼ滅亡していたインドにおける「新仏教」の始まりである。
アンベードカルの仏教復興運動を継いだのは、驚くべきことに、日本人僧侶の佐々井秀嶺であった。佐々井は岡山県で生まれ、タイの寺院への留学を経て、1966年にインドの日本寺へ派遣された。毎年10月頃ナグプールで佐々井が中心となって開いている大改宗式には、今でも3 日間で100万人にも及ぶ群衆が押し寄せている。
第6章 インドの中立外交— 中国、パキスタン、ロシア 、米国とのはぎまで
1947年の独立以来、インドの外交は非同盟中立の立場をとってきた。かつての米ソ冷戦期にも、インドはどちらの陣営にも属さずに中立を保っていたが、現在も引き統き主要国との全方位外交を展開しており、インド政府自らが言うところの「戦略的自律性」を貫徹するという姿勢を崩していない。
その一方で、国境を接する南アジアの周辺国との関係については、これまでインドはその圧倒的な力を背景に、各国と個別に対応する二国間主義を選好する傾向にあった。2020年の中国との国境での軍が衝突以来、 インドでは周辺国に対する外交姿勢はかつてより友好的・協力的になってきている。
インドが急ごしらえの「グローバル・サウス」を旗印に、世界に向けた積極外交を展開し始めた理由としては、いくつかのことが考えられる。
第一に、インドが経済大国の道を歩み始め、IMFのゲオルギエバ専務理が言うように世界経済の牽引車となっていくとともに、経済大国としてのその自信が、インド外交をより国際社会に向けて積極的な発信をしていく方向へ導いたに違いない。
第二に、ロシアのウクライナ侵攻以���、西側の先進国からロシアを批判せず、原油を輸入し続けていることを責められてきたことに対して、インドは「グローバル・サウス」の国々のためという大義名分を使って反論しようとしたと思われる。
第三に、インドはその「非同盟外交」の再構築を「グローバル・サウス」という言葉を用いて試みたに違いない。
第四に、カシミール問題等で米国や欧州諸国から人権問題にいろいろな形で口出しをされて、モディ首相やジャイシャンカル外相が西側諸国に対する失望感を強めていったのも、理由の一つにあるかもしれない。
最後に、2 024 年の春に総選挙を控え、モディ首相がグローバル・サウスの代表として外交の舞台で指導力を発揮したことを国民に印象づける目的もあったと考えられる。
第7章 日印関係—現状と展望
インドで日本企業がプレゼンスを高めていくための提言はこれまで数多くなされてきた。それらをまとめると、おおよそ次のように要約できよう。
第一に、成功している企業は初期段階から大きな投資を行っている。韓国のLGや現代自動車は進出時点でインドを戦略的な拠点としてとらえて大きな投資を行った。大規模な広告宣伝活動の効果もk表徴すべきである。韓国企業はインド進出時に本社が広告経費を負担して積極的な宣伝を行って、ブランド・イメージを確立させた。
第二に、投資におけるパートナーとの良好な関係構築が重要である。スズキの合弁相手マルチ・ウドヨグは設立時に、インド人の最優秀な官僚を送り込んだ。
第三に、日本企業が大規模なM&Aを行う場合は、現地のネットワ— クを用いて十分なデューディリジェンスをすべきである。
第四に、恐らくこれが最も重要なことと思われる「現地化」の重要性についても協調しておきたい。日本以外の外資企業の多くは現地法人トップに優秀なインド人を採用し、全世界に向けた研究開発を行っている。
第五に、グローバルビジネスにおけるインドの位置づけも、 明確にすべきである。
第六に、長期的な視野で見た人事評価を行う必要がある。スズキやホンダなど成功している日系企業でも、最初の10年間は相当な苦労を強いられている。何事もスムーズには進まないインドでのビジネスは、成功に時間がかかる。
インドは日本の円借款の最大の受取先である。1958に日本にとって世界で第一号となる円借款が供与されて以来、2022年11月までに累計で6兆9783 億円に上る円借款がインドに供与されている。
デリー・メトロは、日本のODA案件の中でも最も大きな成功を収めた案件として、よく知られている。総事業費1 兆7377 億円(進行中の第4 フェーズを含む) に及び、その半分近い8251 億円が日本の円借款で賄われている。
1947年に独立して91年に経済自由化を開始したインドは、今や新興国の中でも最も注目される国の一つとなり、アジア第3の経済大国であると同時に、世界で第5 の経済大国となった。
米モルガン・スタンレーのアナリストは「中国にないものは全てインドにある」と語った。本書で見てきたように、多くの課題を抱えながらも独自の経済発展を遂げ続ける超大国イン
ドの将来性は、いくら强調しても協調しすぎることはない。
投稿元:
レビューを見る
或る程度専門的な内容も含めて、一般向けに必ずしも知られていないかもしれないことを紹介する、そしてそれが程好い分量というのが「新書」の魅力なのだと思っている。本書は正しくそうした「新書」の魅力に溢れる一冊だ。
「インド」と聞いて、思い浮かべられるモノは限定的であるような気もする。遠い古代から様々なモノを受継いだという文化を有していて人口が非常に多い国という程度のことしか思い浮かばない。加えて、カレー料理が親しまれているが、その起りとなる地域ということも思い浮かぶ。個人的には、札幌に出て食事を摂る場所として気に入っている御店の一軒にインド料理店が在ることも思い浮かべる。
そういう残念ながら「少しばかり貧困なイメージに留まる」というインドに関して、政治、経済、企業活動、社会、外交、各分野の近現代の経過、日本との様々な関係等に関して、その地域や社会が内包する複雑な“多様性”という要素も交えて、広く深く、同時に判り易く纏めることを試みているのが本書である。そしてその「試み」は成功していると思う。
何時の頃からか「グローバル・サウス」という言い方も耳にする機会が増えているように思う。「南半球」というようなことを念頭に置いた表現であると見受けられる。これは南半球に限定するのでもなく、寧ろ「新興諸国」というような感、「比較的近年に存在感を増しつつある国々」という意味合いで用いられていると思われる。
インドはこの「比較的近年に存在感を増しつつある国々」の代表的な国の一つと言い得ると思う。近年の国際関係のニュースで「インドのモディ首相が…」という言辞が耳目に触れる場合も多くなっていると思う。本当に、本書の題のような「グローバル・サウスの超大国」という存在感だ。
本書はこういうインドに関して、比較的最近の様子から少しだけ遡った辺りまで、実に幅広く「知らなかった…」を紹介してくれている。著者はアジア開発銀行や世界銀行でインドに関する御担当を続けた経過の在る大学教員である。この種の本を著すとして、これ以上の適任者は見出し悪いかもしれない。
実に幅広く「知らなかった…」を御紹介いただいている訳だが、個人的には外交関連の事柄が興味深かった。実際、近年の様々な状況の中、インドのような「比較的近年に存在感を増しつつある国々」の注目度は高い。そして「独自に様々な国々との関係の中での“位置”を築くことを模索し続けた」というようなインドの外交の経過は何か興味深く本書で学んだ。
新たな知識を得ようとすることは続けなければなるまい。好い一冊と出遭えて幸いだった。
投稿元:
レビューを見る
2023年9月時点でのインドの概要書です。
急速に変貌をとげるインドは、見るたびに大きくかわっている。
中国を抜いて、世界一の人口となったインドは、経済でも米・中に続いて3位になろうとしている。
本書は、インドの産業を、IT、医療、バイオ、ダイアモンド加工、自動車として紹介している。
日米豪印のクアッド、中印の対立、米露との中立外交、G20 など21世紀の地政学的存在感は増す一方である。
モディ首相は、貧しいカーストの出身であり、勤勉で1日も休まず、早朝から深夜まで仕事に没頭しているとのことに驚いた
気になったのは、以下です。
概要
・多様性の中の統一 Unity in Inversity インドをひと言で言い表す時、よく使われる言葉である
・インド人は、出身地、言語、宗教、カースト、という4つのアイデンティティで規定されている
①コルカタ出身、②ベンガル語を話し、③ヒンドゥ教を信じる、④バラモン といった具合である。
・インドの国土は、北インド(東、西、北)、南インド(南)、それ以外(北東部)の、3領域、5地域に分けらえる
・インドは、28の州、8つの直轄領(含むデーリ首都圏)の、36のエリアからなっている。
・北インドでは、アーリア人が多く、南インドには、ドラヴィタ人が多い。
・インドの言語は、連邦レベルの公用語である、ヒンディー語の外に、州レベルで21の公用語がある、英語も、政府公用語として使われている。
・宗教は 2011年の国勢調査の時点で、ヒンドゥ教 78.8% イスラム教 14.2% キリスト教 2.3% シク教 1.7% 仏教 0.7% ジャイナ教 0.4% である。
・カースト(ポルトガル語であり、インド人は、ヴァルナ(四種姓)という)は、バラモン(司祭)、クシャトリア(王族・武士)、ヴァイシャ(商人)、シュードラ(農民・サービス)。
・そしてこの4つの階層の下に、ダリット(不可触民)、アディヴァシ(先住民)、と呼ばれる2つの最下層が存在する。
政治
・インドは、世界最大の民主主義国である
・総選挙は、9億人を対象として、電子投票を行い、翌日に結果発表される
・議会は2院政、上院は250議席、下院(5年おきに総選挙)は、545議席。
・国家元首は大統領だが実権はない
・インドの政党は、全国政党2(インド人民党(BJP):モディ、インド国民会議派:ガンディファミリ)と、地域政党からなる
・BPJ 都市中間層のヒンドゥ教徒が支持母体で、ビジネス志向が強く、国粋主義、愛国主義的な傾向がつよい
・モディ首相、グジャラート州でやや低いカーストの貧しい紅茶売りの子として生まれ、グジャラート州のインフラ整備をすすめ全国に知られるようになった
・BPJ総裁は、内相である、シャー。モディが国政に専念し、シャーが党務や、選挙戦略を担う2トップである。
・国民会議派は、農村の貧困層やイスラム教などのマイトリティを支持母体としている
・ガンディファミリとマハトマとは血のつながりはない
経済
・輸出先 米、UAE,蘭、中、シンガボール、バングラディッシュ、英(日本は26位)
・輸入先 中、UAE、米、露、サウジアラビア、イラク、インドネシア、シンガポール(日本は13位)
・モディ政権の実績 ①インフラ整備、②投資環境の改善、③汚職撲滅
・インド財閥 タタ、リアイアンス、ビルラ、アダニ
・IT産業の飛躍 中国が、世界の工場なら、インドは、世界のオフィス
①インド人には、もともと、数学の素養があった
②インド政府が早くから、理工系高等教育を奨励、英語圏でもあり
③インド政府のIT振興策
④いきなり、ハイテクではなく、安い労賃を生かしての、ローエンド、ソフト開発を輸出したのがヒットした
⑤米国との時間差、24時間のソフト開発、BPOが可能に
・TCS,インフォシス、ウィプロ、HCLテクノロジーズなど
・インドのシリコンバレーは、バンガロール
・医薬品 シプラ、ドクター・レディ、サンファーマ
①製造コストの安さ、②臨床試験、ケミカルサービスも安価、③国際的な化学合成技術と、品質管理技術
・バイオ産業 バイオ医薬、バイオ農業
・ワクチン製造大国
・ダイヤモンド加工業 デビアス社の研磨加工は、イスラエルとインドが実施
・自動車、自動車部品 世界3位の自動車消費国に
内政
・政策による貧困層圧迫
・医療設備の不足
・深刻な所得格差、資産格差
・農業の低い生産性
・男女間格差と、女性の社会進出の遅れ
・宗教間格差 イスラム教徒への抑圧、新仏教徒
・大気汚染
外交
・中国との衝突 カシミール(ラダック地域)問題
・クアッド 日米豪印 インド・太平洋地域の安全保障
・台湾 インド初の半導体工場建設へ向けて
・露 特別で特権的な戦略的なパートナー ロシアの武器、石油の引き受け国である
・米 インドの信頼度は高くない オバマの中国政策展開、イランへのプラント輸出の阻止など、つのる対米不信
・インド最大の敵国は、隣国パキスタン
・G20議長国としてのインド
日印関係
日本にとって、インドは特別な国
・インドは、世界有数の親日国
・歴史的経緯(仏教による交流、インド国民軍、インパール、東京裁判、1991、IMFつなぎ融資など)
・広島禍、長崎禍での国会での黙とう
・伸び悩む、経済、貿易
・安倍元首相暗殺の衝撃、モディ=安倍ラインで進められていた日印関係の停滞、例に見ない、安倍氏死去を受けた、インド国会での服喪
目次
はじめに
第1章 多様性のインド―世界最大の民主主義国家
第2章 モディ政権下のインド経済
第3章 経済の担い手―主要財閥、注目の産業
第4章 人口大国―若い人口構成、人材の宝庫
第5章 成長の陰に―貧困と格差、環境
第6章 インドの中立外交―中国、パキスタン、ロシア、米国とのはざまで
第7章 日印関係―現状と展望
あとがき
参考文献
近藤正規(こんどう・まさのり)巻末より
1961年生。アジア開発銀行、世界銀行にてインドを担当した後、1998年より国際基督教大学教養学部助教授。
現在、国際基督教大学教養学部上���准教授。
2006年よりインド経済研究所主任客員研究員を兼務。
そのほかに21世紀日印賢人委員会委員、日印共同研究会委員、日印協会理事などを歴任。
東京大学学士、ロンドン大学修士、スタンフォード大学博士。
インドの全ての州と連邦直轄領を訪れて論文を多数執筆。専門はインド経済、開発経済学
ISBN:9784121027702
出版社:中央公論新社
判型:新書
ページ数:320ページ
定価:980円(本体)
発行年月日:2023年09月
発売日:2023年09月21日
投稿元:
レビューを見る
インドのこれまでとこれからを知れる一冊。非同盟中立を貫くインドの各国との外交関係にもページが割かれており、インドを学ぶ人の初めの一冊としておすすめ。
投稿元:
レビューを見る
政治・経済・他国との関わりなどインドについて全般的に触れられている本。インドに関する知識のない人がざっくりと把握することのできる入門書のように感じた。
中国・ロシア・パキスタンと一癖ある国に囲まれていることが中立外交、その先のグローバルサウスに繋がっているということがとても良く理解できた。
投稿元:
レビューを見る
インドの最新の情勢について分かりやすくまとめられていました。どちらかというと政治と経済の話題がメインとなっていて多くの紙面が割かれています。その分、文化や歴史は序盤にコンパクトにまとめられているのですが、逆にその部分の情報密度と読みやすさに感動しました。
ラダックの道路工事の現場や、シッキムの空港などを実際に見て、観光に力を入れてるんだなーと呑気に思っていました。でもその理由が中国との国境紛争にあると知って目から鱗でした。中国、ロシア、欧米との複雑な外交関係から、インド政府の苦労が窺い知れます。
経済発展するインドですが、経済のパイを大きくすることを優先して、格差上等とばかりに突き進んでいるようです。実際インドに行くと、日本並みに高いレストランの横で、屋台で数10円のものを食べる人たちがいて、そのレイヤー構造に驚きます。そんなインド今後どうなっていくのか、本書を読んでますます興味が湧きました。
投稿元:
レビューを見る
インドという国はまだまだこれからの国。
国際的なプレゼンスはこれから強化されていくのであろう。日印関係の強化はこれからの日本の国益にも沿うものであるので更なる発展を期待したい。
投稿元:
レビューを見る
中国とは別の意味での難しさがありながら、非常に魅力あふれる国であることが分かった。
インドの成り立ちから、現在の立ち位置や課題まで網羅的に触れられており、とても分かりやすい。インドについての入門書としてお勧め出来る一冊。
投稿元:
レビューを見る
インドについて網羅的に理解が深まる。
歴史的に中国と緊張関係がある一方、武器供与などでロシアと関係性が深い。
米国のIT業界を人材面、業務のアウトソーシング先として支えている。
パキスタンとは領土や宗教面で対立。
投稿元:
レビューを見る
インド人は出身地、言語、宗教、カースト、によって規定される。
インド経済は内需主導。海外に影響されにくい。
製造業が弱く、サービス業主体。中国と違うところ。
インド経済の担い手は財閥。
人口大国。14億人。現在は合計特殊出生率は2人程度。ただし死亡率が減っているため、人口は増加中。2040年代前半までは人口ボーナス期。それ以降はオーナス期にはいる。製造業が中心になれば、経済発展できる。
人口抑制策は、ガンディーの時代に強制的避妊手術が行われて反感を買った。そのため避妊ではなく女性の教育は保険政策によっている。女性の教育水準が高くなれば出生率が下がる。
世界に印僑ネットワークがある。人材の宝庫。ITからヨガまで。
高額紙幣廃止の影響で、インド経済は減速=水清くして魚棲まずの状態。
インド農業の生産性の低さ。
深刻な男女間格差=ダウリー制度(持参金制度)の影響。出生男女比が偏っている。
大気汚染が深刻。
台湾企業が巨大投資フォンファイのiフォン組み立て工場。
米印関係は中国への対抗から。
戦後日本の復興を支えた=名だたる親日国。日露戦争の勝利は、インド人を勇気づけた。インドの鉄鉱石や綿花が物資不足の日本を助けた。
インドのソフトウエア部門は自社のハードウエアを持たない点で伸び悩んでいる。日印EPA協定は、日本にとって有意義。インドにとっては、日印、インド韓国間のEPAは失敗だったという批判が根強い。
日本人の使節団は急増したが、表敬訪問ばかり。決断が遅い。
日本の新幹線輸出はモディ首相と安倍総理の絆から生まれたとされる。