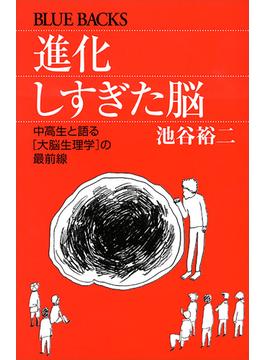読割 50
電子書籍
進化しすぎた脳
著者 池谷 裕二
『しびれるくらいに面白い!』最新の脳科学の研究成果を紹介する追加講義を新たに収録!あなたの人生も変わるかもしれない?『記憶力を強くする』で鮮烈デビューした著者が大脳生理学...
進化しすぎた脳
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
進化しすぎた脳 中高生と語る〈大脳生理学〉の最前線 (ブルーバックス)
商品説明
『しびれるくらいに面白い!』
最新の脳科学の研究成果を紹介する追加講義を新たに収録!
あなたの人生も変わるかもしれない?
『記憶力を強くする』で鮮烈デビューした著者が大脳生理学の最先端の知識を駆使して、記憶のメカニズムから、意識の問題まで中高生を相手に縦横無尽に語り尽くす。
「私自身が高校生の頃にこんな講義を受けていたら、きっと人生が変わっていたのではないか?」と、著者自らが語る珠玉の名講義。
メディアから絶賛の声が続々と!
『何度も感嘆の声を上げた。これほど深い専門的な内容を、これほど平易に説いた本は珍しい』――(朝日新聞、書評)
『高校生のストレートな質問とサポーティブな池谷氏の対話が、読者の頭にも快い知的な興奮をもたらす』――(毎日新聞、書評)
『講義らしい親しみやすい語り口はもちろん、興味をひく話題選びのうまさが光る』――(日本経済新聞、書評)
目次
- 第1章 人間は脳の力を使いこなせていない
- 第2章 人間は脳の解釈から逃れられない
- 第3章 人間はあいまいな記憶しかもてない
- 第4章 人間は進化のプロセスを進化させる
- 第5章 僕たちはなぜ脳科学を研究するのか
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
二年半後の追加、の章がぴりっと効いている。大学の研究室でもこんな「お茶会ゼミ」が普通にあればいいと思うような章。
2008/03/04 09:46
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
三十代の若手研究者が高校生に行った「大脳生理学」の少人数講義4回をまとめたもの。脳のどんな研究があるのか、研究者がどんな風に考えて仕事をしているのかが、わかりやすく、でも刺激的に書かれている。聴き手の学生が見せる反応にも鋭いものあり、意外なものあり、でなかなか面白い。
「脳の構造」「電気による神経伝達」の話から、「脳のあいまいさ」や記憶、意識などの哲学的な話と、基本的な話から先端の重要な問題まで題材は広範である。読みはじめは「わかりやすく」と考えすぎて冗長か、とも感じた。だがだんだんと著者の「わかってもらおう」という熱意と、自分の考えの根源に気持ちが走っていく様子が、著者の若さのよい部分として伝わってきて、ぐいぐいと引っ張り込んでいく。わくわくする面白さに引きこまれてしまった。
「細胞膜の電位差がどうしてできるのか」など、高校生に向けての説明はなかなか上手いな、と思うものがある。これまでわからなかった人はこの説明の仕方でわかるかもしれない。専門の論文をいきなり読むのは難しいだろうが、面白いなと思ったら後ろの参考文献など、別の本にも手を出してみて欲しい。著者に誘導されて特定の印象、結論に導かれたのかもしれないから。(この本に書かれている「脳のあいまいさ」を読んだら、なんのことだかわかるはず。)
ブルーバックス版には、高校生への講義から二年半後、大学研究室の学生たちとの討論が第五章として追加されている。これがなかなかぴりっとしてよい部分になっている。2006年の学術雑誌の引用までしながら最先端の面白い話、本質的な話にすっと入っていく。こんな「サロン風」の会話が研究室で日常的にあればいいのにな、とおもうような会話である。「科学は役に立たなければいけないか?」など、研究者になろうとする人には折に触れて話し合って欲しい話題なのだが、なかなか友人同士でもこういった「固くるしい」話題は出にくいかもしれない。研究室で教授やスタッフを交えてならなおさらむずかしいだろうか?研究室では研究に直接関係するゼミは必須であろうが、どうだろう、「お茶会ゼミ」のような形でこの第五章のような時間をつくってみる、というのは。毎回少し哲学的だったり、社会的だったり、目前の研究とは少し違うテーマをだしあって話をする。
あ、「もうやっている」研究室がありましたら暴言、お許しを。「なんのこと?」と思われましたら、この本(旧版でなくブルーバックス版)を一寸読んでみていただきたい。
紙の本
脳の曖昧さをはっきりと教えてくれる、脳を知るための定番
2007/05/05 17:33
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Living Yellow - この投稿者のレビュー一覧を見る
2年ほど前に、出版された同タイトルの書物に、第5章として「僕たちはなぜ脳科学を研究するのか」と題された、著者とその教え子たちの実感に基づいた、「そもそも脳科学って役に立つの?立っていいの?」という根本的な問いかけもはらんだ座談、索引、参考文献を追加したもの。
前の版と基本的には同じ内容のだが、高校の生物を履修していなくても、理解できる、読みやすい文体、丁寧な説明方針が貫かれている。
ジャーナリズム、特にTVで「脳」を巡るさまざまな「うわさ」に近いレベルの情報が流通している中で、最新の基本的情報を、「心ってどこにあるの」という素朴な問いかけを踏まえつつ、アルツハイマー病のメカニズムの最新研究にまで丁寧な解説を加える本書は、当分、定番の入門書となるだろう。
ただ、高校生相手の講義集とはいえ、その高校が慶応義塾ニューヨーク学院高等部。まあ学校名だけで判断してはいけませんが。相当カンのいい質問を著者に投げかけています。
紙の本
目の眩むようなグルーブ感
2011/05/28 09:25
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Genpyon - この投稿者のレビュー一覧を見る
2002~2005年、ニューヨーク在住であった著者が、現地の日本人口高校生を対象とした4日間の脳科学特別講義をまとめた著書。ブルーバックス版では、帰国後、脳科学を研究する側となる大学の研究室で開いた追加講義の内容が追加されている。
高校生を対象とする講義ということで、非常にわかりやすい。が、単純なことを簡単に解説しているわけではなく、大人にとっても難しいと思われる脳の機能や仕組みについて、けっして簡単ではない内容を、生物学的そして化学的にしっかりと説明していく。
たった4日間の講義には、さらに、その時点での最新の研究成果なども織り交ぜられていく。これら最新の研究成果には、常識的な経験からすると驚かされる内容が多く、高校生ならずとも、目から鱗が落ちる体験を楽しむことが出来る。
そして、この講義が素晴らしいのは、著者本人もあとがきで書いているが、その目の眩むようなグルーブ感だ。著者本人ですら、もう、このようなテンポ・潔さ・自身と勢いのある講義はできない、と、書いているように、その時・場所で起こった「たった一度きり感」がひしひしと伝わってくる。
ブルーバックス版で追加された追加講義は、雰囲気的には、研究室のお茶会という感じで、その落ち着いた空気によって、本著はクールダウンしていく。このクールダウンがなかったら、本著のさわやかな読後感は、これほどまでに引き立ってはいなかっただろう。
紙の本
あいまいな脳の世界
2022/11/10 18:46
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:福原京だるま - この投稿者のレビュー一覧を見る
脳がいかにあいまいであるか、そしてそのあいまいさこそが世界を汎化して捉えることができるようにしているかもしれないという不思議な脳の世界を知ることができ面白かった。
紙の本
帯通りしびれました。
2022/08/24 12:55
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ごーいち - この投稿者のレビュー一覧を見る
脳が世界を作りだしている。
視覚・言葉など脳が無意識に補完するおかげで、今の世界がある。人間は、ほとんどが無意識で出来ているのでは?
記憶があいまいだからこそ、変化する環境に対応でき、イマジネーションがわく。
著者の平易な語り口に引き込まれる。
紙の本
脳科学に詳しくない人にも、教育について考えたい人にもおすすめ
2020/07/18 21:31
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:昏倒遊民 - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者は東大教授で、テーマは脳科学。
というと門外漢の私などは構えてしまいそうになるところだが、中高生向けの講義を書籍化したものということもあり、非常に読みやすい。脳科学に全く予備知識を持たない私でも、最後まで面白く読むことができた。また、私のような文系人間にも知的好奇心をかき立ててくれるという意味で、脳科学のみならず自然科学全体への優れた入門書でもあると感じた。
さて、本書の素晴らしい点は、脳に関する知的に高度な内容を誰にでもわかりやすく解説してくれることにあるのはもちろんだが、ただそれだけではない。著者と生徒との間で繰り広げられる真摯な対話に、否応なしに引き込まれるのだ。ああ、自分もこういう授業を受けたかった、と思わせられる(もちろん、生徒たちが優秀だからこそ成り立つのであって、私には真似できないかもしれないが…)。まさに理想の教育の実践例といっても過言ではないだろう。理系文系関係なく、教育について考えたい人にも是非読んでいただきたい一冊である。
紙の本
大脳生理学の最新の知見をもとに書かれた脳に関する非常に興味深い一冊です!
2020/02/07 15:02
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、科学的知識をとっても分かり易く解説してくれると大人気を誇っている「ブルーバックス」シリーズの一冊で、同巻は、記憶のメカニズムから意識に関する問題といった脳に関わるテーマを扱った科学書です。同書は、最新の大脳生理学の知見を存分に活用して、「第1章 人間は脳の力を使いこなせていない」、「第2章 人間は脳の解釈から逃れられない」、「第3章 人間はあいまいな記憶しかもてない」、「第4章 人間は進化のプロセスを進化させる」、「第5章 僕たちはなぜ脳科学を研究するのか」といった内容が記載されており、これを読むことで、私たちの人生が変わるかもしれません。
紙の本
脳を考える人への贈り物
2018/05/19 16:18
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:病身の孤独な読者 - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は日本で屈指の神経科学者である池谷氏が、高校生を相手に神経科学の話をするというスタイルで書いた書籍である。内容は、その辺にある神経科学の入門書のように脳の解剖がどうちゃらこうちゃらという話ではなく、身近な問いから脳の話に移行し、若干哲学的な内容を帯びている。一見難しそうに思えるが、「高校生にもわかるように」というコンセプトなのですらすらと読めてしまう。クイズのようなものもあり、読者を楽しませてもくれる。池谷氏の一連の書籍の中ではトップを争うほど興味深い書籍である。
紙の本
私には少し・・・
2017/12/24 23:16
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Hide - この投稿者のレビュー一覧を見る
馴染みのない分野でしたが、学生との対話形式のところもあり、興味深く読めています。
脳ってホント不思議で偉大なパーツです。
紙の本
脳科学にはまっています
2016/05/17 18:11
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:匿名 - この投稿者のレビュー一覧を見る
脳科学の本はいろいろと出ていますが、個人的にはこの著者の脳科学の本が面白いと思います。何も高尚なお話をしているのではなく、誰にでも親しみやすい内容になっていると思います。