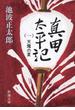真田太平記 みんなのレビュー
- 池波正太郎 (著)
- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
真田太平記 改版 第1巻 天魔の夏
2009/12/26 13:37
武田の壊滅と信長の破滅が真田家を翻弄し草の者が真田家を支える
8人中、8人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toku - この投稿者のレビュー一覧を見る
本の厚さと12巻もの長い物語に、手に取るのを躊躇してしまいがちだが、まったく読むことが苦にならない。
あっと言う間に一日で読み終えてしまうほど、読みやすく面白い作品。
物語は、武田家が織田・徳川連合軍に壊滅させられるところから始まり、織田信長が本能寺にて明智光秀によって急襲を受けるところまでを描いている。
今まで知らなかった武田亡きあとの真田家の動きが描かれているので、非常に興味深く読み進めることができた。
落城した高遠城から辛くも生き延びた武田・長柄足軽の向井左平次と、少年の真田源二郎(幸村)との出逢いや、怪我を負った左平次を助け、真田の庄近くまで連れてきたお江など「草の者」たちの活躍が、今後の物語を方向付けていく存在であると感じさせる。
武田家に仕えて、戦国の世を生き抜いていこうとしていた真田昌幸は、武田家が滅んだ後、真田家のような小さな家が生き残っていくには、大きな組織に仕えなければいけないと考え、北条や弟・信尹(のぶただ)を通して徳川へ道を付けておこうとしている事に興味を覚えた。
昌幸の徳川嫌いはよく聞くことで、始めから徳川嫌いだと思ったのだが、この頃は徳川嫌いなどはまだ無いようである。
家康も昌幸に一目を置いており、これが後々どう転んでいくのかが楽しみである。
また武田家亡き後、信州の一部と上州一国を貰い受けた滝川一益と、仕方なく信長への臣従する昌幸の会談も心地よく描かれている。
真田の心中を察し丁寧に向き合う滝川一益とそれに感銘を受ける昌幸の姿は、相手の腹を探り合う戦国の世にあって清々しいものを感じさせる。
また余計な事は言わず、真田の地は詳しくないので「安房守殿。ちからを貸してもらいたい」とあっさりと助力を請う滝川一益の姿勢は、武将としての大きさを示している。
十分な調査の上に書かれた歴史的事実と創作の部分が絶妙に織り込まれ、読んでいて物語の展開に疑問を感じる余地はない。
史実の部分はしっかり描かれつつ、物語の流れを淀ませるようなくどい内容はなく、あくまで物語の展開を補足する程度のものなので、歴史的な流れも十分楽しめる。
筆者の思想などは織り込まれていないので、物語に集中して入り込める作品となっている。
真田太平記 改版 第8巻 紀州九度山
2009/12/28 19:13
家康、昌幸、信幸それぞれの思いが九度山をめぐる
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toku - この投稿者のレビュー一覧を見る
命を助けられた真田昌幸・幸村が、上田城を徳川へ引き渡して紀州九度山へ蟄居させられるところから、真田昌幸が十余年に及ぶ倦んだ日々によって身体を蝕まれ、やがて病の床につくようになるまでを描いている。
その十年ほどの期間の中に、
・父と弟を紀州へ護送する真田信幸の苦労と心痛
・九度山で再び世に出ることへの期待と絶望に揺れる昌幸と幸村
・関ヶ原の合戦後ちりぢりになっていたが再び集結し、九度山へ配流された真田本家のために態勢を整える真田の草の者
・昌幸とお徳の子・於菊を預かった滝川一益の孫・三九郎一積のその後
・徳川の難題にもまったく隙を見せず、徳川家のために働き、豊臣家への忠節を曲げない加藤清正
などが描かれている。
七巻・関ヶ原では関ヶ原の合戦という大きな歴史の流れを中心に、その中で動く諸大名、忍びたちを描いていた。
本八巻では逆に、個々の大名や忍びたちに焦点を当てたものとなっており、内容が濃く感じられた。
特に本田忠勝の決死の助命嘆願によって命は救われた昌幸が『初めは静かに過ごしていればそのうち赦免され、やがて世にで、その時は』と期待する様子、長年の蟄居生活による倦んだ日々と、赦免運動をしていた本田忠勝の死によって世に出る希望がなくなり衰弱していく様子が多く描かれており、世間で幸村の九度山からの脱出劇が多く語られているなか、九度山での蟄居生活の様子は興味深いものがあった。
本巻で描かれている十年ほどの歳月は、心身の衰弱が激しい甲賀忍び頭領山中俊房とその死、お江と草の者に執念を持つ猫田与助に冷たい目を向ける平和ぼけした甲賀忍びたち、病に伏せる真田昌幸、本田忠勝の死など、一つの世代や意識が変わりつつあるのが感じられる。
年老いてなお、お江に執念を燃やす猫田与助の姿も存分に描かれ、真田太平記の楽しみの一つとなっている。
関ヶ原の合戦後、真田忍びは絶えたと安心し危機感がなくなってしまった甲賀忍びに失望した猫田与助が、この後お江や真田の草の者がどのように対決していくのか、とても楽しみだ。
真田信之(信幸)の、名前を変えてまで父との決別や徳川の臣として生きることを内外に示し、そして父と弟・幸村の蟄居解除を願って、とにかく徳川の神経を苛立たせないための配慮、少しでも徳川の気持ちを和らげようとする思いはとても暖かい。
真田太平記 改版 第5巻 秀頼誕生
2009/12/27 16:31
泥沼の朝鮮出兵、混乱の国内情勢、甲賀と草の者の白熱の追走劇
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toku - この投稿者のレビュー一覧を見る
朝鮮出兵が泥沼の様相となりつつあるとき秀頼が誕生するところから、秀吉、前田利家の死去後の文治派と武断派の争いの結果、家康に庇護を求めた三成が、五奉行を辞して佐和山にて戻るあたりまでを描いている。
本巻では、とにかく泥沼化する朝鮮での戦いとともに、秀頼が生まれたことによる秀吉の病的な喜びと国内での混乱が描かれている。
現地の状況を正確に伝えられていない秀吉の命令と、それをそのまま実行できない現地の苦しい状況や、石田三成・小西行長らと加藤清正たちの不和などによって、日本軍、朝鮮・明軍共に益のない朝鮮での戦いはますます混乱していく。
これらの混乱と合わせ、後継者がいなかった秀吉の秀頼誕生を喜ぶ異常さ、関白・秀次への怒り、戦時中の伏見城築城と醍醐の花見など、国内でも秀吉の手によって起こされる混乱の様子が描かれている。
甲賀の忍・猫田与助たちが真田の草の者・お江たちを追いつめる追跡劇も見所の一つで、思わぬ結末に驚かされる。
また、ドラマチックに登場した鈴木右近の帰還も見逃せない。
そして、草の者として一人前になりつつある、向井左平次の息子・佐助の活躍と、沼田に移った樋口角兵衛が今後どのように物語に影響を与えていくのか楽しみだ。
真田太平記 改版 第3巻 上田攻め
2009/12/26 13:39
徳川を翻弄する真田の姿が痛快
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toku - この投稿者のレビュー一覧を見る
徳川と真田が激突する第一次上田合戦から、秀吉の朝鮮出兵が間近に迫っている所までを描いている。
本巻の見所は、やはり上田合戦。
『北条への沼田引き渡し』を拒んだ真田に対する徳川の示威行動だ。
二軍級とはいえ約五倍の兵力を持つ徳川軍を、決死ではあるが思惑通りに徳川軍を撹乱し、撃退する様は読んでいて痛快。
そして秀吉の密命とはいえ、『見守る』だけであった上杉の『いざとなったら上田へ押し出す』助力も、真田への好意が現れていて気持がよい。
歴史の流れも掴みやすく、細かい出来事の前後関係もハッキリと分かり、細切れだった歴史の知識がつながっていく。
例えば、家康による真田信幸と本田忠勝の娘との婚姻の提案。上田合戦後、秀吉が徳川と真田の仲介をし、真田が徳川へ出仕したときの提案だとは思わなかった。
また朝鮮出兵の小田原征伐から二年の経たず計画されだした事についても、国を安定させる間もなく戦いに出向いていくことに驚いた。
このことは史実と年号を付き合わせていけば、分かることなのだが、物語を読みながらだとその事柄が感覚としても記憶に残りやすい。
池波作品を読んできて嬉しかったのが、「獅子」「獅子の眠り(黒幕より)」「錯乱(真田騒動より)」に登場し、90歳を超えた信幸に長く仕えてきた『鈴木右近』の存在。
池波氏がくどいほど書いてきた信幸と右近の若き姿と、彼らを取り巻く物語が存分に描かれているのは非常に嬉しい。
信幸・幸村の従兄弟・樋口角兵衛も気になる存在だ。
人間離れした怪力で一度は幸村を殺そうとした少年の角兵衛は、自分を十分に褒めてくれないと不満を持つ性格で、思わせぶりな物語中の解説でもう一波乱ありそうだと期待させる。
ちなみに本巻に登場する人物を主人公として描いている作品がある。
●『命の城』(黒幕に収録)
血と汗で勝ち取った沼田城に対する真田昌幸の思いを描いている。
小田原征伐のきっかけを作るためのの原因となった北条の名胡桃城奪取だが、昌幸はそれを知っていてあえて動かなかった。
北条が滅びれば沼田も自分の手に戻ってくるだろうことを計算して、苦悩しながらも名胡桃城を見捨てた昌幸の沼田城への複雑な思いが描かれている。
●『勘兵衛奉公記』(黒幕に収録)
小田原征伐のとき、中山城攻めで一番の働きを見せたが、主・中村一氏に手柄を独り占めにされたことに激怒し、主を見限って去ってしまった渡辺勘兵衛の物語。
十六歳の頃からの勘兵衛が描かれており、『わたり奉公人』として自分の槍先一つにすべてをかけて生き抜いていく勘兵衛の生涯
●『戦国幻想曲』
上記『勘兵衛奉公記』の主人公・渡辺勘兵衛を主人公とした長編小説。
●『角兵衛狂乱図』(あばれ狼に収録)
真田昌幸の血を引きながら、幸村・信幸の従兄弟として育った恐るべき力をもつ樋口角兵衛の物語
昌幸の義妹である角兵衛の母の罪が、角兵衛の生涯を翻弄していく様子を描いている。
真田太平記 改版 第12巻 雲の峰
2009/12/29 19:04
真田家の太平を目指す長い道のりに相応しい物語。しかし太平への道のりは遠い
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toku - この投稿者のレビュー一覧を見る
大阪夏の陣の後、家康が徐々に体調を崩しやがて死んでしまう頃から、徳川秀忠の命により信之一行が国替え先の松代へ向けて出発するところまでを描いている。
またあとがきにて、真田太平記以降の真田家や、滝川三九郎一績の後年について、軽く触れている。
本巻は、短編小説「錯乱(真田騒動-恩田木工-に収録)」、「獅子の眠り(黒幕に収録)」、長編小説「獅子」など、晩年の真田信之と幕府との暗闘を描いた作品を予感させる話が中心になっている。
その予感させる話とは「碁盤の首(真田騒動-恩田木工-に収録)」である。
「真田太平記」の中では、「碁盤の首」の大まかな話の流れが組み込まれている程度であるが、「碁盤の首」を知っていても十分に楽しめる。
「碁盤の首」の中心人物は『馬場主水』なのだが、馬場と言えばこれまで樋口角兵衛とともに真田太平記で怪しい動きをしていた馬場彦四郎。
「碁盤の首」と「真田太平記」の話が混ざり合うとなると、つまらないはずはない。
この話によって真田家に良い印象を幕府が早くも難癖をつけ始めたなと、晩年の信之の奮闘に思いを馳せることができる。
さらに草の者・お江が、真田昌幸・幸村がすでにいない本巻でも思わぬ活躍をし、以前印象に残っていた加藤清正の死についての話も再び持ち上がるものだから、これまで真田太平記を読んできた者にとってはたまらない。
ただ樋口角兵衛については、思わせぶりな行動に反して、期待していたほどの展開もなく、少々残念だった。
これまで長い時間をかけて読んできた真田太平記だが、読み終えるとなにやら寂しさを覚えた。
長編を読み終えた一種の達成感と、真田が生き残るための戦いを間近に感じながら読み進めてきたからだろう。
なんとなく松代へ向かう信之を見送る上田の領民達の気持ちになった……
池波氏はあとがきに、晩年の信之と幕府との闘いを描いた「錯乱」「獅子」の二編の小説との重複を避けたと述べている。
これらの小説はいわば真田太平記の締めくくり的な物語だが、先に読んだからと言って真田太平記がつまらなくなる訳ではない。
むしろ真田、特にあまり世間で語られていない信之について興味が増し、真田太平記を読まずにはいられなくなる。
だから真田太平記に興味があるが、長い話に二の足を踏んでいるという方は、晩年の真田信之と幕府の暗闘を描いた以下3つの小説を読むと真田太平記に手を出さずにいられなくなるだろう。
・錯乱乱(真田騒動-恩田木工-に収録)
・獅子の眠り(黒幕に収録)
・獅子
真田太平記 改版 第6巻 家康東下
2009/12/27 16:32
家康の策動、景勝の胎動、草の者の躍動が物語を動かす
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toku - この投稿者のレビュー一覧を見る
秀吉の死後、天下を手中にすべく動き始めた徳川家康に対して、上杉景勝が帰国後、軍備を整えはじめたところから、西と東に別れた大名たちが機先を制すべく争いを始めたところまでを描いている。
また真田太平記一巻の始まりで、高遠城からの劇的な脱出劇を演じた向井左平次の秘密や、じきに起きるであろう戦に供えて全国を駆け回る草の者を描いている。
この後起きるであろう大戦で、家康と三成の勝つ方に見方しようと考える日和見の大名たちの思惑が入り乱れ、そして関ヶ原の戦いへなだれ込んでいく様子は、なんとか家を守ろうとする大名の人間臭さが生々しく感じられた。
歴史の大きな流れをを描きつつ、真田や草の者たちの細かい動きが描かれているのも本書が面白いことの一つであるが、そのほかにも池波氏が気に入っていると思われる人物達(滝川三九郎一績や勇猛で一命を賭して戦う武士たち)が描かれることよって、面白さと戦の臨場感が増している。
また三成に味方する真田本家に現れた樋口角兵衛も、今後どのような運命を辿っていくのか楽しみにさせる。
真田太平記 改版 第4巻 甲賀問答
2009/12/27 16:30
朝鮮出兵の嫌戦感と悲壮感の裏で行われる忍びたちの壮絶な闘い
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toku - この投稿者のレビュー一覧を見る
秀吉の朝鮮出兵に備え、肥前・名護屋へ大名たちが集結を始めるところから、朝鮮上陸後、勝利を重ね続けるものの戦いに限りなく、やがて朝鮮水軍のまえに補給路が困難な状況になり、兵たちが朝鮮出兵が終息することへの思いを強く思い出すまでを描いている。
それと平行して、本巻の書題である忍びたちの活躍が濃厚の描かれている。
この先、天下にもう一波乱あると見た甲賀忍びの動きと、これを察知した真田の草の者たちの暗闘と脱出劇が一番の見所。
とにかく生き生きと動き回り、闘いを繰り広げる忍びたちに息をすることも忘れて読み耽ってしまう。
期待をしていた跡継ぎ鶴松の死と母・大政所の死によって躰と精神が蝕まれていく秀吉の姿と、無謀な朝鮮出兵により徐々に兵たちが疲弊していく状況が、大名たちの続けなければならない闘いへの悲壮感と嫌戦感を、生々しく描き出している。
伊豆守信幸の元を飛び出した鈴木右近の動向も描かれており、この後どのように真田家と交わっていくのか楽しみにさせ、徐々に真田昌幸・信幸・幸村の間に微妙な空気が漂いだしていることも、今後の真田家の行く末に想像を巡らせてしまう。
真田太平記 改版 第2巻 秘密
2009/12/26 13:38
真田昌幸の処世術が光り樋口角兵衛の狂気が真田家の騒動を予感させる
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toku - この投稿者のレビュー一覧を見る
信長の自刃後、一年経ったところから始まり、第一次上田合戦がいよいよ現実的なものになるところまでを描いている。
書題のとおり、本巻では真田家の秘密が一つのテーマとなっており、歴史の進行の他に女好きの昌幸が根因の家内騒動の様子が描かれている。
一時は落ち着くかに見えた真田家だったが、信長の死後、戦乱生き抜いていくため、上杉氏の東信濃への侵食に対して、北条氏と手を結びながらこれを押さえつつ、上田平(上田盆地)に城を築くことを決意する。
いよいよ北条氏は沼田を手中に収めるべく、徳川とのかねてからの和睦の条件であった沼田引き渡しを迫る。
秀吉との戦い(小牧・長久手の戦い)の間、真田と北条を互いに牽制させておこうと、のらりくらりと北条への返事をかわしていた家康は、いよいよ沼田を北条に渡すべしと真田へ通達する。
しかし昌幸は、沼田は自分たちが血と汗を流し勝ち取った地であるため、家康の命令を拒否した。
沼田を失っては、じわじわと追いつめられてしまうことが目に見えていた昌幸は、家康・北条との戦いを覚悟し、沼田引き渡しを拒否したが、真田のみで戦わなければいけない。
そこで昌幸が考えだしたことは、上杉への「見守って欲しい」という援助要請だった。
真田に散々苦汁の飲まされていた上杉景勝は、昌幸自らが春日山に出向いてくるのが筋、と返答してきた。
昌幸は、家臣が反対するのを聞き入れず、人質の源二郎(幸村)と共に春日山へ向かった……
本巻は、昌幸の女好きに起因する騒動、そして恐るべき力を備えた源二郎たちの従兄弟・樋口角兵衛の出奔などが見所で、徳川・北条・上杉の間を泳ぎ回る真田の綱渡りのような処世術も見所だ。
昌幸自身が春日山へ向かうところなどはハラハラし、景勝との関係には互いに潔さがあり爽快。
また、ある事件により、徳川との激突を回避できるかもしれない状況が生まれる。
史実通りではあるが、徳川との激突がありうる状況においてこの事を入れ込むことが、物語に起伏を与えるスパイスになっており、物語に引き込まれる一因となっている。
真田太平記 改版 第11巻 大坂夏の陣
2009/12/29 19:03
幸村の捨て身の突撃が家康を追いつめる
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toku - この投稿者のレビュー一覧を見る
大阪冬の陣は和睦が成ったが、徳川方によって内堀までも埋め立てられた大阪方が反発し、再び戦いが起きようとするところから、大阪夏の陣が終わり、徳川家が戦後処理を始めようとするあたりまでを描いている。
本巻の見どころは何と言っても、後半に描かれている大阪夏の陣での大阪方の凄まじい攻撃と真田幸村の家康本陣への突撃。
志気の低い上層部、そして全軍を束ねる総司令官がいない大阪方にもかかわらず、徳川方に手痛い打撃を加えた戦闘シーンには引き込まれた。
特に印象に残ったのは、戦いの中で真田昌幸の娘・於菊を妻にした滝川三九郎一積と義兄・真田幸村が出会った場面。
凄まじい赤備えの真田軍の突撃を描いている中で、家康を守るため真田兵と戦う滝川三九郎。そしてそこに現れた真田幸村。
この二人が出会い、槍をまみえていた間、周囲の争いのざわめきから隔離され、二人のみの世界で複雑な思いを抱きつつ闘う様子が目に浮かんできた。
その他にも、幸村と信之の対面、草の者と甲賀忍びの闘いなど、楽しめる場面が多い。
そして本巻の最後にある信之が家康に目通りする場面は印象に残る。
頬がげっそりとした家康が信之に言った『豆州。左衛門佐には手ひどい目に会うたわ』という言葉は、かなり重い。
この幸村への感想に、密度の高い思いが詰まっているように感じられた。
次の12巻はいよいよ真田太平記の最終巻。
夏の陣を前に行方を眩ました樋口角兵衛、樋口角兵衛とともに怪しい行動をする信之の侍臣・馬場彦四郎、夏の陣でバラバラになった草の者の今後、そして真田家への徳川家の今後の対応など、最終巻でどのような結末になるのか非常に楽しみだ。
また草の者へ怨念を燃やす甲賀忍び・迫小四郎の存在も気になる。
真田太平記 改版 第10巻 大坂入城
2009/12/29 19:02
九度山を抜け出た真田幸村の活躍が東軍を翻弄し、家康の攪乱が豊臣を手玉に取る
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toku - この投稿者のレビュー一覧を見る
片桐且元が大阪を離れたのをきっかけに東西が手切れとなり、真田幸村が大阪城へ入城するところから、開戦した大阪冬の陣が休戦となるところまでを描いている。
そして休戦協定における徳川のしたたかな戦いによって、大阪方が再び振り回され始める。
本巻のサブタイトルは「大阪入城」だが、幸村の大阪入城よりも大阪冬の陣が中心に描かれている。
前半は、家康の片桐且元を利用した豊臣家撹乱が功を奏し、且元が暗殺から逃げるように大阪を去ったのをきっかけに、家康が兵を挙げる。
その東西の手切れをいち早く掴んでいた幸村が、九度山を脱出し大阪入城するあたりまでを描いている。
その間、甲賀忍びの猫田与助がしぶとく登場するのだが、お江と猫田与助の闘いは思わぬことで幕を閉じる。
個人的にはこのあたりが一番印象に残った部分だった。
お江と猫田与助の闘いの終焉は読者にとっては残念な終わり方だが、それを池波氏に告げたら、きっと「作者冥利に尽きるが、どうしてもそういうことになってしまう」と言うことだろう。
これは池波氏のエッセイ「私の仕事(下)(日曜日の万年筆に収録)」を読むと分かる。
『登場人物達が生命を得、勝手に動き出し、その人物の過去や性格によってその結末が訪れた』ということらしい。
残る半分以降は大阪冬の陣の終始を描いており、この部分については大阪内の空回り感がというか、指示する側と戦う側の志気の隔たりが描かれている。
死に場所を得た牢人達の気勢は高かったが、反面、大野治長や淀の方などは秀頼と豊臣という「宝」を守ることばかりを考え、開戦を主張したものの志気は低く『うまい具合に和睦に持ち込めれば』ということを考えてしまっている矛盾が、読んでいてイライラしてしまう。
その中で、幸村による徳川方の作戦の裏をついた作戦と真田丸での活躍、それによって天下に轟くことになった武名、そしてこれまで幸村を相手にしていなかった大野治長の一変した態度にはスッキリ爽快な気分にさせられる。
幕府を開いた徳川家が天下をほぼ掌握して天下はまとまり始めた感があり、特にこれまで物語を盛り上げてくれた猫田与助とお江の闘いが終わってしまったので、なんとなく寂しく感じてしまう。
しかし樋口角兵衛の前9巻での行動と本巻の怪しい態度や、大阪夏の陣における幸村の活躍、そして戦後の真田家がどのように「獅子」など後年の真田家の物語に繋がっていくのかという楽しみもあり、まだまだ目が離せない。
ところで、本巻の中に「冬の陣・布陣図」が掲載されており、これは特に真田の動きを想像する上で、非常に役に立った。
真田太平記 改版 第9巻 二条城
2009/12/28 19:13
豊臣家滅亡阻止に奔走する者たちの死が大阪に暗雲をもたらす
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toku - この投稿者のレビュー一覧を見る
家康からの豊臣秀頼上洛の申し入れに対し、加藤清正や浅野幸長らが秀頼上洛に奔走するころから、豊臣家が再建した方広寺の梵鐘の銘に難癖をつけ始めた徳川と、大阪方の雲行きがいよいよ怪しくなってきたところまでを描いている。
中心に描かれているのは、家康と秀頼の二条城での対面であり、それを実現させようと奔走する加藤清正と浅野幸長、そして豊臣の将来にそなえて動く両名とその死がたっぷりと描かれている。
そしてとうとう出会ってしまった真田の草の者・お江らと甲賀忍び・猫田与助らの闘い、そしてお江と草の者弥五兵衛の決死の逃走劇も見所。
さらに九度山を出奔してした後、沼田に現れた樋口角兵衛の怪しい行動が、今後、真田家に対してどのような影響を及ぼすのか非常に気になる。
豊臣の将来を案じ東奔西走する加藤清正の死には「むむっ」と唸らせられる。
本書では加藤清正の毒殺説を採っており、それを誰が指示したのかは明確に描かれていないのが残念。
ただ毒を盛った者が甲賀山中忍びなので、指示の元が「徳川家の誰か」が指示したのだと想像できる。
また清正と共に秀頼と家康の対面に骨を折った、浅野幸長の突然の死は清正の死因を想起させた。(特にその死について触れられていない)
真田昌幸や加藤清正始め次々と豊臣家のために働く大名がいなくなり、家康の揺さぶりに、怒り、戸惑い右往左往する豊臣の者たちを見ていると、もう少し何とかならなかったものかと、少々イライラしてしまった。
特に片桐且元の振り回されっぷりは、豊臣家にとっていかにも頼りないが、豊臣家と徳川家との交渉役として且元を任命したのが家康だから、且元の性格を見抜き、豊臣家を徐々に追いつめいていくために利用したのだろう。
淀の方や大野治長などの側近達は秀頼を「宝」としてしまい、持ち腐れてしまったのが残念だ。
ところで本巻で登場する馬場彦四郎と、真田太平記の個性的な登場人物の一人・樋口角兵衛について、彼らを主人公とした池波氏の短編小説がある。
●馬場彦四郎「碁盤の首(真田騒動-恩田木工-に収録)」
本巻で囲碁を好み、小川治郎右衛門の碁敵であり、勝負への執着が異常に激しい人物として描かれているが、「碁盤の首」ではその人物像にクローズアップした物語が描かれている。(この小説では馬場主水となっている)
●樋口角兵衛「角兵衛狂乱図(あばれ狼に収録)」
真田昌幸の血を引きながら、幸村・信幸の従兄弟として育った恐るべき力をもつ樋口角兵衛の物語
昌幸の義妹である角兵衛の母の罪が、角兵衛の生涯を翻弄していく様子を描いている。
真田太平記 改版 第7巻 関ケ原
2009/12/28 19:12
草の者の家康暗殺に白熱し、日和見大名が大戦を揺るがし、清廉の武士が敗者を敬う
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:toku - この投稿者のレビュー一覧を見る
西へとって返す東軍の先発隊が岐阜城を落とした報を聞き、家康が江戸を発して西上を決意するところから、関ヶ原の合戦の決着がつき敗戦の将たちの処分を行われるあたりまでを描いている。
また甲賀忍び・猫田与助が、真田の草の者・お江に異常なまでの怨念を感じている理由が明らかにされている。
関ヶ原の戦いを目前にして、真田の草の者が家康の命のみ集中して狙うシーンは、大群がぶつかり合い、勝敗のみに目がいきがちな合戦の中にあって、命を狙い狙われる緊張感がひしひしと伝わってくる。
真田昌幸・幸村父子が徳川秀忠率いる第二軍を上田で足止めする有名な場面もあり、こちらも白熱が伝わる。
中心的に書かれている関ヶ原の合戦では、東西勝つ方に味方しようと、戦いが始まった後も日和見している大名達など自分の保身に走る『卑怯な』武士達が醜く描かれている一方、清廉の武士たちが対照的に気持ちよく描かれている。
特に、戦後、福島正則の家来と八丈島に流された宇喜多秀家との話や、真田信幸の岳父・本田忠勝が真田昌幸・幸村の助命を願うシーンは、敵味方、勝敗を越えて相手を敬う好意が気持ちよい。
少々残念だったのが、西上する徳川を追撃しなかった上杉の様子が描かれていないこと。
藤沢周平著「密謀」のように上杉内の様子が描かれていると面白かったのだが。
しかし状況説明はされている。関ヶ原の決戦が終わったあとも、結城秀康、伊達政宗、最上義光らと戦闘していたため、家康が西上をはじめた時機に追撃をはじめれば、背後から最上、伊達が上杉領に侵入してくる心配があったこと。そしてこの頃から上杉景勝は直江兼続との呼吸が合わなくなったと書かれている。
結局、西上する徳川を追撃するには『最上、伊達の侵入を許してでも』という一か八かだったのだろう。
ところで作中で池波氏は、直江兼続について世間で評されているほど兼続を買っていないと語っている。
その理由は書かれていないが、その前に述べられている『直江兼続も石田三成も「一か八か……」の激烈な闘志に揺り動かされてい、大局を看ることができなかった』という部分から、その言わんとしていることが窺える気がする。
真田太平記 改版 第12巻 雲の峰
2017/09/10 23:26
真田信之こそが一番たいした人物であったのではないかと思わせられた、『真田太平記』の最終巻
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みなとかずあき - この投稿者のレビュー一覧を見る
真田昌幸・信之・幸村を中心とした長い物語が終わりを迎えました。
これまで真田というと幸村や、架空の話としての真田十勇士くらいしか知らなかったので、この『真田太平記』もなんとなく大坂の冬・夏の陣で終わりだみたいなつもりでいました。なので、この第12巻は後日譚のようなつもりで読んでいましたが、読み終えてみれば全然そんなことはなく、一人残された信之がいかにして、武力とはまた違った形で徳川とやりあって、真田家を残そうとしたのかという非常に重要な話が続いているのだと思えてきましたし、池波正太郎はこの最後のところこそ書きたかったところなのではないかとも思えてきました。
しかも、そこに草の者・お江が尚活躍する話も盛り込まれており、こちらも池波正太郎が書いておきたかったところなのかと思えてしまいます。
長い話であり、読み終えてしまうのが勿体ない気分にもなってしまいましたが、読み終えてみると本当に壮大な話であり、そうでありながら数え切れないほど登場してきた人物たち一人一人が真田一族に劣らず活躍した話が丁寧に書かれていたのだということに圧倒されながら、どことなく爽やかな気分にさせられました。
でも、確かに勿体ないところはあるので、池波の他の真田ものもこの際読んでみようと思えてなりません。
真田太平記 改版 第4巻 甲賀問答
2017/03/19 00:11
秀吉の朝鮮出兵を表として、草の者たちの暗躍がむしろメインに描かれている4巻目
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みなとかずあき - この投稿者のレビュー一覧を見る
『真田太平記』の面白いところは、真田昌幸・信幸・幸村親子を中心とした真田一族が戦国時代末・安土桃山時代・江戸時代初めにいかにして活躍したかを描いているだけでなく、その背後に「草の者」と称される歴史の表舞台に出てこなかった者たちの暗躍が描かれているところだと思いながら、読み進めてきたところですが、この4巻目はその「草の者」そのものがもっぱら描かれているのがすごいです。
むしろ真田一族が脇役となり、「草の者」たちが主役であるかのように、巻頭から数十ページにわたって甲賀一族の頭領同士のやりとりが続きます。ここがまたすごいのですが、豊臣秀吉が権勢を振るっている最中に、その先を見越して動きを始めようとする「草の者」の見識が十二分に描かれています。
さらに、そのあとには「草の者」の生き様とでも言えるような、田子庄左衛門が真田の草の者・お江を救う顛末が描かれており、これもまた読み応えがあります。
大きな歴史の流れとしては、秀吉が天下統一を果たす一方、その先が不透明となりつつ朝鮮出兵を企んでいくところが描かれています。上で書いたように、真田一族は脇役に押しやられたような感じで、そのあたりは淡々と描かれています。それでも、信幸・幸村兄弟がそれぞれの道を歩み始めたり、幸村が大谷義継の娘を娶ったりという、今後につながっていくエピソードも盛り込まれており、すぐ5巻目を手に取りたくなってしまうのです。
真田太平記 改版 第1巻 天魔の夏
2017/01/26 23:02
長い物語の始まりは、武田家の滅亡から
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みなとかずあき - この投稿者のレビュー一覧を見る
1974年から1982年に雑誌『週刊朝日』に連載された大長編小説。
言わずと知れた真田一族、特に真田幸村として知られる真田信繁とその兄信之、二人の父親昌幸の話である。
が、この物語の最初数十ページにこの三人は登場しない。
真田はいつ出てくるのだ、いつなのだと思いながら読み進めるのだが、これがまた読めてしまうのだ。そこが池波正太郎の面白さなのだろう。
長い物語の始まりは、武田家の滅亡から語られる。武田家が滅びたことによって、真田一族がどこへ向かっていくのか、何を目指していくのか、真田昌幸の行動がメインではあるが、そこに信之、信繁がところどころ姿を見せる。そこがまた長い物語の始まりにふさわしく思えてしまう。
そこに、忍びの者たちの話が絡まっていくのだから、ついつい読み進んでしまうわけだ。
この第1巻は武田家の滅亡から本能寺の変までが書かれている。
特に本能寺の変はいくらかあっさりと書かれているように思える。京都から離れた上州・信州の真田一族が知る本能寺の変はこんな感じだったのかと思わせるものだ。
ちなみに、私の読んだのは1988年に刊行された新潮文庫版の初版です。