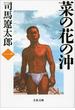菜の花の沖 みんなのレビュー
- 司馬遼太郎
- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
| 12 件中 1 件~ 12 件を表示 |
菜の花の沖 新装版 2
2016/09/18 17:43
主人公が船乗りとして、また船主として、大いに名を挙げる快挙に拍手を送りたくなる。頑張れ嘉兵衛!
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:大阪の北国ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
本当に面白い本だった。
菜の花の沖 第2巻は、兵庫の湊の豪家北風家の描写から始まる。この時代の物品集散の大中心地大坂が近過ぎるため、船もモノもヒトも通過してしまう「兵庫」に活力を与えるため、北風家当主が、縁があろうがなかろうが、やってくる全ての「船員」に、風呂も食事も宿泊も無料で厚くもてなすさまを描く。それによって、少々の荷物であっても兵庫に流れ、商いの場所となり賑わいを生むとともに、集まってくる船員同士の操船技術や航海情報などの情報交換の場ともなり、また商品相場や航路沿岸の情報集積の場ともなった。何やら今日の商工会議所活動の数段先をゆく活動とも思え、商売繁盛の原点を教えられた思いがした。
続いて江戸に清酒を届ける樽廻船で一番乗りを果たして名を挙げた主人公嘉兵衛の、北風家デビューの場面へと続くが、この北風家との接点が後に嘉兵衛が船を持つ重要な契機となる。次に嘉兵衛は、紀州藩銘木12本を筏に組み、弟たちとともに無謀にも真冬に江戸まで波と潮にのっていくという快挙を遂げ、益々名を挙げる。
そして滞在していた江戸で、船を手にできるとの情報を得る。その船で荷を運んだ秋田での「船大工棟梁」との出会いが、自分の巨大船、千五百石船建造へと繋がっていくが、数々の冒険譚の合間合間に、司馬さんらしく木綿の大衆化の歴史と北前船によるその肥料の運搬、酒田など寄港地の賑わいの風景などが「街道をゆく」さながらに描かれる。また司馬さん独自の「日本人の気質や村社会文化の特性」、「商人からみた武家社会の非合理性」への考察も展開され、読んでいて飽きさせない。それにしても作家である司馬さんが、和船、唐船、オランダ船などの船の構造と耐久性、その進化について、これほど深く極められたことに敬服せざるを得ない。また脱帽させられた。
物語は商売と船建造資金、船員育成への人材援助を求めて、若い頃村八分にされた故郷へと戻っていく。そこで思わぬ吉報が待っていた。
次の第3巻が楽しみであるとともに、6巻本の この第2巻だけでも一編の歴史小説、商売の極意に触れられるビジネス書としても充分楽しめるたいへん内容の濃い一冊であった。
菜の花の沖 新装版 6
2014/02/09 18:11
外交官 高田屋
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:やびー - この投稿者のレビュー一覧を見る
ロシア船に拿捕された、嘉兵衛は遠くカムチャッカの地へと幽閉される身となる。
もちろん、拉致をされた経験も無く自らの生殺与奪の権利を他者に委ねる経験も無い私には、いつ殺されるのか?という環境に身を置く事はこうも生きる意欲を奪うものなのかと、息を呑む気持ちで読み進めました。
幽閉中に嘉兵衛は国家の存立とはどうあるべきかと言う中で…
他を謗らず、自ら誉めず世界同様に治まり候国は上国と心得候(意味:上等の国とは他国の悪口を言わずまた自国の自慢をせず、世界の国々とおだやかに仲間を組んで自国の分の中におさまっているくにを言う。)と、語ります。
この台詞は今の日本人の耳にどう聞こえるでしょうか?
リコルドと嘉兵衛は言葉が通じ無いながらも交流を得ながら、互いに礼を持って接する事で信を得て行きます。国家間の問題をどう解決するのか?信頼を担保に置ける事が交渉をこうも感動的に彩れるのかと胸を熱くします。
現代の東アジアを取り巻く環境を補助線に読み進めると考えさせられました。
菜の花の沖 新装版 4
2017/01/09 18:10
司馬先生が惚れこんで、書きたかった主人公の人物像を実感できる、内容の濃い巻でした
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:大阪の北国ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
択捉島での活躍の幕が上がる。
本巻の冒頭に嘉兵衛は高田屋箱館支店を任せた金兵衛に「決して金儲けと思うな。たかが金儲けで、上方と蝦夷地を往復するという命がけのしごとがつづけられるものではない。蝦夷地を、京のある山城国や江戸のある武蔵国とおなじ暮らしができる土地にするためだ。」という。
また巻末に近く、択捉の蝦夷びとに漁法・加工法を教えたあと、これまでの為政者 松前藩は住民の幸せなど一顧だにしなかったのに対して「人の一生は、息災に働くことにあるのだ。息災のためには、住む場所、着るもの、食べるものが大切だ。エトロフ島を蝦夷第一等のよい処にしよう。」「今年の冬はひもじくないぞ。腹いっぱい食べて、温かい寝床に寝て、丈夫な子を生むのだ。」という。
住民である蝦夷びとから見ると(彼らのカミは大自然とそこにおわす大いなる意志であっても、また嘉兵衛が以上のセリフを実際に云ったかはさておき)「まさに神が目の前に現れた」という心境ではなかったかと想像する。
現代の云い方をすると、一介の“流通商人”である高田屋嘉兵衛という人物の生き方を通して、われわれ一般市民は「そんなこと(=住民の福利厚生の充実)は政治の責任だ」という言い訳しかしていない、言い換えれば思考停止している怠惰さに対して、司馬先生の大いなる叱責の声さえ響いてくると思える。
横道にそれたが、物語はいよいよ北方最前線の東蝦夷地・択捉島開発に関して、最上徳内・近藤重蔵・伊能忠敬などというお歴々が登場し、嘉兵衛が自身は望まないながらも大公儀定雇船頭に出世。官船並びに自分の船8隻を同時に建造し、北の海をめざすところで巻をとじる。本巻では北方での主人公の活躍の前奏曲を堪能した。 巨大な金額を投資することばかりに人目が集まる現代においても、その投資に如何ほどの地球レベルの福利厚生意欲が盛り込まれているのかも考えてみたいと感じるところである。
正月を迎えると、間もなく菜の花の季節がくる。司馬先生の旧居に、今年もまた菜の花を拝見にお邪魔しようかと思っている。
菜の花の沖 新装版 3
2016/12/11 17:40
一人の船頭の目を通して見た北方史の物語が幕を開ける。正義感の強い主人公の立ち回りが痛快。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:大阪の北国ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
いよいよ嘉兵衛の兄弟たちが結集し「高田屋」の旗揚げとなる。
待望の北前船「辰悦丸」が竣工し、嘉兵衛が船頭となり松前に向けて出航する。
司馬先生による松前藩史も展開されるが、それはこれほど無能で私腹を肥やすことだけに専念し、「住民のための政治姿勢」を微塵も感じさせない呆れた支配層も珍しいと云うトーンで語られていく。極端な秘密主義を貫いたのは、幕府からの搾取を恐れたかららしいが、自らは搾取のし放題という驚くべき藩である。しかも搾取の対象が謙虚で礼儀正しいアイヌだというから恐れ入る。所謂弱いものイジメである。われわれも昭和の世になってからの近現代にも周辺諸国に似たようなことをしていたのではないかと謙虚に振り返らないといけないと考えるものである。
さて、正義感の強い嘉兵衛は、その松前藩の下級武士たちとの諍い、小競り合いを起こしながらも、最上徳内、三橋藤右衛門という人情味溢れる幕臣達と出会っていく。いよいよ北の海を駆け回る嘉兵衛の生涯を懸けたドラマの幕開けだ。
北方でのロシアとの接触や国防、また日本人の起源を知る上でも、「オホーツクから樺太・シベリアと日本の関わり合い」は日本人として知っておかなければならない大変重要なテーマだと考えるが、歴史教科書では幕末から維新の数十年の出来事として数行の記述しかないのは、教科書執筆者達の勉強もしくは見識が足りないのではないかと思わざるを得ない。少しは本編や「ロシアについて」などの司馬先生の本を入口として、自らの研鑽を積まれんことを期待するものである。
菜の花の沖 新装版 1
2016/07/17 18:45
人間くさい、素晴らしい歴史小説です。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:大阪の北国ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
いつもは『街道をゆく』を読んでhontoのレビューに投稿していますが、司馬さんの長編小説は長過ぎる気がして、今まで中々手が出ませんでした。今回北海道ものを読みたくて、初めて『菜の花の沖』を読み始めましたが、一巻も終わりに近づいたとき「えっ、もう終わりなの」と感じたほどの面白さでした。読む前は、商人の生涯なんて、どれほど偉大に描けるのだろうかと斜めにみていたのですが、さすが司馬さんが選んで採り上げる主人公は「人間くさく、大きいなあ」という印象です。
『街道をゆく』は、「沿道の風景プラス歴史や風俗の蘊蓄」という構造が面白く、読者を飽きさせませんが、この本はその「沿道の風景」が「嘉兵衛の生きざま」に置き代わって同じように展開されていきます。例えばこの第一巻では「蘊蓄」の部分が、
1.阪神地域での水車を利用した搾油業とその製品輸送業の発展
2.対岸の淡路島における搾油原料「菜の花」栽培の起源
3.当時の若者集団の組織である「若衆宿」の風俗やポリネシア等の南島文化と日本文化との関連
4.徳川幕府の海運・船舶政策と船舶の構造
などとして説明され、単なる主人公の人生のみが語られるだけの薄い小説とは違い、読み飛ばさずに真面目に読むと「勉強になる」というような深みが感じられます。
嘉兵衛が少年期に遭遇した貧困や村八分などのつらい体験にも、読者がつい引き込まれ感情移入してしまう、人間くさい描き方がまた司馬さんの特技だと思います。
嘉兵衛が生きた淡路島から兵庫、大坂などの風景は、今と重なる身近な地形や町の習俗が描かれており大変面白く、夢中になって読み進めました。これなら「六巻まで行けそう」という感覚です。司馬さん、面白い小説をありがとう。
菜の花の沖 新装版 5
2014/02/03 23:15
ロシアとの対峙からみる現代
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:やびー - この投稿者のレビュー一覧を見る
この巻では、高田屋として独立した嘉兵衛が、蝦夷地に生活基盤を置き着実に北方の復興を図りつつ、その成功とは裏腹に、ロシアの強行的な外交政策に裏付けされた圧力が日本を北方より押し迫り、嘉兵衛の未来を不確かな物へと押し流して行きます。
舞台は日本とロシアの外交へとシフトし、初期のような、青春活劇は失われて行きます。人生を謳歌する時期を鮮やかに描きつつ、経営の成長を加味しながらロシアという外圧を、緊張感を保ちつつ躍動感を失わない表現力。
司馬氏の知識に裏付けされた文体は嘉兵衛の成長に伴う慎重な判断を示しつつ、ページをめくるスピードは更に速まります。
嘉兵衛の成熟と躍動感の対比における文脈の衰えを一切見せない所は流石の一言に尽きます。
実際には、この巻で氏の得意とする、「余話として…」に始まるロシアの歴史や民族の成り立ち。思想や観念論まで、司馬氏の考察が巡らされ、ストーリーが中々進まず、読み進めるのが苦しいと感じる読者もいると思います。
現代でも通じると思いますが、イニシアチブを握る上で、或る国との外交や歴史を俯瞰的に比較し互いの国家感を認識しあう際には我が国の内情だけでなく相手国の歴史、文化、思想や哲学。信仰心や国家の欲望を捉えて初めて相手の意図を掴み交渉の糸口を掴む「インテリジェンス」が必要なのでは無いでしょうか?
近世末期の江戸、日本から見るロシアへの評価として、不凍港の確保といった大それた物では無いと思います。
食料や水の提供、薪等のエネルギーの手配など、交易に置ける「交換」を主体に置いた国家のコミュニケーションの確保としての必要性に鈍感な回答を示し得ない行動に対する反作用が今回の事件の真相であったと氏は読み解く。
「それ(反作用?)」はやがて、帝国主義的侵略の一端として遥か遠く日露戦争へと続き、果ては、ノモンハンに辿り着く伏線ではないでしょうか?
司馬史観と巷で言われる、「昭和は魔法の杖でおかしくなり、大日本帝国は侵略国家に変わり果てた末路がかの敗戦であった」と、戦後(現代)知識人は未だにメディアで繰り返す。その事に対する明確な回答を未だ日本人は示せない…。
佐藤優氏は「ロシア事情を司馬作品だけで理解してないけない」と警鐘をならしますが、ロシアを理解する入口にこの作品から入るのも良いのではないでしょうか?
菜の花の沖 新装版 1
2001/03/14 15:52
マーケティングの基礎講座
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:すみのえ - この投稿者のレビュー一覧を見る
極貧のいじめられっ子が全国を舞台とする商人になっていくサクセスストーリー。淡路島から物語がスタートし、北海道の美しく厳しい自然と人々の交流がこまやかに描かれています。
農本社会の日本人が貨幣経済の隆盛を迎えるということはどういう事なのか。ルネッサンスが商都フィレンツェの繁栄を土台とするように、商売は人間に構想力と認識力を身に付かせ、新しいものを創造することを可能にします。ペリー来航から半世紀程度前が舞台ですが、明治維新を展開するパワーがどのような土壌からでてきたかを知ることができます。
外資系超大手流通の上陸に脅威を持ってる方、あわてる前にまずこの作品を読みましょう。外国人との付き合い方や、商売の基本である商品政策、顧客満足から得られる「信用」についてまで幅広く学べますのでマーケティングの教科書としてもお勧めします。
菜の花の沖 新装版 6
2021/12/30 19:16
楽しめました。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Kanye - この投稿者のレビュー一覧を見る
司馬遼太郎の作品が好きで,よく読むのですが,この作品はいまひとつ入り込めませんでした。どこかで,司馬さんが会ってみたい人に主人公をあげていらっしゃったので,かなり期待して読み始めたのが原因かも知れません。それでも楽しい時間でした。
菜の花の沖 新装版 1
2017/02/27 13:00
若き嘉兵衛
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たはりゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
若き嘉兵衛のハラハラドキドキの展開。次巻が気になる一冊です。
菜の花の沖 新装版 1
2015/05/08 03:37
異色の経済小説
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
司馬遼太郎の作品のなかでは、珍しく商人が主人公だ。江戸時代の廻船商人高田屋嘉兵衛を通して造船技術やマーケティング論、当時のゴローニンなど政治的な事件にもふれている。作者の引き出しの広さには驚かされる。2月12日の命日は著者が好きだった花の名前にちなんで「菜の花忌」だ。このころに、こんな一冊を読むのもいいかもしれない。
菜の花の沖 新装版 1
2001/12/12 00:06
和船の性能は悪くないのだ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しっぽ - この投稿者のレビュー一覧を見る
主人公は淡路島で生まれて兵庫に出て、船の水夫から船頭になり、ついには商人として蝦夷地との貿易に乗り出した高田屋嘉兵衛という男。この人、最後にはロシアの船につかまって、ロシアと日本の外交上の掛け橋にさえなろうとした人です。
こいつもぼくが好きな「帆船もの」ではありますが、ちょっとだけ毛色が変わっています。ここに登場してくる船は、いわゆる「和船」です。なんていうんだろう、「帆掛け船」みたいなイメージのやつかな。マストが一本しかなくて、でっかい帆が一枚ついててっていうあれです。七福神の乗ってる宝船みたいなやつね。
西洋の帆船と比べると、和船は性能が悪いというのが通説なんだけど、じつはそれは、徳川家康が船の建造を制限したからなんですね。船の大きさも上限を決めて、マストの本数も一本と限定されてたらしい。その制限の中でいろいろ工夫を重ねてたどり着いたのが、ああいう船だったということらしい。
が、しかし、昨年、大阪市が博物館に展示するために江戸時代当時の和船の忠実なレプリカを造ったところ、せっかく造ったんだから試しに走らせてみては、と話が盛り上がってしまい、実際に大阪湾でなんどか帆走実験をするという楽しいことになってしまったらしい。ぼくは直接は参加していないけど、実際にその実験で航海した人によると、和船も意外とよく走るらしい。ただ、操船自体はけっこう大変みたい。風が安定している時はいいけど、細かく風が変わるようなコンディションだと、帆がでかいぶん調整が大変だし、なおかつきちんと調整しないとうまく走らないような気がするとおっしゃっていました。あっ、なんか、本の話じゃなくてただの船の話になってる。
物語としてもとても面白いと思います。武士の視点からではなく、商人という、江戸時代の身分階級の中では下に見られていた社会の、その中でも異端の廻船問屋という立場からの、時代や社会に対するとらえかたが面白い。幕府による武士の支配が世の中の末端からきしみだしていくような感覚がある。そういう視点から歴史を見るのもなかなかに面白いですよ。
2025/02/16 18:58
嘉兵衛
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みみりん - この投稿者のレビュー一覧を見る
司馬遼太郎さんの長編です。
江戸後期の高田屋嘉兵衛という人についての話らしい。
そんな人は全然知らなかったので、だれそれ!?から始まった。
| 12 件中 1 件~ 12 件を表示 |