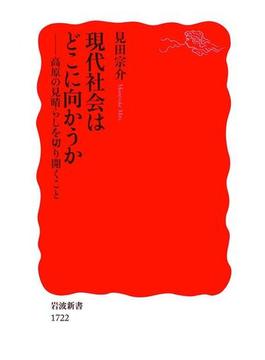ロジ曲線の第III段階について「高原からの見晴らし」と記述するセンスはやはりさすがの一語
2022/08/20 13:12
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Haserumio - この投稿者のレビュー一覧を見る
世界を変革しなければ地球が立ちゆかなくなるという真摯な問題意識に支えられた世界変革のための「見田総論」。「人間の歴史の第IIIの局面である高原」(91頁)、すなわち、ある種ピダハン的な境地(詳細につき三章参照)を如何に実現するか。その方法論も末尾に示される。一語一語の奥に深い思索と検証の迫力を感じさせる記述が続くが、内容はわかりやすい。読後は、自らの視界がさっと開けたかのような爽快感。人間やはり志と理想が大事であることを、改めて感得。
「『存在と無』においてサルトルは、わたしたちの「所有」というコンセプトを、偏狭なホモ・エコノミクス的「所有」の観念から解き放っている。サルトルが挙げている例は、認識による世界の所有、愛撫による女体の所有、滑走による雪原の所有、登頂による風光の所有、であった。」(100頁)
(ロジスティック曲線は)「一定の環境条件下での生物種の消長を示す」ものであり、「ある時期での急激な、時に爆発的な増殖という局面と、環境容量の限界に接近した後の、増殖の停止、安定平衡の局面への移行とが示されている。」(114頁)
「「危機をむりやりに突破しようとする行動自体が、新しい危機を誘発する他はない」という、本格的な危機のループの中に、現代社会はあるということである。」(121頁、社会変革は着実かつ自発的なものでなければならない!)
「これ以上の経済成長の問題ではなく、分配の問題である。分配の問題を根本的に変革しないで、いくら経済成長をつづけても、富はそれ以上の富の不要な富裕層にぜい肉のように蓄積されるだけで、貧しい人びとは、いつまでたっても貧しいままである。計算してみれば分かることだが、日本を含む先進産業諸社会においては、まずすべての人びとに、幸福のための最低限の物質的な基本条件を配分しても、なお多大な富の余裕は存在している。この巨大な余裕部分にかんしては、経済ゲームの好きな人たちは、いくらでもシェアを争って、自由な競争をしたらいいとわたしは考えている。」(129頁)
「紀元前六〇〇年から〇年までの、人間史の第一の巨大な曲がり角である<軸の時代>の転回が六百年を要したように、第二の巨大な曲がり角もまた、六百年を要するだろう。少なくとも、百年を要するだろう。」(131頁)
「貨幣はおそらく、神と国家の中間に定位している。」(132~3頁)
「展開の基軸となるのは、幸福感受性の奪還である。再生である。感性と欲望の開放である。存在するものの輝きと、存在することの祝福に対する感動能力の開放である。」(135頁)
「依拠されるべき核心は、解き放たれるべき本質は、人間という存在の核に充填されている、<欲望の相乗性>である。人によろこばれることが人のよろこびであるという、人間の欲望の構造である。」(141頁)
「新しい世界の胚芽となるすてきな集団、すてきな関係のネットワークを、さまざまな場所で、さまざまな仕方で、いたるところに発芽させ、増殖し、ゆるやかに連合する、ということである。・・・ 自分の周囲に小さいすてきな集団やネットワークが胚芽としてつくられたその時にすでに、それだけの境域において、革命は実現しているのである。」(155~8頁、着実な連鎖反応による「一〇〇年で一〇〇億人」(157頁、10の十乗ですね)のネットワークの完成!)
なお、119頁の「環境機器」は「環境危機」の、134頁の「発生機」は「発生期」、同じく「初機」は「初期」の誤植であろう(当方読了版による、それとも後二者は著者の用語法?)。それにしても、最近の本は本当に誤植が多くなった、日本における国語力の低下がよく分かる。
山口周『ビジネスの未来』の元ネタ
2021/04/01 15:04
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:レノボ - この投稿者のレビュー一覧を見る
山口周『ビジネスの未来』を読んで本書を知ったが、ほとんどそのまま用いている箇所多数。読み比べてみると面白い。
とはいえ両者の違いは、本書は「ビジネス」の領域に限った話ではないこと、「未来」に「目的」を置いて書かれた本ではないことだと思う。
最終章の最後から引用↓
「自分の周囲に小さいすてきな集団やネットワークが胚芽としてつくられたその時にすでに、それだけの境域において、革命は実現しているのである」
明快な理論が読みやすく書かれている
2018/08/20 09:34
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:oo - この投稿者のレビュー一覧を見る
説得的なデータに基づいて論理展開されている貴重な一冊だった。
現代社会を大きな歴史的視点でつかみながら、現時点で取り組むべき方策を具体的にきちんと書いている。
新鮮な切り口で今の時代、人々が本当に必要な理論を提供している。
著者の偉大さを感じた。
私は20代後半だが、環境を守らなければいけないという感覚や、消費主義への反発(いわゆるさとり世代?)といった感覚を、言葉に落としてもらって自分自身の理解にもつながった。中学校~大学の授業でも是非扱ってほしいと思った。
副題の「高原の見晴らしを切り開くこと」がすばらしい
2024/06/14 22:25
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:まなしお - この投稿者のレビュー一覧を見る
副題の「高原の見晴らしを切り開くこと」がすばらしい。内容も分かりやすく、よく理解できたと思う。
投稿元:
レビューを見る
『現代社会はどこに向かうか』見田宗介
見田宗介さんの『現代社会の理論』は、消費社会の仕組みをわかりやすく、取り出してれる感銘を受けた本だった。
今回の著書は、2000年以降を描こうとしたようだけど、正直、ロスジェネ世代、団塊ジュニアのわたしには、言い尽くされたことばかりに思えた。
見田さんは1937年生まれ、団塊世代より上の世代だ。その世代にとって、この現状が事件なのかもしれない。でも、われらにとっては当たり前だし、それをメタな視点で解説してくれるわけでもなかった。自分自身や同世代に伝えようとしているのかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
「幻の社会学者」見田宗介の最新の書。脱成長時代には「貨幣経済に依存しない幸福の領域の拡大」が生じ、さらに「必要な以上の富を追求し、所有し、誇示する人間がふつうにけいべつされるだけ」の社会がいずれ来るだろうと言う。率直な感想を言わせてもらえば、著者の見方はあまりに楽観的だと思う。「すべての人に、幸福のための最低限の物質的な条件を、まず確保する」ことから、また富の誇示が軽蔑される社会から、今の日本は遠ざかるような方向へ走っているように見える。むしろ若い世代としては、経済的な安定を得られる層がどんどん縮小し、人々ー特に高学歴の人々が少ない「勝ち組」に入るための椅子取りゲームに明け暮れ、視野狭窄に陥っていくのではないかという危機感がある。シンプル志向だってそんなに簡単なものではない。マクロな視点では著者の言うことが間違っているとは思わないが、ミクロに見ていくと、話は全く違うはず。本書ではそのバランスが取れていないと感じた。
投稿元:
レビューを見る
見田宗介氏(1937年~)は、現代社会論、比較社会学を専攻する社会学者。真木悠介の筆名でも多数の著書がある。東大の著者のゼミは抜群の人気を誇り、その出身者には、大澤真幸、宮台真司、小熊英二、上田紀行といった、現代日本を代表する思想家・社会学者がいるのだという。
本書は、初出2011年の序章のほか、いくつかの著作、学会やシンポジウムでの講演内容に加え、本書のための書下ろしをまとめたものである。私はこれまで見田氏(真木氏)の著作に縁がなかったのだが、本書の題名と上述のような構成から、著者のこれまでの論考のエッセンスがまとめられたもの、即ち「集大成」と考え、手に取った。
本書の論旨は以下のように明快である。
◆人間は、地球という有限な環境下に生きる限り、生物学でいう「ロジスティック曲線」から逃れることはできない。人間はこれまで、原始社会<定常期>から、カール・ヤスパースのいう「軸の時代」(古代ギリシャで哲学が生まれ、仏教や儒教が生まれ、キリスト教の基となる古代ユダヤ教の目覚ましい発展があった時代)<過渡期>を経て、文明化による人口増加<爆発期>を経験してきたが、近代はその<爆発期>の最終局面だったのであり、現代はその後に訪れる<過渡期>、即ち未来社会<定常期>への入り口にある。
◆それは、人間は、「軸の時代」以降、貨幣経済と都市社会の勃興を前に、世界の“無限性”を生きる思想を追求し確立してきた(その究極の姿が資本主義であろう)が、現代において、グローバル化が極限まで進み、環境的にも資源的にも、人間の生きる世界の“有限性”を生きる思想を確立しなければならなくなった、ということである。
◆そして、その思想とは、経済成長を追求しない、生きることの目的を未来に求めない、他者との交歓と自然との交感によって「生のリアリティ」を取り戻すことである。
◆その思想は、シンプル化、ナチュラル化、素朴化、ボーダーレス化、シェア化、脱商品化、脱市場経済化という現象として現れつつあり、価値観調査における若い世代の幸福感の増大のような結果も併せると、新たな世界が広がりつつあると言えるのかも知れない。
これは社会学者・広井良典氏のいう「定常型社会」と共通するものであるが、私はこの思想に深く共感を覚えるし、人類の進むべき方向はこれしかないと考えている。しかし、現実に目を転じると、政治家は「一億総活躍社会」などとぶち上げて「経済成長」を錦の御旗にし、少なからぬ人々が「経済成長」の呪縛に捉われたままである。現在の課題と進むべき方向が明らかな今、どのようにしてそれを実現するのかにこそ、人類は知恵を絞る必要があるのだと思う。我々に残された時間は多くはない。
(2018年9月了)
投稿元:
レビューを見る
よくわからない部分が多く、精読を重ねればよいかもしれないが、たぶんそうはしないだろう。岩波新書には、老眼に優しい校正になっているものがあり、ワイド版を作成する必要はないものがあるが、本書もその一つ。知的なものはさておき、単純なコストパフォーマンスの面では、物足りない。
投稿元:
レビューを見る
希望を伝えたい意志はよくわかる。ヨーロッパと日本の若者が現状を「幸せと考えている」こともよいことだろう。しかしそれは未来へ向けた希望のありかなのだろうか。現代が歴史上の大きな変曲点であることは水野和夫も指摘しているとおりだろう。ではこの現在の「幸せな現在を全世界に広げること」をどのように現実化させるのだろうか。その回答が胚芽を作るでは私はリアリティを持てない。野本三吉の「福祉は衝動だ」との言葉が胸に刺さった。
投稿元:
レビューを見る
エッセイを集めたようなもので、これといって心に響くものがなかったのは残念。いろいろな投稿からあつめたものなので仕方がないかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
コンサマトリー(consummatory)知らなかった。ショック。いまのいままで、このことばを知らなかった。ネットでパラパラ調べてみると、社会学ではよく使われているようだ。いや、絶対どこかで読んでいるはずなのだけれど、意識にのぼっていなかったのか。定訳はないらしいが、自己充足的と訳されているものもある。要するに、何かのためにする(インスツルメンタルinsturmental、手段的、何か目的があってそのためにいまの行為がある)のではなく、その行為それ自体が楽しいというようなこと。「何のために勉強するのか?」ときかれたときに、「将来のために」とか「試験に合格するために」とかではなく「もっと深い勉強がしたいから勉強する」「勉強自体が楽しいから勉強する」要は「学びたいから学ぶ」と言ってきた。2,3年前に思いついて、これはいい、と思ってずっと使ってきた。しかし、こういうことはずっと以前からいわれてきていたのだし、特に最近の若者がコンサマトリー化しているという議論が古市さんあたりにはあったようなのだ。やっぱりそうか。たいがい、自分で思いついたと思っているようなことは、どこかでとっくにほかの人がいっている。というか、どこかで読んで知ったものを、無意識のうちに自ら編み出した考え方のように思っているだけかもしれない。ということで、本書を読んで興奮しているわけです。私自身、2,30年先を行ってるなあと思うことがります。(これ、自慢というわけではなく…ちょっと自慢です。)つまらないことですが、私は30年まえから美容院に通っています。いまの若者なら、男でも美容院は多いと思いますが、50歳代で美容院に来ている男の人はほとんど見かけないのです。会社人間じゃないし、家族を養うためにはたらいているとも思わないし、お金はあった方がいいけれど(だから最低限の収入=ベーシックインカムBIがあるとうれしい)、だからといってお金のために働いているわけではない。だから、お金あげるからがんばれといわれても、がんばれないんですね。そうではなくて、働くこと自体が楽しいのですね。学ぶこと自体が楽しいのです。こういう感覚は、最近の若者にはふつうになっているようですが、30年まえにはそれほど多くなかったはず。梅棹先生は50年先を見据えていた、といつもいっているのですが、私は30年先を歩いている、ということにしておきましょう。時代が追いついてきたのかな?
ちょっと他の人のレビューを見てみると、わりと否定的にとらえている。最終行「いまここに一つの花が開く時、すでに世界は新しい。」を読んで、パッと世界が開けたような気がしたけど、若者たちはそうでもないのかなあ。
投稿元:
レビューを見る
文明のパラダイムの転換とでもいうべきものの見取り図を示す。壮大なお話であながち間違っているとも思わないが、やはり日々を生きる我らの関心事とはズレているというかそれらが無視されている観があって、不満も残った。たとえば人口減少にどう対処するかとか、AIが社会や経済をどう変えるのか、とかそうした点への言及はゼロだった。
投稿元:
レビューを見る
今ここに一つの花が開く時、すでに世界は新しい。
ポジティブなラディカリズム。肯定する革命。
人に喜ばれることを喜びと感じられるように生きる。
(欲望の相乗性)
有限性の自覚。
自己を目的化しない。
二重疎外からの脱出。
・かつてに比べ、世代の距離は、ほぼ消失している。
歴史は加速度的に進化する(人々が未来を信じていた時代)という団塊世代との乖離。
・地球は、無限であり、有限。
・グローバリゼーションによって実証されてしまった「有限性」。その有限性にどう立ち向かうか。
・封建制とは、戦闘合理性。→近代の現実原則としての合理性。
それは、近代の理念である自由と平等の対極。
=近代家父長制も人間の生の合理的・生産主義的な手段化。
婚姻、女性の子育て、も然り。
・キリスト教=生きることの意味を、未来の救済に求める。
→未来志向の発生
・ピダハン。
他者と自然の《交歓》を通じて、未来ではなく、現在の生「そのもの」を幸福に感じる。
ピダハンは、全世界を所有していると言える。
※サルトル的所有。
認識による世界の所有。滑走による雪原の所有。愛撫による女性の所有。
・未来のために現実を手段化する、ということが無意味になりつつあるのが低成長な現在。(生存のための物質的な基本条件は確保されている)
他者との交歓と自然との交感で、現在を楽しむことが必要。
・貨幣経済の本質は、世界の抽象化。等質化。
・感性と欲望の開放。幸福感受性の奪還。が必要。
・現代は、否定主義、全体主義、手段主義、を乗り越えるべき。
→肯定的、多様的、現在的(consummatory)
投稿元:
レビューを見る
考えてみれば、アートとモード、ファッションの領域における、20世紀までの、「新しさ」というう価値の自己目的化、常により「新しいもの」を求めつづける脅迫は、人間の歴史の第二の局面の、とりわけその最終スパートであった「近代」というみじかい沸騰期、加速しつづける「進歩」と「発展」と「成長」を追い求めてきたステージに固有の価値観であり、感覚であり、美意識であった。三浦が報告しているような、新しいミレニアムに入ってからの、シンプルなもの、ナチュラルなもの、持続するものに対する志向は、たんに一時期の流行ではなく、(もちろん何回もの「ゆり戻し」はあるであろうが、)基本的な動線としては、もっと巨大な歴史の曲がり角を告知するものであると思われる。(pp.49-50)
「所有」ということについての、徹底した考察を行った哲学書『存在と無』においてサルトルは、わたしたちの「所有」というコンセプトを、偏狭なホモ・エコノミクス的「所有」の概念から解き放っている。サルトルが挙げている例は、認識による世界の所有、愛撫による女体の所有、滑走による雪原の所有、登頂による風光の所有、であった。ピーダハーンがすでにこの地上において富める者たちであるのは、彼らが交歓と交感という仕方で全世界を所有しているからである。(p.100)
「近代」という時代の特質は人間の生のあらゆる領域における<合理化>の貫徹ということ。未来におかれた「目的」のために生を手段化するということ。現在の生をそれ自体として楽しむことを禁遏することにあった。先へ先へと急ぐ人間に道ばたの咲き乱れている花の色が見えないように、子どもたちの歓声も笑い声も耳には入らないように、現在の生のそれ自体としてのリアリティは空疎化するのだけれども、その生のリアリティは、未来にある「目的」を考えることで、充たされている。(中略)未来へ未来へとリアリティの根拠を先送りしてきた人間は、初めてその生のリアリティの空疎に気付く。こんなにも広い生のリアリティの空疎の感覚は、人間の歴史の中で、かつて見なかったものである。(p.110)
どんな人間も、性格がよくてもわるくても、基本的な生活のための物質的な条件が確保されれば、それ以上の経済などにはあまり関心を持たないものである。(p.127)
経済競争の脅迫から解放された人間は、アートと文学と学術の限りなく自由な展開を楽しむだろう。歌とデザインとスポーツと冒険とゲームを楽しむだろう。知らない世界やよく知っている世界への旅を楽しむだろう。友情を楽しむだろう。恋愛と再生産の日々新鮮な感動を享受するだろう。子どもたちとの交歓を楽しむだろう。動物たちや植物たちとの交歓を楽しむだろう。太陽や風や海との交歓を楽しむだろう。
ここに展望した多彩で豊饒な幸福はすべて、どんな大規模な資源の搾取も、どんな大規模な地球環境の汚染も破壊も必要としないものである。つまり、永続する幸福である。(p.135)
投稿元:
レビューを見る
2011年「定本 見田宗介著作集」第一巻『現代社会の理論』、あるいは2016年「現代思想」総特集『見田宗介=真木悠介』で一度ならず二度までも触れていた論でした。たぶん、前もそう感じたと思いますが、捉えている視野の大きさと視点の能天気さが今回も。そこが社会学ピーターパン(勝手に命名)、見田宗介節の真骨頂かも。