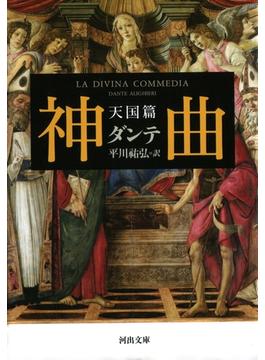語るに余る天界を静かに見せる天国篇
2023/09/10 00:27
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:H2A - この投稿者のレビュー一覧を見る
天国篇は正直に視覚的にはイメージしづらいところが多い。それでも天界に上がって浄罪されているはずなのに堕落した俗世間への批判、フィレンツェへの怒りが最後まで語られずにいられない。天界ではヴェルギリウスにかわってベアトリーチェが、ここではもうダンテの母のように彼を導き励ます。無数の天使に出会い、フランチェスコ、ペテロたち、昇天した歴史上の聖人たちに議論さえする。至高天にいたる十の天をベアトリーチェに誘われて生きた身のままに上昇していく。至高天ではマリアに出会い、とうとう神を垣間見る。その調節的な存在が世界全体を動かしていることを語って壮麗な言葉の旅を静かに終える。当時想像し得る最高の世界像を描いたのだと思う。
ダンテの『神曲』のいよいよクライマックスです。
2020/05/21 10:14
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、中世イタリアにおける詩人ダンテによって著された「地獄篇」、「煉獄篇」、「天国篇」の三部からなる長編叙事詩です。聖なる数「3」を基調とした極めて均整のとれた構成となっており、文学界のゴシック芸術とも呼ばれています。同書、天国篇では、地獄の大淵と煉獄山の存在する地球を中心として同心円状に各遊星が取り巻くプトレマイオスの天動説宇宙観に基づき、ダンテは天国界の十天を構想します。地球の周りをめぐる太陽天や木星天などの諸遊星天の上には十二宮の存する恒星天と万物を動かす力の根源である原動天があり、さらにその上には神の坐す至高天が存在すると考えました。ダンテは、ベアトリーチェに導かれて諸遊星天から恒星天、原動天と下から順に登っていきます。そして、地獄から煉獄山の頂上までの道をウェルギリウスに案内され、天国では至高天に至るまではベアトリーチェの案内を受けるのですが、エンピレオではクレルヴォーのベルナルドゥスが三人目の案内者となります。天国へ入ったダンテは、各々の階梯でさまざまな聖人と出会い、高邁な神学の議論が展開され、聖人たちの神学試問を経て、天国を上へ上へと登りつめていきます。こうして、至高天において、ダンテは天上の純白の薔薇を見ることとなり、この世を動かすものが神の愛であることを知ります。
投稿元:
レビューを見る
眩しいばかりの光で目が眩みそうだった。
神学理論は難解で理解に苦しんだ。
ベアトリーチェの美しさは抜きんでていた。
聖母マリアの慈愛は心を溶かした。
聖母の助けによって至高天に昇った時、全てがわかった。
地獄を下り、煉獄の山を登り、天国で神の玉座まで上昇していく。
「神曲」という建築物を駆け上ることができたのは、平易な現代語訳があればこそであった。
ゴシック建築は立体的な聖書と言われるが、高校時代の無神論者であrと公言していた師が、フランスに旅行に行った折、シャルトル大聖堂に入り、思わず跪いて神に祈ったと語ったことが忘れられない。
たとえ全てが理解できなくともこの3冊を読み通すと同じように神に祈りを捧げたくなる気持ちになる。
自分もキリスト者ではないが、聖書の引用があれば聖書にあたり、ジョットをはじめとするルネサンスの絵画をみたことで少しキリスト教について理解が深まったように思う。
投稿元:
レビューを見る
「神曲」もいよいよ最後,天国篇に入りました。ダンテは地球を離れて高みを目指し,月から水星へ,金星へ,さらに太陽へ…と,天動説そのままのシステムで動く天上世界を廻ります。そこでは,それまでの地獄篇,煉獄篇とは全く違った,観念的,抽象的な神学の世界が描写されています。
本書では,煉獄篇の最後で初めて作中でのダンテと会うことになったベアトリーチェがそのまま天国の案内役を務めるわけですが,その印象にまず驚かされます。現実でのダンテはこの女性に懸想していたようですが,本書からはそのような「想い人」としてのベアトリーチェに出会うことはできません。彼女は既に天に在り,人間を越えた存在としてダンテを包み,励まし,時には叱咤しつつ導いていきます。その様は「女性」というよりむしろ「母」であるかのようです。そしてそれに合わせるように,ダンテもまた幼く,赤子のように力のない存在と変容します。この関係性はいろいろな解釈ができそうですが,フィクションに描かれる男女の関係の元型の一つが,この作品からは見出すことができそうです。
本書の冒頭でダンテが警告を発するとおり,天国編の描写はその具体性をことごとく失い,天国の住人との会話も高度に形而上的なものになっていきます。表現技法や比喩もさらに複雑になり,前2篇とは比べ物にならないほど読み進めるのに苦労しましたが,第11歌と第12歌で描かれるトマスアクィナスとボナヴェントゥラの語りや,第24歌以降で行われるダンテとペテロ,ヤコブ,伝道者ヨハネの3人との「信仰・希望・愛」をめぐる対話などはなかなか読みごたえがあります。特に後者は,当時の神学における議論や試問が「まさにこのように行われていたのだろう」と思わせるような,緊張感の高い雰囲気が伝わってくるようで,私としてはこれだけでも読んでよかった,と思えるものでした。
3篇を通して改めて思い返すと,神曲は「政治家ダンテ」の作品であるということが強く印象に残りました。私は神曲から,当時のイタリアに法王党(白党 vs. 黒党)vs. 皇帝党という派閥争いがあったことを初めて知りましたが,まさか本書を読んで,世界史の復習をしているかのような,不思議な感覚を味わうことになるとは思いもしませんでした。自身の体験を,これほど長大かつ壮大な作品に仕上げるとは。西洋の「詩聖」の力を,思い知らされた気がします。平川祐弘訳。
(2009年7月入手・2011年8月読了)
投稿元:
レビューを見る
三昼夜を過ごした煉獄の山をあとにして、ダンテはペアトリーチェとともに天上へと上昇をはじめる。光明を放つ魂たちに歓迎されながら至高天に向けて天国を昇りつづけ、旅の終わりにダンテはついに神を見る。「神聖喜劇」の名を冠された、世界文学史に屹立する壮大な物語の完結篇、第三部天国篇。巻末に「詩篇」を収録。
投稿元:
レビューを見る
言葉にも血にも土にも神にも共通をもたない私が、道中、取り零す以前に直観し得なかったものは、莫大である。が、代わりに極公正な機能でもって眺めた時、一連の旅路を拓ききった詩人の空想・構想・信念・情熱・自負の力、乃ち愛の強大は圧巻だ。
全てを同じに有すべく、又視覚的刺戟——TVやスクリーン、果てはRPGなど含めた処の——の未だ自然の域を出ない時代に産まれた人々には、きっと、本当に詩人は死後の世界を巡って還って来たと思われたのではないだろうか。真摯に心眼見開き耳聳てれば、同じ民だ、同じものを観得ると信じられたに違いない。その信頼のもたらす恩恵は、読書に在っても無論絶大である。書物離れた雑務の時にさえ、それは励みとなって読み手を鍛えたことだろう。
又、「愛の強大」さから言うなら、訳者のそれも詩人の道と同じほどに苦難と祝福とに溢れている。
全てを異にする上、天文数学の頭を幼少からすっかり放擲したきりの私には、殊にこの「天国篇」は、彼の大業なくしては単なる記号の羅列に過ぎなかったろう。辛くも一個の人として何かしらを感じ得たのは、偏に訳者の努力と、また其れに報いんとする私の敬意の賜物である。
趣も信念も別の姿で往く訳本が複数存在する中で、先ず何れを採ろうか迷う向きには、私がそうで在ったように、気負いも気取りも棄て、此の平明にして繊細な配慮ゆき届いた、平川訳から繙くことを薦める。その上で未だ詩篇としての味わいに飢えるなら、他と共に掘り下げるのが佳いと想われる。
投稿元:
レビューを見る
地獄篇・煉獄篇を経て終局たる天国篇(Paradiso)へ。
ダンテは遂に、至高天にて、"天上の薔薇"とも呼ばれる光の中心に「いっさいの望みの究極(はて)」である神を観るに到る。
「ただそれだけが真実な、崇高な光輝の/光線の奥へ、さらに深く、はいっていった」 「その光の深みには/宇宙に散らばったもろもろのものが/愛によって一巻の書にまとめられているのが見えた」(以上、第三十三歌)
全三篇、粘着的なまでに体系的な、宗教という強迫観念の大伽藍を見せつけられた。
□
ダンテ自身が冒頭で述べているように、天国篇は地獄篇・煉獄篇に比して難解であり退屈でもある。神的宇宙と云う肉体的現実界とは隔絶された観念体系を、神学的な抽象語で以て綴らねばならぬのだから、尤もではある。それに、善を語るには小理屈を練らねばならぬが、悪にはそれ自体の生々しさがありそれだけでも興味を惹くものだ。
神の絶対性を中心に据えてしまえば、そこから無尽蔵のレトリック・贅言冗語を導出し、如何ようにも言葉を踊らせることができる。「神意」だの「至上善」だの「愛の光」だのと定義不明瞭・定義不可能な語を持ち出されては、叙述や対話の論理的連関は曖昧模糊となること不可避だが、その曖昧さを伴ったまま、神学体系は至高の天上へ向けて何処までも恣意的に語り上げられていく――その「厳格さ」だけは決して放棄されることなく。神の裁きや地獄の罰の如何もこのように恣意的に導出されてしまうなら、これはもはや専制だ。こうして宗教的権威は世俗に於いて権力をもつことになる。権力者と云うのは、言葉を支配し同時に言葉を支配の手段にするものだが、宗教的権力こそが人類史に現れた最初の"言葉の創造=支配者"ではないか。
なお、"永遠の女性"であったはずのベアトリーチェは、最後までキリスト教の教説をひたすら復唱するだけの「自動人形」(正宗白鳥)に過ぎない。
□
第二十二歌の訳註で紹介されている、クローチェ(1866-1952)によるダンテ評が興味深い。
「世界からの逃避、神への絶対的帰依、禁欲主義、などは、ダンテの精神にとって異質なものであったから、『天国篇』の中にこうしたものは見あたらない。ダンテは世界から逃避しようとしない。彼は世界に教訓を垂れ、世界を矯正し、世界を改革しようとして、天上の至福に言及する。・・・。天と地という二つの世界が公然たる対照裡に示された時でさえ、神的なるものが人間的なるものにうち克ち、それを徹底的に放逐してしまった、とはどう見てもいえないのである」(『ダンテの詩』)
確かにダンテは至高天に於いてもなお俗世の政治家や聖職者をしつこく非難し続けており、天上に在りながらも現世に於ける政治的事業のことが心から離れているようには思えない。
宗教に神秘的な忘我の契機を求める者は、アリストテレス-トマス・アクィナス的な目的論的世界に於いてもいたであろう。しかし、ヴェーバーの『中間考察』にあるように、断片化された自我がその全体性を回復しようとして非合理的な対象との合一を求めようとするのは、資本主義と官僚制��覆われニヒリズムに到るもなお留まることのない機械論的世界、則ち近代の人間に特有の傾向なのだろう。
□
最後に警句を一つ。
「見当のつかぬ事柄については早急に是非を論ぜず、/疲れた人のように歩みを遅らせるのがいいだろう。/・・・/細かい判断もなしに肯定否定を行う者は/愚か者の中でも下の下たる者だ」(第十三歌)
投稿元:
レビューを見る
天国篇では当時のスコラ哲学の神学議論を前提としたダンテの宗教観が最も直接的に表れている分、やはり読み進めるのに苦労するのは否めない。それにしても全篇に渡って挿入されているギュスターヴ・ドレの荘厳な挿絵と平川祐弘による読みやすくリズム感のある素晴らしい日本語訳、そして各歌ごとの丁寧な前文と詳細な解説がなければ、この全3篇100歌14233行からなる叙事詩を読み切ることはとても叶わなかっただろう。3の数字を基底とする、幾何学的に構築されて無限へと向かおうとするこの世界観にボルヘスが夢中になるのも無理はない。
投稿元:
レビューを見る
すいぶんかかって読破。
地獄篇~煉獄篇~天国篇と、あわせて1000ページを軽く越えるボリューム。
ちなみに、宗教的な興味がとくにあったわけではない。
「分かりやすい」と好評の訳だけあって、さながらダンテと旅する気分。地獄篇では、さまざまな罪によって罰を受ける人々を見て、ちょっぴり自分の罪を悔いてみたりもした。
煉獄から徐々に抽象的になっていき、天国はまったく理解を越えていた。まだ私の魂はそこに到達できないらしい。(笑)
投稿元:
レビューを見る
地獄編より煉獄編、煉獄編より天国編を面白みがなくなっていくという、読書が難行になってくる神曲。
天国編はこれまでと比べ、抑揚がなく、さらに哲学的というか宗教学的になるので、相当、理解をするのに時間がかかりました。しかも、解ったところで面白くないという‥‥。
しかし、そのなかで第十九歌にある、
“遠いインダス湖畔で生まれた男は、キリストについて知ることは不可能である。洗礼を受ける機会は生涯あらわれない。
その彼が、何一つ罪を犯すことなく死んだとして、地獄に落とす正義はどこにあるのか。“
という、ダンテの問いかけは、『神曲』を読んでいる間中、私に思考させていたものだったので、やはりダンテもキリスト教の絶対主義に対して、疑念を抱くことがあったのか、と思った。
もちろん、そこにはウェルギリウスの存在があるのでしょうが。
それにしても、河出書房の平川さんの翻訳は非常に解りやすく、注釈も楽しかった。
時にダンテの表現を「ふさわしくない」と断言したり、ダンテ研究者の言葉を引用したり、と丁寧で興味深い内容を多く記載してくださっている。
この翻訳でなければ、絶対挫折していただろうなと思う。
『神曲』をこれから読もうという方には、お勧め。
ドレの挿絵も美しい。
投稿元:
レビューを見る
天国では、各天球に魂たちが住んでいます。ベアトリーチェは説きます。星の輝きは魂たちの喜びのあらわれ。喜びが光となり、ひとつに集まり輝きとなる。そして喜びとは神に愛への歓喜であると。
そして二人はたどり着きます。神の国:至高天(エンピレオ)へ。
ダンテは神の愛の光に包まれながら気付きます。神は愛そのものであり、愛は光となって輝きを増す。すべてはつながっているのだと。花は枯れても、種は光を浴びて再び芽を出す。肉体は土に還っても魂は愛となり、光となり輝き続ける。
愛とは、光とは、神とは、すべてにおける初動の源なのだと。
しかし、地上を見渡すと、光が薄れています。
再びベアトリーチェは説きます。
神の愛は永遠に強く輝いていても、人々が堕落しているために光が届かない。ではなぜ堕落するのか?それは自由意志を手に入れたとたん、神の意志を忘れてしまったからだ。
地獄は神が必要としているわけではない。人が正しく生きるために、地獄と煉獄と天国が存在するのであり、死後の世界があることを知れば人々の意識も変わるのではないか。正しい生き方に気付いてくれるのではないかと。
ダンテは天上に消えゆくベアトリーチェに約束します。私は現世に戻り見てきたことをきっと伝える。それが、自分の進むべき道であり、あなたが私に望むことであろうからと。
最後にベアトリーチェはこう伝えます。私だけの望みでなく、みんながあなたに愛と希望を抱いている。あなたは私たちの希望の光である。
そして私を愛してくれてありがとうと。
投稿元:
レビューを見る
けっきょく、偉大な人間とはわたしなど及びもつかない人びとなのだということがわかる作品だった。
訳をされた平川さんという方の全人格をかけてダンテに立ち向かった気概と天賦の才能に嘆息するより他ない書物です…
できれば河出書房新社「神曲(完全版)」を手元に置きたい!
Mahalo
投稿元:
レビューを見る
ダンテ(平川祐弘訳)『神曲』天国編,河出文庫,2009年(初版1966)
全33歌。ダンテはベアトリーチェとともに天に昇っていく。天国篇は「瞬間移動」で道中というものがない。最初の「月天」ではクララ会(女子修道院)に入る誓願を破って還俗しなければならなかったピッカルダやコンスタンツァなどの女性から話を聞く。天国にも階層はあるが、そこに住む人々は上を望んだりせず、自分の場所に安住している。「自由意志」を犠牲にささげる「誓願」の意味がベアトリーチェから説明される。「水星天」ではローマ皇帝ユスティヌアヌスの魂とあう。「金星天」ではハンガリア王カルロ・マルテルロに会い、運命が性に合わないと、育ちが悪くなることから、不肖の子孫がでる理由が説明されている。「金星天」では多情の女性クニッツアの魂やマルセーユの人フォルケ(アルビジョア十字軍で戦った人)などからも話しを聞く。「太陽天」ではトマス・アクィナス(ドミニコ会士)がフランシスコを讃えるのを聞き、ボナヴェントゥーラ(フランシスコ会士)がドミニコを讃えるのを聞く。また、ソロモンから肉体の復活の話を聞く。「火星天」では、十字軍でたたかったダンテの祖父カッチャグイダがでてきて、昔のフィレンツェの質朴な様子を話し、ヴェローナのカン・グランデがダンテを助けてくれるであろうと予言する。「木星天」では数多の魂が「鷲」の形で飛び回っているのをみる。ここでは栄光に輝く魂、ダビデ、トラヤヌス(大グレゴリウスの祈りで復活しキリスト教徒として死んだことになっている)、コンスタンティヌスなどと会う。ただ、キリスト教を知らなかったであろう人物もいて、ダンテは疑問に思うが、神意の深さを人間の智慧で測ろうとすることに警告が発せられる。「土星天」では、「ヤコブの梯子」をみて、ピエトロ・ダミアーニから、神の定めの知り難いことを諭される。また、「西欧修道制の父」ベネディクトゥスが身の上を語り、修道生活の堕落を非難する。「ヤコブの梯子」を昇り、「恒星天」に昇り、あわれな地球をふり返ってから、ペテロから信・望・愛について、口頭試問をうける。ダンテは「信仰とは望みの実体であって、まだ見ぬものの論証」、「希望とは未来の栄光を疑念を差しはさまず待つこと」と答え、強烈な光によって一旦目がくらむ。ここでヨハネやアダムがやってきて励まされ、「愛」について滞りなく答えることができた。そして「原動天」に昇り、無数の天使たちをみる。ベアトリーチェは天使・天球・地球の創造や、堕天使の反逆などについて語る。第十の「至高天」に入り、祝福された魂が巨大な「白いバラ」の姿で座っているのをみる。第三十一歌でベアトリーチェは姿を消し、聖ベルナール(シトー会士)があらわれ、マリアの光をみるように促され、最後に「三つの円」(三位一体のキリスト=神)をみる。それは「太陽やもろもろの星を動かす愛であった」で終わる。
第三十一歌までダンテはベアトリーチェに案内されるが、彼女は天を昇れば昇るほど美しくなっていくそうである。ベアトリーチェは基本的に解説者のような役割で、あまり人間の女性としての親しみはない。例によってダンテは政敵への怨念を天国でももらしている。ダンテは法王党の白��というセクトから選ばれて、フィレンツェの国務大臣級の職についたのだが、白党が同じ法王党のセクト黒党にやぶれ、ダンテは国費費消の罪で二年の国外追放になったが、出頭しなかったので、永久追放になり、フィレンツェの官憲につかまったら、火刑にかけられるという過酷な生活を送り、生涯フェレンツェに帰れなかった。自分が故郷で桂冠詩人になる夢をすてられなかったらしく、神聖ドイツ皇帝ハイリッヒ7世のフィレンツェ入城に期待をかけ、わざわざ天国にハインリッヒの席を準備したりしている。天国篇といっても、ダンテの政治的主張がないわけではない。
科学史的にみると、地球の直径や、火星の軌道、機械式時計の歯車の仕組み、当時はじまったばかりの都市統計などの観点がみえ、とても興味深い内容だった。『神曲』は九重の地獄、七層の煉獄、十天の天国を、一週間で見てまわる話であるが、基本的に「旅行ガイド」的で、ダンテ自身がなんらかの行為をするということがない。つまり、旅行者の文学で生活者の文学ではない。天国篇は全てが光り輝いて美しいのであるが、そこでダンテは神の恩寵に浴して、すべてを見たというだけで、力強く生活することがない。これはダンテが「他人のパン」を食べる傍観者としての人生を余儀なくされたことと無関係ではないだろう。美しいが何か寂しさを感じる作品である。ベアトリーチェは最後にはいなくなるし、ダンテは至高天で消えるわけではない。最後にみたものは何か幾何学の図形のようなもので、正直に言って、拍子抜けであった。美しさも突き詰めると非人間的になるのかもしれない。
「洗礼を受けずに死んだ者を地獄に落とす正義」(第19歌)や、「キリストが法で裁かれたのは正しく、ローマ帝国の権威は合法(つまり、キリストが殺されること=人類の救済、ローマ帝国は人類救済の手段であった)」(第六歌)などの観点は興味深いものである。
ちなみに、ダンテの正妻の名前はジェンマ、夫がベアトリーチェ(一応、若くして死んだが、実在の人物)にべた惚れな詩を書いているのを見て、どう思ったのだろうか?
投稿元:
レビューを見る
目次より
・天国篇
・詩篇
天国篇はほぼ宗教論に終始していて、今までの映像的な描写は格段に少なくなり(挿絵も激減)、小難しいやり取りが続きます。
“君たちはおそらく
私を見失い、途方に暮れるにちがいない”
さて、地獄篇からの懸案事項、「キリスト以前に死んだ善人が地獄にいることの是非について」にとうとう回答が!
“その男の考えること、為す事はすべて
人間理性の及ぶかぎりでは優れている。
その生涯を通じ言説にも言動にも罪を犯したことがない。
その男が洗礼を受けず信仰もなくて死んだとする。
その彼を地獄に堕とすような正義はどこにあるのだ?
彼に信仰がないとしてもそのどこに罪があるのだ?”
“天の王国は熱烈な愛と熾烈な望みによって
掟が破られることを許すことがある。
それらが神意にうち勝つのだ。
人が人に勝つのと同然ではない。
神意が負けることを望むから勝つのだ。”
問いに対する答えがこれ。
熱烈な望みがあれば、掟をまげて天国に受け入れることもある。
ただし、それは人が神に勝ったというわけではなく、あくまでも神が受けいれようと思ったからだ、と。
つまり神の自在定規ってこと。
“そしておまえら現世の人間よ、判断はけっして迂闊に
下さぬがよい。神を見る我々の目にも
神に選ばれるべき人々の姿がみな映るわけではないのだ。”
そして神の決定に口を出すな、と。
アダムとイブが楽園を追われたのも、禁じられたリンゴを食べたからではなく、リンゴを食べることによって神と同等の存在になろうとした高慢のためにだというのには納得。
なるほどね。
地獄が非常に感覚に訴えるものであったのに対して、天国篇は論理的。
“人は感性で知覚されたものから
はじめて知性に適するものを学び取るからです。”
宗教って感覚的なものから始まるけれど、最終的には論理に向かう。
それはつまり、人間はそういうものだからだ。
…ということしかわからんかったわ、結局。
そして、天国で、一糸乱れぬポーズでうじゃうじゃといる天使がとても気持ち悪い。居心地が悪いと思う私は、とても罰当たりです。
自分らしさ=業ってことなのかな。
自分らしさ、人間らしさを捨てないと天国に行けないのであれば、人として生まれた意味は何なのだろう?
やっぱりもっと勉強しないとダメですか?
ちょっとしんどいな。
投稿元:
レビューを見る
ダンテ 神曲 天国篇 。訳注のおかげで読了。ダンテの宗教的到達点までの軌跡を綴った叙事詩。特に 終盤の至高天は壮大。地獄篇から始まって、ダンテの宗教観の確立とともに 上に昇っている感覚になる。
初読ポイント
*キリスト教の思想体系
*神とは何か、教会のあるべき姿とは
*天国=宇宙説
「天国篇は 万物を動かす者の栄光にはじまり、太陽や星を動かす愛で終わる〜神は愛であり愛をもって天球の動きを規制している」