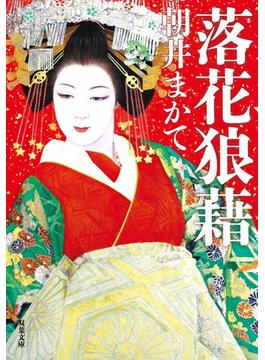江戸文化を支えた吉原創設を描く
2022/09/21 10:42
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nekodanshaku - この投稿者のレビュー一覧を見る
江戸初期、傾城屋の町吉原を創設した庄司甚右衛門の妻の一代を描いた物語である。吉原は造り物のせかいであり、虚実を取り混ぜて見せる夢の世界であったが、その創設は簡単なものでなかった。公儀の許認可が必要であるし、社会から蔑まれたことも事実であり、そこで働く遊女たちの生い立ちは多くは悲しいものであったから、女性の経営者としては大いに悩んだものだろう。江戸の文化を振り返ってみれば、吉原の存在は必要不可欠なものだと思う。知らなかった世界を、物語として読むことができ、良かった。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:イシカミハサミ - この投稿者のレビュー一覧を見る
江戸時代を語るうえで欠かせない存在、吉原。
あらゆる物語がここにはあると思うのだけれど、
当然「始まり」があるというところには、
わりと手薄な感じがする。
視点は吉原の確立に尽力する傾城屋「西田屋」の主
甚右衛門の妻、花仍。
ひとりの視点から移り行く時代を映していく、
これぞ朝井まかて、という一作。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かずさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
江戸の遊郭吉原で生きた女将一代記。でもその女将は年の離れた遊郭の主人であり吉原の街の発展と秩序を本気で考え御上や町衆との交渉や意見統一を図った男の妻。なかなか本当の女将になれず周りを手こずらせるが時と共に女将の姿になっていく。
華やかだけではない街の人達を描いている。お互いに血のつながりは無いのに何かに向かって行く姿。知られているようで知られていない世界を表現する作者のいつもの姿勢。
もうちょっと主人公の深い思いが表せられていればよかったか。
吉原ができるまでの顛末
2023/08/31 11:23
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:トマト - この投稿者のレビュー一覧を見る
あちこちで売色をする店を集めて、一つの傾城町を作ろうとした話です。
当時は、子は親の持ち物として売り買いされていた。特に女の子は色町に売られることが多い。信じられない時代です。今の感覚で読んではいけないとは思いますが、いくら、主人や女将が遊女たちのことを思っていても、やっていることは彼女らを食い物にしていること。矛盾を感じながら読みました。
投稿元:
レビューを見る
戦国乱世が終わって、吉原が出来上がるまでの物語を一人の女将の目から描いた作品。
元々、新しいものが作り出されていく作品が大好きな私には最高に面白かったです。
葦しか生えず、水はけも悪い最悪の土地に売色の場所を作ろうという江戸幕府の思惑から始まった吉原の計画。
土地を埋め立て、ここで生きていくためのルールを定めて、ここへの力への入れ方は凄いなぁと思いながら読んでいました。
戦国の時代は終わって新しい時代を自分たちで作っていくのだという巨大なエネルギーと売られてきて色を売る女たちの哀しさ。その対比の見事なこと。
朝井さんの小説は本当に面白いです!
投稿元:
レビューを見る
朝井さんのお話なので期待したんだけど、どうにも。主人公のカヨが最後までどうにも好きになれず全体に時代の進み具合が早くついていけなかった。
投稿元:
レビューを見る
売色御免/吉原町普請/木遣り唄/星の下/
湯女/香華/宿願/不夜城
「吉原」が誕生した経緯。その後の幕府との駆け引きを吉原が生き残る方向へ向けるための思案。何となく栄華を誇っていたと思っていたけれど、それなりの努力があってこそだったのですね。春を売らせる男たちにも矜持があった。そういう人もいたかもしれない……
投稿元:
レビューを見る
大変失礼な言い方だけど、最初あんまり期待しないで読み始めたのだけれど、期待?に反して、面白かった。志を持っていれば、仕事に貴賤はないのだと思った。
投稿元:
レビューを見る
202208/とても面白かった!さすが朝井まかて先生!これも名作!素人考えなのは承知の上で、もっともっと読みたいので、年月とばさずに日常や再建のとことか細かく書かれた上下巻にして欲しかった…。
投稿元:
レビューを見る
一つの出来事を微に入り細に入り語るというより吉原が形作られる流れを大きく語る物語。感情移入しやすいというより俯瞰的な目で時の流れを眺めている感じがした。
主人公カヨの成長は見もの
投稿元:
レビューを見る
吉原が舞台なので、遊女たちの色恋沙汰が淡々と続く小説かとの思惑は、見事に外れた(良い方に)。
主人公とも言うべき西田屋の女将花仍も夫の甚右衛門も狂言回しとも呼ぶべき役割で、主役は傾城町吉原そのものではないだろうか。
著者は、江戸随一の遊郭となった吉原をその黎明期から緻密なタッチで描き出し、吉原の変遷や遊女たちの実態を、読者の目の前に開かせてくれた。
投稿元:
レビューを見る
江戸の初期、吉原を幕府公認の傾城街にしようと働きかけた者達がいた。大見世の女将の花よの一代記。幼い頃迷い子だったかよを引き取り、後に夫となった甚右衛門と共に吉原を造り、何人もの妓達をまとめて見世を切り盛りするかよ。だが生来の気の強さで周りとぶつかる事も多い。そんなかよを叱咤しつつ導いてくれるやり手婆や揚げ屋の女将、番頭など人に恵まれながら成長する。
後の吉原の安定が、意外にもこんなに多くの苦労があってこそだったのだと知る事ができる。女郎を主人公にした物は多いけど、見世の女将を主人公にした話は珍しいのでは。それも吉原が出来たばかりの頃の話で読み応えあった。
投稿元:
レビューを見る
花街としての吉原を江戸初期の幕府に認めさせた実質的創始者である庄司甚右衛門の貰い子で後に女房となった花仍の一代記。
売色御免(専売)の公許を受け、侍の世から商人の世に変わる中、幾度の大火事や公儀の命令による移転、裏で売色をする風呂屋や茶屋との争いなどの困難と戦いながら、太夫を擁する花街としての矜持を失わず、吉原を他と同格の「町」として築き上げた甚右衛門とそれを支えた花仍。
町を支える大女将としての生を全うし、孫たちに見守られて迎える眠るような最期は、激動の生涯の末のご褒美だろうか。
投稿元:
レビューを見る
吉原というと真っ先に花魁が道中を練り歩く様子が目に浮かびます。しかし、実際はどのような仕組みになっているのか、そこにいる人々はどのように過ごしているのか分からずにいましたが、この小説を読みその成り立ちも含め理解できました。
江戸時代の初め、城下と隔られた日本橋のはずれの町に位置する場所、吉原で遊廓を営んでいる西田屋の女将、かよ。彼女は幼少期に迷子か捨子かもわからず育った素性の持ち主ですが、主人の甚右衛門に拾われ育ち、女房になって間も無い。ずっと年上の甚右衛門は、売色稼業の吉原を発展させるために様々な見世を一ヶ所にまとめた場所を造り、他の町では売色が出来ないように公儀から許しを貰う。ここから始まる物語ですが、主人公のかよも含め、遊女やその周囲で働く様々な人物が個性豊かで、境遇が恵まれないことを踏まえながらも、生き生きとしていて惹き込まれます。
そして、その生き方が“外道”という言葉が当てはまるほど壮絶な道を歩んだ親仁さん(ととさん)、甚右衛門の偉業が吉原の興盛の基礎を造ったことに間違いないのでした。
投稿元:
レビューを見る
出だしからの面白さに引き込まれていましたが、若菜が亡くなってしまった処で一旦興味が薄れてしまいました。
一週間程経ってからの読了。
吉原遊郭の経営者視点からの展開、もう少し下から目線が欲しかった様な気がしました。
また終盤は年月が飛びすぎていて、無理矢理ランディングさせた感が残念。
もっと長編でもよかったんじゃないのかなぁとも思いました。