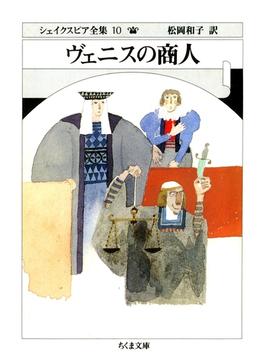0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:令和4年・寅年 - この投稿者のレビュー一覧を見る
借金のかたの1ポンドの肉。ユダヤ人の商人の頑なまでの態度。遂に裁判で決着がつけられる。法には法を。追い詰め、追い詰められていく過程と一転、立場の逆転がまさに劇的。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:iha - この投稿者のレビュー一覧を見る
善のキリスト教徒と悪のユダヤ人の対立という、分かり易い勧善懲悪作品だと思います。ただ、そんな悪の金貸しシャイロックにも、キリスト教社会におけるマイノリティとしての矜持と悲哀が見え、単純な悪党に終わらない奥深さも見せています。また主要人物のひとりポーシャはこの騒動を作った張本人バサーニオの新妻で曲者。夫にばれないよう、男装して裁判に乗り込むと、悪党を懲らしめ夫の親友を救ったかと思うと、妻とは気づかない夫に無理難題を吹っ掛け、今後の新婚生活の主導権を握るという、賢さとしたたかさを併せ持った恐るべき女性でした。
喜劇にも悲劇にも
2017/11/12 02:25
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:藤和 - この投稿者のレビュー一覧を見る
シェイクスピアをお好きな方ならお馴染みのあのテンションで、話は進んでいきます。
たまに訳注というか、フレーズや単語の解説が入っているのはとてもありがたい。
喜劇という事なのだけれども、その中にも偏見や差別など、そう言った考えさせられる要素があり、視点を変えると悲劇へと変わってしまう物語。
その辺りの感じ方は人それぞれだと思うけど、ただのハッピーエンドとしてはちょっとスッキリしない感じでした。
投稿元:
レビューを見る
肉を担保に金を貸りた人間と、貸したユダヤ人の金貸しの物語。金貸しシャイロックの訴えは、現代の世においては人種差別という問題を呼び覚ます。ハッピーエンドのように見えて、その裏には何か釈然としない問題をはらんでいる素晴らしい作品。
投稿元:
レビューを見る
これも授業で読んだ本。思い出す、隣の友達と一緒に本文を探しまくったあの日を。あの時間を。思い出すと楽しいものだな。肉を切り取る、ってのがイマイチ、ピンとこなかったな。
投稿元:
レビューを見る
あいつは神に選ばれた俺達ユダヤ人を憎んでいる。苦難に耐えるのは私たちユダヤ人の印だからな。
ユダヤ人から逃げだせば悪魔のいう通りにすることになる。あのユダヤ人は悪魔の生まれ変わりだ。
ユダヤ人がキリスト教をひどい目にあわせたらキリスト教徒のお手本どおり、ユダヤ人の忍従はどうなる?やっぱり復讐だ。
投稿元:
レビューを見る
アントーニオと対になるシャイロックの、悪役としての存在感が素晴らしいです。アントーニオは無償で親友に大金を貸す一方、シャイロックは貸した金を二倍三倍にして返すという条件をつっぱねて仇敵アントーニオを「法」というルールの上で殺すことを望みます。
アントーニオもシャイロックも金銭に拘らない自分なりのルールに従った上での「信念」があるところに引きつけられます。
オチもシャイロックが「法」を利用したからこそのオチでとてもいいです。そんな中、指輪のやりとりで男女間の「誓い」を破ってしまうのはなかなか示唆に富んでいて面白いですw
投稿元:
レビューを見る
さすがにシェイクスピア作品だけあって、非常におもしろかった。とくに「人肉裁判」の場面は白眉で、こういうロジックがあるのかと関心すらさせられた。しかし、いっぽうでたんなる喜劇としてみれない部分があることも事実である。シャイロックが一転窮地に追い込まれるシーンは、たしかに快哉を叫びたくなるし、実際舞台で観たら痛快このうえないと思う。しかし、人種差別的な要素も含まれており、シャイロックに対する同情の余地もすくなくない。たんなる喜劇とは違った深みがあり、そこもまたやはりシェイクスピアが書いた作品なのだと感じさせられる。喜劇をたんなる喜劇にしないところが、文学の文学たる所以なのだろう。
投稿元:
レビューを見る
ハムレット、ロミオとジュリエットに続いてシェイクスピアちゃんと読み3冊目。これが今のところ1番おもしろくて読みごたえがあった。
契約・法・金の怖さ、友情のありがたさ、ユダヤ人の気の毒さ、等々、普遍的テーマだからこそ、400年も前に作られた物語が今も読み継がれているのだとおもう。
また時々、読みかえしてみたい。
投稿元:
レビューを見る
どうしてアントーニオは肉の証文に合意したのか?どうしてポーシャはだらしないバサーニオを気に入ったのか?解説にもあるが人間何がどうなるのか分からない代物。
投稿元:
レビューを見る
シェイクスピア全集 (10) ヴェニスの商人
(和書)2009年04月16日 19:11
2002 筑摩書房 W. シェイクスピア, William Shakespeare, 松岡 和子
学者としての翻訳、原文の性的表現の指摘などいろいろ註があって参考にはなります。詩的霊感としての表現についてもうちょっと追求したら面白いのになと思った。
一切の諸関係をくつがえそうとする姿勢がここにもみられる。シェイクスピアの世界性・普遍性・世界市民という認識がここにも良く現れている。ここがなければ元になった作品と同じ道を歩むだろう。
彼の作品が今でも読まれるのはこの為かもしれない。
岩井克人の「ベニスの商人の資本論」を読んだ。拓大で机の下に本を置き忘れたら学生課に届けられていた。いい奴もいる。
投稿元:
レビューを見る
うーん、僕にはこれは、いじめてきたユダヤ人に仕返しされているお話としか読めなかった。それなのに最後にはこのユダヤ人は、男装の法学博士にやりこめられて、ぐうの音も出ない。あわれである。さらに、このヴェニスの商人の船は沈没してはおらず、結局ぼろもうけである。商人側に立てばめでたしめでたしなのだが、ユダヤ人の立場で見ると何とも気の毒なお話である。ユダヤ人がどうしてこうもいじめられなければならなかったのか、その歴史的背景はまた内田先生の本でも読んで勉強し直さないといけない。さて、それにしてもこの男装である。2人の女性が男装をしてやってくる。自分のフィアンセである。どうして気付かないのか。もうこれが不思議でならない。お芝居だからのお約束事か。シェイクスピアの時代であったとしても、こんなことが本当に起こり得たのか。それとも芝居の中だけの話なのか。男装しなければ話をさせてももらえなかったということか。女性のままではだれも話を聞いてくれなかったのか。そしてもう1つのエピソード。結婚相手を選ぶのに、運にまかせるということ。3つの箱の中から正しいものを選んだ人を夫とする。それが父親の遺言?いったいどういうことか。とは言え、結局は気に入っている人に決まってしまう。(解説を読んで分かったのだけれど、どうも音楽か何かで正しい箱を教えていたらしい。そうなのかなあ。全く気付かなかった。)それと、毎度おなじみの道化。その役割は何なのか。ちょっとググってみると、これだけでもかなり大きなテーマになりそうだ。歴史的背景を知らないと読みとれないなあ。「源氏物語」を読むと、1000年前でもみな同じ人間だなあと思えることが多かったが、シェイクスピアは、時間的にも空間的にもずれているからか知れないが、なかなか事情が呑み込めないことが多い。全集9作品目。読むのには慣れてきたが、まだまだ時代になじむことができていない。
投稿元:
レビューを見る
「体からきっかり一ポンド」「好きな部分を切り取る」裁判以外のことはあまり知らずに読んだ。
シャイロックに娘がいたことや、
箱選びの話が挿入されていること等、
知らないことがたくさんあった。
アントーニオの尽くしっぷりが浮いている感じがしたけど、
元ネタではアントーニオ的な人はバサーニオ的な人の養父なのね。
シャイロックがひたすら可哀想。
リアルで周りにいたら絶対敬遠するであろう
バサーニオをどうも憎めないのが不思議。
投稿元:
レビューを見る
ちくま文庫版シェイクスピア全集第10巻。商業都市ヴェニスと架空の都市ベルモントを舞台に金と愛の取引を描く。
短いにも関わらず、いくつもの要素が混みいった構成になっていて、非常に密度が高い。商人のアントーニオが窮地に陥る「人肉裁判」がメインに思えるが、シャイロックを通してユダヤ教徒とキリスト教徒の関係性の問題が描かれていたり、「金銀銅の箱選び」や指輪のやり取りで結婚や夫婦関係の問題を扱っていたりなど、奥が深くて一読では消化不良となった。裁判の痛快さと喜劇の余韻を味わったあとは、何度も読み込んだり、他の解説や考察などに触れて思索を必要とする作品だと思う。しかしこの奥さんはちょっと恐いかもなぁ(汗)。
投稿元:
レビューを見る
最後、どうしようもなくごちゃごちゃで笑ってしまった(爆笑、とかでなく、鼻で笑ってしまうというのかなんかそういう感じの…)。あらすじ読んだ時に「喜劇なの!?」となったけれど、読み終わった今、「喜劇ってこういうこと……?!」となったりした。
シャイロックがもっとこうなんかするのかと思っていたよ。
「いっそ大酒くらって肝臓をほてらせたい、
命を削る溜め息で心臓を凍らすのはまっぴらだ」
グラシアーノのこの台詞はなんか好き。