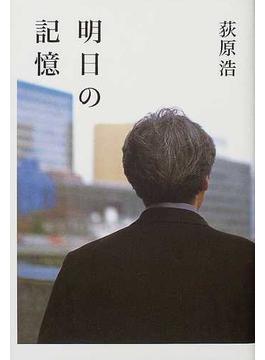「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
【山本周五郎賞(第18回)】人ごとだと思っていたことが、我が身に起きてしまった。若年性アルツハイマーと告げられた佐伯。彼には、記憶を全てなくす前に果たさねばならない約束があった…。身につまされる長編小説。【「TRC MARC」の商品解説】
著者紹介
荻原 浩
- 略歴
- 〈荻原浩〉1956年生まれ。広告制作会社勤務を経てコピーライターとして独立。「オロロ畑でつかまえて」で小説すばる新人賞を受賞。著書に「メリーゴーランド」「僕たちの戦争」など。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
消えゆく記憶
2008/05/17 16:25
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ココロの本棚 - この投稿者のレビュー一覧を見る
涙なくしては読めませんでした。
広告代理店の営業部長佐伯は、50歳にして「若年性アルツハイマー」と診断される。病気を隠しつつ仕事を続ける佐伯。愛する妻と、結婚間近の娘。失われていく記憶・・・・・・。
アルツハイマーに罹った主人公の一人称で語られる本書。
頭痛や目眩、不眠に悩まされ病院を訪れて宣告された「若年性アルツハイマー」という病名。
物忘れが激しい。簡単な計算ができなくなる。
そういう自覚症状を抱えつつも仕事を続ける佐伯。周囲に気づかれないよう、会話などはすべてメモにとりポケットに忍ばせて仕事をまっとうしようとするのですが。
自分の記憶が周囲と少しずつ食い違っていく恐怖。
社会から取り残されてしまうのでは?という焦り。
愛する人の顔すら忘れてしまう日がくるという絶望感。
徐々に記憶を蝕まれていく悲しさが伝わってきます。
佐伯の趣味である陶芸、その陶芸教室でのエピソードがとても悲しい。
小さな裏切り。
人はこんなにも残酷になれるものなのだろうかと、胸が痛みました。
そして裏切りに気づいた佐伯が、そのことすらも忘れていってしまうであろうことも。
ラストは残酷なまでの美しさ。
家族の闘いは続くのだろうけれど、佐伯の心の葛藤はあそこで終わったのかな。
肉体の死、脳の死、生命活動はしていても自分の人格を失う「記憶の死」
人にとって、死とは何なのか深く考えさせられました。
紙の本
若い人たちに読ませたい感動の書
2005/06/12 12:07
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:jis - この投稿者のレビュー一覧を見る
雨の日、ふらりと書店に立ち寄った。文芸作品が平積みしている場所の横に、ひっそりとこの作品が置かれていた。オビには、山本周五郎賞受賞・本屋対象2位と言う文字が飛び込んだが、私がはっとしたのは「若年性アルツハイマー」という言葉だった。奥付をみると、昨年の10月に発行、9刷りという大層売れた作品のようだった。寡聞にして著者の萩原浩という名前は存じ上げていなかった。手に取ったのが、間違いの元だった。
自分の母親を思い出した。若年性アルツハイマーではなく、老人の痴呆症だった。病状は序序に進行する類のものだったが、家族は大変だった。親の介護に忙殺され、本人のみならず家族全員が疲労困憊、一歩間違えば家族崩壊という状況だった。子供の名前すら認識できなくなった親を看るのは辛かった。
さてこの物語だ。主人公佐伯は、50歳の広告会社のサラリーマン。ばりばり仕事をこなし、一応の地位も得ている。夫婦中も波風立たず、一人娘も結婚する時期を迎えている。平凡といえば平凡な、人生を送ってきた。ある日、こまった事が起こる。大事な取引先との約束の日日を間違える。本人に自覚がない。
突発的な事故は急に発生するゆえ、衝撃度が強い。緩慢な事故は、慢性化しているため本人の認識が遅い。なんだか変だ。相手の名前が浮かばない。すぐ物忘れする。簡単な計算に手間取る。思い出そうとしても思い出せない事が頻繁にある。等等。やっかいなのは、初期には自覚症状が、無いことだ。周りの人がいち早く本人の異常に気づく。その時は既に、症状が相当進行したときだ。
主人公の父親もアルツハイマーだった。記憶喪失ばかりでなく、人格喪失と言うところが怖い。人を疑り、怒り、温厚な人間が訳もなく豹変する。周りの者は、病気の所為だと頭で理解出来るものの、気持ちや体では理解できない。遺伝だろうか。佐伯も時々考える。家族も考える。遺伝だろうか。こんな風に、世代を超えて影響力を与え続ける。
長生きする老人が増え、健康であればこれほど喜ばしい事はない。しかし実際は違う。多くの病気を持った老人が増え、医療の向上はあるものの、施設に問題があったり、看護に家族が疲れ果てるというのが現実だ。特にアルツハイマーという病気は、やっかいだ。人格が変わってしまう患者と家族や周辺の人が、どのように付き合っていくかが大いに問題となる。
この作品の最後の場面、佐伯が特別養護老人ホームの予約の帰り、学生時代に師事した陶芸家を訪れる。死んだ友人児島と、通い慣れた山道や周りの風景は、以前と変わらず思い出すことができた。菅原老人とは、酒をのみ野焼きをした。意識ある最後の思い出となる夫婦茶碗を焼いた。もうそろそろ失礼しなければ。
吊り橋の手前までいった。これが、佐伯本人と別人格佐伯との別れの橋だ。今までの佐伯はこれを以てお別れだ。アルツハイマーに取り込まれた。前をみると、見知らぬ女性がたっている。一緒に橋を渡る。名前をきく。「枝実子っていいます。枝に実る子と書いて、枝実子」
妻が現れたが、この女性は佐伯にとって今や妻ではない。ではだれか。誰でもない。ここからまた新たな夫婦関係が始まった。これから二人して、困難な道が待ちかまえている。一方は記憶を無くし、ある種幸せであるかもしれない夫と、一生連れ添う苦労が目に見えている妻。
身につまされる話であり、感動の物語であり、若い人達に読ませたい作品である。
紙の本
心の準備をしたい・・・
2005/04/17 14:03
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:テノール - この投稿者のレビュー一覧を見る
主人公の佐伯氏は、アルツハイマーと診断され、次第にフェイドアウトしていく自分の記憶や、思いを忘備録という形で書き始める。症状が進んでいくうちに、忘備録には、同じ内容が重なって書かれ、読み手に「ああ…」と言う思いを持たせる。忘備録以外の記述で、症状がプツッという音を感じて進むという場面がある。そのプツッという音は、外に聞こえる音ではないが、読み手にも不安の増す気持ちが、伝わり、また、本の最後、症状が進行し、連れ合いの顔さえわからなくなった時点では、落ち着きが伝わってくる。
まず、ちゃんとした病院に行けたこと・本人に行く決意ができたこと。
そんなにうまく病院に行けるだろうか? 良い病院があるのだろうか? だが、佐伯氏が病院に行けたのは、まだ4〜50代の自分…その自分の不安を解決しよう、アルツハイマーでないことを、はっきりさせようという気持ちだったのかもしれない。
私事ではあるが、30年ほど昔、父の友人で、電車の通勤定期の期限が半年も過ぎていることを駅員にとがめられ、家に連絡が入り、奥さんが呼ばれ…ということがあった。「初老性痴呆症」という病名がつき、すぐ入院され…それはまだ40歳代だったように思う。まだ、アルツハイマーという言葉が出回ってはいない時代だった。会社では、どうされていたのだろう?と思っていた。「明日の記憶」の佐伯氏のような思いをされていたのだろうか? 今は、私自身、物忘れの王者といってもよいほど、毎日、捜し物をしない日はないほどで、情け無い思いをしている。また、80歳になる母も、昨年夫を亡くし、とんでもない物も冷蔵庫にしまったり、今日が何曜日だということを日に10回ほど聞くことがある。
アルツハイマーであってもなくても老いていく中で記憶についての不安はつらいものがある。
前半、佐伯氏が仕事上で、部下との対応やクライアントとの対応、出張先への道順や場所自体に不安を覚えているあたり、病院に行くまでは、読むのがつらかった。しかし、人間、何があっても自分の状態を受け入れられれば、他の病気と同じように苦しみを減らせるかもしれない。もし、はやくから、アルツハイマーの可能性がわかっているなら、様々な準備や心の整理がほんの少しかもしれないが、できるかもしれない。症状の進行を遅らせる薬が開発されていると聞く。期待している。ま、本当は、誰もが、いつどうなるかは分かっていないから、ある意味での死(精神的な死の含め)への準備をしながら生きて行かねば、という気もする。ただ、なかなかそれが難しいのであるが…
紙の本
病を受け入れた先にあるもの
2005/01/11 21:01
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:吉野桃花 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ごく普通のサラリーマン。そろそろ固有名詞がぱっと出てこない50代に突入した。うまく眠れない。どうも体調が思わしくない。家族の勧めもあってようやく病院を訪れた佐伯は、数度の通院の後、若年性アルツハイマーの病名を告げられる。
この物語は、佐伯が病を自分のものとして受け入れていくまでの物語だ。
単なる物忘れとして済ませられないほどの病状になっても、今は会社を辞めたくない一心であがく彼の姿が切ない(何故今は辞めたくないのかは事情があるのだ)。身につまされる。頑張れ、頑張れと思いながら読みすすむ。忘れてしまうので、どんな細かいことでも執拗にメモを取りポケットにメモを詰め込んでいる姿。周りもうすうす何かおかしいと気付いているのに、本人は気付かれていないと思うその気持ち。いやほんとはわかっているのだけど、誰もつっこんではこないのでバレてないと信じたいのだ。痛いほどわかる。
会社という組織のなかで、何かおかしいけど自分がフォローしてでもこの人と仕事をしたいと思ってくれる人もいれば、何か変なのでこれをチャンスと引きずりおろそうという人もいる。この人になら打ち明けても大丈夫と「私はアルツハイマーで忘れてしまうので、おかしなときがあるかもしれないけれど教えてください。」と言えば、利用されて裏切られる。
こう羅列すると何か陳腐なようだけど現実はほんとうにそんなもので、私の父も入院したときに「人が自分をどう思っちょるかようわかるのう。今まで仲良くしてて、こっちもできることは色々協力してやった奴が見舞いにも来ん。そうかと思や何遍も来てくるっ人もおる。」と話していた。
周りの人間。家族、同僚などがどう病を受け入れるかというのも、ものすごく重要なことなのだとわかる。そしてここが難しいのだ。「元に戻って欲しい。」と思ってしまうから。
私は現状を受け入れて、その中でのベストを探って行きたい。受け入れるには少々時間がかかっても、大切な人の今の状態を受け入れて、だけれども投げやりになるのではなく一緒の時間を過ごしたいと思う。そしてそれは闇雲に自分で面倒をみたいということとは違う。介護をされる方も身内でないほうが事務的でいい部分もあるわけだし、そこのところは使い分けたい。
これをきれい事だと思うだろうか。きれい事かもしれない。それでも。愚痴ったり、もう知らん!と思ったりしながらも、芯はその心持ちでいたい。
そう思わせてくれる物語だった。人格とは記憶の積み重ねかもしれない。でも記憶がなくなることが人格の崩壊だろうか。本人が覚えていなくても周りの私たちが覚えているのだ、彼らの今までを。病のせいでずたずたにされた精神も身近な者の心のなかには生きているのだ。それを忘れずにいたい。
ラストシーンは哀しいと思う人もいるだろう。でも私は、病を受け入れられた彼らのスカッとした姿が浮かんで「よかったね。」と思った。ものすごく晴れ晴れとした青い空を思うラストだった。
紙の本
人生の中で読まないことが損だと思う本がある。この作品はその中の1冊である。読むべし!
2004/12/11 11:46
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エルフ - この投稿者のレビュー一覧を見る
読みながら泣いた、いや途中からはずっと泣き続けながら読んでいた。
50歳で「若年性アルツハイマー」と診断された佐伯、なぜ自分が、なぜ「アルツハイマー」なのだ? 絶望や怒り、恐怖に怯える日々の中、唯一心の支えにしたのは娘の結婚式までは「今の自分」でいること、だから会社にも病気のことは隠し通す決心をしたのだが病気は待っていてはくれない。
突然忘れる取引先の場所、毎日のように通っていたのに見知らぬ土地に思えてしまう。一体ここはどこなのだ? 恐怖にパニック状態になる佐伯。
手から砂がこぼれ落ちるように佐伯の記憶はどんどん抜けていく。
「備忘録」として日記を書き始めるがその記録すら読み返すと忘れていることが多い。
また周りの人々も変化をみせる。佐伯を利用する者、裏切る者、また別の顔を見せて救う者。
実は最近主人公の佐伯と同じで固定名詞は出てこない、人の名前は覚えられないし同じものを二度買いする事もある。とても人事ではない。
そういうのもあり、また佐伯の一人称で語られているせいか自分と佐伯がいつの間にか同一化しているのである。忘れたくない、最愛の家族。だが妻の顔をいつまで覚えていられるのだろうか、娘の顔を忘れないでいられるのだろうかという恐怖と悲しみ、それらが読んでいて自分に迫ってくる。
いつの間にか私は佐伯自身になっているのだ。
世界中で読まれ涙の渦に巻き込んだ「アルジャーノンに花束を」と雰囲気は重なる。今の自分を失う恐怖やそれを綴る部分も切なさもだ。だがあの作品はSFの作りモノに思えて感動しなかったのだが、この「明日の記憶」は違った、作りモノとは思えないのだ。あまりにも身近過ぎ、そして佐伯の心情が伝わり過ぎて涙が止まらなくなった。
これはただの「アルツハイマー」患者の物語ではない、書かれている中で一番の柱となっているのは夫婦愛である。
ラストの一行まで一切手を抜かないのが荻原氏なのだが、これまでの作品の中でもこの「明日の記憶」には群を抜いているラストである。
この一行を読んだ後、またしばし涙が止まらなかったのは私だけであろうか。
紙の本
最初はただの物忘れだと思っていたのに…
2004/11/01 19:06
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なかちん - この投稿者のレビュー一覧を見る
広告代理店の部長職にあった、50歳の主人公
度重なる、物忘れや不眠に悩まされ精神科の門をくぐる。
そこで、明らかになった病名「若年性アルツハイマー」
どんどん自分の中から記憶が消えていく恐怖と
一人娘の結婚式までは何とか会社に残っていたいという
サラリーマンの悲哀。
徐々についさっきやっていた事も忘れてしまうという
事を会社の人間に悟られないように、次第にメモを残していく。
自分が自分でなくなるという辛さ。
アルツハイマーという徐々に記憶を失い、
刻々と迫り来る時間との戦い。
身近な家族の顔すら忘れてしまうというむごさ。
果たして彼はどういう選択をしていくのか…
読み終わった後には、虚しさとともに悲しみも沸いてきます。
病気と闘うには家族の理解が不可欠という事も
あらためて実感できる一冊です。
紙の本
本屋大賞を見て、読みました。
2014/10/31 22:02
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:shingo - この投稿者のレビュー一覧を見る
本屋大賞を見て、読みました。
アルツハイマーの話。救いはありませんが、それでも生きる形をちゃんと描いています。
紙の本
「身につまされる」のはいくつからだろう
2005/01/28 11:46
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:びっけ - この投稿者のレビュー一覧を見る
主人公、50歳。若年性アルツハイマーを患ってしまう。
物語は淡々と、そして確実に病気の進行を記していく。
この小説ほど、読者の年齢によって心への「のしかかり度合」が変わるものはないのではないか。
40代以上の読者は、感情移入とはちがった意味で主人公に自分を重ねてしまい、次のページを(つまり、それは主人公の人生のページを)めくりたくない、けれど、めくらずにはいられない、その繰り返しで最後まで一気に読んでしまうであろう。自分だったらどうだろう。自分の家族はどうだろう。常に頭の片隅でそう問いかけながら…
20代、30代の読者はどうだろう? きっと病気の恐ろしさ、主人公の苦しみははわかるだろう。
けれども、何か棒のようなものを飲んでしまったような感覚はもたないのではないか。
どっかりのしかかられてしまった私にとって、最後の場面は本当にありがたかった。
何度も何度もその場面を読み返してしまった。そして、その都度胸につかえた棒が溶けていった。
主人公の人生が、最後の場面で終わらないことを私たちは知っている。
病気が更に進行することも知っている。
けれど、最後に描かれた微笑があるから、ほっとして本を閉じることができるのである。
紙の本
予想以上にスリリング。荻原版「アルジャーノンに花束を」。
2012/05/18 02:42
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しのはら - この投稿者のレビュー一覧を見る
流行りモノが苦手で、2006年に映画化され話題になった本書にも長らく手をつけていなかったのですが、「そろそろほとぼり冷めたかな」と読んでみました。(何のほとぼりだ?)
近年、解明が進み話題になってきた「若年性アルツハイマー」という病。若くして神経細胞が減少し脳が萎縮。その機能が低下し、記憶障害のみならず、最終的には生命にも関わる病気だといいます。
「若年性アルツハイマー」と診断された本書の主人公は、50歳。広告代理店の部長職にあり、まだまだ働き盛り。彼は進行していく病といかに葛藤し、またどのようにおかされて行くのか。また、その時家族は・・・。
映画化の時に、さんざんマスコミに流布されて大筋は分かっているし、なんとなく先が読めそうで、失礼ながら、なめていたかも知れません。
しかし、読み始めてみるとこれが、予想以上にスリリング。ページをめくる手が止まりません。テーマがテーマなのにただ暗いばかりでもなく、折々に著者お得意のユーモアも。
同じ著者の「神様からひと言」の時にも思ったのですが、分かりやすくキャッチーなシチュエーションを題材に、しかし、それを、書き込まれた人物像や具体的なエピソードの力で、ぐいぐい読ませる話に作り上げていくのが上手い方なのです。
本書の場合、何といっても、病を得てからつけ始める主人公の「日記」が鍵。
これは著者も確信犯だと思うのですが、SFファンタジーの名手・ダニエル・キイスの「アルジャーノンに花束を」を彷彿とさせます。
(病への不安が書かれているとはいえ)普通に安心して読めた日記の文章に、日を追うに従ってある変化が・・・。読者がそれに気付いた時の、冷やりとする恐ろしさ。
主人公が何を失おうとしているのかをリアルに感じさせる、著者快心のトラップなのです。
でも、話も終盤に差しかかる頃、主人公が、生まれたばかりの孫の寝顔に「頼むぞ」と声をかけるシーンで、思ったのです。
その思いは、アルツハイマーであろうがなかろうが、同じなのではないか。
いつかは個としての生を終える運命の、すべての人間にとって。
終わっていく自分の命から、新しく生まれてくる命へ、バトンタッチするさまざまな思い。願い。自分にとって大切なもの、失いたくないもの、残したいもの、託したいもの・・・。
この主人公の場合は、若年性アルツハイマーという病のために、それが特に凝縮されたわけなのだけれど。
本書は、すべての人間がいずれは失う「自分という個」と「生命」について考えさせられる、とても切なく、非常にスリリングな物語であります。
紙の本
最後が少々できすぎだが、それはやはりフィクションだからか
2009/03/08 00:50
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みなとかずあき - この投稿者のレビュー一覧を見る
特にこれといった理由があるわけではないが、ベストセラーは読まないことにしている。多くの人が読んでいる本を自分も読むというのが何だか癪なだけというだけのことと言えなくもないが。
さらに山本周五郎賞や本屋大賞を受賞したり、映画化をされたりというと尚更読むのが癪に思えてしまう。
それでも映画は見てしまったし、何よりここで取り上げられている若年性アルツハイマー病は自分の仕事とも関係がなくはないので、いつかは読むことになるのだろうとは思っていた。
なので、もうそろそろいいかと思って読んでみたのだけれど、なかなか身に詰まされる話だった。
仕事柄若年性というわけではないにしてもアルツハイマー病の方たちと接することがあるが、そんな立場から読んでもかなり的確に描写されていると思う。その部分だけ取り上げればノンフィクションと言ってもいいと思う。そして、自分もこんな風になるのではないか、なりたくないと思わせるくらいだ。
だからこそ、最後が少々きれいすぎというか、出来すぎのような気がする。病気が進行したその先にあるのはこのようなまとまり方ではないのでは。
主人公が結果最後となる会社の忘年会を終えた帰り道に考えるところで次のような言葉がある。
「人の死は、心臓の停止した瞬間に訪れるのか、そえrとも脳が機能を失った時からなのか、その論争に関してはいろいろな話を聞かされてきたが、記憶の死はどうなのだろう。記憶の死だってイコール人の死ではないのか」
人間らしさを失うという意味でいうのならば、やはり記憶障害などが進行していくのは死に等しいものがあるのではないかと思う。しかし肉体としての人は死んでいないのだ。そこのギャップを本人が感じることなく、周囲の人たちにこそ感じさせてしまうところにアルツハイマー病などの残酷さがあると思う。この物語の最後は、そこをなんだかきれいにまとめてしまったように読めてしまうのだ。
また、これは病気であることを主人公が知って初めて成り立つ物語なのでやむを得ないかと思うが、主人公が比較的すみやかに病院にかかり、診断を受けるというところもやや出来すぎのように思う。現実は、病気であることもわからず、診断もされないままに病気が進行していくという問題もあるのだが。
というように少し気になるところはあるが、全体としてはかなり読み応えのある話で、やはり文学賞を取るだけの作品だと納得してしまった。ベストセラーとなるにはそれだけのものがあるのだ。
もう一度映画も見てみようと思う。
紙の本
記憶がなくなっていくことに立ち向かう心
2005/07/10 05:53
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:未来自由 - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者の作品を読むのは二作目である。『僕たちの戦争』と本書。感心するのは、それぞれの作品が、社会的なテーマに真正面から立ち向かっていることである。
本書のテーマは、若年性アルツハイマー。50歳になったサラリーマンが、不眠や頭痛、眩暈に襲われる。ストレスによる心身障害かとおもいきや、若年性アルツハイマーと告知される。
記憶が突然失われるという恐怖、怯え。記憶をつなぎとめようと、必死にメモをとる姿。初期の段階では、社会生活は営めるが、それ以後は社会生活にも支障が出る。
通いなれた道を突然忘れパニックになる、人の名前が思い出せない、相手が誰だかわからなくなる。
少しずつ、アルツハイマーとは何かが、読者にもわかるように日々の日常から描かれている。そして、まだまだ理解しようとしない社会の現実と、介護保険制度や施設の不十分さも描かれている。
苦しんでいるのは本人だけではない。周りの人も苦しんでいることに本人は気がまわらない。ここには、本人だけの問題ではなく、家族や社会の問題でもあることが訴えられている。
『博士の愛した数式』がベストセラーになり、博士は愛すべき人物として描かれている。しかし、アルツハイマーは記憶だけでなく、人格さえ失われていくようである。
治療法の解明が進められているが、まだまだ治療法は確立していない。そのもとで、人々が支えあう、社会的な人間環境が大切であろう。そんなことを考えさせてくれる作品である。
記憶が失われ、人格が変わっても、人間は人間である。脳死が人の死とされる現代、記憶死をも人の死と考えるような論調があるのなら賛成できない。脳死、それもやはり人の死ではないと考える。
著者は、はっきりとは書いていないが、どんな状況でも人間に変わりないことを描こうとしている。
美しい自然の中を歩く姿の描写は、人間への声援歌のように聞こえてきた。
紙の本
こみ上げるもの噛み締めん
2004/10/20 12:48
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ナカムラマサル - この投稿者のレビュー一覧を見る
主人公・佐伯は広告代理店営業部部長、50歳。
一人娘の結婚式を前に、若年性アルツハイマーと診断される。
結婚式まではなんとか自分らしい自分でいたいと、娘や会社の人間には病のことは伏せて、それまでの生活を維持しようとするのだが、当然仕事に支障をきたすようになる。
得意先の河村という自分勝手な男には嫌みを言われ、職場の仲間でさえも心の許せない存在となっていく。
彼の唯一の趣味は陶芸。木崎という教師には本当のことを打ち明けることができる。
「年をとり、未来が少なくなることは悪いことばかりじゃない。そのぶん思い出が増える」と思っていた矢先、その「思い出」を失い始めた彼のつらさは、「アルツハイマー=ぼけ」と軽んじられるつらさ、死に直面したつらさ、も同時に背負っている。
通常の痴呆が脳の血管の異常が原因であるのに対して、アルツハイマーは脳内の神経細胞そのものを冒す、死に至る不治の病である。
そしてそのことは世間では深く認知されていない。
本書は、アルツハイマーに罹った主人公とその妻の苦しみだけでなく、周囲の人間の変化も巧みに描いている。
それまで仲間だと思っていた人間が、彼の病をきっかけに、彼を裏切る存在になり得たり、逆に、敵だと思っていた人間が、彼を慰める存在になり得たり…
そういった現実の世知辛さや闇の中の灯火を、感情に流されずに描いている。
これだけの材料が揃っていれば、おそらくもっと「泣かせる」小説ができたはずだ。
そこをあえて抑制したことによって、本書は心の奥の引き出しにしまわれる一作となった。
決して泣けない小説ではない。
ただ、その涙は一過性の涙ではなく、「ここで私が泣いちゃあいけない」と飲みこむ涙、頬の上の辺りがひくひくとするような涙なのである。
読後に残るのは、“人間にとって最も怖いのは記憶を失うこと”という思い。
たまらなく苦いが、噛み締めなくてはならない味だ。
紙の本
人間というのは記憶の集合体
2005/04/15 21:18
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:yukkiebeer - この投稿者のレビュー一覧を見る
広告代理店の部長を務める50歳の私は原因不明の頭痛に襲われるようになる。診察の結果告げられた病名は若年性アルツハイマー。徐々に記憶が薄れ、取引先とのアポイントメントやその所在地も記憶できなくなる。やがて病気のことが勤務先に知られてしまい…。
「記憶は自分だけのものじゃない。人と分かち合ったり、確かめ合ったりするものでもあり、生きていくうえでの大切な約束ごとでもある」(214頁)。
この言葉がとても心に沁みました。
この小説の第一の核はもちろん、記憶を失っていく主人公の悲しみにありますが、同時に妻の枝実子もまた、分かち合ってきた夫との記憶を無理やり剥ぎ取られてしまう哀しみを抱えている。そのことを象徴した言葉です。
そんな風に考えながら読み進めると、最後に待ち受けていた結末はやはり私の想定した通りでした。ダニエル・キース作「アルジャーノンに花束を」、ニコール・クラウス作「2/3の不在」など、記憶に関する小説をいくつか読んできた私の目には、その場面は決して新奇なものには映りませんでした。
ですが、私は決してそれを否定的に読んだわけではありません。これこそが最も苛酷で切ない幕切れなのです。上記2作品では私はその結末部分を幾度も読み返したものです。
ここでその詳細に触れるのはレビュー規約に反するために出来ませんが、この「明日の記憶」もまた同様に美しい結末をもった物語であったとだけ申し上げておきましょう。
紙の本
身につまされる、それは本当にいい小説の条件だろうか、勿論、ベストセラーの条件ではあるだろうけれど。でもラスト、ここだけは認めます
2005/03/06 14:24
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みーちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
果たしてこの本を傑作と読んでいいのか、正直気になるところではある。それは、例えば有吉佐和子『複合汚染』『恍惚の人』を、文学史的にどのように位置づけるか、と同質の問題であるといっていい。ただし、面白い。いや、そういう軽い言葉が罰当たりのように思える。そう、珍しく長女より先にこの本を読み終えた中二の次女がいった言葉「なんだか、とても可哀想」というのが正しいのかもしれない。
扱われるのは若年性アルツハイマー。決して悲劇的ではない、ただ予想よりちょっと早まった発症で、周囲よりも何よりも自分が蝕まれていく、そんな病気である。そして、この病の厄介なところは、決して治らないことである。良くて現状維持、いやそれすら稀なことかもしれない。加速する、それが普通なのだろう。
そんな病に取り付かれた(こう書くといかにも悪霊かなんぞに乗っ取られたかのようだけれど、ある意味、それも正しい)のが、広告代理店で営業部長を務める佐伯、49歳、いやご当人のおぼろげになりつつある記憶では、つい先日50歳になったばかりである。妻の名前は枝実子、年齢は書かれてはいない。二人には24歳になる娘梨恵がいる。その娘は、設計事務所をもつ建築家で9歳年上の渡辺ともうじき結婚をする予定である。そして娘は妊娠している。
仕事の面で言えば、二週間後に控えた競合プレゼンテーションの陣頭指揮を執るのが、主人公ということになる。その企画会議で、佐伯は自分の記憶が怪しくなっていることに気付く。最近人気の俳優の名前が出てこない。いや、一昔前の有名な作家の名前も怪しい。しかし、実務は何とかこなせる。だから、今回の仕事もあっさり勝ってしまうのだ。しかし、それをきっかけにしたかのように佐伯の記憶障害は進行する。そして下された診断結果が、若年性アルツハイマー。
それは、全64章の15章で明らかにされる。あとは、身につまされながら一人称で語られる話をひたすら追うしかない。脳裏をかすめるのは、私にとっては夫であり、娘にとっては自分たちの父親だろう。この本を最後に読んだ夫は、現在ひとりで暮らす母親、或いは晩年の父親のことを思い出すという。
そう、義父は亡くなる前の数年間、軽い痴呆状態ではあった。義母の止めるのも聞かず、思いつけば電車に乗ってどこかに出かける。そして泥だらけになって夜遅く帰って来る。そして、周囲といっても、一緒に暮らす義母に当り散らす。それを哀しそうに伝える母親の言葉に、相槌だけをうっていた夫。その義父が亡くなったのが77歳。
その義父を看取った義母も、最近は同じ言葉を繰り返し、曜日の観念が曖昧になってき始めた。いや、夫ですら、以前ほど記憶力を誇示することはなくなってきた。ただ、佐伯と違うところがあるとすれば、義父にしても義母にしても、痴呆の気配を見せ始めたのは70過ぎである。いや、夫も一応は50歳を越えはしたものの、ごく普通の老化を見せているに過ぎない。
しかし、佐伯を襲うのは若年性の記憶障害である。それを第三者の視点ではなく、当人の視点で描く、それが読者をこの話を他人事にはしない。しかし、だ。この本の読まれ方は、明らかに『恍惚の人』の21世紀バージョンであって、例えば週刊誌の記事の読まれ方と全く変わるところはない。
それが、多くの読者の「身につまされる」「明日のわが身」といった反応に現れる。それが悪いとは言わない。しかし、これが文学的感動かといわれれば、違う。それでも、ラストの三行、もしかして荻原はこれを書きたいために、全てを作ったのでは、そう思わせるものがある。ここで涙しなければ、貴方は介護をする側にもされる側にもなることはないだろう。
紙の本
病気の恐さはもちろんのこと、真の夫婦愛について再認識させられる作品です。
2004/12/04 12:44
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:トラキチ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本作は、主人公が“若年性アルツハイマー病”に罹って段々悪化していく過程を描いたものである。
内容からも推測できる通り、いつもの荻原さん特有のハチャメチャなユーモアが完全に抑制されている。
そこに氏の並々ならぬ本作への“熱き想い”を感じ取られた方も多いのであろう。
本作を通して読者はアルツハイマー病という病気の恐さを否応なしに知ることが出来る。
荻原さんは本文中の日記において病気の進行度を如実に描写した。
始めは誤植かな思われた方もいらっしゃることだと思う。
一番胸に打たれたのはやはりアルツハイマー病に罹っているとわかりつつも、愛娘の結婚式まではなんとか会社に残りたいと言う愛情である。
ただ、この作品ほど周りに患っている人がいるか否かによって感じ方が違う作品はないのだと思う。
幸い私自身身近にいないので自分の幸せを身に沁みて感じ取ることが出来た。
しかし危ないのは私自身である。
本作における様々な兆候が自分自身にも見出すことができるのであるが、果たして私だけであろうか?
自分には関係ない思えるのはせいぜい20代ぐらいまでで、やはり30代に突入すると物忘れも本当に激しくなる。
年々忘れっぽくなっている自分を自覚されてる方も多いであろう。
しかし敢えて周りの人々=家族の大切さを謳った作品であることを強調したいなと思う。
「もういいよ、俺のことは。おまえはまだ若いんだから、俺がいなくなってからのことを考えろ」
「なにそれ? 安っぽいドラマみたいなことを言わないで。言われる身にもなってよ。こっちには最終回なんかないんだから」
枝美子が声をあげて泣くのを聞いたのは、いつ以来だろう。たとえ病気でなくても覚えていないほど遠い昔のはずだ。
すなわち、本作において1番大切な点は病気の恐さを身を持って知ってほしいことではない。
それは2番目に大切な点だと思う。
いたわり合い慈しみ合うことのできる人がいることの喜びだと思う。
荻原さんのシナリオは寸分の狂いもなくラストへと導かれて行く。
ラストシーンがいつまでも脳裡に焼き付き、心に小春日和をもたらせてくれた。
私は主人公に代わって、奥さんに強く感謝したい気持ちで本を閉じたのであるがみなさんはどうであろうか…
病気は深刻であるが、“主人公は幸せものだ”と声を大にして叫びたいなと思う。
トラキチのブックレビュー