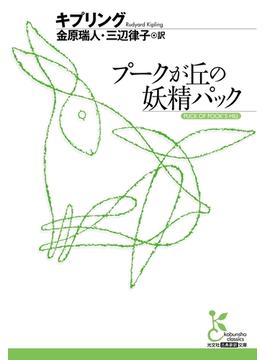いったいなぜ、この作品が100年も未訳だったのだろう。イギリスの歴史を語る楽しい「歴史むかしばなし」
2007/04/20 17:23
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
二人の子供が「真夏の夜の夢」の劇で遊んでいて、偶然、妖精のパックを呼び出してしまう。パックは二人に、彼らの住む土地、イングランドの昔の話をその時代の人を呼び出して語って聞かせる。イングランドの歴史を子供に聞かせようとしてキプリングが書いたお話だそうです。キプリングは「ジャングル・ブック」ぐらいしかしらない日本人は多いのではないでしょうか。こんな楽しいお話もあったのか、と思う作品です。
まるで、田舎に行ったらおじいさんやおばあさんが「この裏山ではね。。」と昔の戦争や、その又昔のお殿様の話をしてくれるような、そんな雰囲気です。あちらの国でも、子供はこうして自分の国を教えられていたのかな、と状況が目に浮かぶようです。新しい時代の子供たちと、昔の人物たちの会話もユーモアのある、楽しいものです。
イングランドにもローマ人がいたこと。ノルマン人が攻めてきたこと。攻めてくる二つの民族の間で立ち回らざるを得ない土地の民がいたこと。イギリスの歴史の一幕を書いているのですが、その中にどこの時代、どこの国にも起こった話でもあると感じさせる内容があります。闘った人々の心や生活にも、違和感無く共感できるものは多いです。例えば二つの民族に侵略され、どちらにつくかと苦労する民の話は、アジアの隣国をも想起させるもの。戦争の中でも芽生える友情、信頼。若者特有の反抗や熱情。家族への思い、それを聞く子供たちの感想。どの国、どの時代にも共通する何かを見出し、目頭を熱くする場面もありました。立ち回る人間のこすっからさ、それがその場では一番よい方法だったような事件があったりもします。子供向けに書かれたそうですが、まず大人が読んで楽しむ部分がおおいでしょう。
1906年の作品ですが、日本では100年たってやっと翻訳されました。キプリングは「愛国的過ぎる、アジアへの偏見がある」といわれていた時期もあったようです。このおはなしの中でも、侵略してきてイングランドに住むようになった兵士の「ノルマンではもはや無く、イングランド人p144」と言う言葉や、最後にのっている子供たちの歌で「私は永遠に故国のもの」などと言わせているあたりが「国粋的」と言われたのかもしれません。しかし、インドで生れ、6歳までインドいたと言うキプリングは、土地の人々の大切さ、融和することの難しさを人一倍知っていたとも考えられます。このおはなしにはそんな一面の方が強く出ていると思います。
ラテン語の詩がでてくるあたりなどは、いかにもイギリスの、教育を考えた子供向きの話だな、と思わせます。エピソードのそれぞれを挟むように挿入されている詩も、さすがキプリング、雰囲気をだしています。ぜひ、原語の音感でも読んでみたくなりました。
いったいにこの光文社古典新訳文庫の訳者には、本当にこの本を今読んで欲しいという気概が溢れています。この本などもその好例でしょう。あとがきなどにもその思いがよみとれ「読むことの嬉しさ」「読めることの嬉しさ」をひとしお深くしてくれます。「あとがき必読」のシリーズでもあります。
トネリコの魔法に語らしめよ
2011/06/30 23:26
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:SlowBird - この投稿者のレビュー一覧を見る
キプリングという人は、インドで生まれ育ち、作家としての地位を得てからイギリスに戻った人だ。少年時代の一時期にイングランドで教育も受けている。大英帝国を外から、散文的な感覚で眺めた経験がある人とみなしたい。インドを舞台にした作品も素晴らしいが、イングランドの歴史を題材にした本作も、愛郷心とコスモポリタンとしての視線が混交して、子供向けファンタジーの域を越えた悲哀を奏でている。
オークとトネリコとサンザシの森の繁る、キプリング自身が家族と住んだサセックスの地。その森で二人の子供達が一人の妖精に出会う。シェークスピアにも登場するパックであり、彼の言うところでは古くからその土地をずっと見て来たのだという。そのパックが古い古い友人を(時間を越えて)招いては、子供達に昔語りを聞かせてくれるのだ。
それは古くにはたくさんいたという神々や妖精の話から始まって、それからローマからの征服者や、フランスの敵対者、北方からの侵略者、ブリテン島の古い種族とのせめぎ合い、それらに関わった人々が、この地で時間を越えて交錯していたことが、かわりばんこに語られる。
彼らは、王、百人隊長、兵卒、様々な土地の様々な出自を持ち、よってイングランドにとっての正義やナショナリズムなどは求めようもない。彼らも自身の利益、欲望に従って行動するだけで、英雄的と言えるようなものでもなく、時には駆け引きも奸計も用い、しかし公正さや思いやりといった行動規範に支えられている。しかしだからこそ、子供達が夢中になるハラハラドキドキに溢れていながら、大人も楽しめる苦さを備えた歴史物語ともなっている。
歴史の中に名前を埋もれさせているそんな彼らの残したものは、少しずつ積み重なって、イングランドの大きな歴史の流れの鍵になることもある。
そんなダイナミックな歴史観を見せながら、いつの間にか森と土と川と海が物語の半分を占めてもいる。その土地をもっとも愛しているのは、人々が移り変わっても変わらぬ大地を見続けて来た妖精パックなのだろう。そしてパック自身も、時とともに人々から忘れ去られる運命にある。
なにかこう、イングランドの森がこれから失われて行くことを、ロンドンからデヴォン、サセックスと移り住んだキプリングが予感したか、その兆しを既に見て取っていたのか、その哀借の情がこの物語を書かせたんだろうなあとも思えてくる。
投稿元:
レビューを見る
ある夏の日、ダンとユーナが<妖精の輪>で「夏の夜の夢」を演じていると、妖精パックが現れる。彼は子供たちの前に歴史上の人物を呼び出し、彼らの口からイギリスの歴史を語らせる。 これが本邦未訳だったなんて信じられない。確かによその国の歴史なんて取っつきにくいけど(前提となる通史もよくわからないし)、子供向けの本なので、もうちょっと子供が手に取りやすい形で発行できてもよかったかなぁと思います。大人も面白いよ。
投稿元:
レビューを見る
正直イギリスの歴史なんて全然知らんけど楽しく読めた。
『ジャングルブック』書いた人なんだ。へぇ。
つーかノーベル文学賞とってる人なんだ。へぇ。
無知丸出しですな。
歴史上の人物+妖精+兄妹での展開が新鮮。歴史上の人は誰一人知らないけどね。
なにより最後の『子どもたちの歌』が良かった。
力強くていい歌です。
投稿元:
レビューを見る
日本語訳なかったんですか。日本でも結構有名なのに意外だ。イギリスの歴史がわからない人でも楽しめると思います
投稿元:
レビューを見る
「ウィーランドが剣を与え、その剣が宝をもたらし、宝が法律を生んだ。オークが伸びるように自然なことだ」
日本と同じ島国であるが、何度も異民族の侵略と土着化が繰り返されたイギリスの歴史を、<古き者>パックが幼い兄妹ダンとユーナに語るという枠立てで、その枠の中にそれぞれの時代に生きた人々が生き生きと語るエピソードが納められている。
イギリスの歴史と伝承を知っていた方がずっと楽しめるのは確かだけれど、たとえトールキンやエリナー・ファージョン、スーザン・クーパー、ローズマリー・サトクリフ、フィリパ・ピアス、ジョーン・エイケンなどの作品に当たり前のように出てくる丘の住人やウェイランド・スミス、黒の乗り手などが作者個人の創作ではなく周知の存在だと知らなかったとしても、ノルマン人とサクソン人の騎士の友情や、裏切り者の神父と領主の顛末、密輸をするサセックスの村人達のしたたかさを味わうことはできる。
それにしても家庭教師からラテン語を学び、詩を暗誦し、夏至の前の晩に「お茶をすませてから、ゆで卵とバスオリヴァーのビスケットと封筒に入れた塩を持って」妖精の輪でシェイクスピア劇を演じる子ども達には羨望を抱くよ。
※バスオリヴァーのビスケット;バースの医師、オリヴァー氏が(バース名物のバースバンは甘くて脂肪分が多く、リウマチ患者の健康によくないからと)考案した脂肪分の少ないビスケット、らしい。
http://www.cornwall-calling.co.uk/famous-cornish-people/oliver.htm
投稿元:
レビューを見る
「真夏の夜の夢」のパックってロビン・グッドフェローという別名もあったのね。この本を読んで大人になったサトクリフは「第九軍団のワシ」の三部作を書いたそうです。だからなんとなく「銀の枝」に挫折したように、時間がかかってしまいました。続編「ごほうびと妖精」もあるそうです。いずれ翻訳されるのでしょう。サトクリフの三部作やこの本を読むと、クライブ・オーウェンの「キング・アーサー」に納得がいきます。イギリスの歴史のお勉強をしてしまいました。
投稿元:
レビューを見る
イギリスの児童文学。ふたりの兄妹が、妖精パックが呼び出したイングランドの歴史上の人物に物語を語ってもらうという体裁。
イギリス史お勉強強化中&妖精が気になる近頃なので、読んでみました。
キプリングはじめて読みましたがけっこうすてき。読みやすいしワクワクします。代表作もそのうち読んでみたいなと思う次第。
投稿元:
レビューを見る
「真夏の夜の夢」の妖精パックが主役。いいなぁ、私も召喚したい。
イギリス史の勉強にもなります。
投稿元:
レビューを見る
すごくワクワクさせられる、
童心に帰ることができる本でした。
もちろん読めたことに感謝であります。
内容としては、
古い歴史の物語を
プークや歴史に出てきた人物その人が
話してくれるものなのです。
私は世界史こそ苦手ですが、
そんな歴史があったことや
いかにして駆け引きをしていったのか
垣間見れて面白かったです。
それと、ダンとユーナの兄弟が
とてもかわいいのです。
純粋な子供の心をもっていて
でも、賢くて。
(ダンはラテン語で大目玉を食らいますが)
きっとワクワクさせられると思いますよ。
投稿元:
レビューを見る
イギリス史や出てくる歴史上の人物に、自分なりのイメージを持っている人が読めば、かなり楽しめると思う。
子供が読む場合、史実や背景を説明できるレベルの大人がいるのでは?
投稿元:
レビューを見る
1906年に出版され、100年後に初めて邦訳が出た。たしかにイギリスの古い歴史は日本人にはとっつきにくく、子ども向けの本だし、おとな向けに翻訳するという考えはなかっただろうと納得する。
舞台となっているペベンシーは歴史的に重要な拠点として英国の歴史に登場するという。タイムトラベルものといえるだろうか?子どもたちが時代を超えるのではなく、語り手たち歴史上の人物たちが時空を超えてやってくるのが、ちょっと変わってるかもしれない。
投稿元:
レビューを見る
イギリス海岸沿いに住む幼いダンとユーナの兄妹が近くの牧草地の丘で『真夏の夜の夢』のお芝居をしていると、妖精パックが現れる。
パックは、プークが丘の近くにある海岸都市ペベンシーに関わりのある歴史の人物を呼び出して、彼らの物語を語らせる。ペベンシーは小さい都市ながらもイギリスの歴史的に重要な役割を果たしてきた土地だった。ダンとユーナは、彼らの話を聞きながらイギリスの歴史をしるだった。
キプリングが、イギリス歴史を児童文学として書いた本。二冊セットらしいが、こっちしか買わなかった…。
イギリスの歴史語りではあるが、若者たちの友情や冒険、歴史にこっそり顔を出す妖精たちの存在など、物語としてとても楽しめる。
かつてイングランドに来た民族たちは、それぞれ自分の神を連れてきた。だが土地が合わずに去っていった神々もいる。そんななかでちゃんと働いた神様もいる。鍛冶屋の神ウィーランドだ。人々に混じりすっかり普通の鍛冶屋になったが、仕事を感謝されることにより神々の国に戻ることができる。最後に設えた一本の剣は、見習い僧でサクソン人のヒューの手に渡った。
やがてノルマン人がイングランド征服にやってきて、サクソン人との戦いとなる。そんななかでノルマン人リチャード卿と、サクソン人のヒューの間には友情が結ばれる。ヒューの家の所領はリチャード卿のものとなった。だがヒューはリチャード卿とともに土地を管理した。二人の働きを認めたペペンシー城主アクイラは、正式に二人に土地の所有を認める。
やがて年月が経ち、引退を考えるリチャード卿とヒューは、北海への旅に出る。海賊ウィッタの人質になったり、木の上に住み唸り声を上げる悪魔(ゴリラのことだろう)と戦ったりしながら、海賊ウィッタとも友情を育み、大量の金を手に入れて戻る。
金はペベンシー城のアクイラのもとに預けられ、二人も城に残る。そしてアクイラに仕掛けられた反逆者という罠を既に年寄りとなった彼らは跳ね除けるのだった。
/『ウィーランドの剣』『荘園の二人の若者』『騎士たちの愉快な冒険』『ペベンシーの年寄りたち』
ローマ皇帝がイングランドから撤退すると、残されたブリトン人たちは自分たちだけで、ピクト人たちから土地を守らなければいけなくなった。
グラティアヌス帝の時代に、イングランド生まれのローマ人パルネシウスは(ローマ生まれでイングランドに派遣された兵と、イングランド生まれのローマ人の間には階級の差があった)、軍隊に入り、百人隊長に任ぜられる。
将軍マクシムスの意に逆らったことで出世の道は閉ざされたが、変わり者のパルティナックスと気が合い、ピクト人アロを仲介としてピクト人対策を練る。
/『第三十軍団の百人隊長』『大いなる防壁にて』『翼のかぶと』
聖バルナバ教会再建には多くの人の力が関わった。騎士たち、海賊たち、そして絵や図面ばかり書いていたので図面ひきのハルと呼ばれた若者の物語。
/『図面ひきのハル』
非道な宗教改革の時代、フェアリーたちはイングランドから脱出を試みた。人間の力を借りる代わりに、人間にある約束をし��のだ。
/『ディムチャーチの大脱出』
ユダヤ人カドミエルの物語。ペベンシー城に紛れ込んだ彼は、かつてリチャード卿とヒューが隠した金を見つける。だがこれをイングランド王が見つければより戦争が深まってしまう。
/『宝と法』