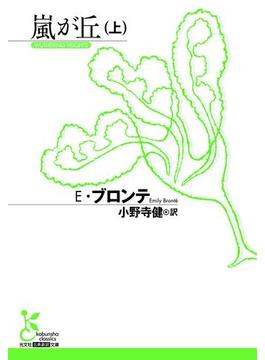イギリスならではの作品
2019/01/27 19:12
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
「高慢と偏見」をジェイン・オースティンが発表したのが1813年、それから34年後の1847年にエミリー・ブロンテがこの凄まじい作品を発表した。この2作品のイメージは、前者が出演者全員がお花畑で歌を口ずさんでいるとするならば、後者はといえば主人公のヒュースクリフがただ一人絶壁に立って何か意味不明ではあるけれど呪詛のような言葉を叫んでいるというくらい極端に違う。目の前にダーシーが現れたら、おそらく心臓がどきどきして顔が真っ赤っかになってしまうだろうけれど、キャッシーが現れたら、何かひどい言葉を浴びせられそうで逃げ出したくなってしまうだろう。誰一人、登場人物を好きになれない。でも、登場人物と同じに世界に浸って、のたうち回りたくなってくる
投稿元:
レビューを見る
キャサリンはヒースクリフ、ヒースクリフはキャサリン。
幼い日にかたく結ばれた愛情が
許されないものだと知ったとき、
若いふたりに致命的なすれ違いが生じる。その狂おしい顛末。
あらためて読んでみると、ネリーしゃべりすぎ(笑)
ネリーが妙な気をまわすせいで
こじれてる部分もかなりありそうだし、
案外「信頼できない語り手」なのかもしれない。
小野寺訳はネリーの小姑じみた嫌味も、
キャサリンの純粋さもうまくひろいあげてあざやか。
おどろおどろしさだけでなく、
風俗小説ふうのおもしろみがあることに気付かされた。
投稿元:
レビューを見る
一旦造形された性格や品性っていうのはずっと変わらない物なんだと思った。でもそれは愛情感情も同じ。
「嵐が丘」という題名にふさわしい登場人物達。荒々しい感情と相容れない立場をぶつけ合いながら、これからどうすればいいのか、どうなるのか、どうしたいのか。
衝撃を受けつつも期待して下巻に進みます。
投稿元:
レビューを見る
※全体のネタバレになってしまうので、具体的なテキストレビューは下巻の方に書きました。
非常に面白かったです。
憎み合おうがどうしようもなく惹かれあう激しい愛憎劇がお好きな方にはほんとお勧め。
投稿元:
レビューを見る
嵐が丘がどのような話なのか興味を持ったので読んでみたが、ヒースクリフはじめ、でてくる登場人物のセリフが過激だし、行動もいまいち理解できない部分が多い。キャサリンも意味が分からない。とにかくよくわからない話なのだが、最後まで読まずにはいられない。
投稿元:
レビューを見る
さて、この物語に関しても KiKi のこれまでの読書体験をちょっとご披露しておきたいと思います。 KiKi がこの物語を初めて手に取ったのは高校生の頃でした。 実家にあったハードカバーの新潮社(だったと思う)の「世界文学全集」の中の1冊として、そして高校時代に学んだ「文学史」の中の1冊として夏休みか冬休みといった長期休暇の間に読んでみよう思った物語の中の1つだったんですよね。
で、一応この時は当時の KiKi としては「かなりの忍耐力」を発揮して読了したんですけど、正直なところ読後感は最悪だし、何だか気持ちが落ち着かず混乱だけさせられ、「とにかく名作と呼ばれるこの作品を読了した」というレコードが残せたからまあよし・・・・という程度の印象しか残りませんでした。 ヒースクリフにしろキャサリンにしろ、その他どの登場人物にしろ「同じ人間とは思えない」という感想がやっとこさっとこ・・・・っていう感じでした。
次にこの本を手に取ったのは大学生の頃でした。 こちらも「高慢と偏見」と同じように「英文学を学ぶ学生の必読書」という感覚で再読してみました。 少しは成長した KiKi なら高校生の頃とは何か別の感慨を持つかもしれないという儚い期待を抱いていたんですけど、結果は最悪で「この病的なまでの暗さは何だ??」という印象しか残りませんでした。 ただこの時に高校時代とは異なって少しだけ魅せられたのは荒涼たる風景の描写の部分で、その部分だけは結構心に残って何度か読み返してみたりもしたものでした。
ただ、「紀行文」とか「自然描写」がテーマの小説ならいざ知らず、「小説」と名がつくものには「人間」を、それもどこか「共感できる要素のある人間」を求める KiKi にとってこの物語に登場する人物は悉く気に入らないんです。 で、その時点では「人がどんなに名作だと言おうが、KiKi には合わないし、良さがさっぱりわからない物語」として封じ込めちゃう道を選びました。 その後、今回の再読に至るまで KiKi はこの本を手に取ってみたことはありませんでした。
この決心は我ながらかなり強固なものだったみたいで、その後30年ほどの年月の間、ただの一度もこの物語を再読してみようという気にはなりませんでした。 このブログの読書カテゴリーの主軸を「岩波少年文庫」と「光文社古典新訳文庫」に定めていなかったら、そして「高慢と偏見」で満足感を得ていなかったら今回もこの物語に手を出してはいなかっただろうと思います。
そして今回。 正直なところ今回の読書でも KiKi はこの物語にさして感心することができませんでした。 やっぱりこの年齢になってもアーンショー家の誰一人(召使も含めて)として、リントン家の誰一人をとってもチラとでも共感できなかったんですよね~。 でもね、今回、ちょっとだけ大人になった KiKi は「気に入らないなりにこれは何を表現しようとした物語だったのか?」を考えてみたんですよ(苦笑) そして、今感じていることを、このエントリーを書くことによって整理してみたいと思うんですよね。
まず初代キャシーを含むアーンショー家の面々ですけど��唯一 KiKi がご近所さんとしておつきあいしてもいいかなぁと思えたのは、ヒースクリフをリヴァプールの街角で拾ってきたご主人のみです。 でもそんなご主人にしても「どういうつもりで彼を拾って家まで連れ帰ってきたのか、今後彼をどんな風に育てるつもりなのか?」に関してあまりにも「考えなし」なのが気に入りません。
そうでなくても「人種差別」や「階級差別」の激しい環境(嵐が丘周辺はある程度隔離されているとはいえ)の中です。 肌の色も育ちも名家であるアーンショー家とは相容れない存在であることが歴然としているヒースクリフを「飢え死にさせるわけにもいかないだろう」という一見「お優しい心遣い」により拾ってあげたところまでは良いとしても、養子にでもして守ってあげる気がないなら、「下男見習いとして」育てるべきだったんだろうと思うんですよね。
恐らくそれまでの人生でも蔑まれて生きてきただろうヒースクリフのことですから、中途半端に扱われるよりは「下男見習い」として最初から扱われていれば、それなりの成長の仕方もあったように思うんですよ。 でも、彼のポジションってあまりにも中途半端で、結果としてアーンショー氏の息子のヒンドリーは自分の父親の愛情を盗んだ盗人として彼を蔑むし、我儘娘の初代キャシーはまるでペットか自分の所有物かの如くにヒースクリフを猫かわいがりするに至ったような気がするんです。
そしてそんな「自分を頭ごなしに否定しない」キャシーはヒースクリフにとって熱烈な思慕の対象となっていったし、男尊女卑の激しかった時代のアーンショー家のご令嬢、キャシーも彼との交友の中で育まれる「自由な空気」に溺れちゃって何か大きな勘違いをしちゃったようなところがあったんじゃないかと思うんですよね。 結局アーンショー家の人々は誰一人として「一人の人間としてのヒースクリフ」とまともに向き合った人はいなかったんじゃないか・・・・・そんな風に思うんですよ。
これは召使陣も御同様で、本来自分たちが仕えるべきアーンショー家の一族ではないし、人種的にも自分達より劣ることはあっても優れているとは思えない(というのが当時のジプシーに対する見方だったと思う)ヒースクリフが分不相応な態度をとる(但し、この時点でヒースクリフには別に悪意もない)ことを苦々しく思うことはあっても好意的には受け止めることは決してできなかっただろうと思うんです。 それを表立って表現せずに陰湿にチクチクやるのは偏に「旦那様」の目があるからに過ぎなかったんだろうと思うんですよね。
そういう意味ではヒースクリフはアーンショー家に引き取られてからというものの、どちらかというと不当(?)に甘やかされ、大人の裏表のある行為に晒され続け、ひょっとしたら彼の奥深いところには眠っていたかもしれない「謙虚さ」も「素直さ」も呼びさまされないまま「頑固さ」と「ねじまがった卑屈さ」だけが醸成されちゃったんじゃないのかなぁ・・・・・と。
だからアーンショーの旦那様の死後、ヒンドリーやキャシー、はてはエドガー・リントンに至る所謂「地主階級」と「持たざる者」である自分の差別に気が付かされた時にはもはやそれをどうしても受け入れることができなくなってしまっていたし、ヒンドリーの変貌ぶりは横暴としか思えずに「憎しみの芽」を育て始めるようになっちゃったんじゃなかろうか・・・・と。 恐らくどこかの時点で、自分と他の人たちが外見という点でも大きく異なることにも気が付いたんだろうと思うんです。 でも、「その違いが何なのか」を教えられることだけはなかったんですよね。
彼は「持たざる者」から「持つ者」に生まれ変わることだけがこの不当な世界から自分を解放してくれる唯一の方法だと信じ、ついでに自分を蔑んだ人々に復讐できるとも思ってしまったのではないかしら?? そしてその「持つ者」になった時、自動的に自分の手に転がり込んでくるはずのものは恋慕の対象だった初代キャサリンだったんだろうな・・・・と。
だから彼は嵐が丘を手に入れてもキャサリンを手に入れられなかった時、恐らく辛うじて残っていたかもしれない「人間性」みたいなものを失ってしまい、そこから先は現代的に言えば「偏執狂」的な凶暴さを増幅させ、その果てにキャサリンの幽霊に憑りつかれたかのような最期を迎えるに至ったのかなぁ・・・・・・と。
この物語は全編通してアーンショー家及びリントン家の女中だったネリーの口から語られているわけだけど、彼女のフィルタを通すことによって「客観的」な仮面を被った「主観的な物語」になっちゃっていると思うんですよ。 で、彼女のフィルタを作っている価値観は恐らくは当時の普通の感覚 もしくは「女中根性」とでも呼ぶべきものだったと KiKi は思うんですよね。
そんな彼女にとってヒースクリフみたいな「どこの馬の骨ともわからない、しかもどことなく斜に構えた小僧」は好感情を向ける対象にはなりえないし、逆に自分が仕える貴族のご子弟は崇拝の対象であるのと同時にある程度自分の力が及ぶ(影響力がある)存在でもあるという摩訶不思議な関係にあったと思うんです。 そうであるだけに、彼女が彼女の表現を借りれば「良かれと思って」やっていることの中にも、現代人の KiKi からしてみると「はぁ?? 話をややこしくしてどうする??」と感じられることもあったりして、これが又、KiKi の読後感を混乱させる要因の一つになっていたりもするんですよね~。
いずれにしろ、この狭い世界の中でこれだけ多くの事件が発生しつつも、最後の最後、要するに「最後に立つ者」だったのが、アーンショー家の末裔であるヘアトンとリントン家の末裔である2代目キャサリンというのが暗示的だなぁ・・・・・と。 これにより結局、どこの馬の骨ともわからないヒースクリフは歴史の中に埋もれていくだけの存在と化し、見方によればアーンショー家 & リントン家はどちらも安泰なわけで、先々代のアーンショー家の旦那様の時代と変わらない(というよりも両家が合体することでさらに大きくなって)この地方の支配者階級を続けていくわけですから・・・・・・。
ま、てなことをつらつらと考えてはみるものの、やっぱり今の KiKi にもこれがどういう物語なのかさっぱりわかりません・・・・・ ^^; はっきりと断言できるのは KiKi にとってこれは決して「恋愛小説」ではないし、「復讐劇の物語」でもないと感じられるということです。 どちらかと���うと「個人」がどんなに抵抗し、挑戦したとしても決して打ち破ることができない「何か」(しかもこれが「社会的な因習」といったようなものでもなければ「階級社会」「人種差別」といったような社会通念的なものでもないあたりが「何か」としか言いようがないんですけど)の物語だったんじゃないのかなぁ・・・・・と。
投稿元:
レビューを見る
せっかくブロンテ三姉妹の生家に行ったことがあるのだから、読まなきゃ損だろう!と思って読んでみました。
内容をまったく知らずに読んだだけに、ドロドロ具合にまずびっくり(笑)
これだけ感情的な人たちがたくさん出てくる小説を読んだのはたぶん初めてかなぁ。うん。
下巻を読むかはしばらく考えてみよう。
投稿元:
レビューを見る
帯の強くて脆い愛とありましたが、どこが!と全力で言える。
登場人物全員過激で辛辣で非情です。
今のところ誰も好きじゃないんですけど、この先がどうなるのかすごく気になる。
一番可哀想なイザベラ・・・せめてイザベラだけでも救いがあればいいのですが・・・
投稿元:
レビューを見る
『嵐が丘』というタイトルだけで、詳しい内容を知らずに読み始めた。
こんなに激しい物語だとは思わなかった。
でもどんどん話に惹き込まれる。
投稿元:
レビューを見る
再読。改めて読み返してみても凄まじい、荒れ狂う感情と罵詈雑言の暴風雨。著者の生い立ちを知った今となっては、思わず「お嬢さん、そんな辛辣な言葉をどこで身につけたのでしょうか」と問い正したくなる。ここには汲めど尽きぬ感情の濁流はあれど、純粋な感情は存在しない。愛は憎しみを帯び、憎しみが愛の源泉となるような、愛憎割り切れぬ思いが出口を求める事もなく渦巻いていている。決して嵐が丘の外の世界を描こうとせず、外部のものも決して関与できないその世界観が作者の内面そのものだと考えてみて、ただただ呆然とするばかりであった。
投稿元:
レビューを見る
文学史上に残る世界的な傑作……とされているが、個人的にはそこまで評価したいとは思わなかった。理解が難しいこともあるが、そもそも内容が暗すぎるのである。とくにヒースクリフは、いまでいう「サイコパス」としか思えない。屋敷を2つとも手中に収め、両家の家族をバラバラにしてしまうその様は、人こそ殺してはいないが、「北九州一家監禁殺人事件」「尼崎連続殺人事件」を想起させられた。むろん、内容が暗いからといって文学として質が低いということはないし、実際このような物語を着想することはすばらしいと思うが、とはいえやはり1人の読者として、積極的に評価したい気持にはなれなかった。最終的にキャシーとヘアトンが結ばれたことはよかったが、キャシーもまたさんざん悪態をついていたので、すなおに喜ぶ気にはなれない。とにかく登場人物の誰もが「イヤなヤツ」で、誰にも感情移入ができないのである。そういうなかで延延と恋愛要素を描かれてもしらけてしまう。作品の舞台同様に、まさに荒れ果てた大地のような小説である。
投稿元:
レビューを見る
激情。野蛮なまでに人を愛すること。地位や裕福さが幸せにつながらない不条理さ。憎い、でも愛しいあなた。あなたは私そのもの。
投稿元:
レビューを見る
仕事でやむを得ず読みました。うーん、荒涼としてますねえ。だれも「善い人」が出てこない。ミスタ・アーンショウだって、自分の息子をさしおいて拾い子ばかり愛するってどうよ。
なんかもう、みんな愛憎ともにむき出し。といって、中心人物たちは全然単純じゃないし。
以下、下巻へ。
投稿元:
レビューを見る
キャサリンは本当に鼻持ちならない少女なんだけれど、読み終わる頃には若干の共感じみたものが湧いている。
自分勝手で、他人に心があることに気づかないのになぜ自分の望み通りに他者が振舞ってくれないのかと憤慨する。攻撃性の塊みたいな彼女が、自分の粗暴な部分に訴えかけてくるんだろう。
投稿元:
レビューを見る
古い名作と言われている本を読んでみたくて手に取った一冊。何の予備知識もなかったので、難しい内容なのかと思ったら、普通の恋愛小説だった。でもあまり心には残らなかった。