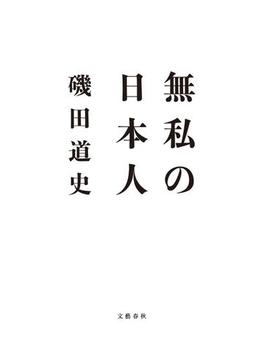「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
武士にお金を貸し、利子で郷里を潤すという事業を成し遂げた穀田屋十三郎をはじめ、儒学者・中根東里、歌人・大田垣蓮月という江戸時代を生きた3人の評伝を通し、日本人の「無私の精神」を描く。『文藝春秋』掲載を単行本化。【「TRC MARC」の商品解説】
『武士の家計簿』で知られる歴史家・磯田道史が書いた江戸時代を生きた3人の人物の評伝。仙台藩吉岡宿の困窮を救うために武士にお金を貸して利子を得る事業を実現させた穀田屋十三郎、ひたすらに書を読み、自ら掴んだ儒学の核心を説いて、庶民の心を震わせた中根東里、幕末の歌人にして、「蓮月焼」を創始した尼僧・大田垣蓮月。有名ではないが、いずれの人物も江戸時代の常識や因習を疑い、ときにはそれと闘い、周囲に流されず、己の信ずる道を突き進むことで、何事かをなした。空気に流され、長いものに巻かれるのが日本人だとすれば、3人は「例外的」日本人である。しかし、磯田道史は3人の人生にこそ日本人がもっとも強く、美しくなるときに発揮する精髄を見出した。それは、己を捨て、他人のために何かをなしたい、とひたむきに思う無私の精神である。評伝にとどまらない、清新な日本人論が登場した。【商品解説】
著者紹介
磯田 道史
- 略歴
- 〈磯田道史〉1970年岡山市生まれ。慶應義塾大学文学研究科博士課程修了。博士(史学)。静岡文化芸術大学准教授。著書に「武士の家計簿」「殿様の通信簿」など。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
涙を流しながら読んだ古文書
2015/05/10 21:54
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:れいんぼう - この投稿者のレビュー一覧を見る
「涙を流しながら読んだ古文書」という題の磯田さんの講演会を聴いてこの本を購入した。
磯田さんが涙を流しなら読んだという古文書とはこの本に登場する仙台藩吉岡宿の危機を救った商人たちを記録した「国恩記」のことだ。
穀田屋十三郎ら9名の商人は貧困で衰退する吉岡宿を再建するために、倹約してためた私財を投じて1000両を工面、それを仙台藩に貸し付けして利子をもらい再建費用にするという事業を計画。前例主義の武士たちとの苦しい交渉を重ね、遂にこの前代未聞の財政再建事業を成功させたという話は本当に泣ける話だった。よく時代劇に登場するような強欲商人とは次元の違う、まさに無私の人たちがここにいる。
紙の本
無恥な日本人へ
2012/11/15 11:04
4人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:hitsun - この投稿者のレビュー一覧を見る
最近、小説を敬遠している。知りたいのは事実と、その背後にある真理である。絵空事、空論に割く時間などない、と考えるようになっている。
磯田の著を読んでみてもいいかと思ったのは、『武士の家計簿』の著者であり、作品中の会話を資料にもとづいて構成した、と知ったからである。半ばノンフィクションなのである。
一巻の過半は十三郎をはじめとする仙台藩の肝煎(庄屋)達の苦闘の経緯である。しかしもっとも共感したのは中根東里である。学者なのに本も残そうとしない。姪のための書き残しが1冊あるだけで、無私という点で傑出している。日本には庄屋階級が50万人いただけでなく、在野にこのような知識階級があったことが文化的特色なのだろう。
それにしても、磯田の語り口が、ちょっと司馬遼太郎に似ていると感じるのは、私だけだろうか。知らず知らずのうちに影響されたのではなく、意図してやっているのであればそれは無私とはいえない。
ともかく、近いうちに佐野を再訪してみたいと思うようになった。これまでは買いそびれた干し羊羹を食ってみたいという野卑な動機しかなかったのだが、泥月庵跡の植野小学校を訪ねてみたいからである。司馬が敗戦を迎えた地でもある。
紙の本
「素直なる心ことばはいにしへに帰らん道の姿なり」
2017/01/04 12:08
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:読書はじめました - この投稿者のレビュー一覧を見る
「穀田屋十三郎」「中根東里」「太田垣蓮月」が起こした奇跡と生き様が書かれた3話。
「太田垣蓮月」さんの生き様に感動した。
注意:下記に少し詳しく書いてしまいましたので未読の人は読まないでください。
絶世の美女で文武両道(和歌・舞・薙刀・鎖鎌・忍者のように竹竿を使って城の塀を飛び越えたり)と誰もが羨む才能に溢れた人。
普通ならば失敗しても容姿を利用して良い処に嫁げばと思ってしまうが、
この人はそれまでの不幸な人生を繰り返そうとせず、自身の信念から尼となり、
唯一不得手な埴(はに)細工を生業にして、人に良いように利用されても、
人々のために20年間もコツコツと貯めたお金(生まれ故郷に橋を架けようと貯めたお金)など惜しげもなく飢饉で苦しむ人々に寄付したり、
揚句自分が死んだ時にと作っていた棺桶まで人にあげたりと、本当に無私の人だった。
蓮月の弔いで「これはいくつめの棺桶やろな」と村人が呟いた時には、涙がこぼれそうになった。
紙の本
素晴らしい私たちの御先祖
2016/03/12 14:29
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:暴れ熊 - この投稿者のレビュー一覧を見る
私たちの国にはこんなに素晴らしい御先祖がいらっしゃった。名も無き民に至るまで、凛とした人たちであった。江戸期の農民や町人の素晴らしさを知った。このような人たちの物語を知ることが出来たことに感謝。ただ、文章に関して言えば、読点の打ち方がどうもおかしい所が散見され、違和感を覚えたので☆4点。意図的にそうしているのならともかく、その点が残念ではあった。