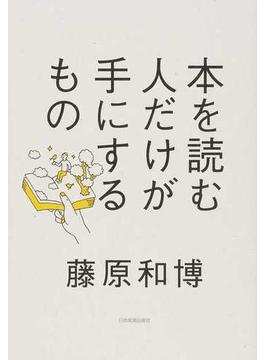「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
- カテゴリ:一般
- 発売日:2015/09/29
- 出版社: 日本実業出版社
- サイズ:19cm/270p
- 利用対象:一般
- ISBN:978-4-534-05317-6
読割 50
紙の本
本を読む人だけが手にするもの
著者 藤原 和博 (著)
なぜ本を読むといいのか? これまで3000冊以上の本を読んできた著者が、仕事と人生に効く読書術を紹介する。「これだけは読んでほしい」と思う本50冊も掲載。【「TRC MA...
本を読む人だけが手にするもの
本を読む人だけが手にするもの
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
なぜ本を読むといいのか? これまで3000冊以上の本を読んできた著者が、仕事と人生に効く読書術を紹介する。「これだけは読んでほしい」と思う本50冊も掲載。【「TRC MARC」の商品解説】
「なんで、本を読んだほうがいいのか?」という質問に答えられますか? 教育の世界、ビジネスの世界の両面で活躍する著者だからこそ語ることができる「人生における読書の効能」をひも解く本書は、まさに「読んだほうがいい本です」(おすすめ本リスト付き)。【本の内容】
著者紹介
藤原 和博
- 略歴
- 〈藤原和博〉1955年東京生まれ。東京大学経済学部卒業。教育改革実践者。東京都で初の民間校長として、杉並区立和田中学校校長を務めた。著書に「たった一度の人生を変える勉強をしよう」など。
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
納得の一冊
2015/11/26 20:34
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:としちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
改めて本を読むことがいかに重要なのか再認識することができました。本書の言葉を借りるなら、”様々な著者の脳をかけらを集めること”で自分のものの考え方や視野を広げることができる、その為に読書は必要だと学びました。以前から読書を習慣づけるようにしてましたが、今後は自分の興味のある分野以外にも、今まで避けてきた分野について書かれた本にも挑戦しより多くの著者の方々の脳や知識のかけらを集めて”21世紀型成熟社会を良く抜くための情報編集力を身に着けていきたいです。今後は電車での移動中は緊急時を除きスマホをいじるのは止めます。
電子書籍
読書は人生を大きく左右する
2019/05/02 18:18
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ルート - この投稿者のレビュー一覧を見る
人間は情報がないと、怖くて前に進めなくなる。
本をいっぱい読んでいる人と、そうでない人は、
明らかに行動範囲で差がでる。
特に新しいことへの挑戦する行動ができるのは前者である。
本を娯楽で終わらせている人もいるので、一概には言えませんが‥。
紙の本
さぁ、読書を始めよう!
2018/11/14 08:22
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:KEN - この投稿者のレビュー一覧を見る
何が変わったか?すぐには分からないこともあるけど、1冊読み終えれば、その1冊分だけ、自分が変わってる。1冊分だけじゃない、今までの蓄積分に繋がって相乗効果でさらに変化が起こるかも。自分が変わらないと何も始まらない。旅に出て世界を広げることもできるけど、今この場で本を読むことでも世界は広げられる。なんてハードルが低くて簡単なんだ。やっぱり読書ってすごい!
紙の本
スマホを閉じて、本を読もう
2015/10/28 07:26
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
株式会社リクルートからはさまざまな特異な人材が輩出されている。
本書の著者藤原和博氏もその内の一人で、今や有数の出版社となったメディアファクトリーの創業を手掛け、2003年からは東京都初の民間校長として5年間勤めあげ、その経験を生かして現在は教育改革実践家として活躍している。
本書はそんな藤原氏が「なぜ本を読むといいのか」について考えた一冊である。
藤原氏は「これから先の日本では、身分や権力やお金による“階級社会”ではなく、「本を読む習慣がある人」と「そうでない人」に二分される“階層社会”がやってくるだろう」と言い切っているが、それには前提となる社会変革が存在する。
藤原氏は1997年を境として、「みんな一緒」という時代から「それぞれ一人一人」の時代に変わったとみている。
「それぞれ一人一人」の時代こそ、「本を読む習慣がある人」が有利になってくるというのだ。
この本全体がそのことを丁寧に説明している。
例えば、「読書によって身につく、人生で大切な2つの力」を、「集中力」と「バランス感覚」としている。
本が好きだからといって、このようにロジカルに説明できる人はあまりいない。
だから、「なぜ本を読むといいのか」といった単純な問いにもなかなか答えられないのだと思う。
答えは一つではないだろう。藤原氏のように考えることもあるだろう。
本を読むということは、そういう多様性を認識することだろう。何か一つが正しい答えではない。それは他を排斥することではなく、他を受けいれ尊重することで社会が成立する。
本書を読むことで、読者一人ひとりがこの問いについて考えてみるのもいいだろう。
藤原氏は「本の読み方」として「乱読」を推奨しているが、その一方で読書をするにもトレーニングが必要だとみている。まったく同感である。
日頃読書をする習慣がない人が「乱読」を薦められてもできるものではない。
また「本には、人それぞれに読むのがいいタイミングがある」というのも正しい意見だ。
読書好きだけではなく、読書嫌いな人にも読んでもらいたい一冊。
何を読んでいいかわからない読書嫌いな人には、「付録」として藤原氏が薦める50冊の本を活用するのもいい。
電子書籍
脳のカケラ
2016/01/19 16:01
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ううまん - この投稿者のレビュー一覧を見る
たくさん読んで、脳のカケラを集めたい。
紙の本
教養のためには幅広いジャンルの読書
2016/01/03 12:30
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちくわ - この投稿者のレビュー一覧を見る
1人1人が自らの人生を切り開くために、教養としての読書が重要性の説明が説得力あります。
本を読む行為=自分の中からどのくらい引き出せるかという営み。
巻末の本の紹介も、幅広いジャンルであり、教養のためにはビジネス本だけではダメということも痛感。『奇跡のリンゴ』や『手紙屋』など、早速読んだが、いずれも読まな今間終わらなくてよかったと思える名著。
集中力とバランス力も得られる。
紙の本
本がもっと読みたくなります
2015/12/21 20:29
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:あぼんぼん - この投稿者のレビュー一覧を見る
本を読む人と読まない人では自分の中の世界の広がりが大きく異なる。電車のなかでは皆がスマートフォンをいじくっており、その姿は滑稽である。その間に本を読むことで大きな人になっていく。本を読む人だけが何を得ていくかこの本には詰まっている。
紙の本
若干の矛盾や齟齬が気になる
2018/10/29 21:34
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ライサ - この投稿者のレビュー一覧を見る
筆者は「携帯電話がもたらしたのは初めての個人の拡大」だという。
それはしかし。携帯の前に流行ったポケベルはなんだったのか。
また様々に経済についても語っているが、どう見ても「政府の経済政策の誤りを認めず責任転嫁して」いるようにしか見えない。
ただこの本をもとにして「メールとネット」「家族制度の崩壊」「少子化」「超絶高齢化」について思考するのも悪くはないと思った。
ちょっと本に対して価値を過大評価しすぎではあるが良作の部類には入ってくる一冊
紙の本
新たな発見
2016/11/29 09:37
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:imikuto - この投稿者のレビュー一覧を見る
新たな発見というと大げさだが
他人(その本の著者)の脳を自分の脳につなげる、という言葉は新鮮だった。
こういうことを意識しながら本を読めば、身につくだろう。
特に古典だと、大昔の作家と考え方を共有できてしまう。これはすばらしい。
じつはこの考え方で本書の全体が貫かれている。
ただ各論もそれなりによいが、基本的にはビジネス書だ。無理に読書とつなげている感がある。
ビジネス書としては得るものはあったが、「読書」をテーマにした本としては平均的ではないだろうか。
おすすめの50冊にしても、ビジネス書が多いし、古典がないので説得力に欠ける。まあでもそのほうが、当たり前さがなくて、むしろいいのかな?
結局、リクルート社フェロー -> 中学校校長 -> 教育改革実践家 という経歴の著者が書いた読書に関する本ということで釣られた感はあったが、読み終えてみれば、読んで損はなかったというところか。
紙の本
これだけは読んでほしい。は新たな発見です。
2015/12/28 19:25
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ロン - この投稿者のレビュー一覧を見る
本好きにはとっては、書かれている内容は同感の域にあり、新たなものではありませんでしたが、期待以上だったのが、これだけは読んでほしい50冊の紹介でした。特に、学校では教わらない現代史を学ぶ10冊でした。こんな本があったのかと、新たな発見に感謝です。