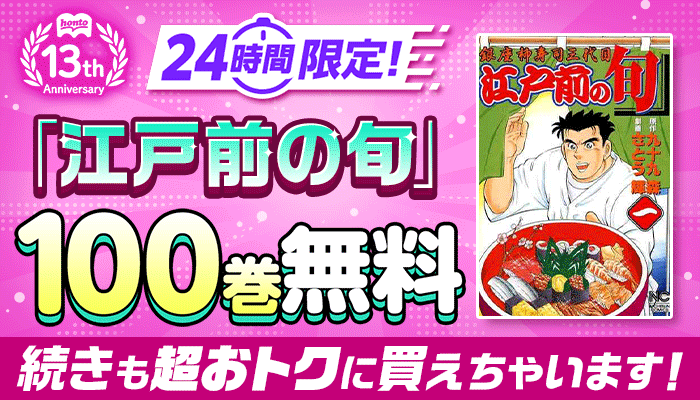本書の読み方として、「おわりに」を読んでからはじめにに戻って読み進めていくといいのではないかと私は思う
2017/08/14 09:58
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くりくり - この投稿者のレビュー一覧を見る
戦後72年。第2次世界大戦を実感として語れる人は残り少なくなった。
8月15日を前後して、NHKは戦時下の状況を連日のように放送している。民放が、8月15日をすでに無視する中で、NHKの歴史の事実に学ぶ姿勢は、今後も大切にしてもらいたい。
本書は、歴史に「何を」学ぶかを問いかけている。
「過去はじつはわたくしたちが向き合っている現在、そして明日の問題につながっている」「いま私の周りには、自己を正当化し、歴史を公正に学ぶことを『自虐史観』と排する人が少なくない」何たることかと・・・終戦の経緯を「日本の一番長い日」としてノンフィクションを著した著者が、戦争に至った経緯を明治維新前からとき起こし、戦争の愚かしさを再び語る。
いま語るその決意は、「おわりに」に書かれている。ヒトラーが台頭した1930年代からの様子は、今の日本の状況とよく似ていることにも気づかされる。
本書の読み方として、「おわりに」を読んでからはじめにに戻って読み進めていくといいのではないかと私は思う。
2032年に日本は没落するって!
2022/01/31 19:35
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:future4227 - この投稿者のレビュー一覧を見る
昨年1月にご他界された筆者が半生を振り返りながら、近代史における自身の歴史観を綴る本。長岡中出身ということもあり反薩長的歴史観が強いが新鮮でもある。伊藤博文や山県有朋なんかもバッサリこき下ろし。40年ごとに歴史の大転換が起こるという彼独自の40年史観によると、日本が没落するのは2032年という大予言。また、半藤さんの人脈もすごい。大学生にして高見順と知り合い、行きつけの店では永井荷風の隣で酒を飲み、坂口安吾の自宅に1週間泊まり込んで語り合う。おまけに奥さんは夏目漱石の孫。類は友を呼ぶとはこのことだ。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:疾風のエディ - この投稿者のレビュー一覧を見る
歴史探偵として名高い半藤さんの著作だったので、遺言を読む思い出購入。
昭和の歴史を「戦争」という切り口から分析する貴重な本です。
戦争をテーマにしていますが、決して戦争(軍部)礼賛というわけでもなく、海軍善玉論に終始するわけでもない。
本当に惜しい方を亡くしました。
愚者は経験に学び賢者は過去に学ぶ
2018/01/21 14:09
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ねずみごっこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
きっかけはラジオで宮崎駿監督が、この本を周りに勧めているという話をされていて、興味を持ち手に取りました。
ところが読んでどっこい、日本の近代・現代史に関心が少ない人にはなかなかハードルがお高い。
なんとか半藤氏の著作2,3作を読んでいた私は辛うじてついていきましたが、一読で終わらせるのではなく、知識を増やし知恵が付いた節目節目に、再読すべき本だと強く思いました。
若いころに災害にあったことがある、現在苦学している、そういった方々に図書館で借りてでも読んでみて欲しいです。
そして心に響くところがあれば、「がっつり牛丼を楽しみたいのをグッと押さえてお握り一個で我慢して」書籍を購入し、座右の書にされてください。
また、今まで特に不自由を感じず生きてこれた方も、この先の時代に不安があれば、きっと指針になる、老賢者が次世代の若人に差し出した「バトン」のような良本です。
歴史を知ることがこれからを知ること。少しずつ形を変えて繰り返すかもしれない歴史を考える。
2017/10/05 18:01
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
第二次世界大戦の終戦時期などの考察からさかのぼり日露戦争へ、明治維新へ、そしてその時代を生きた人物へ。
近代史を研究してきた著者の「自分史」のようなものも含めて書かれた、読みやすい「戦後を中心とした日本歴史の見方」である。「天皇退位」は身近な話題なので、冒頭に入れるのにはよかったと思う。勝海舟や夏目漱石などを通してみた形の書き方も上手く興味を引き付けてくれる。
ご自身の著作の話など、少し自慢話めいたところも出てきたりして「おじいちゃんの昔話」的に思える部分もある。本題の「歴史に何をまなぶのか」に至るまでが長いのでそう思うのかもしれない。著者自身が「疑問に思って調べたら違っていた」ことも多いので、そういう風に書き出す必要もあったのかも。記録のために勝者がつくった部分もあるというのが歴史。著者が繰り返し言及するのは「聞いた話をうのみにしない」ということでもあるようだ。
「歴史は繰り返す」という古代ローマ人の言葉もあるが、著者自身は「四十年史観」という言葉で日本の近代史では40年ごとに大きな節目がある、と書く。明治維新から40年で何があったか。日露戦争から40年で何があったか。第二次大戦後40年では何があったか。その後の40年(それが今だ)では何が起こるのか。歴史はただくり返すのではなく(それまでを知ったうえで)少し違う形で繰り返す。「らせん」という単語が心に浮かぶところであった。このあたりでは2017年現在のアメリカ大統領なども登場するので「歴史は繰り返すのか」がとても身近に感じられる。
歴史を知ることがこれからを知ること。少しずつ形を変えて繰り返すかもしれないものであること。読みやすい本なので、おじいちゃんの話を聞くつもりで、著者の考え方も鵜呑みにしないで、そこから「何が本当か」を考えるつもりで読んでみてほしい本である。
投稿元:
レビューを見る
面白かった。やはり著者の本は安定的に読みやすい
と思いました。
天皇の退位問題から明治から昭和までの歴史を
わかりやすくまた、ご本人のこれまでの経緯を
いろいろ書かれています。
”日本のいちばん長い日”のお話を読んでいると
歴史って必然ではなく、偶然の積み重ねだけど
結局必然のように思えるということかもしれません。
であれば、とりわけ、歴史観をゆがめて取ったり
自分の都合のよいように曲解することは大罪のような気がします。
投稿元:
レビューを見る
<目次>
はじめに 歴史にまつわる不思議
第1章 天皇退位問題について
第2章 大好きな歴史上の人物
第3章 歴史探偵を名乗るまで
第4章 日露戦争と夏目漱石
第5章 「歴史はくり返す」
おわりに 「歴史を学ぶ」ということ
<内容>
著者が若い人を対象にした学習会が元だと思う。そういう語り口で書かれている。
近現代史に造詣の深い著者が、自分が歴史に関わる本を書くようになったいきさつや『日本の一番長い日』を書くにあたってのお話、そして現代的なテーマを「きちんと調べたうえで」語ってくれている。妙に訳知りそうな顔で「歴史」を語る輩に比べ、偉ぶったことは一切ないが、正確な歴史談義をしてくれている。歴史好きな、近現代史に興味を持つ中高校生に最適な本である。
投稿元:
レビューを見る
真田十勇士 猿飛佐助、霧隠才蔵、三好清海入道、三好伊三入道、由利鎌之助、筧十蔵、海野六郎、穴山小助、根津甚八、望月六郎
吉田松陰 幕末有名人がほとんど出てくる勝海舟の日記や記録に全く出てこない 松下村塾史観
幕臣の勝海舟、大久保一翁、福井藩の政治指南役だった横井小楠らは激変する国際情勢を視野に入れて、新しい国のかたちはどうあるべきか考えていた
明治10年国家予算 4800万円 戦費 4156万円
西南戦争 このツケはインフレを呼び、その後とられた緊縮財政で一気にデフレ
石橋湛山 小国主義
人の入れ替わりに40年
太平洋戦争開戦前に戦争回避を唱えた召喚には実戦経験者が多かった
歴史は繰り返す 古代ローマの歴史家 クルティウス・ルフス
第一次大戦後戦勝5カ国の軍艦や空母の保有比率
アメリカのGDPは日本の7,8倍 GDP比より対米6割を認められたらラッキーを思って当然だったはず
英語に直訳できない日本語 いっそ、どうぜ、せめて
ヴァイツゼッカー 問題は過去を克服することではありません。さようなことができるわけはありません。後になって過去を変えたり、起こらなかったことにするわけにはまいりません。しかし過去に目を閉ざすものは結局のところ現在にも盲目になります。非人間的な行為を心に刻もうとしないものは、またそうした危険に陥りやすいのです
投稿元:
レビューを見る
歴史の中にはまだまだ埋もれてますよ。それを調べることで、日本と言う国の姿が見えてくる。だから歴史は面白いのです 独裁者が、力の行使に必要な警察や軍を掌握すると、必ずと言っていいほど実行する事は何か。それは粛清なんです 民主政治は、特にやすやすと、独裁に転換すると言うことをよく覚えておいていただきたい 過去に目を閉ざすものは現在にも盲目になる
投稿元:
レビューを見る
人はたえず挫折と我慢の日常をすごしている。どうせとか、いっそとか、覚悟しつつもなかなかいっぺんに思い切れない。そこに、せめての心情が大きく浮かびあがってくる
投稿元:
レビューを見る
最近の世界で起こるさまさな出来事を思うと歴史は繰り返してしまう…と不安ばかりだが、半藤一利さんの「歴史は簡単には繰り返さない」と言う章を読んで、そうかもしれないなぁと少し不安な気持ちが楽になった。それにはまずなぜそうなったのか?歴史を知らないといけない。背景になにがあるのかを。この年齢になってあらゆることが繋がっていて歴史を知ることの大切さを特に実感をする。膨大な資料をよみこんだり、インタビューしたりと決して妥協しない姿勢はさすがだなと思う。
投稿元:
レビューを見る
出鼻をくじかれるように「最初に言っとくけど、歴史学んでもあんま役に立たないから!」あれー?と思いつつ読み始める。役に立つとか意味があるかないかとか、損得とか、しばしば自分はそういうことを気にしすぎた。
著者は、「知らない」でいてしかも「知ろうとしない」状況において、人は最も権力者の扇動に乗りやすいのだと言う。これって、権力云々の話を抜きにしても、例えばこの本を読むワタシのスタンスも同じようでなくてはならんのでは?その通りで、歴史を受け身で学んでいては、嘘っぱちの歴史ストーリーを信じ切って、綺麗事ばかりインプットして、40年ごとに人は悲惨な出来事を忘れてゆく。でも、いい話ばかり耳に残るのは当然。だってその方が聞いていたいし。だから、私たちは歴史を自ら学ばなければいけないのだと思う。人の話を全て肯定的に聞いただけで満足してはいけないのだと学んだ。批判的に(not否定的)本を読んだりってすごく難しい。ワタシはできる気がしないのだが、そのために必要なのは知識をつけることなのかも。以前「インプットしなきゃアウトプットなんかできない」と言う大前提を恩師の何気ない一言から知った。根本的に読書や勉強のあり方について再び考えさせられた。本の内容としては、なんだか歴史の講話を聞いているような感じが否めないので、若干個人的な期待とはそれていた。ただ、いくつか無知な自分に染み渡る偉人のエピソードもあり、特にはじめとおわりが興味深く読めた。またもう少し知識をつけてから読んだら面白いかなぁ。
投稿元:
レビューを見る
至極まっとうなことしか書いていないように思える。
好き嫌いは別として、著者を左翼とかアブナイ人とカテゴライズしたがるのはいけませんね。
正しい歴史認識はどうすれば可能なのか、史実とは何なのか。自分で考えられるようになるには、相応の準備が必要だよね。
投稿元:
レビューを見る
1年前くらいに買った半藤一利さんの積読本を読み終えた。半藤さんの語り口はやはり上手で、目の前で話しているような感覚になる。この本を書いたとき、半藤さんは87歳。読み終えた2019年5月18日時点で88歳だが、あと数日で89歳になられるようだ。おそらくご本人の気持ちとしても、いつ亡くなってもおかしくない年齢だと思われているだろうし、だからこそ、繰り返しやすい歴史を後世に伝えたいと思っているだろう。(ちなみに半藤さんは、「歴史は繰り返す」という有名な言葉があるが、自身は「歴史は、”単純には”、繰り返さない」という言い方が正しいと思われている)
この本に、半藤さんが15歳の時の東京大空襲(昭和20年3月)の経験が書かれている。焼夷弾で燃え盛る火に追われて中川に追い込まれ、川では危うく溺れかかるも屋形船に助けられ、その屋形船から河原の人たちを見ていることが書いてある。赤ちゃんや子供を抱いたお母さんたちに黒煙と猛火が襲い掛かり、女性の髪の毛に火が燃え移るとカンナ屑のように簡単に燃え上がる。炎が鎮まった後は人の形をした真っ黒い炭が残されている。それを見ている自分は、溺れかけた後に船にあがっているから寒くてガチガチと震えている。そして、「正直言って、なんの感情も抱かなかった」と。とても正直に書かれている。生きるか死ぬかで追い込まれ、自分が何もできないときは、人間はそんなものなのかもしれない。
一方で、最近の世界情勢と、日本の雰囲気を感じながら、満州事変やナチスドイツのことを振り返る。あのときの経験は大切にしてほしいと。
今年、2019年は世界も日本も大きく変化をする年になるかもしれない。そんなとき、半藤さんのこの本や、『昭和史』を読み返したいと思った。
投稿元:
レビューを見る
昭和史、幕末史、夏目漱石といった著者がこれまで書いてきたテーマを概観している印象。ちょっと物足りないかな、とも思ったけど、それは著者が何のために本書を出したか、というあたりを考えないといけないのだろう。天皇のお言葉やトランプ大統領の誕生。内向き化する世界各国。今ある世の中の動きに対して、あなたは何を思いますか?そうした問いを、これまで自身の描いてきたテーマとからめて、とりわけフリマー新書の読者となる若い人にむけて出しているのだと思う。まぁ、俺みたいなおじさんにも、考えなければいけないよなぁと思わせる話なんだけどさ。
歴史は繰り返すが、まったく同じように、ではない。歴史から学ぶことはできないのではないか、と絶望的な気持ちになることもあるけれど、でも知ることをあきらめてはいけない。少しでも良い未来にむけて、努力できたらいいね、と著者から励まされている気がした。