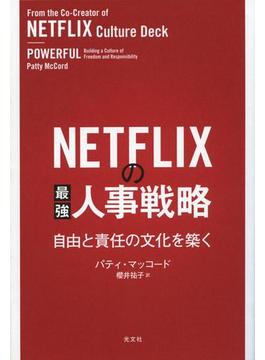驚異的な成長を遂げているネットフリック社の戦略を教示してくれる書です!
2018/08/27 09:07
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、近年、驚異的な成長を遂げ、一躍世界で有数の企業に育ったネットフリックス社の経営の秘密を解き明かした画期的な書です。同社はDVDの郵送レンタルという昔ながらの事業から、映画のコンテンツ配信、オリジナルなコンテンツの制作へと行業務内容を変化させ、世界に約1億人の会員を持つまでになりまました。本書は、同社で最高人事責任者としての役職を担ってきた著者による、同社の成長の秘訣を教示してくれる貴重な書です。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Masaru_F - この投稿者のレビュー一覧を見る
以前にNetflixのCEOが書いた「No Rules」を読み、非常に多くの示唆を得たので、その施策を一緒に実行した人事担当役員の著書にまで手を伸ばしてみました。残念ながら、「No Rules」を超える示唆を得ることはなかったように思います。
人事側面からの経営
2018/09/22 22:00
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:凄まじき戦士 - この投稿者のレビュー一覧を見る
NETFLIXの人事視点での経営について書かれた書籍。
書かれている内容は短期間でのし上がる大企業の人事の在り方についてとにかく語られている印象で。確かに効率的な人事の在り方ではあると思いましたが、長期的に会社をよくする人事であるかは少し微妙なところ。
シビアすぎる側面もあり、まだ大きくなったばかりの企業なので安易に信用するのはどうかなと思う。
人事戦略と文化創造
2018/09/27 16:22
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:caroten - この投稿者のレビュー一覧を見る
業態の大進化を遂げながら、なぜ急成長できたのか――その秘密は、ラディカルな人事戦略と文化創造にあり!
"シリコンバレー史上、最も重要なドキュメント"とシェリル・サンドバーグ[フェイスブックCOO]が絶賛し、ネットで1500万回以上も閲覧されたスライド資料だそうです。
投稿元:
レビューを見る
従業員一人ひとりが自分の能力開発に責任を持つのが理想的。ここは会社の仕事ではなく、製品と市場の開発が会社の仕事
従業員一人ひとりが事業の仕組みを理解する。
カスタマーサービスの事業に与える影響を説明できるか。
重要でない評価指標に固執しない。絶えず見直す。
今のチームがこの先必要なチームになる事を期待してはいけない。
従業員定着率はチームの良し悪しを測る指標には適さない。
会社にもたらす価値をもとに報酬をきめる。
パフォーマンスの高い企業は意図的に不平等主義をとっており、業績にインパクトを与えられる部署に重点的にスター人材を配置している。
フィードバックは頻繁に行う。
従業員の才能と情熱が、会社の目指す将来に合っているかを見極め、他社の方があってれば積極的に支援、解雇する。
投稿元:
レビューを見る
NETFLIXにおける人事方針について説明している書籍。NETFLIXにおいては以下が重んじられている。
・給与等ではなく、ハイパフォーマー(A級プレイヤーではなく、チームのニーズに合致した者)をチームに揃えることによる経験(学び)や楽しさが重要となる。そのため、従業員の定着率よりもハイパフォーマーを揃えることが重要である。
・人事部こそ、事業の仕組みを理解する必要がある
・メンバーには知るべき情報を知らせ、パフォーマンスに対するフィードバックをありのままの真実として伝える。これによりPIP(業績改善計画)が効果的に働く、または、解雇後の訴訟リスクが低減できる
・将来(6ヶ月後程度)必要となる人材をいま雇う。それは社外であってもよい。また、過去多大な貢献した者であっても会社が目指す将来に才能や情熱の観点でマッチしなければ(双方のためにも)解雇(または自ら離脱)するべきである
メンバーの能力を開発するのは会社ではなく、そのメンバー自身である
終身雇用制度の真逆を行く人事方針であり、ある種「使い捨て」とも見なされ兼ねないが、結果として自身として成長することができ、自身が成長できなくなるタイミング(その時点で他社でも活用可能な能力が身についていると想定される)で外に出て貢献できるといったドライながらも理にかなった状況になっている。今後日本においてもグローバルとの競争が激化していくことが想定される中でNETFLIX社の事例を参考に敢えて厳しい環境を作り上げ、会社の成長とともに自らの意志で自ら成長していける風土を作り上げていくことが肝要かもしれない。
投稿元:
レビューを見る
色々と考えさせられるというか、日本と比較してしまうところがたくさんある。
アメリカはいいな、と考えるだけでは何の発展性もないが、少しでも取り入れて組織を改善していくように努めたい。
労働基準法も違うので解雇については難しいかもしれないご、それ以外であればなんとかなるんじょないだろうか。
これから会社を作るならこれが分かる社員だけ採用していくのがいいだろう。私ならそうする。
投稿元:
レビューを見る
型破りで斬新な人事戦略の数々に衝撃を受ける一冊。実例を基に解説されているので読み易くおススメです。経営者や人事領域の方だけでなく、全てのビジネスパーソンに対して会社、仕事、キャリアに関して疑問を投げかけてくれ、考えるきっかけを与えてくれる内容です。
同じような人事戦略を全て自社で実践するのは難しいかもしれませんが、著書の中でも述べられている通り、常識を疑い、小さな事から取り組んでいく事で、一人一人の働き方や組織の改善が進むと良いなと思います。
以下、要点抜粋
* チームが最高の成果を挙げられるのは、メンバー全員が最終目標を理解し、その目標に到達するために、思うままに創造性を発揮して問題解決にとりくめるときだ。
* 無駄な方針、ルール、手順を排除。トップダウンは機動性の妨げ。
* 会社が抱える課題を全従業員が理解しているか。
* 徹底的に正直な姿勢は、緊張を和らげー陰口に歯止めをかけ、理解と尊敬を深める。
* つねに柔軟性を保ち、新しいスキルを学び、新しい機会を検討し、折あるごとに新しい課題に挑戦して、新鮮な気持ちで自分を伸ばしながら働けるようにしよう。
* 従業員一人ひとりが自分の能力開発に責任を持つのが理想的。これができれば、従業員と会社の双方に最適な成長が望める。
* 待遇ではなく、ハイパフォーマーとチームを組んで学び合えること、仕事が楽しいと思えることが、最も強力な決め手となる。
* 優れた人材を採用するとは、チームのニーズに最も合致した人材を探すことだ。
* 面接するすべての候補者に、この会社に入りたいと思ってもらえるようにしよう。
* リクルーターは、どんなに専門的な事業であっても、そのしくみを周知しているビジネスパーソンでなくてはならない。採用プロセスに協力する、創意あふれる積極的なパートナーでなければならない。
* 事業の現状から考えて支払える金額だけでなく、その人材が将来もたらすかもしれない収益も考慮に入れよう。
* 報酬スキームをオープンにすることで、偏見を減らし、業務の業績への貢献について正直に話し合うことができる。
* 従業員は自分の才能と情熱が、会社のめざす将来に合っているかどうかを見きわめ、他の会社の方が自分に合っているかどうかを判断できなくてはならない
* 従業員は自分の仕事ぶりに対する評価を頻繁に受ける必要がある
* 人事決定を下すアルゴリズム「この従業員が情熱と才能をもっている仕事は、うちの会社が優れた人材を必要とする仕事なのか?」
投稿元:
レビューを見る
結構前に読んだ。
Netflixの経営秘話かなと思ったら、まるっきり人事とか組織づくりに関する本。
組織の末端まで、経営者が考えていることや会社の戦略方針の共有を徹底させることが、生産性アップの1番の秘訣という点には同意。
ただNetflixだからできたことではない的なこと書いてあったけど、やっぱりNetflixだからできる話だよなとは思ってしまう。
人事とか経験したこともないし、読む時期が違った気がする。
投稿元:
レビューを見る
・徹底的に正直になる
・自由な知性の応酬ほど楽しいものはない
・ビジネスリーダーの役割は、すばらしい仕事を期限内にやり遂げる、優れたチームをつくること、そでだけ。これが経営陣のやるべきことだ。
・優れたチームとは、これからどこに向かおうとしているかをメンバー全員が知っていて、どんなことをしてでもそこに到達しようとするチームのことだ。
・経営陣が従業員にできる最善のことは、一緒に働く同僚にハイパフォーマーだけを採用することだ。寿司を提供したり、ストックオプションを与えたりするよりずっと優れた従業員特典だ。優秀な同僚と達成すべき成果の周知徹底、この組み合わせが、パワフルな組織の秘訣である。
・経費規定を廃止し、適切に判断して会社のお金を使ってくださいと言ったところ、自由を乱用することはなかった。
・他社で人事を担当していた人材を採用する代わりに、ヘッドハンティング会社から人材を引き抜いて社内に採用機能を構築した
・うちの会社が今期半年間に取り組もうとしている重要課題を5つ挙げてみてと全従業員に尋ねる
・「それ直接言ったの?」
・スタート、ストップ、コンティニュー=誰か1人の同僚に対して、始めて欲しいこと、止めて欲しいこと、続けて欲しいことを一つずつ伝える
・未来をつくるのは若者であり、彼らの知識欲を活用する方法を考えることはビジネスリーダーの利益になる
・採用面接はマネージャーが予定しているどんな会議よりも優先され、また役員会の出席者が会議を中座しても良い唯一の理由
「自由と責任の文化」がなぜできたのか、なぜそれが今も続いており、10年以上の高い成長率を保てているのかをエピソードと併せて書かれている。「まとめ」や「考えてみよう」などで具体的に自分の会社に置き換えて考えると、耳が痛いことが多いように思う。。「優秀な同僚と達成すべき成果の周知徹底が何よりの従業員特典」というのはとっても同意。
投稿元:
レビューを見る
人事の人は読むべき。自由と責任、オープンな議論、文化を徹底するためにどういったことをやっていくべきか。とても参考になる。
投稿元:
レビューを見る
チームとそこに携わる人たちの関わり方、そのチームを経営する側の在り方が、良くまとまっていて分かりやすかったです。
チームの文化を見えるようにしていくために、これから何をなすべきかを考える、ヒントがあちこちに散りばめられていたと思います。
投稿元:
レビューを見る
メモ
・インセンティブいる?
・会社は従業員を子供扱いしてはいけない。従業員は、大人であり、自分の時間は自分で管理できるし、キャリアも自分で開発することができる
・計画は四半期ごとが限界。それ以上は意味ない。
・無駄なプロセスを排除する。顧客のためにならないプロセスは排除していく
・従業員の主体性を引き出すために、従業員に経営者と同じくらいの情報を提供する
・そして、徹底的に説明責任を果たす
・経営者はそれに対して説明
・顧客のために議論する。自分たちのための議論はしない
投稿元:
レビューを見る
『NETFLIXの最強人事戦略』読んだ。シリコンバレーで話題になった同社のカルチャーデックを基にした一冊。”自由と責任の文化を築く”に凝縮される、終身雇用・家族経営とは真逆のプロフェッショナル集団の作り方。構成も筋肉質で読み易い。
投稿元:
レビューを見る
タイトル通り、NETFLIX の人事戦略についてまとめた一冊です。
個人的には共感できる内容が多かったですが、
ストイックな内容が多く誰もが共感できる本とは言えないです。
とはいえ、人事まわりを改善したいと考えてる人にとってはなにかしら得られるものがある一冊なのではと思います。