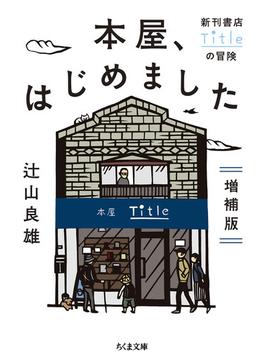「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
読割 50
紙の本
本屋、はじめました 新刊書店Titleの冒険 増補版 (ちくま文庫)
著者 辻山良雄 (著)
物件探し、店舗デザイン、イベント、ウェブ、そして「棚づくり」の実際まで。個人で新刊書店Titleを開いた辻山良雄が、本屋をつくるにはどうすればよいのかを綴る。開業から現在...
本屋、はじめました 新刊書店Titleの冒険 増補版 (ちくま文庫)
本屋、はじめました 増補版 ──新刊書店Titleの冒険
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
物件探し、店舗デザイン、イベント、ウェブ、そして「棚づくり」の実際まで。個人で新刊書店Titleを開いた辻山良雄が、本屋をつくるにはどうすればよいのかを綴る。開業から現在までを書き下ろした新章を増補して文庫化。〔初版:苦楽堂 2017年刊〕【「TRC MARC」の商品解説】
リブロ池袋本店マネージャーだった著者が、自分の書店を開業するまでの全て。その後のことを文庫化にあたり書き下ろした。解説 若松英輔【商品解説】
関連キーワード
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
興味深い
2023/07/09 13:00
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:なつめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
新刊書店を開店するまでの過程が、興味深く読むとかができました。小規模店でも工夫次第で、やっていけると驚きました。
紙の本
小さな本屋さんの道のり
2021/05/26 12:47
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ねこすき旅人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
本を読んで、本屋さんへの想いが伝わってきました。それでいて新しく事業を立ち上げ、お店を営むのに必要な事業計画の立案やお店を始めてからの取り組みを紹介してくれているなど、本屋さんでなくとも、他の分野で小さなお店を始めてみようと思う人には、読んでほしいと思います。別にお店を立ち上げなくても職場で仕事をしている人も、小さな本屋さんがお客様にとって素敵な場になっていく過程をみることで何か得るものがあると思います。
紙の本
本への暖かいまなざし
2020/04/20 18:21
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:aki - この投稿者のレビュー一覧を見る
新刊書店Titleの店長辻山良雄さんの子供のころから書店を開業するまでのものがたり。本への暖かいまなざしに満ちあふれている。時間を見つけて荻窪まで行ってみようと思う。
紙の本
またTitleに行きたくなった
2020/01/18 02:22
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オオバロニア - この投稿者のレビュー一覧を見る
荻窪の個人書店Title店主のリブロ書店員時代から開店初期までを綴った一冊。エッセイにして、業務記録にして、本屋論ともいえる文章から自由に本を売りたい辻山さんのマインドが伝わってくる。なぜ個人なのか、新刊書店なのか、一つ一つ選択に想いが込められている。
この本を読んで思い出したことが二つある。都内の個人書店をいくつも回っていると、利用者ー本屋間のコミュニティ(何とも言えない良い関係性)のあるお店は本の魅力を間違いなく底上げすると感じる。Readin' Writin''さんしかり、B&Bさんしかり、その本屋があるからあの街に行こうと思える力がある。
もう一つは、Titleで出会える本の多様さについて。数々のリトルプレスも串田孫一さんの「緑の色鉛筆」も出会えたのはTitleの棚だったし、年末年始に2階で開いている小さな古本市でたまたま見つけたリャマサーレスの「黄色い雨」は今でも大切に読んでいる。Titleは読む本の幅を広げてくれる貴重な存在。