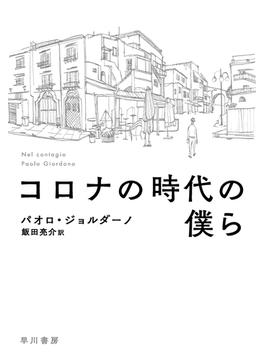すっと理解できる。
2020/06/29 10:20
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:さな - この投稿者のレビュー一覧を見る
著者の思考を簡単に追うことが出来ます。
2020年6月現在、未だ無知や怯えによる差別などの問題が尽きません。
ひとりひとりが落ち着いて行動できるように、皆に読んで欲しい本です。
渦中の国から届く
2020/04/24 19:50
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Todoslo - この投稿者のレビュー一覧を見る
多くの犠牲者が出ているイタリアにおいて、著者のシンプルな表現に切実さが滲み出ています。いざという時にはカリスマ的な指導者よりも、飾らない言葉のほうが大切なのでしょう。
Withコロナを考える一冊
2020/05/21 23:17
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オオバロニア - この投稿者のレビュー一覧を見る
コロナ禍のローマで暮らすイタリア人作家の不安を綴ったエッセイ。科学に対する不信、終わることのない自粛生活をどこかシニカルに描写している。Afterコロナの話が取り沙汰されることが多い中、末尾の文章で筆者は少し違う問いを投げかけてる。
「本当に我々は以前と全く同じ世界に戻りたいのか」。2ヶ月以上テレワークを続けて、毎日ワイドショーの声が耳に入り、外を眺めることもなく過ごして、本当にこの問いについてよく考えるようになった。少なくともウイルスが以前の生活様式の負の部分を浮き彫りにしたことは忘れない方が良いんだと思う
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:エムチャン - この投稿者のレビュー一覧を見る
分かれるでしょうが……私的には、星は三つ。筆者は、イタリアのコロナ蔓延の最中、かなり、冷静な視線で見ています。そして、コロナたからこそ、コロナ以前の社会を、ドライに評価している様子です。
武漢風邪の特質は。
2020/06/28 20:20
4人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ライサ - この投稿者のレビュー一覧を見る
これほど短期間に世界中に広まった疫病はない。
数字は抽象化関係の描写。WW1と同じ……速度の衝撃は速度の二乗に比例、これと同じ。
多は異なり。
ただこの本は反グローバリズムに対して反対派という奇妙な立場をとる。
そもそもこれほど武漢風邪が流行った背景の一番が、無責任なグローバリストらの暗躍があったからだ。
日本はコロナの被害が少なかったとはいえグローバリズムを右も左も推進しまくっているので経済は世界一戻る見込みが少ないとも言われている
この本は、特に後半は差っ引いて読む必要がある
投稿元:
レビューを見る
発売日前の、24時間限定公開のを読了。
素粒子物理学専攻の著者の、数学的見地に、文筆家としての考察、文章としての美しさが交差して、読み物としても素晴らしいし、COVID-19に関しての注意喚起にもなっているのが凄い。この刊行のスピード感も。
感受性人口、感染人口、隔離人口(頭文字を取ってSIR)としての我々は、もはや個人ではない。ゼロ号感染者から全世界へ、今や線で繋げたら世界地図は真っ黒に塗り潰されてしまう。ひとりの行動がR0(アールノート、基本再生産数)を左右する。
と同時に、「The personal is political」という、フェミニズム運動から発生したスローガンも想起した。
緊急事態宣言、休業要請、為政者達の発言や動向ひとつひとつが個人の生活に直結している日常が露呈した。今までもそうだったけど、関係なく生きていた人も多かったはず。COVID-19によって政治に意見する、異議を唱える人が増えたのは、純粋に良かったと思う。
もちろん地球に生息しているのは人間だけではない、人間によってもたらされた環境変化が現状に何の影響も無いとはとても言い難い、でも、みんなそんなことは普段考えないし、コロナが終わった世界で、急速に忘れられていくのかもしれない。
著者はあとがきに、
「いったい何に元どおりになってほしくないのか」を、今からよく考えておくべきと述べている。
日本において思うならば、自己責任の名のもとの相互監視。悪政、そしてそれに対する怒り。かな。
投稿元:
レビューを見る
24時間限定の無料公開版を読了。
COVID-19におけるイタリアの現在に至る過程と未来について、冷静な考察と不安と後悔を行き来しながら、生々しい文章で綴られている。
そして何より、筆者のあとがきの、
「コロナウイルスの「過ぎたあと」、そのうち復興が始まるだろう。だから僕らは、今からもう、よく考えておくべきだ。いったい何に元どおりになってほしくないのかを。」
の部分は、読んで深く突き刺さった。
この部分に、筆者の言いたい事が集約されていると思う。
とても深く、そして重い。
投稿元:
レビューを見る
無料公開版にて。
あとから振りかえって書くのではなく、2月末(29日)から書きはじめることで、そのときどきの国民感情や空気みたいなものが記されているのがとても貴重。あとから振りかえって検証する本はたくさん出されるだろうけど、そういうものでは消されてしまう。かといって、ツイッターやブログでは流れていってしまう。その実況中継のような思考を、しずかに切りとって閉じこめたようなエッセイだった。
やはりあとがきの「すべてが終わった時、本当に僕たちは以前とまったく同じ世界を再現したいのだろうか」という問いが心に残る。そう、できることならいい方に変わってほしいこともたくさんある。(でも悪い方に変わってしまいそうな予感もする。)
そして第13章の「もう一度、運命論への反論」。
「感染症流行時の共同体と言えば、それは人類全体のことだ」「この国の医療システムを守るために我々国民がどれだけ努力をしてきたか──もしも僕らがそんな自画自賛をしているところならば、それはすぐにやめていい」というあたりは、何かにつけて自国の感染者数が他国より少ないと(今のところは、にすぎないのだが)標榜したがる政治家にぜひ読んでほしいと思った。
投稿元:
レビューを見る
新型肺炎まっさかりのイタリアからの記録。
文章が詩的。私には冗長に感じる。
でも論理が整理されて読みやすい。
数字と遊べるタイプの人の文学。
エイミーベンダーっぽい。
よく言われる外出自粛などの予防がなぜ必要なのか、数字で説明してくれる。
考え方がわかりやすい。
科学的な根拠と、今の状況と、感じたことと、それぞれが区別された上で混じり合って、バランスがちょうど良い。
で、書かれているちょっと前のイタリアの反応と日本の現状がそっくりだから、日本の先行きも期待できない。
でも日本はまだイタリアやその他の国から学べる場所にいる。
後書きが感動的。
覚えておきたいのは、感動的なエピソードだけじゃない。
発売前の無料公開版で読了。
投稿元:
レビューを見る
コロナについての意識や考え方について考えさせられる本でした。
「元どおりに戻って欲しくないリスト」がよかった。
投稿元:
レビューを見る
無料公開版を、一気読み。
購入予約もしました。俯瞰的にコロナと、人類を捉えることが出来る本だと思う。
今の自分に流し込みたい。
投稿元:
レビューを見る
2時間もかからず読める手軽さながら、知性に満ちた傑作。
本書は、イタリアの作家が新型コロナウイルス(SARS-COV-2)の感染が拡大する現在の状況について綴ったエッセイ集である。
SARS-COV-2がどういった性質のウイルスなのか、それが我々にどんな影響をもたらしているのか、そして我々人類や現代社会がどのようになっているかに関する、深い洞察に満ちている。
最終章とあとがきで、著者は外出を制限される今だからこそ、日頃は考えられない問題−なぜこのような事態が生じてしまったか、コロナ後の世界をどうしていきたいか−を考えようと訴える。
その主張は、読者に内省を促す強いメッセージであると同時に、今の非日常も前向きに過ごすことができるというエールでもなかろうか。
巣ごもりの日々のお供に、一読をおすすめしたい。
投稿元:
レビューを見る
このコロナの時代において、私達は状況を受け入れて、適宜変わらなきゃ行けない。そして収束して忘れるのではなく、この出来事から学んでいかなくてはいけない。私も今の日々の事を忘れないで心に留めておこうと思う。
投稿元:
レビューを見る
簡潔で読みやすい。そして、臨場感がある。数理疫学的基盤に基づき、人間心理の弱さと偏りを暴く。その弱さを直視・意識し、過ちを繰り返さず、新たな時代を作るために著者は「書き記す」という戦いを起こした。古典になり得る、貴重な文章である。
投稿元:
レビューを見る
早川書房の緊急全文公開で読んだ。今この状況で読んでて恐いところもあったが、読んでよかった。気を緩めてはいけない。巷の、真も偽も含んだ情報や、不安に駆られた発言、普段そんなこと言わない人なのになあという人のよくわからない発言などに惑わされてはいけない、と自分を戒める。平時の歪みが出ている今、正しく怖がり、何が大事なのか我が身を問いたい。そして忘れていけない。