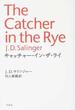- 現在お取り扱いが
できません - ほしい本に追加する
キャッチャー・イン・ザ・ライ みんなのレビュー
- J.D.サリンジャー (著), 村上 春樹 (訳)
- 税込価格:1,980円(18pt)
- 出版社:白水社
- 発売日:2003/04/01
- 発送可能日:購入できません
- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
紙の本
ホールデン君のこと。
2003/06/12 14:36
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:奈伊里 - この投稿者のレビュー一覧を見る
野崎訳の「ライ麦畑でつかまえて」を読んだのは、中学生だったか高校生だったか。ずいぶん昔のことだし、覚えていたのは、ちっとも面白いと感じず、うざったい読み物として投げてしまったということだけ。
新訳に出会い、読了し、それにはちゃんとした理由があったのだとわかった。
わたしはホールデンと似た者同士だったのだ。同じような痛みや憤りを感じていたし、同じように、鼻持ちならない面倒な奴だったのだ。自分だけでも大変なのに、似たようなホールデンのあれこれにまでつきあいきれなかったんだと思う。
人生の折り返し地点を過ぎて読む村上訳「キャッチャー・イン・ザ・ライ」は、甘酸っぱい思いに囚われつつ、あの頃の曖昧な感情たちの在処がこみあげるように蘇る、実に実に愛おしい物語だった。
読んでる間中、わたしはずっとホールデン君に話しかけていた。
「ほら、そんなこと今言わなくったっていいでしょうよ」
「どうしてそうなっちゃうわけ?」
「またそんなわざとらしいことを……」
「なんだ、君、子供のくせして、わかってるじゃない」
「わかる、わかるけどさあ、ほっときゃいいじゃない」
「あーあ、だから言わんこっちゃない……」
ってな感じで。まるで当時の自分に話しかけるみたいにして。
そして、なんと言っても、ホールデン君にはフィービーがいた。
フィービーのためにレコードを買う時間、持ち続けた時間があって、バラバラに割ってしまう瞬間があって、その先に、「そのかけらをちょうだい、しまっておくから」と手を差し出すフィービーがいたってこと。そしてまた、フィービーがスーツケースを抱えてきた時間のちょっと先に、回転木馬の時間があったってことだ。
わたしは、ホールデン君と一緒になって、フィービーが回転木馬に乗る姿を眺めた。わたしも、あやうく大声をあげて泣き出してしまいそうだったし、ぐるぐる回り続けるフィービーの姿が、やけに心に浸みた。ホールデン君が「いや、まったく君にも見せたかったよ」と言うように、わたしもわたしの周りの人に、そのフィービーの姿を見せたかった。
彼と並んで、あるいは彼を俯瞰して読み進め、物語の最後には、不思議な感じを味わった。
わたしはもう、ミスタ・アントリーニの世代だ。彼は実にまっとうな教師でまっとうな人間で、ホールデンへの対し方にも、年齢にふさわしい責任感と愛情が感じられる。わたしはまさしく今、そちら側にいるし、社会に対して、そちら側に立っての責任を担っている。でも、ずっとホールデンの行動につきあった流れでミスタ・アントリーニに出会うと、なんだかホールデンの側に立って、「そんな分かり切ったようなこと聞くのはうざいんだよな」って気持ちにも、なっていたりするのだ。世の中の、正しいとされることへの、嫌悪感不信感っていうのかな。そういう、ちょっと正しいこと当たり前なことに、斜に構えていたいって感じ。
わたしの中で、かつてのわたしと今のわたしが、対峙する。不思議な感覚。
この物語は、全編、ホールデンが誰かに語りかける体裁を取っている。彼が誰に向かって語りかけているのかは明示されない。彼は相変わらず当たり前な人生の波に乗り切れていないような感じだし、もしかしたら、精神病院につっこまれてしまっているのかもしれない。とすると、彼の語りは、ちょっと空しいものになる。でも。読後、わたしの心は明るい。「平気、平気。そんなもんでしょ」と彼に伝えたくなる。「ちゃんと生きてれば生きてるほど、わかんないこと多いよ。おかしいと思わないやつらの方がおかしいんだよ」と。ま、16歳を生きるホールデン君にそんなことストレートに言ったって聞いてくれないのは分かってるから、心の中で。「待ってるよ」と告げる。同じものをいっぱい抱える、仲間として。
紙の本
自分
2003/06/02 14:34
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mute - この投稿者のレビュー一覧を見る
十代の頃、“Nothing gonna change my mind”とはつぶやいてみたものの、やっぱり世界は過酷で、大人になっても変わることができない自分と世界に腹を立ていました、ホールデンのように。
40代になって、彼が大切に思っている記憶や、突然泣き出したい気持ちが、以前よりいっそう痛くわかる気がしました。大半がホールデンの罵詈雑言ですが、だからこそふとそういった場面が心に入ってきます。
紙の本
やれやれ、さ。
2003/05/11 20:49
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:きょん - この投稿者のレビュー一覧を見る
なるほどね、古い映画が何度もリメイクされるように、小説もいまふうに味つけすれば、何度でもリメイクできるものなんだ。それだけ普遍性を持つ作品なんだと言えるのかもしれないけど、若者なんていつの時代だってやけくそで、あらゆるエスタブリッシュメントを侮蔑していて、悲惨で愚かなことは、そう変わらないんだからね、要するに変わるのは語り口と時代の風俗だけなんだ。だけどその語り口っていうのはけっこう重要で、ほとんど文芸作品のすべてとさえ言える要素なんだから、リメイクにはとてつもなく大きな意味があるんだね。その影響力たるや絶大なるもので、読んだあとはぼくの語り口まで自然にこんなふうになっちゃうんだよ。やれやれ。だけど『キャッチャー・イン・ザ・ライ』というタイトルはもうちょっとなんとかならなかったんだろうか。せめて本文に出てくるような『ライ麦畑のキャッチャー』にするとかさ。これじゃ、最近の映画の邦題と同じじゃないか。予告編なんかでナレーターが完璧なカタカナ発音で『リバー・ランズ・スルー・イット!』と絶叫するたび、とことんうんざりさせられるんだよね、まったく。
でもこのホールデンってやつは、けっこういやなやつだと思うよ。自分でもそれがわかっているから、まじで落ち込んでいるんだろう。この世の中の通俗的なもの、ブルジョア的なもの、インチキくさいもの、偽善的なものを軽蔑しまくっているわけだけど、自分もどうしようもなくそういうものの一部であることを知っているから、とことん気が滅入ってしまっているんだ。彼はガラスのなかで展示品がじっと動かない博物館が大好きで、何十万遍でも行きたいくらいなんだけど、そこへ行く人がこのあいだの自分とはもう違っているということをすごく考えるんだ。時間とともに人間が変わっていかざるをえないことに耐えられないんだよ。きたないおとなになっていくと思うと、心底落ち込んでしまうんだね。そういうモラトリアム小説なんだよ、これは。いまどきモラトリアムなんていう言葉を使うのかどうかわからないけどさ。
幼くして死んだめちゃめちゃ性格のいい弟や、ものすごくかわいくて頭のいい小学生の妹のことをしょっちゅう思っているところは彼のいいところだし、この本のもっとも泣かせるところでもあるんだけど、彼はそのふたりに救われてもいるんだよ。ふたりが、もっと言えば子どもが、かろうじて彼をこの世に繋ぎ止めているんだ。この本で子どもだけがきちんとしたまともな人間に描かれているのも、自分はだだっぴろい麦畑みたいなところで、崖から落ちそうな子どもを片っ端からつかまえる「キャッチャー」になりたいと妹に言うのも、そういう意味があるんだよ。つまり、俗にまみれないまともな精神を守りたい、そういうものに繋がって生きていきたい、みたいな。
それでもやっぱり彼は、なんだかんだあったあとで、ハーヴァードみたいなところへ行って、またおおぜいのインチキ野郎に会ってとことんうんざりしながら、すごい美人の感じのいいキャリアウーマンを奥さんにもらったりして、世の中の通俗さに気を滅入らせつつ、人に優しくしたり優しくされてほろっとしたりして、やれやれと思いながら生きていくんじゃないかな。山奥に隠遁するとか、肉体労働をしながら底辺生活をするというような人生は送らないだろう。つまるところニューヨーク生まれのアッパーミドルクラスの育ちで、田舎者や鈍くさいもの、体だけりっぱで頭からっぽの類いには耐えられないわけだからね。そう言われるほうは、へん、なにを甘っちょろいことをとむかつくだろうけど、彼らは本なんて読まないからね。本を読むモラトリアム人間にとっては果てしなく共感を誘う、永遠の青春文学であり続けるわけなんだよ、まったくの話。
紙の本
アメリカ版【引きこもり】雑感
2003/05/10 11:49
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:栗山光司 - この投稿者のレビュー一覧を見る
僕が本当にノックアウトされる本というのは、読み終わったときに、それを書いた作家が僕の大親友で、いつも好きなときにちょっと電話をかけて話せるような感じだといいのにな、と思わせてくれるような本なんだ。とホールデンは君に語りかけるが、[君である私]はサリンジャーに「日本の引きこもりって知っていますか?」と電話したくなった。
野崎訳を再読した時、日本だけの現象らしい「引きこもり」について考えなかったのに、村上春樹訳で思い浮かべたのは、新訳が「内面の葛藤」に重心を置いたメロディカルな文体であったためか。
旧訳はロックのリズムに近い文体だったためか、街を彷徨く反社会的なパンク野郎を背景に想像して、「家出少年」には結びつくけど、「引きこもり」にはリンクしなかった(当時、引きこもりなんて言葉はなかった)。
精神病院らしい施設から発信するホールデンの独白は、社会適応願望が過剰にまで強くて、完全さを求める余り、「大義のために卑しく生きる」ことが出来ず、「大義のために高貴な死を求める」無垢なる未熟さに満ちている。自己防衛のために日本の若者は引きこもる。私の引きこもり解釈と重なったのです。
旧訳の投稿書評では、全く思い至らず、新訳で引きこもり少年の治癒過程の記述と読解したのは新訳の文体のなせる技が一番の因と思う。
それに、「インチキ野郎」を「おぬし、なかなかの役者じゃーのう」と、むしろ、イカサマ氏の度胸に対して感心する日常を経たり、ホールデン君から金を巻き上げた黒人のエレベーター係に拍手したくなる作者の意図と違う読みをやってしまう海千山千の年を経たためであるか。どちらにしろ、ホールデン的イノセントを相対化して、大人の読解が出来る年になった事は間違いない。
この独白的物語のキーワードは「インチキ野郎」である。両訳ともこの言葉を使っている。罵倒語として穏便である。仮に誰かに面と向かって言われても、「それが、どうした、おまえがアホなのよ」と、突っ込みたくなる。私の実体験では「イノセントな男」と言われた方がショックであった。「君って、大人だねえ」と言われてみたかった。逆に、どうしようもない大人を陰で「ガキじゃあ、あるまいし」と、どうやら、無垢なるもの=善、無垢でないもの=悪、と単純に割り切れない価値観の日常で生きてきた気がする。
ホールデン君の立ち位置は、正音者になることを拒否して聾唖者になってみたい吃音者の贅沢な悩みに似ている。日本独自の引きこもり達は、日々ホールデン的呟きをひとりごちて、自己言及し、聴き手を求めているのかも。
もし、君が耳傾ければ、それに似た叫びを聴取ることが出来るはずだ。
【ライ麦畑のキャッチャー】になりたいなんて、日本版引きこもり少年の言いそうなセリフである。もう、インチキ生活に飽きて、余裕の出来た気障な大人も言ってしまうセリフでもあるけど…。
ー僕にとりあえずわかっているのは、ここですべての人のことが今では懐かしく思い出されるってことぐらいだねー。春樹さんらしい濃密な記憶の優しさに包まれる。
野崎訳では、僕にわかってることといえば、話に出てきた連中がいまここにいないのが寂しいということだけさ。クールだねぇ。
村上節は泣かせる。俗情に結託した品性の卑しさはないけれど、そのスレスレのところで、書くことの出来る村上さんの芸が多くの読者を獲得する秘密かも知れない。
紙の本
ライ麦畑でつかまえられて
2003/05/04 19:17
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:夏の雨 - この投稿者のレビュー一覧を見る
私が初めて「ライ麦畑」(ここでは野崎孝氏の『ライ麦畑でつかまえて』と村上春樹氏の『キャッチャー・イン・ザ・ライ』の両訳に敬意を込めて、こう表記する)を読んだのはいくつの時だったろうか。大学の授業も学生寮の生活も面白くなく、それでいて何をするでもない日々の中で、ポール・ニザンの「ぼくは二十歳だった。それがひとの一生でいちばん美しい年齢だなどと、だれにも言わせない」(『アデン・アラビア』)という文章に酔いしれていた、二十歳前だったように思う。生意気にも私は原書で「ライ麦畑」を読み始めたのだ。私の英語の実力からいって、読了できたはずもない。それなのに、今回村上春樹氏の訳による「ライ麦畑」を読んで、主人公のホールデンがこの本の書名となる話を妹のフィービーにする終わり近い場面をよく覚えているのはどうしてだろうか。野崎孝氏の翻訳本を読みながらのことだったのかもしれない。なにしろ、三十年も前の、昔の話だ。主人公は永遠に十六歳だが、私はもう四八歳だ。記憶も薄れていく。
当時の私は主人公のホールデン・コールフィールドのことをどう思っていたのだろう。少なくとも四八歳の私は、嘘つきで、強がりで、それでいて臆病な主人公を最後まで好きになれなかった。もし、こんな少年がいたら、この物語に出てくる多くの大人たちのように、叱りつけたり、あきれたり、見捨てたりしそうな気がする。そして、そういう感じ方は三十年前の私自身を裏切っているような気がしないでもない。あの当時大人たちは何もわかってくれないと地団太踏んでいたのは、この私自身なのだから。だから、当時の私はこの本の書名となった主人公の話を記憶にとどめたにちがいない。
「誰かその崖から落ちそうになる子どもがいると、かたっぱしからつかまえるんだよ。…ライ麦畑のキャッチャー、僕はただそういうものになりたいんだ」(村上春樹訳・287頁)
当時の私は崖から落ちそうな若者だった。自分の居場所がわからずにただうろうろしていた。どこへ行っていいのかもわからなかった。そんな私をつかまえてくれたのが、この「ライ麦畑」であったはずだ。そのように二十歳前の私は「ライ麦畑」を読んだはずなのに、今の私は主人公がもっとも毛嫌いした大人になってしまっている。今の私こそが、本当の「ライ麦畑のキャッチャー」になるべきなのに、である。今回四十年ぶりに「ライ麦畑」が新しく訳し直された。訳者が村上春樹氏ということで多くの若者たちが新しい「ライ麦畑」を読むにちがいない。でも、本当に読むべきなのは、かつて「ライ麦畑」でつかまえられた多くの人たちなのかもしれない。
あなたは「ライ麦畑のキャッチャー」になれましたか。