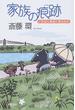- 現在お取り扱いが
できません - ほしい本に追加する
- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
| 7 件中 1 件~ 7 件を表示 |
紙の本
<家族>をめぐる対幻想論との緊張が読める、かも
2006/12/26 18:47
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:T.コージ - この投稿者のレビュー一覧を見る
06年に刊行された著者の本の中でいちばんいいかもしれない。まず読みやすい。そしてラカン派の臨床医である著者の基本的なスタンスがわかりやすく示されている。クールな著者が自らについて語っているのも見逃せないだろう。
ところで、本書は、明らかにその基本的な部分で吉本理論が意識されているようだ。
「家族制度を支えている幻想とは、「対幻想」ではなく、「エディプス三角」なのではないか」(P105)。酒井順子の『負け犬の遠吠え』を援用しつつ唐突に主張されるこの一言は、それだけに印象に残る。
実をいうと「対幻想」を否定するために「エディプス三角」が主張されたこの構図は『構造と力』の再現でもあり(浅田らは団塊や全共闘世代と決別するために彼らの教科書であった吉本・対幻想を否定する必要があった。よくある世代間闘争だ)、大澤眞幸の〝吉本隆明は踏絵だった〟という指摘を待つまでもないかもしれない。
社会の構成要素を、それは<対>(2名の関係)なのか<三角>(3名の関係)なのか....というのはフロイト以来の論議なのだろうが、この論議を現代の日本に当てはめると、それが世代間の論争になってしまう。フロイト=対=対幻想論(吉本)という団塊や全共闘世代がフォローする認識があり、ラカン=エディプス△=『構造と力』など(浅田、斎藤、etc)ニューアカ以降に支持されるドゥルーズ・ガタリ的な潮流がある(あった?)ということだ。その他に〝2名以上いれば権力が生じる〟とした宮台真司の権力論(『権力の予期理論』ほか)があり、社会システムの生成と稼働の根源に対の関係を見いだし、2名の関係で一方の人間の他方の人間への認識が一方の人間を自縛するように作用する過程を説明している。相手に対してどう対応するか
を選択する時、その選択の自由によってその選択肢の構造に自縛されていく訳だ。
P173には本書の理論的な成果が要約されている....
「二者関係の空間こそがプレ・エディパル(前エディプス期)の空間なのである」
「さまざまな自明性」は「プレ・エディパルな二者関係において形成される」
「二者関係は幼児期だけのものではない」「成人して以降も、常に個人の自明性を支える空間として機能し続ける」「しばしば反復する」
「「家族」こそは、この種の反復における、もっともありふれた器のひとつなので
ある」
....プレ・エディパル(前エディプス期)な二者関係による自明性は生涯反復され、家族はその器なのだ....という説明だ。ある種の読者はここでデジャブを感じぜざるを得ないだろう。なぜならこれこそが28年前に吉本隆明がフロイトを徹底的に読解しつつ独創した<対幻想>概念そのものだからだ。
人間は「エディプス三角」を通過することで「社会化」されるが、「自明性」はそれ以前に二者関係において形成される、という説明は、そのまま対幻想論であるし、そして自明性の揺らぎこそが典型的な精神の病ではなかったか?
ことさら吉本隆明を贔屓するつもりはないが、本書の結論は対幻想論と同じであり、それはフロイトを丹念に読んできたものなら当然にたどりつくものだ、ということにつきるのだろうか。
著者のオリジナルな見解を読む機会は多々あり、精神分析とシステム論の融合を略るなど期待したくなる試みは少なくなく、今後も注目していきたいが、個人的には吉本理論との関係が気になった。
紙の本
家族の痕跡
2006/01/16 10:17
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:一読者 - この投稿者のレビュー一覧を見る
「至る所で、自分自身を見る」と言うのならば、「家族」を語るのは、一つのよい方法だと感じた本でした。 しかし、なんか、「居場所」のない人の、「居場所」探しのような気にもなりましたが、たとえ独り者であっても、子供の頃に育った場所としての家族は体験している訳だし、また、生まれてすぐに「孤児」に成ったとしても、「生みの親より、育ての親」で、なんらかの形の家族は持つ訳だから、すべての人たちに読んでもらいたい一冊です。 私は、一気に読んでしまいました。
紙の本
著者コメント
2005/12/12 18:20
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:斎藤環 - この投稿者のレビュー一覧を見る
家族を語ることはひとを裸にします。どれほど客観的なふりをして、あるいは学術的な装いのもとで家族を語ろうとも、そこににじみ出す家族観には、そのひとそのものがどうしたって出てしまう。なんたって家族は、あらゆる人間関係のプロトタイプをはらんでおりますからね、いたしかたありません。でも、だからこそ家族は語りにくいし、家族論は恥ずかしい。その恥知らずぶりが評判を呼んだせいでしょうか、今まででいちばん反響があった連載でもありました。くわえて家族を語ることは、意外なところで自分自身と出会うことでもある。私はこの本を書いてみて、なんと自分が徹底した家族主義者であることを発見してしまいました。まさに想定外です。これほど自分を晒した本ははじめてですが、さらしがいがあったというものです。「共同体」も「中景」も無効化しつつある今、グローバリズムに対抗する処方箋は家族主義しかない。いや、そういうことを主張したい本ではありませんけれど。
紙の本
私小説的家族論
2006/04/27 10:11
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nanako17girls - この投稿者のレビュー一覧を見る
「家族を語ることは、自分を語ること」まさしくそのとおりである。それは誰にも避けることができない。それは精神科医でも、小説家でも、一般人でも、そして僕もそうだ。「家族」というものは初めて会う「他者」である。赤ん坊は母親を「神」と思う。そして、学校へ行ったり、友達と会うことでそれは違うことがわかる。おそらく人間は自分の世界からは逃れることができない。その根源は「家族」なのだ。
斎藤環はいままで「自分語り」を嫌っていた感がある。それを避けてきたのかもしてない。「そんなことは自己満足に過ぎない」ということがわかっていたのだろう。しかし、本書によってかれははじめて「自分語り」をした。それは意味のあることだ。「引きこもり」は家族こそが唯一の「他者」であるからだ。斎藤は自分をかれらと同じ位置にした。それにより「共感」「説得力」「理論」が生まれた。そう、「誰もが家族を語るとこには、自分を丸裸にすることだ」あ〜、いやだ。恥ずかしい。僕なら恐ろしくてそんなことはできない。しかし、ときにはそれが必要になる。はたして、ぼくにもそんな日がくるのかな〜?
| 7 件中 1 件~ 7 件を表示 |