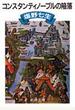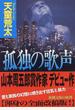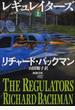hiroさんのレビュー一覧
投稿者:hiro
紙の本Akira Part1
2002/06/04 17:28
AKIRA
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「童夢」「AKIRA」と、いわゆる超能力者を描いた大友作品。背景は現在、近未来と違ってはいるが、リアリティ溢れる絵柄に、引き込まれてもう何度も読んだ。ほぼ同時代の作品と言っていい「ガンダム」が広く長く受け入れられたことを思い出してみると、「超能力」という何か人間を超えたものへの憧れや渇望があった時代なのだろうか。
2002/05/31 22:25
はじめてでもできる!自作パソコンマニュアル
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
図版が多く、初心者でも安心して「自作に挑戦してみよう」という気持ちになれる内容。しかしいかんせん、次々と進化していくパソコンの世界。あっという間に一時代前になりかねないのが悲しいところだ。
紙の本漂流教室 1
2002/05/30 22:54
漂流教室
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
TVドラマをきっかけとして再読。中学生当時に読んで以来だが、中年となった今改めて読んでも、色褪せない名作であると感じた。せりふの大仰さについ笑ってしまうところは確かにある。しかしそんなことは小さなことと思わせるような、大きなテーマを含んだ物語だと思う。私は「あしたのジョー」「デビルマン」と並んでこの「漂流教室」は、漫画というサブカルチャーをメインに引きあげた、手塚治虫以後の、画期的な3大成果だと思っている。
紙の本失速するよい子たち
2002/05/30 22:40
失速するよい子たち
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
元気で優秀な子供たちの燃え尽き状態。突然の登校拒否に陥る、人一倍がんばりやの子供たち。これら多くの子供たちを小児科医としての目で診てきた筆者の結論が、“エネルギーの枯渇”というところが興味深い。本来子どもというものは、尽きないエネルギーに満ちているものなのではないか。“エネルギーの枯渇”なんて、人生に疲れた中年のためにある言葉であるだろう。こうして若くして生きることに疲れてしまう子供たちの出現を、彼らを取り巻く家庭環境や社会状況の変化、子供たちに求められている画一的な価値観等に結びつけて論じるところ、多少強引さも感じるが、深く考えさせられる。
紙の本モンティニーの狼男爵
2002/05/30 22:30
モンティニーの狼男爵
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
フランス革命前後のフランスの片田舎を舞台とした、一風変わった恋愛小説。小さな領地を相続し、何の野心も夢もなく、それでも特に不満があるでもない。そんなさえない男爵が、政略結婚で妻にしたのが、これまたパッとしない平凡な娘。しかし一目で娘に恋をしてしまった彼の人生には、“同じように愛されたい”という大きな目標が。そんな素朴とも言える恋愛物語に狼男伝説が絡み、さらにはフランス革命という史実のスパイスが加わる。
佐藤亜紀という博識な作者の、ユニークな想像力に感嘆してしまう。
紙の本創価学会解剖
2002/01/14 16:27
創価学会解剖
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「公称812万世帯」を会員に有する「日本最大の巨大教団」である創価学会。その全体像を可能な限り客観的にあぶり出す。組織は巨大になればなるほど、その全体像は組織の外にいる者にとって(時には内部の人に取ってさえ)、捉え難いものだろうから、これは労作といえるだろう。
昭和初期、確実に軍国主義化していく世相を背景にして始まったという創価学会。その時々の時代の必要に応じて様々な活動を行ってきたことで、確実に会員を増やしていったその経緯が興味深い。右傾化する社会にあっては当局の弾圧に抗してまで、仏教の慈悲の精神に根ざした「絶対平和」を説き、戦後の混乱期には貧民救済を目指すという、公共の福祉や弱者に目を向けた活動をその中心に置くことで、単なる新興の宗教教団という以上の影響を社会に与え、多くの人々に受け入れられてきた。現在の巨大さを作る基礎がどのようなものだったかが、よく理解される。なるほど学会の目指したものが(例えそれが会員獲得の手段であったとしても)、一般の庶民、大衆の望むところと実に一致していたということだ。そのようにして成長・拡大していった学会の現在の姿。部外者にとってはその金権体質、権威主義、あるいは権力志向(と言っては失礼だろうか)ばかりが目立つように思われるその姿は、現在の私も含めた庶民の目には、どのように映っているだろうか。
紙の本車いすでアジア
2001/08/01 18:17
車いすでアジア
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
仕事柄障害のある子ども達と接することの多いことからも、本書については出版前、夕方のニュース番組で取り上げられた時から大きな興味をもっていた。
障害を克服(或いは障害と共に生きる決意を)するために、人生の目標や楽しみを持つことがどんなに大切かということ。人が前向きに生きようとするために、理屈ではない何かが必要だということは、健常者であっても変わらない。そんな当たり前の事を自らの体験を通して語る山之内氏には、学ぶところが多かった。
しかし氏の「目標」「楽しみ」は、ちょっと尋常ではない。車いすでアジアを巡るとは、「勇気があるなぁ」と思わず声にしてしまった。およそノーマライゼーションの考え方が広く行き渡っている欧米ではなく、その面ではまだまだ遅れているアジアなのである。TV番組で目にしたときには、少し無謀なのでは?という思いさえしたものだ。
しかし本書を読んでみれば、そこはかつては旅行慣れした山之内氏であったらしく、周到な調査と準備に裏打ちされた計画だったよう。なるほど夢の実現にはそれなりの準備が必要だという、これまた当たり前のことを実際に生き様で示してくれた氏に、ぜひ私が接する子ども達にも学んでほしいものだと思う。
この旅行記で特に印象的だったのは、旅行を共にした介助者との関わりだ。どこに行ってもバリアフリーとはおよそ言い難い地で、常に重い荷を背負い車いすを押し、時には氏を背負い、専門的な介護さえする。そんな介助者を見つけられたことが、日本で暮らす者として奇跡のように思えたが、それも目標に向かう氏の強い意志の表れなのだろう。介助する者とされる者、雇った者と雇われた者、この立場の違いの中で時に感情的なもつれがあり、和解がある。この点を特に深めているのが二人の関係を非難した欧州人の存在だ。この、二人を労使の関係として見た欧州人の指摘は、介護者とボランティアの境について考えさせられ、この旅行記に深みを与えていると思う。旅行中の多くの出来事のうち、特にこのエピソードを本書に取り入れたのも、おそらく氏はそこから多くのことを考えたからなのではないだろうか。
いずれにしても、破天荒とも言える旅行記、山之内氏の今後のご活躍を祈ると共に、思わず唸らざる得ないような次回作をまた期待したい。
2001/08/01 17:37
地獄の季節
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
今はもうマスコミでもほとんど取り上げられることのなくなった、神戸児童連続殺傷事件のルポルタージュとしては出色の作品だ。あれだけセンセーショナルな事件だっただけに、それを扱った出版物だけでもかなりの数だったように思う。その中で実際に読んだ作品は僅かではあるが、著者自身の人生をも踏まえてかなり深くコミットしているという点で、群を抜いているという印象がある。
事件その物が如何様であったのかという事にとどまらず、事件が起きた背景の様相を明確にすることで、事件その物の細部を照らしていくというアプローチの仕方は、例えば社会学という大きな枠組みで事件を読み解いた宮台真司氏の著作等がある。一方、少年Aの個人史、家族の歴史(或いはそれを含み込む地域の歴史)といった視点から、事件に近づいているのがこの「地獄の季節」だ。
犯人である少年Aの特異とも思える行動や思考を追いながら、そこに至るまでの父母から祖父母まで遡って家族の歴史を追っていく。その丹念な調査に跡付けられた少年Aと家族の歴史は、詰まるところ地域社会・地域共同体の崩壊から家族そのものの喪失へと至る歴史に他ならず、新興住宅団地の異様さを浮かび上がらせている。これはこの事件以後にも続く少年犯罪に通底する背景であり、とりもなおさず現代が抱える病巣そのものであると言えるだろう。
何よりも、事件そのものの残忍さや猟奇性ばかりがクローズアップされた当時のマスコミによる多くの刹那的な報道と、それを受け取る大衆としての自分自身について、改めて反省させられる、そんな労作がこの「地獄の季節」だと思う。
紙の本コンスタンティノープルの陥落
2001/07/31 20:19
コンスタンティノープルの陥落
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
塩野氏の作品を、私はいつも小説としてよりもノンフィクション、あるいは歴史の教科書として読んでいることが多い。氏の小説の主たる舞台であるイタリアで実際に暮らし、源資料と言える書物を渉猟して書くその姿勢に、大いに信頼がおけるからだ。その例に漏れず、この「コンスタンティノープルの陥落」も、その時代のその場所に生きた人間の息吹が感じられる歴史の教科書となり得ていると思う。
とかく受験指導が主となりがちな中学・高校の歴史教育の中では、中世から近世にかけてのこの地域の歴史は、世界史の中でもサッと通り過ぎることが多いのではないだろうか(私の場合はそうだった)。歴史を学ぶのは好きな方の私も、ローマ帝国の偉業については聞きかじっていても、その最後についてはあまり考えたことがなかったものである。そんな私自身の“世界史”の穴を埋めてくれたのが、この作品だった。
氏のこの作品に続く「ロードス島攻防記」「レパントの海戦」、あるいはベネチア共和国の歴史を綴った「海の都の物語」を読むだけで、中世から近世にかけてのヨーロッパの歴史がかなり概観できると思う。その意味で、氏の作品は私にとっての歴史教科書だ。
紙の本孤独の歌声
2001/06/25 00:00
孤独の歌声
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
天童荒太という作家については、これまでほとんど知らなかったのだけれど、TVドラマで「永遠の仔」を観て、俄然その名前の注目した。「永遠の仔」にしても「孤独の歌声」にしても、サスペンス仕立ての人間ドラマ、刑事ドラマという体裁は共通しているし、驚くほど濃密でありまた希薄でもある人間関係が描かれている点でも共通している。強く他人とのつながり・同化を求めるあまり、ついには自他の区別が無くなり犯罪に走る人間、また自他の同化により自己を見失うことを恐れるあまり、心を閉ざして生きる人間。そうした人達の人生が複雑に絡み合うところにドラマが生まれる。そうした両作品の登場人物達の心の有り様は、極端な形ではあるにしても現在を生きる人間の心理を見事に表象している。「孤独の歌声」は作家のデビュー作に近い作品であるようだが、つい最近の作品「永遠の仔」とをあわせて読んでみると、現代人の心の孤独・心の傷というものが、一貫したテーマとして作家の内にあるようだ。
紙の本レギュレイターズ 上巻
2001/06/12 22:34
レギュレイターズ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
対をなす作品「デスペレーション」が、ひたひたと肌に迫るような恐怖を描いた作品だとすれば、「レギュレイターズ」はバッタバッタと人が撃たれて死んでいく西部劇のようなものと言えるのではないか。個人的には、前者のようなジトッとまとわりつくような恐怖を描いたキングの作品が好きである。
唯一感銘を受けたのは、障害者に対する作者の考え方だ。「レギュレイターズ」では自閉症の男の子が登場し、人間と魔物(タック)との戦いの中心となる。人に対してはほとんど言葉を発することはなく、自らの意志を伝えようとはしない自閉症児であるが、決して知的に劣っているわけではなく、魔物に対しては強い力で対抗している。実際に物言わぬ彼らであってみても、本当は私達健常者には見えないものを見、私達にはわからない言葉で感じているのではないかと思えることが現実にある。ある点では、障害者(自閉症児・者)に対して公平で正確な見方をしていると感じられた作品だった。
2001/06/12 22:20
銃・病原菌・鉄
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
人類が地球上に誕生してから1万3千年。どのようにして現在のような有り様に至ったのか。その謎を考古学や生物学、遺伝子工学等、最新の研究成果を総動員して解き明かしていく。まさしく目が眩むほど壮大なテーマだ。
上巻では食料生産の歴史について、多くの紙数が費やされている。小集団を基にした狩猟採集中心の移動生活から、農耕を中心にした定住生活へという良く知られた変遷についてである。そんな極常識的な説にしても、現在の農産物の遺伝子解析により特定される起源種から、どこで農耕が起こりどのように広まっていったかという具体的な筋道が示されると、それは全く新鮮な知識として受け取られるから不思議だ。古代の人々がどのようにして、起源種を改良して栽培に適した品種を作り出していったかの推理についても説得力がある。食料生産に限らず、人類の営みを明瞭に浮かび上がらせているところは、博学な著者ならではの所業だろう。ただ論の根拠となっている様々な研究成果については、専門書ではないだけに、いかにも必要な部分だけをサッと持ってきたという印象がある。気になるところではあるが、一般読者を対象としているのであればそれが適切なのだろう。私のような門外漢にも、一気に読めたのであるから。
紙の本敵
2001/06/04 23:46
敵
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
大学の教職を引退した老人を主人公として、その生活の細部、衣食住を微に入り細に渡り描写いていく。作者の小説に、人生の末期を迎えた老人を主人公とした作品は、他にもあったような気がするが、このように徹底して老人の日常を追ったリアリズムの小説があったかどうか。それほど日常の些末な物事、毎朝の食事のメニューからタンスの引き出しの中身といったことまで、細々と綴られていく。この主人公のユニークなところは、預金の残高を死期の目印としているところだろう。収入は減ったが生活のレベルは落とさず、次第に減っていく預金残高を見て、何年、何ヶ月先の自決を覚悟する。これは言ってみれば、自分の人生の終わりを老いや病によって左右されるのではなく、あくまで自分の生活の仕方によって決しようとする、反骨精神なのだろう。このように矍鑠たる老人であっても、生活を預貯金に頼る身として昨今の低金利を嘆いたり、病に伏せった時に他人に迷惑がかかるのを恐れ、好きな韓国料理を刺激性の調味料故控えようとするなど、今日的な独居老人の直面する問題をも描いている。するとこの小説は、老年を迎えた著者自身の、かく生きようという意志表示なのか、あるいは現実告発なのか。そんなことも考えてしまいそうだが、そこはやはり筒井氏の小説。ただそれだけでは決して終わらない。主人公の回想や空想が、次第に老人の現実を侵食し始め、境界を曖昧にしていく。現実とフィクションとが互いに近づき混然となっていくという形式の小説は、著者の作品には他にもある。しかしこの「敵」においては、主人公を老人としたことにより、それが「老い」の問題としてクローズアップされるからより切実だ。ラストの主人公の後ろ姿は痛々しく悲しいし、不気味でさえあるのはそのためだろう。
2001/05/19 21:03
奈良の大仏
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
日本の建造物シリーズの2作目。見る者を圧倒する奈良の大仏が如何にして作られたか。歴史的な経過から解りやすく解説してくれる。前作「法隆寺」同様、日本人であれば多くの人が一度は何かで目にしたことのある建造物を、普段は見ることのできない内部までを詳細なイラストで明らかにしている。何よりこのシリーズの良いところは、きちんとした学術調査の裏付けがあるところだろう。
2001/05/12 20:06
法隆寺
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
修学旅行でおなじみの法隆寺。実際に目にした人は多くても、その内部の構造までは、なかなか見ることはできない。構造ばかりではなく、建築の仕方までを詳しく正確なイラストで見せてくれるこの本は、2000円という値段が高く感じられない数少ない本だと思う。