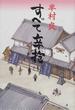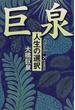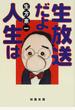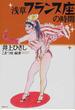たけのこさんのレビュー一覧
投稿者:たけのこ
紙の本天上の音楽・大地の歌
2001/06/20 15:32
故郷喪失者の精神構造
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
阿久悠の野球、なかにし礼のクラシック音楽への傾倒は、いずれも趣味の域をこえている。その原点は、どちらも彼らの《戦後》にある。作詞家なかにし礼の名が歌謡番組のテロップから消えてしばらくたったころ、NHK教育テレビのクラシック番組に出ているのを見て意外に感じ、ああそういう趣味の一つもあったのだなあ、くらいに思っていた。しかしそれどころではなかった。
『音楽の友』の連載エッセイなどをまとめたこの本の冒頭には、ウィーン・フィルの音楽監督に就任が決まった小澤征爾(1935年生まれ)のことを書いた文章が置かれている。かつて海を渡り、マルセイユからパリまで日の丸をくくりつけたスクーターで走った若き日の小澤に、三つほど年下のなかにし礼はおおいに刺激を受けた。小澤が自分と同じ旧満州の生まれということもあった。
《満州出身者にたいして尋常とは思えない親愛の情を持ってしまうのは、私の中で、満州生まれという事実がきわめて重く大きな影を落としているからである。》(p.9)
『赤い月』上・下(新潮社)と同様に、ここでも満州がキーワードだ。
そもそも、なかにし礼がクラシックにのめり込むのは、満州から引き揚げ船で日本に着いて数年後の中学生時代のことである。その当時、「自分で好んで歌う歌がなくて困った」という。やはり同世代の美空ひばり(1937年生まれ)の出現も、歌への欲求に応えてくれるものではなかった。たまたま家にクラシックのレコードがあったので、そればかりを聴いていて、ラジオにもかじりついた。
《クラシックは私の歌だったのだ。……名曲の数々を鼻歌まじりに歌うことによって、私は自分の根っこのありかを探していた。少なくとも、西洋音楽の中には、私が生まれ育った大陸の、日本とはまったく違う風の匂いがあった。》(p.119)
そのレコードの持ち主は、『赤い月』のヒロイン「波子」こと母であったのか、さもなくば『兄弟』(文春文庫)のあの兄か。いずれにせよ、ルーツは失われた故郷としての満州にある。
彼は、このエッセイを、友人の田村勝弘(東京交響楽団副団長)が撮った有名演奏家の写真をながめながら、「私の頭に浮かんだよしなしごとをぼそぼそと書き綴ったもの」(あとがき)だと記す。だがそれにしては、小澤征爾の満州〜日本、フルトヴェングラーのドイツ、マリア・カラスのギリシャ、ダヴィド・オイストラフのロシア、ジョルジュ・シラフのハンガリー、ラヴィ・シャンカールのインド……と執拗なまでに故郷、祖国にこだわる。
その一方で、「民族色が強い」ドイツやイタリアのオペラには疎外感をいだき、多民族都市ウィーンが生んだオペレッタや、アメリカのミュージカルのコスモポリタニズムにひかれるのだという。失われた故郷を夢みるコスモポリタン——なんだか矛盾しているようで、それなりに筋が通っているのかとも思わされ、なかにし礼とは、こういう思考の回路を持つ人なのだということが印象づけられる。
【たけのこ雑記帖】
紙の本赤い月 上
2001/06/20 15:27
激しく燃えて落ちていけ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
阿久悠となかにし礼、というふうに歌謡ファンとしてはどうしても比較してしまうのだけど、この二人、阿久悠が1937年生まれで、なかにし礼が38年生まれの同世代。60年代後半から70年代はじめにおける歌謡曲の構造転換(=専属作家制の崩壊)をリードした作詞家であることに加え、現在、小説家として活躍していることも共通している。
とはいえ同世代として日本の敗戦を小学校低学年で迎えた、その前後の体験はかなり異なる。『瀬戸内少年野球団』(文春文庫)のシリーズや、『ラヂオ』(日本放送出版協会)などに描かれた阿久悠の戦後はあくまで明るい。それに対してなかにし礼は、この小説にもあるように旧満州で1945年8月9日のソ連軍侵攻にいあわせ、そこから命からがら脱出したすえ、父と死に別れ(兄は行方不明のまま)母と姉とで日本に引き揚げてきた。その経験は、幼くして死と隣りあわせの悲惨につきる。
なかにし礼の歌詞世界で、恋人が湖に身を投げたり(「エメラルドの伝説」)、天使の歌を死人のように聴いていたり(「夜と朝のあいだに」)、なにかというと死の影がちらつくのは、あるいはそういう戦争体験が原点にあるせいだろうかと考えたりもするのである。阿久悠の歌詞において、「死」とはすなわち性的エクスタシーの比喩(「白い蝶のサンバ」)にすぎないが、なかにし礼の場合はそうではない。なにしろ、水死体の歌(ジャッキー吉川とブルー・コメッツのラスト・シングル「雨の朝の少女」)まで確信犯で書いている人なのだ。
『赤い月』は、敗戦時において41歳、3人の子を持つ母である森田波子を中心に、その夫・勇太郎、かつて勇太郎と波子を争った軍人の大杉、そして酒造業を営む森田家に出入りする商社員(じつは関東軍特務機関の青年将校)・氷室といった男たちと、波子の奔放な恋を描く。その意味では恋愛小説である。しかし波子と子供たちがソ連戦車隊の迫る満州北部の牡丹江を逃れて、避難列車でハルビンをめざす数日間の語りは、おそらく一個の戦争文学の名に値する。
波子がハルビンで再会できた夫の勇太郎は、ソ連軍の強制労働を免除される年齢でありながら、みずからそれに志願して、その結果、病死してしまう。またロシア人家庭教師のエレナをスパイ容疑で殺害して、罪の意識にさいなまれる氷室が、阿片の吸引に逃避し、中毒状態から禁断症状をこえて立ち直るまでの過程の描写も凄惨をきわめる。この人はどうしてこんなに、堕ちていくほど燃えあがる暗い情熱に執着するのだろう。
ところで、エレナを氷室と張りあって剣道の試合でめちゃくちゃにうち負かされる森田家の長男・一郎。出征して終戦まぎわに、自分は特攻を待つ身であるという手紙を波子によこしたまま消息を断った。この一郎こそ、小説『兄弟』(文春文庫)において、作詞家として世に出た弟の稼ぎを徹底的に蕩尽し、莫大な借金を負わせたあの兄ということになる。テレビドラマ版では、ビートたけしが演じた。『赤い月』→『兄弟』とつづけて読んで、昭和が生んだ稀代の歌謡詩人・なかにし礼の家族史が完結する。
【たけのこ雑記帖】
紙の本すべて辛抱 上
2001/05/29 14:53
江戸時代後期町人層における禁欲と進取の精神
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
18世紀末、天明飢饉から寛政改革のころ。流れ者の和尚に読み書きを学んだ二人の少年が、下野国は鹿沼村(現在の栃木県鹿沼市)から江戸に送り出される。故郷に母を残す亥吉は薬種問屋の丁稚から堅実な商人の道へ、捨て子の千造は湯屋の薪(たきぎ)集めから盗賊の一味へ。出発点のわずかな差が、彼らの運命を分ける。
亥吉の奉公先には番頭の弥吉をはじめとして、同郷の出身者も多い。対するに、千造が投げ出されたのは都市下層の無頼の世界だ。二人が選んだ生き方のこうした違いは、江戸時代後期における都市社会の成熟と町人層の分化にも対応している。
《〔このころ〕利益を追求する勢いが強烈となり、人の利を模倣し横取りすることが遠慮なくなる一方で、地道な努力を続けるべきだという美意識が働きはじめたのだ。/その美意識は、間もなく江戸全体に広がって来るのだが、それにはまだ少し時間がかかる。亥吉はそのあいだ、まだ現われない美意識の最先端を行く立場に止まることになるのだ。》(上巻、p.221)
働き者の亥吉は奉公先の二代目主人に目をかけられ、呉服屋、料理屋と多角経営のお先棒をかつがされる。それでも彼自身は目立たぬように、はしゃがぬように地道に働きとおして、やがて没落した主人にかわって料理屋の経営を引き継ぐ。そればかりか、事業をさらに発展させていく。「すべて辛抱」=禁欲的な労働倫理が“時代遅れ”どころか、資本蓄積に適合的で、きたるべき近代を水面下で準備しつつあった時代。
そのころ千造も盗賊仲間と別れ、職人として身を立てようとしていた。亥吉はそれに手を貸し、二人で知恵を出し合って、人形焼の型焼き鉄板など新商品・新商売を成功させる。また亥吉が詐欺に遭って窮地におちいれば、こんどは千造が助けの手をさしのべる。こうして幼なじみ二人が、たがいに助けあい、幕末前夜の荒波を乗りきっていく(下巻では、そこに亥吉の女房・おりくが加わる)。
しかも彼らは地方から出てきて、ただ単に都市の通念や常識の枠組みに適応しただけではない。のちに推挙されて町役の五人組に加わり、伝統にしばられるようになって、それまでの自由な発想が制限された亥吉は、こう考える。
《もしかすると、江戸とは地方から流入してきた者たちが、自分たちなりの美意識を生かして、新しい江戸の風物などを創造して行く場所ではなかったか。》(下巻、p.100)
故郷の鹿沼を出て数十年、亥吉と千造はたえず、まだ見ぬ新しいものを追い求めつづけてきた。舶来の洋品雑貨や瓦版、後世の銀行にも似た金融システムなど、彼らが取り組んだビジネスは、つねに時代の先端を行くものであった。地方出身で都市に定着した者たちのこのような禁欲と、その半面、進取の精神に富んだ美意識(=エートス)は、亥吉や千造という理念型だけにとどまらず、前近代の都市社会において近代を育む原動力となったことだろう。この小説が提示するのは、そういう社会学的歴史観である。
【たけのこ雑記帖】
2001/05/14 07:02
電子テキスト時代の必読書
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この本は執筆者のためのマニュアルである。印刷所に入稿するテキストファイルをどのように作成すればよいか、基本的な考え方と原則を示し、平易に説明している。そんなもの読まなくてもわかっている、という人こそ読むべし。チェック・ポイントを以下にあげる。
▼Microsoft Word が段落のはじめを自動的に1字下げてくれるのは便利だと思っている。
▼あるいは、うっとうしいと思っているが解除する方法を知らない。
▼引用文などの字下げは、スペースと改行でなんとかでっちあげている。
▼段落の終わりに改行を入れず、画面の端までスペースを入れて改行したつもりになっている。
▼第一、一種、一つなど漢数字であるべきものまで、第1、1種、1つと書いている。
▼英数字を全角文字で書いている。
▼マイナス(−)と音引き(ー)とダッシュ(—)は区別しろといわれても、なんのことだかわからない。
▼省略記号のつもりで、・・・(中黒三つ)などと入れている。
ほかにもあるが、すくなくともこれらのうち一つでも当てはまるものがあれば、この本を読んで出直しなさい。わたし自身、あらためて目を見開かされた箇所もあった(その点については、自分のサイトの全ファイルに検索・置換をかけて修正をほどこした)。
西谷の主張そのものは、きわめてシンプルだ。重装備のワープロ・ソフトを使うのはやめて、テキストエディタにする。よけいな装飾に凝らず、執筆者は内容の入力だけに専念すればよい。さらに、できればもっと日本語の表記に気をつかおう。煎じつめれば、この三つにつきる。これらは執筆現場にワープロ、パソコンが普及しはじめた当初から、ずっと言われつづけてきたことである。にもかかわらず、このシンプルな考え方がなかなか理解されず、いまだに原稿整理に余分な手間がかかっている。著者サイドでテキスト処理の技法を身につければ、編集コストが下がり、いままで陽の目をみなかった企画も世に出せるのではないかという。
またテキストファイルでは表現できないルビや圏点、欧文特殊記号や上付き・下付き文字などの指定方法の標準化にも意欲を示す。それから付録の名刺サイズ・カード型CD-ROMにも驚かされた。この中には本書全文のHTMLファイルや、Webサイトと連携した未來社出版図書目録、それに Windows、Macintosh 双方のプログラムツールなどが入っている。かつて『現代政治の思想と行動』や『経済学の生誕』といった名著を生んだ版元の二代目は、またの名を持つ現代詩人・評論家であるが、そうとうのコンピュータ・マニアでもあるらしく、ファイル管理法からエディタのカスタマイズまでをとくとくと語る。後半のそのノリもなかなか楽しい。
【たけのこ雑記帖】
紙の本わたしはスポック
2001/05/10 09:24
“異邦人”とアメリカ都市社会
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
耳のとがった宇宙人(正確には地球人とのハーフ)、ミスター・スポック役で知られるレナード・ニモイは、かれ自身がロシア系ユダヤ人移民の息子であった。1931年3月、ボストンのウェストエンド生まれ。幼い頃を、アメリカ社会における少数民族コミュニティ(イタリア系移民社会)の、さらに少数派として過ごした。
ニモイが8歳になったときのこと。街の映画館で兄といっしょに彼は『ノートルダムのせむし男』を見て、嫌われ者の“せむし男”カジモドに激しく感情移入をする。
《自分は“異邦人”だ、“ほかの人間とは違う”という気持ちを理解できない人間がいるだろうか? 8歳のわたしでさえ、わかっていた。わたしはイタリア人の多い地区で暮らすユダヤ人だった。親しい友だちにはイタリア人も多かったが、彼らと自分が“違う”ことは、幼いときからわかっていた。わたしたちの友情は教会の前どまりだったのだ。》(p.31)
やがて役者の道に進んだニモイは、容姿が醜くて社会から疎外された青年ボクサー役や、エキセントリックな映画人の役などを経て、『スター・トレック』のプロデューサー、ジーン・ロッデンベリーに出会う。半分地球人で半分ヴァルカン人のスポック役を、ニモイは即座に気に入った。とがった耳に変な髪型、つり上がった眉毛‥‥外見からしてスポックは“異邦人”である。そしてニモイは試行錯誤をくり返しながら、冷静沈着で論理を重んじるスポックのキャラクターを作り上げていく。中指と薬指の間を広げるヴァルカン流のあいさつは、正統派ユダヤ教の儀式から借用してきたものらしい。
実際、オリジナル・シリーズの『スター・トレック』に魅力を与えていたのは、SFドラマとしてのクォリティもさることながら、典型的なヤンキー・ヒーローのカーク船長(ウィリアム・シャトナー)や皮肉屋のドクター・マッコイ(ディフォレスト・ケリー)らとスポックが織りなす異文化接触の人間模様であった。スポックとマッコイの会話は、アボットとコステロの漫才にヒントを得ているのだという。
しかし人気を博した『スター・トレック』もロッデンベリーが制作を降りる騒動があったり、大幅に予算が削減されたりで質の低下が著しくなり、1969年の第三シーズンをもって、いったん米国での放映が打ち切られる。その後『スター・ウォーズ』の成功を受けて、映画版『スター・トレック』が制作・公開されるのが1979年。もっともニモイ自身は映画の出来に不満だった。その不満を晴らしたのが、みずからの監督作品である『スター・トレック4 故郷への長い道』(1986年)だ。エンタープライズ号のクルーが20世紀のサンフランシスコに降り立つこの作品は、テンポといい、ジョークといい、一連のスター・トレック映画の中でも出色の娯楽大作に仕上がっている。長寿のヴァルカン人として、スポックは新シリーズの『スター・トレック/ザ・ネクスト・ジェネレーション』にも登場を果たした。
本書は、30年以上にわたってスポック役を演じて、この架空の“異邦人”の役作りを究めたニモイの自伝であり、その視点から見たアメリカ社会論でもある。なお、現在放映中の『スター・トレック/ヴォイジャー』でヴァルカン人士官を演じているのは、黒人の俳優(ティム・ラス)である。スター・トレックのシリーズにおける「惑星連邦」がアメリカ合衆国そのものを象徴しているのは一見して明らかだが、体制内異分子としてのヴァルカン人の配役がユダヤ人や黒人だというのも、またずいぶん露骨な話ではある。そこまでわかりやすくする必要があるのだろうかと、思わないでもない。一方、東洋人はオリジナル・シリーズのミスター・カトーにしても、ヴォイジャーのキム少尉にしても、ちゃっかりアメリカ社会に適応していて、これはこれでみごとな批評に苦笑させられる。
【たけのこ雑記帖】
紙の本巨泉 人生の選択
2001/05/08 18:16
戦後放送文化史における早稲田大学人脈
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
セミ・リタイア後の優雅な生活や自慢話の部分ばかりに注目が集まるけれども、むしろ戦後放送文化史の貴重な証言として読むべき本である。
1934年3月・東京下町生まれの大橋巨泉は、45年8月の敗戦を小学校6年生のときに疎開先の千葉県で迎えた。
《今から考えればボク達の同期生は、大日本帝国が最も高揚していた紀元2600年(昭和15年、1940年)に小学校に入り、その帝国が灰燼と帰した1945年に、(当時の)義務教育を終えようとしていた、最も苛酷な運命の世代なのだ。》(p.46)
そして高度経済成長期の各分野における文化の革新を担ったのも、ほかならぬこの世代である。ジャズに魅せられ、ジャズ評論家、ジャズ喫茶の司会者として世に出た巨泉は、やはり同じ世代の制作者集団が集まっていたテレビの世界に迎えられ、放送作家からテレビタレントに転身する。ある日、日本テレビの井原高忠に呼び出されて出かけてみると、その席にはキノ・トール、永六輔、前田武彦、中原弓彦(=小林信彦)、青島幸男ら一線級の放送作家が勢ぞろいしていて、それが『11PM』の企画会議だったのだという(この顔ぶれについては巨泉も記憶がさだかでないとことわっており、別のところでは岡田憲和や井上ひさしの名もあげている)。
ところで、このうちすくなくとも永六輔、小林信彦、青島幸男は巨泉と同じ早稲田大学の出身である。『お笑い頭の体操』『クイズ・ダービー』のプロデューサーだったTBSの居作昌果も早大の同期生だ。当時巨泉がなにかにつけて「早稲田大学中退」を売り物にしていたのを覚えているが、彼にいわせればタモリも久米宏も筑紫哲也も早大の後輩であって、大橋巨泉の人的ネットワークに早稲田大学人脈の占める比重は非常に大きい。
さてもう一人、いまは亡き寺山修司も、大橋巨泉の早稲田大学における後輩だった。巨泉が4年生で俳句研究会の幹事をしていたころ、新入部員の歓迎句会に青森から上京したばかりの寺山が現れた。
そのとき寺山が詠んだこの句——
黒人霊歌桶にぽっかりもみ殻浮き
に、当時すでにジャズ評論家として売り出していた巨泉がかみついた。「寺山君、君はどれ程黒人霊歌について知っていますか? 例えばこの句ではどんな曲をイメージしたのですか?」(p.57)。
それに対して、寺山はこう質問を返した。「それではうかがいますが、大橋さんは東北のうす暗い厨房について、どのくらいご存知なのですか?」(同)。これは江戸っ子巨泉の弱点に、みごとにはまったようだ。そもそも「巨泉」の名は高校時代に自分でつけた俳号だったが、寺山の才能に圧倒されて俳句への情熱がしぼみ、大学中退後はまったく句作をやめてしまったと書いてある。
それでも万年筆のCMで有名な「ハッパふみふみ」は俳句の才能とジャズのアドリブの融合で、この「ポップ短歌」は岡井隆編著『現代百人一首』(朝日新聞社、1996年)にも収録されているらしい(知らなかった)。
各種の社会調査が明らかにしているところによれば、一般に高学歴の人ほど平均して知人・友人の数が多い。むろん学校とは同年齢集団の接触機会を提供し交際を促進する場であるのだからして、教育年数が長ければ長いほど知人・友人の数が増えていくのは道理である。しかし高学歴者のパーソナル・ネットワークにみられる特徴は、たんに直接の知人・友人数が多いということばかりではなくて、社会の各分野にエリートとして進出した同窓生を、職業生活においても私生活においても有力な人的資源として動員活用できる点にある。学歴格差の社会学的意味は、そういうところにもあるのだ。
【たけのこ雑記帖】
2001/05/08 18:03
続・“紙一重の人”
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
これはその名のとおり会話術の本なんだが、読むにつれその会話(=人との接し方、世間とのつきあい方)を通して、“紙一重の人”萩本欽一の人となりが、ありありと浮かび上がってくる(取材・構成/立川竜介)。
こんなにひねくれて屈折して、頭の中でいろんなことを二回転も三回転もさせて考えていて、ピリピリとして怖い人はそういない。まったく人前に出さない妻子との関係など、前の本(『まだ運はあるか』大和書房、1999年)にはないエピソードも多数。
ついでだが大橋巨泉(『巨泉』講談社、2000年)と萩本欽一、この二人は両方とも下町のカメラ商の息子で、子どものころ親が事業に失敗して辛酸をなめたという共通点があることに気づいた。
【たけのこ雑記帖】
紙の本まだ運はあるか
2001/05/08 17:51
紙一重の人
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
1960年代末、コント55号全盛期の萩本欽一は、常識人たる坂上二郎を徹底的にいたぶる狂気のサディストであり、野球拳で女性タレントを脱がせて衣装や下着を競売にかけるハレンチ男であり、なおかつ、わけのわからなそうな映画(暗闇から手が出てくるやつ)を自主制作したりもする若きカリスマであった。
この本のインタビュアーにして構成者、斎藤明美も取材後記にこう書いている。
《実は、単なる視聴者としての私にとって、「コメディアン・萩本欽一」は、小学校の頃にお腹を抱えて笑った「コント55号の欽ちゃん」で尽きていた。その後の『欽ドン』『欽どこ』などにおける「萩本欽一」を、失礼ながら、わたしは面白いと思ったことはない。》(pp.227-228)
上の世代や下の世代がどう思うかは知らない。小学生でコント55号を体験したかどうかということが、なんだか決定的な問題であるような気もしてきた。
しかしその「55号の欽ちゃん」は、ドリフターズとの視聴率戦争に破れて、あっというまにぼくらの前から消えていった。70年代以降の萩本欽一は、『スター誕生』や『オールスター家族対抗歌合戦』で司会業が板に付き、『24時間テレビ 愛は地球を救う』で「いい人」のイメージを決定的にし、80年代になると『欽ドン』『欽どこ』『週刊欽曜日』の三つの番組合わせて、視聴率100パーセントというような偉業も達成する。
かつて低俗のレッテルを貼られた男は、こうして国民的お茶の間の人気者として頂点をきわめた。一線を退いたあとも『仮装大賞』あり、長野オリンピックの閉会式あり、NHKにだって毎週出ている。
欽ちゃんがNHKだって? なんたることだ、「55号の欽ちゃん」のあの狂気はどこへ行ってしまったのだろう。——この本を読んでわかったことがある。どこにも行っていない。萩本欽一は70年代から1999年のこんにちまで一貫して「変人」(p.89)であり、「紙一重の人」(p.128)だった。ただそれがテレビの画面に出てこないだけだ。この本は実際すごい本で、ただのインタビューを無難にまとめただけのしろものではない。斎藤明美が欽ちゃんに仕掛けた心理戦は、固い自我の殻にすぐぶつかって「人間・萩本欽一」の実像になかなか踏み込めないのだが、その「踏み込めなさ」をまるごとこういうかたちで示した点がすごいのである。ツッコミの欽ちゃんが突っ込まれて、ぽろっと本音をもらす瞬間がなんともスリリングでもある。冒頭に引用した言葉——「だから人間って付き合いたくないんだ、俺」——を、あなたはどう解釈しますか。
※やはり欽ちゃんの変人ぶりをインタビュー構成で示したのが、萩本欽一『快話術』(飛鳥新社、2000年)。欽ちゃんファンはこれも必読。
【たけのこ雑記帖】
紙の本生放送だよ人生は
2001/05/08 17:37
芸能アナウンサーの職場史
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
生方惠一とかけて、サラリーマンの悲哀ととく。そのこころは1984年のNHK紅白歌合戦、引退を表明していた都はるみの最後のステージ。——白組司会の鈴木健二アナウンサーがしゃしゃり出て、「私に1分間時間をください」と言い出したのも変だったが、アンコールを求める満場の拍手のなか、都はるみをこともあろうに「ミソラさん、ミソラさん」と呼んだ総合司会のこの人もどうかしていた。きっとみんな、なにかの熱に浮かされていたのだろう。
生方アナはこの「ミソラ事件」がもとで翌年大阪放送局への転勤を命じられ、けっきょく民放(日本テレビ)の誘いに乗ってNHKを退職する。この本(親本1990年刊)の初版は「ミソラ事件」に多くのページを割いていたそうだが、あれから16年がたった。今回はその部分を大幅にカットして、むしろNHK時代のエピソードや、歌手・スターの思い出話を中心とする構成になっている。
おかたいNHKにも芸能アナウンサーの系譜というのがずっとあって、なぜか蝶ネクタイがよく似合う。古くは藤倉修一、高橋圭三、宮田輝。「NHKの顔」とまで呼ばれた山川静夫や、最近では紅白や『歌謡コンサート』の宮本隆治といった人たちがそうだろうか。生方はこのうち山川と同期で、ともに1933年生まれ、56年入局。アナウンサー養成所時代に「芸能番組志望の者は手を挙げなさい」と言われて、いつも手を挙げていたのが生方と山川の二人だったのだという。
養成期間の最後に志村正順アナウンス部長(尾嶋義之『志村正順のラジオ・デイズ』新潮文庫)から任地の内示があって、赴いたのが北海道の旭川。以後、札幌・大阪を経て、大阪では、『のど自慢』が東西に分かれていた時代に西の司会者として顔と名を売る。いったん東京に戻ってきた1970年に担当したのが、月曜夜8時の『おたのしみグランドホール』である。このときには当時17歳の岡崎友紀がアシスタントについた。ふたたび大阪勤務を経て、1975年から東京で『NHK歌謡ホール』の司会。それが退職まぎわまで続いた。
だれとだれが同期で、そのとき上司にだれがいたか。そしてその職場集団は、時間の経過とともにどう変化したか。全国規模の放送局網を持つNHKでは、地方局を異動して東京で「あがり」というのが、出世コースとしてあるようだ。このような内部労働市場における競争と「同期」集団の連帯は両立するのか、いずれ破綻するのか、そんなことなどもいろいろと考えさせられる。
また、こういう履歴の人だから芸能人との交友も多いのだが、やはりいちばん印象深いのが美空ひばりと都はるみである。弟の不祥事でNHKを追放されていた美空ひばりがひさびさに復帰したのが、1977年の『ビッグショー』、ついで生方司会の78年『ひるのプレゼント』だった。西武池袋線のひばりが丘に住んでいた生方が、ひばりが好きだからひばりが丘に引っ越したんだと定期券をひばりに見せると、ひばりは「あら、ひばりのアナウンサーになったのね」と笑った(どういう意味だろう?)。そしてあの紅白ミソラ事件があって、いまはもう、ひばりはいない。2000年12月、都はるみがはじめて美空ひばりのナンバーを歌った日生劇場のステージを、生方は客席から見ていて、そのときとらわれた感慨についても書いている。
このほか、NHKアナウンサーの「言い間違い」列伝というのもおかしい。また特急の「はつしお」が遅れているのが原稿に「初潮が遅れています」とあって女性アナウンサーが絶句した話とか、「陰影」が「陰景」になっていたのをそのまま読んで怒られたとか、おやじギャグの連続もたまらない。
【たけのこ雑記帖】
2001/05/08 00:51
大阪下町、家族と地域社会の昭和史
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
大阪市阿倍野区松虫市場——空襲で焼けず、高度成長にもバブルにも見放され、いまだ昭和初期の風情を残す下町の路地の奥に、古びた洋館の玉撞き屋がある。そこで84歳のおばあさんが、客を相手にヨロヨロ玉を撞いている。壁には「くわえタバコはやめませう」「キューは水平にたもちませう」と、はり紙が貼ってあったりなんかする。そこへテレビカメラマンを名乗る男がやって来て、ドラマの舞台に店を使わせてほしいと言い出すが、さて…。
そんなエピソードではじまる、これは創業60年近いビリヤード場「保名(やすな)倶楽部」とそのマダム・千代さんの物語だ。小説の形式をとってはいるが、おそらく実話にもとづいており、日記や手紙も引用される。千代さんは、放送作家である著者の母。大正生まれで、女中奉公、キャバレーの女給を経て、船場の洋傘問屋のぼんぼん・南川栄一と知り合い、妾に囲われる。玉撞き屋の営業権を買って商売をはじめるのが戦時下の1943年。その年の暮れ、二人の姉につづいて長男・泰三を生む。
しかし1945年3月の大阪大空襲で、栄一は船場の本宅を焼け出され、阿倍野の「保名倶楽部」に転がり込むことになる。本妻と離縁し、千代さんは晴れて栄一と夫婦(めおと)になったが、おまけに和歌山の実家に身を寄せていた姑まで付いてきたから、たまらない。もとはといえば庄屋の娘、船場の奥様。南川家は、1階がビリヤードの風俗営業、2階が姑の仕切る船場の老舗という二重構造を家庭の中に抱え込んでしまう。
しかもぼんぼん育ちの栄一は、理想家の文学青年で遊び人と来た。働かず大量のレコードや本を買いあさり、“浪速のジャン・ギャバン”を気どって、おしゃれにも抜け目がない。泰三の下に生まれた妹も含めて、4人の子を抱えた生活が千代さんの肩にのしかかる。戦後の混乱期、実家の妹や弟も非行に走って、千代さんを悩ませる。客で韓国人の李さんに惚れられ、いっしょに東京へ行こうと切り出されたときには、この人について行こうかとさえ思ったという。だが、ついに子供たちを見捨てることはできなかった。
それからのち、千代さんが「保名倶楽部」の営業を続けながら、娘たちを嫁に出し、泰三を東京の大学に入れ、姑と夫の最期を看取って、そして今日(こんにち)にいたるまで、涙と笑いの女の一代記がつづられる。そのキャラクターは、ミヤコ蝶々か森光子か。それに歯医者の藤田先生、戦前からの客で自ら玉撞き屋をはじめた木村さん、お菓子屋の西村さん、本屋の石野さん、親子二代で計理士の杉本さん…いかにも大阪下町らしい常連客のコミュニティが、まだここにはある。都市はやはり、こういう人情が持ち味である。
【たけのこ雑記帖】
紙の本ぼくが読んだ面白い本・ダメな本そしてぼくの大量読書術・驚異の速読術
2001/04/26 14:54
「書評の書き方」を学ぶ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
『週刊文春』連載の読書日記をまとめたものだが、書き下ろし約70ページの「序 宇宙・人類・書物」は(こんなタイトルにもかかわらず)実用的な読書論・書評論で参考になる。
とくに書評を《本の紹介記事》と心得、さまざまなジャンルの新刊書の中から、「その本が読む価値があるか否か」、「読む価値があるとして、どの点においてあるのか」、「それをできるだけ、要約と引用によって、本自体に語らせる」(p.19)という方針は、一つの見識だろう。むろん、そうでない書評が世にあふれているからこそ、こういう主張が意味を持つのである。立花が嫌う、専門家の偉そうな蘊蓄、エッセイまがいの身辺雑記、的外れの批評…たしかに、どれも本の情報としては不要のものだ。
このほか、チャート式速読法(『「知のソフトウエア』講談社現代新書で述べられていたことの発展形)や、「人類共同体の文化」の重層構造(p.47)にまで話が飛躍する出版文化論など、啓発されるところが多かった。
読書日記の部分は、本人が「私は結構変なものが好きなのだ」、「異常なものに対する偏愛がある」(p.38)というとおり、独特の立花隆的世界をかもし出している。「ニュートンは近代科学の祖と考えられているが、実は、古代科学の最後の人でもあった。ニュートンは万有引力の発見の前、魔術やオカルトや錬金術の研究家でもあった」(p.85)からはじまるドブズ『ニュートンの錬金術』(平凡社)の紹介など、こういうの、いかにも好きなんだろうなあという感じである。それが、「実は『万有引力』という概念も、こういうニュートンのオカルト的世界観から生まれてくるのである」(p.86)と結んであれば、うむむ、読んでみたいと思わせるじゃありませんか。
【たけのこ雑記帖】
紙の本噂
2001/04/26 14:50
うわさの伝播過程とその構造の社会学
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
広告代理店が情報操作を狙って女子高校生のあいだに流したうわさが、連続殺人事件に化けてしまう。しかし捜査に乗り出したのは、はぐれ刑事の藤田まことを若くしたような40代のおじさんで、ちかごろの若者の風俗などさっぱりわからない。年下だが階級は上の女警部補の助けを借り、また妻に先立たれ男手一つで育ててきた娘のアドバイスも聞きながら、すっかり変貌してしまった渋谷のストリート・コーナー・ソサエティに立ち向かっていく。
社会学として面白いのは、「オルレアンのうわさ」やハンバーガー・ショップの都市伝説などをネタ元に企画会社の社長が思いつくWOM(Word of Mouth)——口コミ——による広告戦略と、それを携帯電話のチェーン・メールで広げていく女子高校生のコミュニケーション行動だろう。特定の携帯番号を「タンツボにする」なんて表現は、はじめて聞いた。やもめ刑事の相棒の女警部補が地図を描いて、うわさの伝播過程とその構造が明らかになってくる物語中盤も、ちょっとした社会学的興奮を味わえる。ついでにいうと、犯人がつかまったあとの展開もなかなかスゴイ。社会学でいうと×××××××だな、これ。
【たけのこ雑記帖】
紙の本浅草フランス座の時間
2001/04/26 14:45
コメディアンの“出世の階段”
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
渥美清、ビートたけしを生んだ伝説のストリップ劇場「浅草フランス座」(萩本欽一がいたのは階下の「東洋劇場」)。昭和30年代はじめ、井上ひさしはここの文芸部員で、渥美清が結核療養から帰ってきてテレビの世界に行くまでのわずかな月日をともに過ごした。当時をふり返った1973年、1991年の渥美との対談が収録されているのが珍しい。その対談の二度とも、井上ひさしが渥美清におかずのコロッケを横から取られた話をくり返しているのも、またおかしい。
この本冒頭の井上に対するインタビューによれば、ストリップ劇場の踊り子に「普通の踊り子」「セミ・ヌード」「ヌードさん」の階級(順にギャラがはね上がっていく)があるように、喜劇役者にも劇場の格に応じた階級があったのだという。
《ここで大切なのは、喜劇役者は、いきなりフランス座には出られないということです。百万弗劇場やカジノ座のような小さな劇場に出て、そこで「あいつは、おもしろいぞ」と評判がたってはじめて、フランス座から声がかかる。さらにフランス座から、丸の内の日劇ミュージック・ホール、そしてさらに日劇というふうに登って行く。つまり社会全体に喜劇役者のための出世の階段が埋め込まれていたんですね。》(p.13)
別の文章ではこれを「喜劇役者のための登攀装置」ともいい、井上は渥美清を「この社会システムが生んだ最後の、そして最大の俳優」(p.57)と呼ぶ。フランス座が「ストリップ界の東京大学」だとすれば、日劇ミュージック・ホールは東大大学院で、日劇出演は大蔵省入省のようなものらしい。そのたとえはともかく、「出世の階段」「登攀装置」が社会システムにどのように構造化されているかを見きわめるこの観察眼は、社会学の勉強になる。芸能人のみならず、たとえば政治家は、あるいは大学教師は、どのような「出世の階段」を歩むだろうか。そのパターンはかつてと現在とで、どう変化しているだろうか。
後半は戦後ストリップ小史。浅草フランス座で渥美清、長門勇、玉川みどり、河原千鳥が演じた井上ひさし台本「看護婦の部屋〈白の魔女〉」(1957年)も収録する。この台本をめぐる井上ひさしと小田豊二の対談から——井上「ストリップ・ショーが台本を必要としなくなったのは、関西から特出しストリップが攻めのぼってきてからです。特出しというのはあれは個人芸ですからね」。小田「ははあ、つまりその時から、ストリップは綜合芸術ではなくなったわけですね」(p.211)。
【たけのこ雑記帖】
2001/04/26 14:40
演歌のこころと高度経済成長期の精神
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
まず寺山修司の本からの引用があって、「私は《詩の底辺》ということばを使うなら、星野哲郎こそ、もっとも重要な戦後詩人のひとりだと考えるのである」(『戦後詩』紀伊國屋新書→ちくま文庫)と。しかし寺山にいわれなくとも、星野哲郎作詞の流行歌の数々は、子供のころから耳にこびりつき身体に染みついて、詩情というか情感というか何なのか、ともかく感動の核の一つを形成している(ような気がする)。
はるばる来たぜ 函館へ/さか巻く波を のりこえて(「函館の女」北島三郎)
三日遅れの便りを乗せて/船が行く行く 波浮港(「アンコ椿は恋の花」都はるみ)
ぼろは来てても こころの錦/どんな花より きれいだぜ(「いっぽんどっこの唄」水前寺清子)
俺がいたんじゃ お嫁にゃ行けぬ/わかっちゃいるんだ 妹よ(「男はつらいよ」渥美清)
この本によれば星野は1925年、山口県生まれ。戦後まもなく清水の高等商船学校を出て日魯漁業の漁船員として就職したが、結核をわずらい療養生活を余儀なくされる。そんななか雑誌『平凡』とコロムビア・レコード共催の作詞コンクールに応募して入選したのがきっかけで、当時すでに売れっ子作詞家だった石本美由起が主催する中国地方の同人誌に参加する。さらに新聞や雑誌への投稿を経て、のちに名コンビとなる作曲家船村徹と知り合い、御大古賀政男にも才能を認められ、上京してプロの作詞家となる。
コロムビア・レコードの分裂騒動(1963年)のときには、文芸部長の伊藤正憲、ディレクターの「艶歌の竜」こと馬渕玄三、斎藤昇ら“七人の侍”と行動をともにして、新設のクラウン・レコードに移籍した。北島三郎の「兄弟仁義」の歌詞にはこのときの思いが込められているらしい。
親の血を引く 兄弟よりも/固い契りの 義兄弟
義理と人情、すすんで苦労に立ち向かう決意。——星野の詞は、日本の高度経済成長を支えながら、高度成長の結果、急速に失われていったある種のエートスを歌い上げているようにも思われる。あの時代、星野哲郎を世に出した社会構造と、それを受け入れた社会構造の両方の「底辺」(寺山修司)に共通して流れていた何か。
クラウンで水前寺清子に書いた「涙を抱いた渡り鳥」「いっぽんどっこの歌」「三百六十五歩のマーチ」などは、人生の応援歌ともいわれた。
しあわせは 歩いてこない/だから歩いて ゆくんだね
一日一歩 三日で三歩/三歩進んで 二歩さがる
この歌詞もちょっとすごいなと、しみじみ、つくづく思う。
70年代以降も「昔の名前で出ています」(小林旭)、「風雪流れ旅」(北島三郎)、「兄弟船」(鳥羽一郎)、「みだれ髪」(美空ひばり)…とヒット曲を世に送って、75歳のいまも現役である。正月にNHKで、「風雪流れ旅」のモデルになった高橋竹山を、生前、星野が津軽に訪ねていく様子を再放送で流していた。ぺらぺらしゃべる高橋竹山よりも、シャイで朴訥な星野哲郎のほうが絵になっているのがなんだかおかしかった。
【たけのこ雑記帖】
2001/04/23 18:02
さらば友よ、荒井注よ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ドリフターズの全盛期をいつと見るかは、世代によって異なるだろう。われわれ(1959年生まれ)はやはり、「いい湯だな」や「ドリフのズンドコ節」「誰かさんと誰かさん」などのヒット曲を連発していて、まだ荒井注がいた1960年代末から70年代はじめのドリフにいちばん思い入れがある。またその時期は、高度経済成長の最後の日々ともぴったりと重なる。あれから30年。荒井注が2000年2月に亡くなり、翌月にはドリフの前にいかりやが在籍していたマウンテン・プレイボーイズのリーダーだったジミー時田も逝ってしまった。この自伝の執筆依頼を出版社から引き受けたのには、彼ら若き日の盟友への追悼の気持ちがあるのだという。いかりや自身、ことし古希を迎える。
1931年、東京・墨田区生まれ。芸事好きだが「堅気の誇り」を持ち合わせた父の影響を受けて育つ。戦時中に静岡県の富士に疎開して、東京大空襲を富士山のすそ野から目撃した。帰るところを失って一家は戦後も富士にとどまったが、いかりやは東京が恋しく、バンドマンになって上京する。クレージー・ウエスト、マウンテン・プレイボーイズなどのバンドを経て、「桜井輝夫とザ・ドリフターズ」のベーシスト。やがて桜井からリーダーの座を譲り受け、日本テレビの「ホイホイ・ミュージック・スクール」にレギュラー出演するようになる。
しかしそれもつかの間、メンバーの小野ヤスシやジャイアント吉田らがドンキー・カルテットを作ってドリフターズを脱退し、窮地に立たされる。そのときいかりやのもとに残ったのがドラマーの加藤茶で、高木ブー、荒井注、仲本工事は、レギュラー番組を続ける穴埋めに急きょ集めた男たちだった。
「トリスのおじさんみたいな面白い顔のピアニスト」(p.10)荒井注は、満足にピアノが弾けず、年齢もいかりやより三つ年上なのをサバ読んでいた。だがテレビでは、そのふてぶてしいキャラクター(「なんだ、馬鹿野郎」)が受けた。
《嫌われ者の私、反抗的な荒井、私に怒られまいとピリピリする加藤、ボーっとしている高木、何を考えてるんだかワカンナイ仲本。メンバー5人のこの位置関係を作り上げたら、あとのネタ作りは楽になった。…》
《ドリフの笑いの成功は、ギャグが独創的であったわけでもなんでもなくて、このメンバーの位置関係を作ったことにあるとおもう。もし、この位置関係がなければ、早々にネタ切れになっていただろう。そして、先走って結論を言うようだが、荒井が抜けたとき、ドリフの笑いの前半は終わったような気がする。メンバーの個性に倚(よ)りかかった位置関係の笑いだから、荒井の位置に志村けんを入れたからといって、そのままの形で続行できるものではなかった。志村自身も荒井の役を継ごうとはおもっていなかっただろうし。だから志村加入以後は、人間関係上のコントというより、ギャグの連発、ギャグの串刺しになっていった。》(pp.90-91)
いかりや自身によるこの分析は、前期ドリフと後期ドリフの違いを的確に示している。荒井注がいてこそのドリフターズであったから、その荒井に辞めるといわれたときのいかりやの狼狽は想像して余りある。
また年齢の点でも三つ年上の荒井が抜けると、高木は二つ下、仲本や加藤は10〜12歳下、志村にいたっては19歳下で、メンバーとの距離感も出てくる。実際、ドリフのメンバーよりクレージー・キャッツの植木等や谷啓、また同じ東京下町の出身で一つ年上だった三波伸介らと親しかったのだという。そうだったんだ。そんなふうに世代で区切って考えたことがなかったので、これは意外だった。
【たけのこ雑記帖】