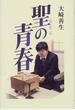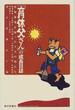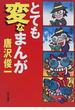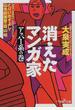Stellaさんのレビュー一覧
投稿者:Stella
紙の本痛快!心理学 Global standard★psychology
2001/02/08 11:49
臨床心理学の入門書
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
臨床心理学について素人が知るにはちょうどいいレベルの内容だと思う。少なくとも次のステップに上がる気にさせてくれる。心理学食わず嫌いだったら、それを治すのにちょうどいい本だ。
私は『心理学の本』の類にはあまりいい思い出はない。難解な専門用語に辟易して投げ出すか、逆にわかった気にさせられて、結局身についていないかのどちらかだった。フロイトやユングに関してはたくさんの入門書が出ているが、以降の心理学についてここまでわかりやすく書いてあってうれしかった。
ただ、精神病や神経症といった病気方面のことは詳しいが、人付き合いなどにもかかわってくる認知心理学については物足りないと感じた。
章の冒頭に出てくる赤塚不二夫の『天才バカボン』がいい味を出している。ちょうど章のテーマにあったネタなのがすばらしい。
紙の本ブレンダと呼ばれた少年
2000/12/29 21:46
性科学スキャンダルに終わらない人間ドラマ
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
包茎手術のミスにより、一卵性双生児の男児の片方が陰茎を失い、性転換手術を受けてブレンダという名の女児として育てられることになった。
「性差は生まれより育ちである」と主張する性科学の権威ジョン・マネー博士によって性転換の実証例とされ、著書に「女児としてすくすくと育っている」と発表されていたが、手術から30年後に別の学者によって公表された事実は「《彼女》は、女としてのジェンダー・アイデンティティーが受け入れられず、14歳のときに男として生きることを選んだ」というものだった。《彼》は現在3児の義理の父親として幸せな結婚生活を送っている。
この件は日本で今年発覚した「前期旧石器捏造事件」にも似た構図が浮かぶ。ある学説をめぐって論争が起き、学説を証明するために事実を隠蔽または捏造してしまう。最初に事実を伝えたのは学者ではなくマスコミだったことも同じ(本書の件は、マスコミ報道が見事に無視されましたが)。
いわば性科学のスキャンダルを描く本書だが、それにとどまらない魅力を持つのは、《彼》の、男としてではなく人間としての強さに負うところが大きい。あえて実名と写真を公開し、ブレンダであった過去をしっかりと見据えた姿勢は賞賛に値する。
2002/05/17 22:56
技術の進歩と心のケアの遅れを指摘
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
不妊治療の技術がどの程度までできるようになったか、という情報は氾濫していますが、実際に不妊治療で生まれた子どもやその家族がどうなったか、どのような問題を抱えているかという情報はあまりありませんでした。医師から心無い言葉をかけられた例、不妊治療がきっかけで離婚に至ってしまった例、不妊治療をやめると決意し医師に話したその日に自殺した妻……。美談では語られない生々しい話が語られています。
もちろん、デザイナー・ベビーや既にいる子どもへの臓器移植のために子どもを作るといった倫理の問題、あまった受精卵は「人」か否か、不妊治療の安全性の問題、諸外国のも詳しいです。
2002/05/08 12:58
ダルタニャンを通して見る17世紀フランス
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ダルタニャンといえば『三銃士』で、その後の話があるとは知らなかったのですが、本書はどちらかといえば『三銃士』の二十年後以降の彼の行動とフランスの政治や軍事を語っています。
ピレネー山麓からパリで銃士になったいきさつ、ルイ14世時代の大きな事件への関わり、立身出世を果たした後の彼の行動、コルベールなどとの関係など、フィクションであってもおかしくない彼の生涯が紹介されています。
2001/10/15 10:09
血の色の薔薇の秘密
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
男子寄宿学校を舞台としていますが、同性愛要素はありませんので、そういったものがお嫌いな方にも安心してお勧めできます。
田舎町の名家に伝わる絵画と伝承、特殊な薔薇の苗を伝えつづけてきた人々の過去が明らかになるにつれ、二転三転となる様が非常に興味深い作品です。
2001/08/21 13:05
ただのエコロジーじゃない料理法
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
手軽でおいしい料理を紹介し続けている小林カツ代が紹介する、地球と人にやさしい料理法が満載です。
たとえば、野菜の品種改良の結果、昔から言われてきた下ごしらえでは味や栄養が抜けてしまうものが増えてきているので、それを踏まえた方法を紹介しています。他にも油の有効利用、鍋一つで作る多種料理の紹介など、料理リストラ術がいろいろと掲載されています。
紙の本聖の青春
2001/03/02 10:33
将棋に寿命を削った棋士
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
難治性ネフローゼにより入退院を繰り返しながら、奨励会に入り、プロとなり、数々の壁にぶち当たりながら必死に名人位への道を模索していった彼。そして、「この弟子にしてこの師匠あり」という感じのする彼の師匠森信雄。何人もの友人、そして目標である谷川とライバルの羽生。
世の中に神がいるのなら、彼になんと残酷なものを背負わせてしまったのだろう。ネフローゼにならなければ、この師匠と出会わなければ、羽生が同時期にいなければ、もっとたやすく名人位を取れたであろう。しかし、これらの出会いが彼を将棋に向かわせ、勝ち進んでいく原動力になったのは否定できない。
彼の不屈の精神と著者の筆により、無冠の村山聖は「記憶に残る棋士」になるかもしれない。記述は村山並に不器用だ。しかし、その不器用さゆえに感動させられる。
紙の本私の居場所はどこにあるの? 少女マンガが映す心のかたち
2001/02/27 17:56
フェミニズムの視点から見た少女マンガ史
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
フェミニズムの本というと、なんともとっつきにくいというか、女性の私から見ても疲れるものが多いのですが、本書は題材が「少女マンガ」ということもあって、非常に読みやすい本です。また、「こうあるべき」「こうすべき」という内容でもなく、ただ少女マンガの内容から時代の価値観の推移を見るものであるため、押し付けがましさを感じることはありません。取り上げた内容が、恋愛・家族・トランスジェンダー・仕事・生殖、というあたりが実にフェミニズムらしさを感じさせますが、それは仕方がないでしょう。
少女マンガの「ブスでドジだと思っている女の子がハンサムで頭のいい男の子と結ばれる」というステレオタイプはふた昔前の話になっていて、純文学はだしの芸術性と繊細さあふれる物語になっているのは少女マンガ読みならご存知のとおり。生命や環境などに関しては、世間の一歩どころか十歩ぐらい先を行く作品があるぐらい。
ただ、こと仕事を題材にしたものに関しては、読者層が高校生以下と想定される少女マンガでは扱いきれないからか、例として取り上げられる作品がレディースコミックや青年誌に連載されていたものになってしまっているのが残念。これは著者の責任ばかりではなく、少女マンガの限界なのでしょう。
紙の本クォータームーン
2001/02/26 10:26
インターネット利用者なら必読のミステリーホラー
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
インターネット利用者なら必読の作品。角川ホラー文庫ですが、ホラーというよりミステリーに近いです。『ノーライフキング』を現代にして外側から見た物語、という説明がぴったりです。
作家の描くネットワーク社会というのは、現実にはありえないくらい御都合主義なことが多いですが、この作品中のものには説得力を感じます。また、神戸児童殺人事件でインターネットで起きた事柄など、ネットワーカーが管理や規制を厭うあたりのリサーチがしっかりしています。まあ、いくらチャットなれしていてもテレパスにはなれないでしょうが。
中ほどになると事件の概要が見えてきますが、打つ手打つ手が全て裏目に出て、先の読めなさが妙に心地よくなります。
紙の本「育休父さん」の成長日誌 育児休業を取った6人の男たち
2001/02/26 10:20
父親が育児休業を取ったらどうなるか
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
朝日新聞朝刊家庭面で1997年から週一回連載されていたものをまとめたもので、さらに男性の育児休業に関する法律知識と育児休業をした男性に対するアンケート結果が加えられています(母数がかなり小さいですが)。
本編は七人の育児休業経験者によるリレー連載です。この七人のうち、後半二人は育児休暇を取った時期からかなり経っているからか、育児休暇そのものの話よりはサラリーマンにありがちな転勤や単身赴任、大きくなった子供のことが中心になっています。育児休業の話がほとんど出てこないので、「タイトルに偽りあり」の感が否めません。
育児の様子や周りの反応、仕事との関連は七者七様ですので個別に感想は言いませんが、男性が育児に専念することに関してまだまだハードルは高いんだな、と考えさせられました。
紙の本巷説百物語
2001/02/26 10:18
怪談が京極夏彦の手にかかると
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
七編収録の短編集。江戸時代の怪談話の真相、といったところでしょうか。
京極夏彦の他の小説と同じく、章ごとに視点が入れ替わっています。話の筋が見えなくて挫折するほどには長くないのが私にとっては幸いです。話の筋が見えないがゆえの「めまい感」と、最後の謎解きの驚きがいいという趣もありますが。
残念ながら、玉ばかりではありません。「小豆洗い」「芝右衛門狸」はお勧め。反対に「塩の長司」「帷子辻」は嫌い。どうも私は仕掛けが自己主張するのを好まないようですね。
紙の本とても変なまんが
2001/02/25 13:32
手塚治虫を中心とした正統派まんがからふと横道にそれて、B級まんがの迷路を旅してみよう
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
とかくまんが界というのは、手塚治虫を幹の中心に多くの枝葉にわかれた大樹として描かれることが多い(実際、そういう系統図を見たことがある。あれは十数年前の朝日新聞元旦特別面だったか)。そういった「手塚治虫史観」「まんが進歩史観」に疑問を投げかけたのが本書である、なんて言い方をするとかっこいいが、ようするにヘタウマというよりはっきり下手だったり、あまりにもマニアックだったり趣味に走ってたり、それでもって影響力がまるでなかったまんがについてのウンチクです。
あえて内容は説明しませんが、普通誰も知らないだろう的ヘタまんがもあれば、ええっと驚く有名人も含まれています。
著者はそれなりに思い入れいっぱいに紹介しているのですが、たしかに一部には不運な作家とか編集の陰謀とか某先生のかわりの捨て駒とかあるでしょうが、やはり主流になりえなかったのはそれなりの理由があることがおのずから明らかになっている、そういう風に私は感じました。
2001/02/24 12:10
太田出版版の再構成+鳥山明新興宗教入信説
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
太田出版から発行された『消えたマンガ家』全3巻を再構成し、ボーナストラックとして鳥山明新興宗教入信説をめぐるルポルタージュが入っています。
『ダウナー系の巻』とは違って、生きたままあちらがわに行ってしまった人、たとえばに教祖になってしまった少女漫画家や天狗になった漫画家など、つぶされてはいないけどエンガチョくらった風な漫画家が集められています。ダウナー側に持っていったほうがよさそうな人もいるけど。
著者が名をはせたのは新興宗教関係のルポルタージュだったからか、新興宗教がらみの記事はいきいきとしています。鳥山明を扱ったものは、事実をつかむまで焦らせる焦らせる。「オチはそれかい!」というものでしたが、現実とはえてしてそんなもんでしょう。おすすめ。
紙の本だれが「本」を殺すのか
2001/02/23 17:57
延命治療か、それとも?
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
数年来の出版不況の原因はいくつも言われてきています。取次から配本される本を並べることに甘んじて独自性を持たない書店、書店から注文を受けた本を効率よく配本できない取次、「数打ちゃ当たる」とばかりに新刊出版点数ばかり増やす出版社、増えすぎた本を置くために巨大な書店を作らざるを得ない書店と取次、再販制度の隙間をかいくぐるかのように見えて実は昔のベストセラーの倉庫と化している新古書店。まだまだ他にも言われていますが、著者は根本原因は出版関係者で本を愛す人が減ってきたのではないかという推理を行っているようです。
通常この手の本は「再販・委託制度」問題と、本が消費品になってしまった事実を嘆くのが常で、本書もそこから脱却してはいないのが残念です。最大の問題は〈本を買う人・買わない人〉が全然見えてこないこと。なぜ馬鹿売れする本が出て、いい本が全然売れないのか、いい本が売れるようになるにはどうすればいいかを言及してほしかった。
2000/12/30 10:04
児童心理学・発達心理学の本としてなら悪くない
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
子の性格は親の育て方によって決まるという「子育て神話」は、実は根拠のない学説によって作られたものだ、と主張する本です。多くの学説や実験成果が、その恣意的な調査方法や論点がずれた結論として批判されたり、別の結論を導き出されています。
著者の主張は、よっぽど極端なことでないかぎり、子の性格は環境(友人など)によって決まるのであり、親の育て方が子の性格に直結するわけではないというものです。端的に言えば「親がなくても子は育つ。しかし友達がなければ異常に育つ」ということでしょう。
内容は濃いですが、平易な文章で書かれているため、一部訳語が日本の精神医学用語に沿っていないという問題を無視すれば理解しやすいかと思います。ただ、あまりにも膨大なので、論点が散漫になってしまっています。この点が非常に残念です。
この本は、育児関連書として読むのではなく、児童心理学・発達心理学の本として読むべきでしょう。育児書としては「『子育ての大誤解』神話」を生み出す危険性に満ちています。