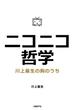丸善 丸の内本店書店員レビュー一覧
丸善 丸の内本店書店員レビューを75件掲載しています。1~20件目をご紹介します。
| 検索結果 75 件中 1 件~ 20 件を表示 |

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
星間商事株式会社社史編纂室 (ちくま文庫) 三浦しをん
気軽に読めてかつ読後感がスッキリした小説
もうすぐ年末年始休暇という方も多いかと思います。
ということで、今回はのんびりしたいときにぴったりの、気軽に読めてかつ読後感がスッキリした小説をご紹介いたします。
本作は、一見企業小説と見紛うタイトルですが、中身にお堅い要素はほぼありません。
とある中堅商社の社史編纂室に配属された面々が、自社の歴史をひも解く姿を中心に、彼らの日常を笑いあり涙ありで描きます。
特に私がオススメしたいのは、主人公の29歳独身女性のリアルな描写。
私事で恐縮ですが、著者の三浦しをん氏とは同じ大学の同じ学部出身で、同じく女子校出身ということで共通点が少なからずあり、著作を読むたびにきっと同じようなキャラクターの人間に囲まれて学生生活を送っていたに違いない、と勝手に親近感を覚えています。
本作も、女子校出身者が陥りがちな趣味を中心とした女性のコミュニティーや、年齢を重ねて人生のイベント(特に結婚)を迎えることでそのコミュニティーのバランスが少しずつ崩れていく姿を、恐らく実体験に基づいて描いていて、読みながら「あるある!」と頷いてしまうことしきりでした。
女子校に通っていた方はもちろんのこと、そうでない方には女子校出身者ってこういうかんじなのか、と秘密の花園を覗くような楽しさも味わえると思います。
タイトルの通り社史の編纂を軸にストーリーは進みますが、「女子校出身者あるある」としても楽しむつもりで読んでいただくのもオススメできる一冊です。
(評者:ハイブリッド総合書店honto ネットストア担当 AT)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
「なぜか売れる」の公式 理央 周 (著)

なんで「あの本」はこんなに売れるのだろう?
なんで「あの本」はこんなに売れるのだろう? 「この本」はあまり売れないのだろう?
長年書店で働いていますがそう思うことが、多々あります。
本に限らず、この世に出回っている商品や儲かっている店についてなんで?なんで?と思うこともしばしば。
商品や店が、どう仕掛けたら売れるのか、なぜ売れるのかが、とてもわかりやすい言葉で語られています。
商品の機能や性能ではなく顧客にいかに価値があると思わせるか。思わせるためにどうするか。新しい市場をゼロから作るのではなく、市場にあるよく知っているものを組み合わせたらどうなるか。
など具体的な事例をもとに分かりやすく解説されており、あの企業の高級路線はこう言う思惑があるんだな、あの商品が売れるのはイメージが価値として見られているんだな、などなど売れる秘密がわかります。
「あの本」を売るために策を考えたいと思います。
(評者:丸善丸の内本店 1階一般書フロア 村山)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
ニコニコ哲学 川上量生(著)
川上さんの魅力がたっぷり詰まった1冊
この本はKADOKAWA・DOWANGOの会長である川上量生さんが、ウェブメディアのcakesで連載したインタビュー原稿をまとめたものだ。会員制、有料のウェブメディアでの連載だったこともあり、就職活動に関してとある会社を実名で批判したり、ニコニコ動画のUIはわざとユーザーが嫌がるように作っているというような、絶対に他のインタビューでは語らないような危険な話題にも踏み込んでいる。
もちろんKADOKAWAとDOWANGOの経営統合についても語っている。IT企業と出版社という異業種間の経営統合にどんな意味があるのだろう?と思っていたところ、川上さんもよくわからないといっているのには笑った。でもよくわからないからこそ、おもしろいし、競合相手がいないので、独自のポジションを築くことができる。という発想には驚かされた。
インタビューを読んでいると、川上さんの頭の切れのよさと、発想の豊かさ、深さに驚かされる。メディア論からクリエイティブ論。国家論から人類の未来まで、思いもよらない話が次々と飛び出してくる。その一方でやりたいことを聞かれたら「もっと寝たい」だとか「とくにない」とかいうので、そのギャップがまたおもしろい。川上さんの魅力がたっぷり詰まった1冊である。
(評者:丸善丸の内本店 ビジネス書担当 田中大輔)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
被災地デイズ 矢守 克也 (編著)

災害に遭遇した時、最適な状況判断ができるか?
災害に遭遇した時、最適な状況判断ができるか? 本書のロールプレイング形式の問いの殆どに思考停止してしまった。
「Q1 自宅で地震に遭遇。10分後に津波が来るという。近所には一人暮らしのおばあさんがいるが様子を見に行く? Yes or No」
といった問いが、時には会社の管理職、時には自治体職員、あるいは報道関係者の立場にあると想定して次々に提示される。正答はない。それでも、東日本大震災や阪神淡路大震災の経験に基づいたシチュエーションごとの解説は災害発生後にどのように行動するか考える助けになる。普段からの災害対策が必要であることは分かっているつもりだったが、非常持ち出し袋の準備や避難経路の確認という程度だった。現実にはいつ、どこで被災するか分からない上に避難中や避難所でどんな問題があるか分からない。震災の直後は誰もが、その時の反省を踏まえて、備えることを考えるが、時とともに日々のことにかまけて、次に震災が起こっても似たような行動しかとることができない。この本を読んでみて、災害とはこんなにも非日常なのだと理解した。防災や避難だけが災害対策ではない。非日常を乗り切る覚悟を持ちたい。
(評者:丸善丸の内本店 和書グループ 伊藤美保子)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
ママだって、人間 田房永子 (著)
田房永子さんの2作目の著書
一昨年大変話題となった『母がしんどい』(新人物往来社)の著者、田房永子さん。この本は今まであまり表面化していなかった母娘関係の悩みにスポットライトを当てた本で、この本の出版を機に色々なメディアで、いわゆる毒母・毒親の問題が取り上げられるようになりました。その田房さんの2作目の著書が、この『ママだって、人間』です。
この本も前著と同じく、今までたくさんの人が思い悩みつつも口に出しにくかった「ママであること」に対するモヤモヤが妊娠・出産を経験したての田房さんの立場から綴られています。
出産の痛み、産後の身体の変化、とにかく眠れない産後初期の赤ちゃんとの生活…育児書にはサラリとしか書かれていない産前産後の様々な出来事、そして夫をはじめとする周囲の人々の言動は、ただの「私」だった田房さんを、否応無く「母」にしていきます。田房さんがすごいのはそのことに疲弊しつつも、周りに流されることなく、また自分を守りすぎるのでなくきちんと自然であろうとし続けることです。人生に対するこういう姿勢は、産む産まないとか、男だ女だとか関係なく、我々に必要なのではないか、としみじみ考えさせられる一冊でした。
(評者:丸善丸の内本店 実用書担当 望月あゆ美)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
「最悪」の医療の歴史 ネイサン・ベロフスキー (著)

古代~近代に至るまでの色々な治療例
本書には、古代~近代に至るまで実際に行われた色々な治療例が紹介されている。現在ではどれも信じられないような方法が真剣に用いられていたようだが、治療を受けた患者にとってはまさしく「最悪」な医療そのものだったのではないだろうか。
しかし、これは我々にとっても他人事ではない。
以前よりも診断基準、治療方法、倫理観は向上しているとはいっても、見直しは現在でも続いている。また、日常の診療の場においても実際に誤診などによる治療法の選択ミスもおきている。患者側にセカンド・オピニオンなどの選択肢はあっても軽度な症状であればあるほど実際にはなかなかできることではない。
不安を煽るようだが本書を読み歴史を振り返る事で、これまでの医療に対する考え方がかわるかもしれない。心配性の方はくれぐれも気をつけてお読み下さい。
(評者:丸善丸の内本店 理工・医学書担当 工藤誠也)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
企画は、ひと言。 石田 章洋 (著)

思考錯誤を繰り返す日々を打開するヒントになる一冊
駆け出しの頃は、とにかく企画を作る事が苦手なダメ企画マンだった著者が、どのようにしてヒットする企画を生み出せる売れっ子放送作家になったのか? そのきっかけとは何だったのでしょうか?
著者曰く、ウケる企画はみんな「ひと言」であるといいます。ヒットに共通するのは、その物事に対してひと言で言えるという。
例えばトヨタ「プリウス」をひと言でいうと「地球にやさしいエコカー」や、AKB48とは「会いに行けるアイドル」というように「ひと言で見える=イメージできる」ものであり、優れたアイデアは必ずひと言でいえるそうです。
でも、ひと言でいえるには、言葉のセンスみたいなも物が必要なのではないか?「私にはセンスがないから・・・。」と思ってしまいます。
しかし「見えるひと言」にセンスは不要だと著者は言います。では、なぜ企画は「ひと言」でうまくいくのでしょうか?
そのひと言を表すには、5つのSがポイントだそう。
そして、更には、ウケるアイデアの5原則、アイデアをひと言にまとめる技術や、“なぜひと言でいうとうまくいくのか?”“ひと言でいうには、どうすれば良いのか”というノウハウが細かく紹介されています。
今までアイデアを出すために、頭を絞りに絞って悩んで思考錯誤を繰り返す日々を打開するヒントになる一冊です。
(評者:丸善丸の内本店 ビジネス書担当 伊賀並寛子)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
雪の香り 塩田 武士 (著)

京都を舞台にした、最近は珍しい純愛ミステリー
京都を舞台にした、最近は珍しい純愛ミステリー。
雪のようにはかなく美しい容姿、性格は関西のじゃじゃ馬である雪乃と金のない学生恭平が偶然出会い、一緒に暮らし始め恋におちる。失踪してしまった雪乃と新聞記者になった恭平は12年後に再会し、また暮らし始める。雪乃が失踪した理由、本当の正体は誰なのか、記者ならではの緻密な操作で暴いていく。真実を知りたい気持ちと愛してるからこそ知りたくない恭平の心の葛藤がせつない。
相変わらずの流暢なユーモアあふれる関西弁の文章が作品を暖かく仕上げ、SNSなどネットを扱ってないところが懐かしいラブストーリー映画を観ているような気持ちにさせてくれる。
(評者:丸善丸の内本店 文芸担当 三瓶ひとみ)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
南朝の真実 忠臣という幻想 亀田 俊和 (著)
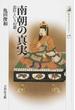
歴史研究の面白さに気付く一冊
後醍醐天皇の倒幕運動に応じて挙兵した後、一貫して天皇に忠誠を尽くした楠木正成ら南朝側の人物たちは忠臣、その一方で倒幕の最大の功労者足利尊氏といえば、天皇を裏切って北朝を樹立したという事実があるがゆえに逆賊という印象が強い。
こうした「南朝忠臣史観」は、戦前からの代表的中世史家である平泉澄が集大成した皇国史観に最も鮮明に表れており、それが多くの日本人が南朝と北朝にもつ印象に影響しているようである。だが南朝の内実はといえば、天皇に従わずついには配流された息子の護良親王や、内部対立の結果北朝側に帰順した正成の子の正儀を見れば、ご内紛あり、裏切りありと、清廉潔白な忠臣のイメージからは程遠い。
本書ではそうした南朝の内実が暴かれていくのだが、筆者の目的は「南朝中心史観」の単なる否定ではない。ある史料によれば、正成は全国の武士をまとめるには尊氏の力が必要だとして、尊氏が九州に没落した段階で講和すべきだと天皇に献策するなど現実的・合理的な考えを持った武将であったという見方ができるという。一方で尊氏はといえば、後醍醐天皇の本名の尊治から偏諱を受けた尊氏という名を終世使うなど、天皇に対して親愛の情を持っていたという。
本書を読むと先行研究をただ否定するのではなく、正しく評価しなおす、あるいは違った見方ができるということを提示できる面白さが歴史研究にはある、とうことを気づかせてくれる。
(評者:丸善丸の内本店 人文科学書担当 喜田浩資)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
ビジネスパーソンの誘う技術 ベリッシモ・フランチェスコ
著者曰く「誘う」とは「人生を変える魔法である」
お金もコネもないただの留学生だった著者は、自らの「誘う技術」を磨いていくことで、あらゆる人を巻き込んでいった。それにより数人からはじめた料理教室は大人気となり、タレントとしても活躍していくようになる。この本はそんな著者の「誘う技術」をあますところなく紹介した本だ。
著者曰く「誘う」とは「人生を変える魔法である」。確かに人生というのは待っているだけでは何も始まらない。自ら人を誘うことで、ものごとはどんどん動いていく。なぜなら人はみんな誘われることを待っているからだ。誘われて嫌な気持ちになる人はあまりいないはずだ。(もちろん嫌いな人から誘われたら嫌かもしれないけど……。)
断られるかもしれない。そう思って人を誘うことに二の足を踏んでいる人も多いだろう。でも断られることが当たり前だと思えば、人を誘うハードルというのは下がるのではないだろうか? また数をこなすことも重要だろう。私は実際にこの本を読んでから、色んな人を、食事や遊びなどに誘ってみた。するとどうだろう? びっくりするぐらい人生が色々と動き出したではないか。騙されたと思ってこの本に書かれていることを実行してみてほしい。きっと人生が面白くなるはずだから。
(評者:丸善丸の内本店 ビジネス書担当 田中大輔)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
英国一家、ますます日本を食べる マイケル・ブース (著)

多くのファンを獲得した『英国一家、日本を食べる』の第二弾
昨年、多くのファンを獲得した『英国一家、日本を食べる』の第二弾。
本書は正確には新作ではなく、原書『Sushi & Beyond』の中から、一作目に収録されなかったエピソードを中心に新たに加えられた番外編と、著者マイケル・ブースから日本の読者に向けたメッセージで構成されています。
イギリス人ジャーナリストの著者は、日本人の友人に紹介された辻静雄の本の影響を受け、本物の日本食を食べる為、日本へ行くことを決意。本人の思いとはうらはらに、妻の発案により一家で日本を訪れることになります。
本作では、定番の築地魚河岸、旨味調味料の総本山である味の素本社、天城山の山葵、かっぱ橋道具街、松坂牛から下関のふぐ、沖縄の豆腐よう、ぬちまーすの塩などなど、著者が体験して、独特の感覚で感想を添えています。前作同様、日本食べた褒めではなく、一刺しあるユーモアと家族のドタバタを交え、日本食の世界を堪能。そこがまた本シリーズを面白く読ませるポイントです。
巻末の日本の読者に送るメッセージは、我々日本人が自分たちの食べ物を見直す良い機会になります。前作を読んでいない方は上下巻のような作りになっているので、是非とも前作から手にとって見てください。
(評者:丸善丸の内本店 実用書担当 半田純一)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
オオカミと森の教科書 朝倉 裕 (著)

オオカミの悪いイメージを払拭すべく、オオカミの生態に迫る
オオカミほど悪者扱いされている動物はいないかもしれない。子ぶたの家を吹き飛ばしたり、可愛い赤ずきんちゃんを食べたりと、邪悪、獰猛、残忍といったイメージがつきまとう。それゆえ世界各地で駆逐され、日本のように絶滅してしまった地域も多い。だが著者は声を大にして言う、「オオカミはとても賢く愛情深い、美しい生き物だ」と。本書ではこれまで根付いてしまったオオカミの悪いイメージを払拭すべく、オオカミの生態に迫る。
オオカミはシカを捕食するが、そうすることでシカが草や樹木を食い尽くさないように調節するという生態系の中で重要や役割を担っているのである。欧米では1970年代頃からオオカミの生態系の中での役割に気づき、駆除から保護へと方向転換した。生態系の中でのそうした存在を生態学用語で「キーストーン種」という。キーストーンとは石組みのアーチを頂点で支える石で、それがないとアーチが崩れてしまう重要な石のことである。アメリカのイエローストーン国立公園では、オオカミがいなくなったことで崩れた生態系のバランスが、オオカミを再導入することで見事に復活し、オオカミがキーストーン種であることが証明されたのだという。
モンスーン気候の日本では森が再生しやすいというが、やはり増えすぎたシカのせいで再生が遅いという。日本でも森からオオカミの遠吠えが聞こえる日が再びやってくるのだろうか。
(評者:丸善丸の内本店 理工書担当 工藤誠也)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
黒田官兵衛・長政の野望 もう一つの関ヶ原 (角川選書) 著者:渡邊大門
播磨の国でもっとも有名な戦国武将
2014年の大河ドラマの主人公黒田官兵衛は、私の郷土播磨の国でもっとも有名な戦国武将といえる。
有名だといってみたものの、司馬遼太郎の「播磨灘物語」を高校生のころに読んだだけで、意外と何も知らないことに大河ドラマを見ていて気づかされた。そこで著者が播磨の守護赤松氏の研究に実績があるということで、本書を読んでみた。
まずわかったことは、史料が乏しさゆえに黒田官兵衛、そして黒田氏についての研究がそれほどなされていないということだ。有名な史料として『黒田家譜』があるが、17世紀後半に黒田家の正史として編纂されたもので、先祖である黒田官兵衛がかなり美化されているようで、信頼のおける1次史料としては扱えないようである。そのなかで天下分け目の戦いとして知られる関ヶ原合戦については近年一次史料を用いた研究がなされるようになっており、本書は副題にもある通り、関ヶ原合戦前後における黒田官兵衛・長政親子の動きを追うことが中心になっている。
官兵衛は豊臣氏に従うことで姫路の一城主から、豊前に大きな領地を得ることになる。その一方で息子長政は家康に近づき、関ヶ原合戦では重要な役回りを演じ、合戦後には筑前の大大名となることになる。彼らの動きをみていると、大河ドラマにもしばしばでてくる、「全ては生き残るため」というセリフに凝縮されているように思われた。
(評者:丸善丸の内本店 人文書担当 喜田浩資)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
ローラの炎 長野 慶太 (著)

米国リーガルサスペンスを盛り込んだ社会派ラブストーリー
「神隠し」で日経小説大賞を受賞した著者の新作は米国リーガルサスペンスを盛り込んだ社会派ラブストーリー。
故郷群馬に苦い思いを残し逃げるようにアメリカに留学したジュン。ネイティブアメリカンの娘ローラとの運命的な出会いから、村へのカジノ建設の是非を問う論争に巻き込まれる。法廷での争いは迫力があり読者をぐっとひきつける。そしてこの争いが思わぬ窮地に彼らをたたせてしまう。
カジノ利権問題そしてネイティブアメリカンの血の問題、民族のアイデンティティと普段あまり考えられない事が題材として使われ興味深い。
二人の恋の行方も二転三転して恋愛小説としての読み応えも十分である。
(評者:丸善丸の内本店 文芸書担当 三瓶ひとみ)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
USJのジェットコースターはなぜ後ろ向きに走ったのか? V字回復をもたらしたヒットの法則 (角川書店単行本) 森岡毅 (著)
アイディアを生み出すための4つの技法
最近、ユニバーサルスタジオジャパンの2013年度年間集客数が1000万人突破と言うニュースを見ました。
『なぜ集客が伸びて続けているのだろう?』
私はテーマパークが好きでUSJにも数度行って楽しかった記憶があります。
しかしUSJについて、
『以前は映画だけにこだわったテーマパークだったのになぜ今はそうでなくなったのか。』
『いろんなキャラクターに手を出して迷走しているのではないか。』
上記のように思っていた私はこの本を読んで考え方が偏っていたと痛感しました。
落ちた集客を取り戻すためにどうしたのか。映画だけにこだわるのをやめたのはなぜか。限られた予算で集客するためのアイディアやリノベーションのアイディアなど、実在のアトラクションやイベントを事例にピンチを打破するアイディアとストーリーが描かれています。
アイディアを生み出すための4つの技法=イノベーションフレームワークについても読みやすい文章で書かれているのでマーケティング知識がない私のような初心者でも理解できました。
ハリーポッターの新アトラクションが今年の夏OPENなど話題が絶えないUSJ、その話題性の影には常に挑戦し続ける企業努力があり、また発想を次々生み出す柔軟性があると感じました。
逆向きに走るジェットコースターに乗りに行こうと思います。
(評者:丸善丸の内本店 和書一般書担当 村山美尾)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
動的平衡ダイアローグ 世界観のパラダイムシフト 福岡 伸一 (著)

生物学者・福岡伸一による『動的平衡』シリーズの第三巻
生物学者・福岡伸一による『動的平衡』シリーズの第三巻。「ダイアローグ」のタイトルどおり、今回は対話形式となっています。対話のお相手も、ジャレド・ダイアモンド(進化生物学者)や佐藤勝彦(宇宙物理学者)のような分野の似た人たちから、カズオ・イシグロ(作家)や隈研吾(建築家)、千住博(日本画家)といった全く別の分野の人たちまでバラエティ豊かな顔ぶれとなっています。
シリーズの中で一貫として語られているのは、「生命とは何か」ということ。そして、その中で著者は「生命は『動的な平衡状態にあるシステム』」と定義付けています。生命は、細胞の内でも外でもなく、絶えず新生し古いものと入れ替わっていくという「流れ」の中にある。では、常に入れ替わっているとするならば、変わらない「自己」を形成するものは何なのか。さらに言えばこの世界、ひいては社会の成り立ちに、この「動的平衡」という概念をもって迫ります。
各分野の第一線を行く人々との対話により、「生命とは何か」という問いと答えにより深みが増していき、こちらの世界観すらもかえてしまうほどの説得力を持って読者の心に響いてきます。生物の本なんて難しそう、なんて思わずに、幅広い層の人に読んで欲しい一冊です。
(評者:丸善 丸の内本店 理工書売場担当 山口静香)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
北極男 荻田 泰永 (著)

北極を舞台に活躍している日本人冒険家
今年は植村直己さんの没後30年ということで、関連書が刊行されていますが、現在も北極を舞台に活躍している日本人冒険家がおり、今も北極点に向かって歩を進めています。
今もというのは、正に“今”2014年4月の北極点到達に向けた行程の真っ最中。
その当人、荻田泰永さんが昨年11月に刊行された初の著作が本作『北極男』です。
著者は2000年に初めて北極に行ってから13年間で12回の北極通い。
本書にはその内の1回、友人である角幡唯介さんと共にフランクリン隊の足跡を追った遠征も収められています。この調査遠征は『アグルーカの行方』として角幡さんの著作になったものです。
現在挑戦中の“無補給単独徒歩による北極点到達”はここ10年成功者ゼロ。
成功すれば日本人初、世界で3人目となるチャレンジ。
今年は植村さんを思い、荻田さんを応援し、北極を身近に感じてみては如何でしょう。
(評者:丸善 丸の内本店 実用書担当 半田純一)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
ヤンキー経済 消費の主役・新保守層の正体 (幻冬舎新書) 原田 曜平 (著)

日本国内の消費はマイルドヤンキーに支えられている
日本国内の消費はマイルドヤンキーに支えられている。大ヒット商品の裏には必ず彼らの存在がある。スズキやトヨタ、イオンといった企業はそのことに気がついている。都心で働いていると、彼らの存在を認識する機会はあまりないが、全国的に見ると彼らが、消費の中心にいるということがわかってくる。
マイルドヤンキーというのは、地元が大好きで、地元の仲間とずっと楽しく暮らしていけたらいいと思っているような人たちのことだ。ヤンキーといっても危ない人たちのことではない。態度はマイルドで内向的。小中学校時代の友人と、大人になってもずっとつるんでいることを望んでいるような人たちのことである。
彼らはITへの関心が低く、スキルもない。低学歴で、低収入の場合が多く、休日はイオンに行くのが最高のレジャーだという。上昇志向もなく、地元を出てなにかをするということを望まない。仕事もできることなら地元でしたい。将来は地元に一軒家をもてたらいい。そんな思考を持っている。
都心にいる若者がSNSなど、人との交流にお金を使い、モノを買わなくなっているのに対し、マイルドヤンキーはクルマやショッピングモールでの買い物など、モノの消費が多い。彼らの消費動向は今後どんどん無視できなくなるだろう。むしろ彼らの生態をいまのうちから知っておけば、将来、大ヒット商品を生むヒントになるかもしれない。
(評者:丸善 丸の内本店 ビジネス書担当 田中大輔)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
ウイスキーと私 竹鶴 政孝 (著)

男性へのプレゼントにもおすすめです
ここ数年NHKの朝ドラ人気が高まっています。
出版業界ものその人気に乗り、さまざまな本が出版されました。『あまちゃん』はファンブック、『ごちそうさん』はレシピ、『花子とアン』は『赤毛のアン』関連の書籍が大いに売れたのが記憶に新しいです。
現在放送中の『マッサン』は、ニッカウヰスキーの創業者である竹鶴政孝とその妻リタをモデルとするドラマで、朝ドラ初の外国人ヒロインを掲げていることなどが話題になっています。
今回紹介する『ウイスキーと私』は、日経新聞の『私の履歴書』で竹鶴氏が連載された文章が基となっており、竹鶴氏の生い立ちから、造り酒屋に生まれた氏がいかにして本格ウイスキーの製造を学び、国産本格ウイスキーを作り上げていったかが描かれています。淡々とした文章ですが、その内容はとてもダイナミック。『マッサン』のファンの方はもちろん、成功した企業家の一代記としても楽しめる作品であると感じました。装丁もシックで素敵な本なので、男性へのプレゼントにもおすすめです。
(評者:丸善丸の内本店 実用書担当 望月あゆ美)

書店員:「丸善 丸の内本店」のレビュー
- 丸善
- 丸善|丸の内本店
ルポ・罪と更生 西日本新聞社会部 (著)

この本に出てくる受刑者達と私に大きな違いなどない
2011年秋から約2年間にわたり西日本新聞でキャンペーン企画として「罪と更生」が連載された。本書はその連載をまとめたものに西日本新聞に掲載された関連記事やキーワード集を加えて編集されている。
「刑務所が「姥捨山」のようになっている。」という一行から始まる。犯罪の高齢化について耳にしたことはあるが、深く追求して知ろうとはしなかった。軽犯罪で有罪判決を受け服役後、生活に行き詰まり刑務所に戻る為に再び罪を犯す累犯者は少なくないという。高齢者に限らず、障害者も同様で自立して生きることの難しい人達が何度も刑務所に戻ってきてしまう。
罪を犯すと裁判で刑を確定され、懲役刑は刑務所で刑に服し出所後、社会復帰して自立する。という流れになっているが、自立して生きるのが困難な人はどうすればいいのか。出所後、帰る場所や就職口が見つかるかどうか。社会が受け入れ、支える手がなければ路頭に迷ってしまうだろう。罪を犯した人が更生するには周囲の理解が欠かせない。怖いから、危険だからという先入観で更生施設の開設に住民が反対する地域もある。私も偏見や先入観を持っている。そういう私自身何の力も持たない人間で少しのきっかけで簡単に転落するだろう。この本に出てくる受刑者達と私に大きな違いなどないのだ。
(評者:丸善丸の内本店 和書グループ 伊藤美保子)