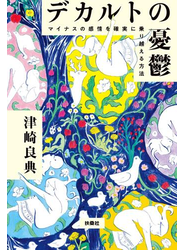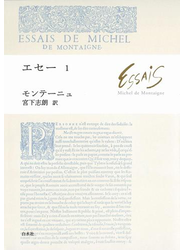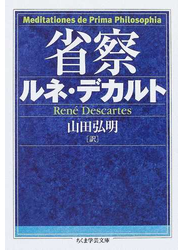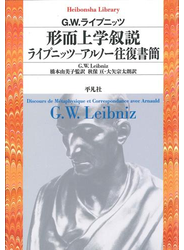ブックキュレーター哲学読書室
ブックキュレーター哲学読書室
哲学書の修辞学のために
ジャンルとスタイル──『広辞苑』によれば「詩・小説・戯曲など文芸作品の様式上の種類・種別」と「文章の様式」のこと。じつは《哲学書》にも多彩な様式がある。人は哲学書を読むとき、何が書かれているかに傾注しがちだ。しかし、それでは片手落ち。どう書かれているかにも注目しよう。【選者:津崎良典(つざき・よしのり:1977-:筑波大学准教授)】
- 116
- お気に入り
- 6801
- 閲覧数
-
デカルトの処女作『方法序説』が一人称で《回顧録》のように書かれていることの意味を考え抜いたうえで、彼も私たちと同じく、学校で学び、青年時代を送り、色々と迷い、悩みながら本人なりに哲学を学び、生活していったという《経験》を読書人と共有すべく、21個の動詞を章立てに用いた著者初の《随筆》のような単著。
-
『枕草子』『方丈記』そして『徒然草』に親しんできた日本の読書人は、時代と言語を異にするも同じ《随筆》というジャンルの『エセー』にも惹かれてきた。モンテーニュの手沢本である通称ボルドー本を底本に幾人かによって全訳されてきたが、ようやくデカルトが読んだ1595年版を日本語で読めるようになった。事件である。
-

省察
ルネ・デカルト(著) , 山田 弘明(訳)
西洋哲学史に燦然と輝く哲学書なのに、《瞑想書》というキリスト教文学のジャンルをいわば換骨奪胎して書かれた六部構成の《独白録》。それだけでも仰天ものだが、本文について有識者たちから寄せられた《反論》に著者が返した《答弁》を付録として合本のうえ刊行するという共著スタイルも哲学書にしては前代未聞のこと。
-
当代きっての神学者・アルノーは、デカルトの『省察』に論文形式の《反論》を送ったが、ライプニッツの主著『形而上学叙説』には《書簡》によって疑問や異論を寄せた。17世紀ヨーロッパの知識人たちは頻繁に手紙のやり取りをして《文芸共和国》を築いた。そのネットワークを鳥瞰することで、哲学者たちの思索を虫瞰したい。
![]()
ブックキュレーター
哲学読書室知の更新へと向かう終わりなき対話のための、人文書編集者と若手研究者の連携による開放アカウント。コーディネーターは小林浩(月曜社取締役)が務めます。アイコンはエティエンヌ・ルイ・ブレ(1728-1799)による有名な「ニュートン記念堂」より。
ブックツリーとは?
ブックツリーは、本に精通したブックキュレーターが独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの"関心・興味"や"気分"に沿って紹介するサービスです。
会員登録を行い、丸善・ジュンク堂・文教堂を含む提携書店やhontoでの購入、ほしい本・Myブックツリーに追加等を行うことで、思いがけない本が次々と提案されます。
Facebook、Twitterから人気・話題のブックツリーをチェックしませんか?
テーマ募集中!
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを募集中です。あなたのリクエスト通りのブックツリーが現れるかも?
テーマ応募フォーム
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを入力してください。
ご応募ありがとうございました。
このテーマにおける、あなたの”6冊目の本”は?
※投稿された内容は、このページの「みんなのコメント」に掲載されます。
コメントを入力するにはログインが必要です