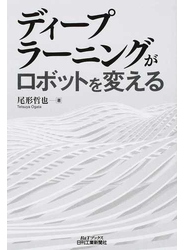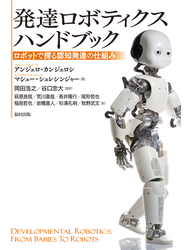ブックキュレーター立命館大学情報理工学部教授 谷口忠大
ブックキュレーター立命館大学情報理工学部教授 谷口忠大
人工知能(AI)/情報/ロボット 知能を創ることでコミュニケーションの理解に近づいていく
コミュニケーションする知能を理解することは、コミュニケーションする知能を生み出すことだ。構成論的アプローチと呼ばれる科学では、創ることによって対象を理解する。僕らはどこまでコミュニケーションする知能を創ることができるのだろうか。
- 14
- お気に入り
- 2736
- 閲覧数
-
記号創発ロボティクスとは、記号創発システムへの構成論的アプローチである。昨今では汎用人工知能と呼ばれるような知能全体を、環境との相互作用を通したロボットの学習により実現しようという挑戦。マルチモーダル概念学習なども詳しく解説されている。
-

ディープラーニングがロボットを変える
尾形 哲也(著)
昨今話題のディープラーニングはニューラルネットワークと呼ばれる機械学習のアプローチ。ニューラルネットワークをロボットに適用し続けてきた、日本の代表的な知能ロボット研究者である尾形教授がディープラーニングの現在と、人工知能とロボットのこれからをわかりやすく語る。現在のロボットの知能を知るのにわかりやすい入門書。
-

オークション理論の基礎 ゲーム理論と情報科学の先端領域
横尾 真(著)
情報技術は人々の意思決定を高度に集約し、人工知能はその集合知を高速にまとめ上げることができるかもしれない。しかし、そこで重要になってくるのが、いかにその人々が参画するシステムの制度を設計するかということだ。メカニズムデザインはゲーム理論を通して人工知能や情報科学と接続される。丁寧な数学的なポイントも含めてゲーム理論や制度設計の導入を与えてくれる一冊。
-

AI時代の「自律性」 未来の礎となる概念を再構築する
河島茂生(編)
ますます複雑化し、ますます自動化されるAIに駆動される人工システム。そんなAIに取り囲まれた時代に私達の「自律性」はどこに向かうのか。AIは生命のような本当の「自律性」を獲得できるのか。AI時代の自律性をネオサイバネティクスの社会学者や哲学者とともに考える。
-

発達ロボティクスハンドブック ロボットで探る認知発達の仕組み
アンジェロ・カンジェロシ(著) , 岩橋 直人(訳) , 杉浦 孔明(訳) , 牧野 武文(訳) , マシュー・シュレシンジャー(著) , 岡田 浩之(監訳) , 谷口 忠大(監訳) , 萩原 良信(訳) , 荒川 直哉(訳) , 長井 隆行(訳) , 尾形 哲也(訳) , 稲邑 哲也(訳)
ロボットや人工知能の研究とは便利な道具をつくるためだけではない。ロボットは人間のモデルだ。人間のモデルを作ることが人間の理解につながるならば、ロボット研究は人間の理解のためのものでもある。特に幼児の発達に着目した発達ロボティクスという学問の全体像を説明した初めての本。
![]()
ブックキュレーター
立命館大学情報理工学部教授 谷口忠大1978年京都府生まれ。立命館大学情報理工学部教授。パナソニック株式会社客員総括主幹技師。「どうして僕らは相手の頭の中をのぞけないのにコミュニケーションできるようになるんだろうか?」「僕たちは分かり合えるんだろうか?」などといった身近な問いから、気づけば人工知能とロボティクス、そして、人間のコミュニケーションへとつながる学際的な研究者になっていた。記号創発システムという概念を提案し、記号創発ロボティクスという研究分野を創出し、人間と人間がコミュニケーションできることの秘密、未来のコミュニケーションロボットの実現へと迫る。世界に広まる書評ゲーム・ビブリオバトルの発案者としても知られる。
ブックツリーとは?
ブックツリーは、本に精通したブックキュレーターが独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの"関心・興味"や"気分"に沿って紹介するサービスです。
会員登録を行い、丸善・ジュンク堂・文教堂を含む提携書店やhontoでの購入、ほしい本・Myブックツリーに追加等を行うことで、思いがけない本が次々と提案されます。
Facebook、Twitterから人気・話題のブックツリーをチェックしませんか?
テーマ募集中!
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを募集中です。あなたのリクエスト通りのブックツリーが現れるかも?
テーマ応募フォーム
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを入力してください。
ご応募ありがとうございました。
このテーマにおける、あなたの”6冊目の本”は?
※投稿された内容は、このページの「みんなのコメント」に掲載されます。
コメントを入力するにはログインが必要です