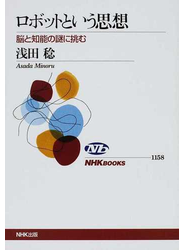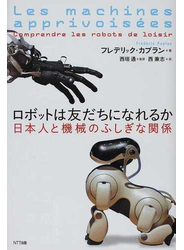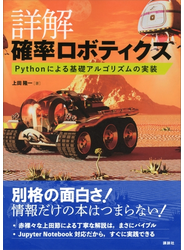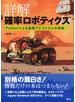ブックキュレーター立命館大学情報理工学部教授 谷口忠大
ブックキュレーター立命館大学情報理工学部教授 谷口忠大
人間の心を理解するために、僕らはAI・ロボットを創る必要があるのか?
「人の心を知りたい!」という疑問は、自分が自分である理由を知りたいという、人間の根源的な欲求です。宇宙の始まりを知ること。生命の誕生を知ること。それらを物理学や生物学が果たしてきたように、人の心の原理を知るのが心理学、認知科学―そして人口知能(AI)とロボティクスなのです。
- 24
- お気に入り
- 3434
- 閲覧数
-

越境する認知科学 5 心を知るための人工知能
日本認知科学会(編) , 谷口 忠大(著)
ブックキュレーター本人の最新刊。2020年の現在、大いに進歩した人工知能やロボティクス技術は、人の心を知るための科学―認知科学のあり方をアップデートしようとしている。20世紀の人工知能研究が考えていた心の像を批判的に考察しつつ、2010年代のディープラーニングによる人工知能の革新、記号創発ロボティクスの研究を紹介する。それを通して、人工知能・ロボットを創ることで、人の心を理解する認知科学の新しい方略を解説する。
-

ロボットという思想 脳と知能の謎に挑む
浅田 稔(著)
本書の著者である浅田稔(大阪大学)を日本の重要人物として発展してきた分野に認知発達ロボティクスがある。それは発達心理学や認知科学とロボティクスの協働を経て、より豊かな人間理解に辿り着こう、また、より発達的なロボットに辿り着こうという研究である。著者が牽引したERATO浅田共生知能システムプロジェクトの成果を踏まえて十年前に書かれた本書は、ロボットを創ることで人を理解するという視点において、未だに多くの示唆を与える。
-

ロボットは友だちになれるか 日本人と機械のふしぎな関係
フレデリック・カプラン(著) , 西垣 通(監修) , 西 兼志(訳)
日本発で世界中のロボティクス業界を席巻したソニーのAIBO。一世を風靡したその自律ロボットの裏側には日本と欧米のロボットに対する認識の違い―文化差があった。フランスの研究者が日本人のロボットに関する受容性、そして欧米でのロボットの捉え方の違いに関して論じた本。これからまた、日本がロボット産業を盛り上げていく上でも、「ロボットへの愛」の視点から、大切なことに気付かせてくれるかもしれない。
-
人工知能の研究は常に哲学と背中合わせにあった。なぜならば、それは心の問題だからだ。今でこそ、人工知能技術は「技術」の視点から語られることが増えたが、「人間の心とは?」という疑問に耳を傾ければ、さまざまな哲学の問題に繋がっていく。様々な哲学のキーワードと、人工知能の接点を紹介したガイドブック。
-
環境を認識して実世界を移動していくロボットは、そもそもどういうふうに作ればよいのだろうか。知能ロボットのための基本的な理論であるSLAMと、それを包含する確率ロボティクスの理論を、簡単なプログラミング言語Pythonを使って実装するという視点から書かれた書籍。ロボットによる世界認識を学べば、それとの対比で人間の世界認識が見えてくる?
![]()
ブックキュレーター
立命館大学情報理工学部教授 谷口忠大1978年京都府生まれ。立命館大学情報理工学部教授。パナソニック株式会社客員総括主幹技師。「どうして僕らは相手の頭の中をのぞけないのにコミュニケーションできるようになるんだろうか?」「僕たちは分かり合えるんだろうか?」などといった身近な問いから、気づけば人工知能とロボティクス、そして、人間のコミュニケーションへとつながる学際的な研究者になっていた。記号創発システムという概念を提案し、記号創発ロボティクスという研究分野を創出し、人間と人間がコミュニケーションできることの秘密、未来のコミュニケーションロボットの実現へと迫る。世界に広まる書評ゲーム・ビブリオバトルの発案者としても知られる。
ブックツリーとは?
ブックツリーは、本に精通したブックキュレーターが独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの"関心・興味"や"気分"に沿って紹介するサービスです。
会員登録を行い、丸善・ジュンク堂・文教堂を含む提携書店やhontoでの購入、ほしい本・Myブックツリーに追加等を行うことで、思いがけない本が次々と提案されます。
Facebook、Twitterから人気・話題のブックツリーをチェックしませんか?
テーマ募集中!
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを募集中です。あなたのリクエスト通りのブックツリーが現れるかも?
テーマ応募フォーム
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを入力してください。
ご応募ありがとうございました。
このテーマにおける、あなたの”6冊目の本”は?
※投稿された内容は、このページの「みんなのコメント」に掲載されます。
コメントを入力するにはログインが必要です