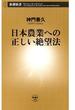技能集約型農業か…
2012/10/08 12:38
2人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ジョニー - この投稿者のレビュー一覧を見る
海外との競争力をつけるため、 大規模化などを進めようとする政策を真っ向否定し、技能集約型農業なるものを提唱している。よく判ります。その通りです。でも、その通りできたら誰も苦労せえへんねん。
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:わびすけ - この投稿者のレビュー一覧を見る
新書を自分の意見の発表の場と考え、読者に押しつけるタイプの著者が多く、そういう新書にあたるとすごく損した気分になる。これがまさにそんな一冊。著者は独善的だし、タイトルからもわかるように「ではどうすれば?」になると急にトーンダウン。読者を想定して書いているのだろうか?この人の本はもういりません。
投稿元:
レビューを見る
著者は、博士(農学)だが、経済学部の先生で、
多少過激な表現が多いが、「本当の農家」には敬意を払っている。
投稿元:
レビューを見る
就農、有機農業、粗放農法など、おそらく都市生活者の中で農業ブームが起きている。自分自身、農業には興味があって(それはたぶんブームにまさに乗せられているのだろう)いろいろ農に関する本を読んでいるのだが、本書はその希望を粉々に打ち砕く内容でもある。日本農業の置かれた状況は予想以上に深刻であり、まさに絶望的であるという。もっとも大きな問題は農業の技能伝承者がいないこと。もうすぐ技能が消えてしまうのだ。少しでも農業に興味がある人は、マスコミが報道する成功話には表れない、ほんとうの問題がまだまだ根深くあることを知る必要がある。まさにその通りなのだが、果たしてどうしたらいいのか...。重苦しい問題提起の書である。
投稿元:
レビューを見る
有機栽培はまやかし、六次産業化は幻想、「奇跡のリンゴ」は欺瞞―。農業ブームを後押しする、これらのキーワードにことごとくノーを突きつける本書。
読む前に、農業がご専門のFB友達から「そういう見方もあるのだという程度にとどめた方がいい」と助言されたこともあり、いつにもまして冷静に読みました。
ただ、世間一般に流布する農業に対するイメージとはあまりにかけ離れていて、何度もある種の興奮を覚えました。
私は農業に関する知識が圧倒的に不足しているので、ここに書かれていることの大半について当否を判断できません。
それでも、首をひねる個所もあれば、なるほどと膝を打つ場面もありました。
膝を打ったのは、たとえば「日本人の舌は愚鈍化している」「マスコミや識者が農業ブームを過剰に演出している」など。ドキリとしました。
有機栽培だから安心、生産者の顔写真が貼ってあるから安心―。本当にそうでしょうか。自分の舌に自信がないから、こういう「能書き」に従順になってしまうのではないか。そんな著者の問題提起は、まっとうなものだと素人ながら感じました。「おいしいと感じるあなたの舌はまともなの?」と言われたら、多少なりともファーストフード文化に浴している私はぐうの音も出ません。
マスコミ等の問題については、こちらは関係者なので反省もしました。たとえば新規参入者であれば手放しで称賛し、その結果、つけあがらせて、当該の新規参入者の人生そのものを狂わせてしまう愚。肝心なのは、しっかりした農業技能を育むこと、その過程であるはずなのに、しばしばそうした本質を無視ないし軽視するのは、たしかに問題だと感じました。
本書を通じて、著者が何度も強調している「日本農業の本来の強みは技能集約型農業」との主張は、私を含め多くの方の賛同を呼ぶのではないでしょうか。
それにしても「技能不足で低品質で環境にも有害な農業が増えるくらいなら、『嵩』は少ない方がまし」とか、かなり辛辣な物言いが散見され、物議を醸すことでしょう。いろんな意味で刺激的な書です。
投稿元:
レビューを見る
自分自身の嗚咽を搾り出すように書いた
と終章にあったように感情や事実を隠すことなく書き出した感じ(故に刺すような文体)
「大半の有機栽培」は土を殺し、かつ味を上げることはなく付加価値をつけるためだけにやっている空虚なもので、そういったことも含めた技能の低下は農作物の栄養価を下げるという記述について
前者は衝撃的、後者は「最近の野菜は野菜の味がしない」という祖母や母の勘違いと見ていたことが事実であることを裏付けた
その他にもマスコミの無能(無思考で数字にしか興味がないかの如き姿勢)、農政の無能やその裏で打算的にうごめく「なんちゃって農家」、「本物の農家」を残すための素人農家(研究や新技術開発と臨床という大学と一般病院の関係)という考えなど、事実を盛り込み過ぎたりして読みにくい部分もあったが、学びもある一冊
投稿元:
レビューを見る
20121011 この本を読んで問題がわかれば良いが。一時的になにを信じれば良いか分からなくなる。答えを出すには自分で探すしか無い。
投稿元:
レビューを見る
12.12/12〜13.1/4
技能の喪失を大きな問題と捉え土地利用に関する問題、消費者の舌が正しい評価を出来ないことについて語ってる
投稿元:
レビューを見る
【お勉強】
神門善久『日本農業への正しい絶望法』
読了
農業ブーム批判は当たっていると思う。企業にいた私自身の実感からも。他の指摘も間違ってはいないのだろう。
......ただ、「絶望」するとすれば、日本農業に、ではなく、都合の悪いことには蓋をして見て見ぬ振りと思考停止をしてしまう人間の愚と不誠実さに、だと思う。
賛否両論ある本をだと思う(あらゆる書籍がそうだろうけど)。でも、農業バブルに浮かれる「識者」や訳もわからず雰囲気にのまれて「意識の高い消費者」になっている人には(自戒も込めて)、農業に対する別の一面を知るという点で、とても有益な本だと思う。
農業に希望を抱くにしろ、絶望するにしろ、「現実」を知ることは大切。
そして「現実」はのぺ~っとした単一な一面じゃぁないし、切り取った部分しか知り得ないし、語り得ないからね。
世界はデジタルではなくアナログ、一色ではなく多色。静物ではなく「動」物。
…というのが今の感想。
明日のゼミでは私には思いもよらぬ話になるだろうね、楽しみです。
投稿元:
レビューを見る
日本農業への正しい絶望法
神門善久
新潮社
日本の農業の実態に詳しい筆者が、なにかにつけて農業農業と騒がれる割には状況が進展しない理由を明らかにした本です。マスコミや識者によって日本の農業について論じられるときの虚構を指摘し、その虚構に落ち込んでしまう罠を明らかにしています。
日本農業への遺言と題された終章から、本書を特徴的に述べている部分を抜粋します。
以下、終章より抜粋。
社会が現実逃避的になって架空の議論に盛り上がるというのは、75年前にまさに日本社会が経験したことだ。
自由なはずの今日の日本においても、不愉快な正論を大衆は抹殺しようとする。マスコミと識者が事実を捻じ曲げた論陣を張ることでそういう大衆に迎合する。本書では、農業という話題を使って、75年前も今も変わらない日本社会の体質を描いた。
抜粋ここまで。
この本との出会いは、別の本を買いに本屋に行った際に、たまたま目に止まったことにはじまります。帯に養老孟司氏のコメントがついていて「ちょっとでも食や農に興味がある人は読んでおいたほうがいい」とありました。
最近、特に強い関心を持っているテーマの1つに「無関心という状態から脱する方法」があります。食や農に高い関心を持っていたわけではありませんが、こうした背景があって「興味がある人は読んでおいたほうがいい」とついているコメントの意味するところが気になり手に取りました。
投稿元:
レビューを見る
この本で言っていることに全く賛同はしないが、こういう問題提起は面白いと思った。
日本農業への筆者の渾身の一撃。終章が「遺言状」という気の入り具合。最初のうちはメディアの欺瞞を暴くようで頭にガンガンきながら筆者の主張を受け容れていたのですが、引用が赤旗や毎日新聞なこともあってああそういう人なのかなと思い始めました。筆者の主張をただ鵜呑みにするのではなく、批判的に読みました。
結局はこの本も農業をしない人が語る農業だということかもしれません。
投稿元:
レビューを見る
農地利用の乱れ,消費者の舌の愚昧化が日本農業衰退の張本人,という著者の主張の繰り返し。
有機農法,農工商連携の取り組みなど美談とりまぜてマスコミが作った「明るい農」のイメージはハリボテにすぎない。本当に日本農業が復活するには,本来の日本の強みである耕作技能を取り戻すしかないが,もはや手遅れか…。という内容。
著者の本何冊か読んだけど,だいぶ尖鋭的な人。自分でも異端認定してるし,なんかもう投げやりな感じ。バカな消費者が踊らされてるというような物言いは,そりゃ煙たがられるし,受け入れられないわなあ。
投稿元:
レビューを見る
農業で重要なのは農作業技能の向上ではないか?農政改革の方向性はおかしくないか?と鋭い問題提起には頷かされる点が多い。しかし、あれはダメ、これもダメと言いっぱなしで、著者の主張は、結局のところ、正しいことを主張する自分が正当に評価されない残念な世の中であるということだけのようだ。自分に酔って書いたとしか思えない。
投稿元:
レビューを見る
日本の農業の現実について書かれている。今までおれが抱いていた日本の農業に対する思い込み、例えば日本の農作物は質がいいだとか農家は生活苦しいとか、そうゆうのが間違ってたと知りました。統計では農家の人は他の同世代より15%も収入がいいらしい。
そして現代の日本の農業の問題点と復活のための方策、例えば技能型集約農業のこととか、計画的な土地の開発とかも書かれている。
あとがきに書いてるんだけど、農業だけでなく満洲を理想郷として宣伝してたことと今の農業に対する宣伝が似ていると指摘してたり、私権の主張ばかりで参加型民主主義が根付いていないことなど、日本の問題に触れてます。
ただこの人は自分の身をめっちゃ心配してるんだけど、そんなにこの世の中って恐ろしいのかな。
投稿元:
レビューを見る
そうなのかもしれないし、そうでないかもしれない。でも、農業に関してのなんだか、しっくりこない部分を明確な立場で、未来や可能性に逃げることなく論じられている印象。農業に起こっていることは「伝統的なもの」が時間の経過の中でたどる過程とよく似ている。