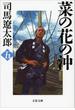ロシアとの対峙からみる現代
2014/02/03 23:15
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:やびー - この投稿者のレビュー一覧を見る
この巻では、高田屋として独立した嘉兵衛が、蝦夷地に生活基盤を置き着実に北方の復興を図りつつ、その成功とは裏腹に、ロシアの強行的な外交政策に裏付けされた圧力が日本を北方より押し迫り、嘉兵衛の未来を不確かな物へと押し流して行きます。
舞台は日本とロシアの外交へとシフトし、初期のような、青春活劇は失われて行きます。人生を謳歌する時期を鮮やかに描きつつ、経営の成長を加味しながらロシアという外圧を、緊張感を保ちつつ躍動感を失わない表現力。
司馬氏の知識に裏付けされた文体は嘉兵衛の成長に伴う慎重な判断を示しつつ、ページをめくるスピードは更に速まります。
嘉兵衛の成熟と躍動感の対比における文脈の衰えを一切見せない所は流石の一言に尽きます。
実際には、この巻で氏の得意とする、「余話として…」に始まるロシアの歴史や民族の成り立ち。思想や観念論まで、司馬氏の考察が巡らされ、ストーリーが中々進まず、読み進めるのが苦しいと感じる読者もいると思います。
現代でも通じると思いますが、イニシアチブを握る上で、或る国との外交や歴史を俯瞰的に比較し互いの国家感を認識しあう際には我が国の内情だけでなく相手国の歴史、文化、思想や哲学。信仰心や国家の欲望を捉えて初めて相手の意図を掴み交渉の糸口を掴む「インテリジェンス」が必要なのでは無いでしょうか?
近世末期の江戸、日本から見るロシアへの評価として、不凍港の確保といった大それた物では無いと思います。
食料や水の提供、薪等のエネルギーの手配など、交易に置ける「交換」を主体に置いた国家のコミュニケーションの確保としての必要性に鈍感な回答を示し得ない行動に対する反作用が今回の事件の真相であったと氏は読み解く。
「それ(反作用?)」はやがて、帝国主義的侵略の一端として遥か遠く日露戦争へと続き、果ては、ノモンハンに辿り着く伏線ではないでしょうか?
司馬史観と巷で言われる、「昭和は魔法の杖でおかしくなり、大日本帝国は侵略国家に変わり果てた末路がかの敗戦であった」と、戦後(現代)知識人は未だにメディアで繰り返す。その事に対する明確な回答を未だ日本人は示せない…。
佐藤優氏は「ロシア事情を司馬作品だけで理解してないけない」と警鐘をならしますが、ロシアを理解する入口にこの作品から入るのも良いのではないでしょうか?
投稿元:
レビューを見る
次巻の6巻で主人公・嘉兵衛がロシアに拉致されることの背景説明の巻。
当時のロシアの国情に関する記述や、ロシアから日本に初めてつかわされた使者レザノフの航海、レザノフ配下による択捉島の日本人集落襲撃のエピソード、これに対して当時の幕府がロシアに対する態度を硬化させロシアからの使者ゴローニンを2年間幽閉した経緯、といった周辺ストーリーを緻密に描写。
投稿元:
レビューを見る
あらすじ(裏表紙より)
ロシアは、その東部の寒冷地帯の運営を円滑にするために、日本に食糧の供給を求めた。が、幕府が交易を拒絶したことから、報復の連鎖反応が始まった。ロシア船が北方の日本の漁場を襲撃すれば、幕府も千島で測量中のロシア海軍少佐を捕縛する。商人にすぎない嘉兵衛の未来にも、両国の軋轢が次第に重くのしかかってくる…。
この巻はほぼ、まるごと嘉兵衛以外のお話です。
お話というより、この時代のロシアについての解説ばかりで、
読んでいて退屈でした
投稿元:
レビューを見る
嘉兵衛に関する記述は少なく、当時のロシア事情や日本への航海、襲撃などについて主に書かれています。前半とイメージが違うのでなかなか読むペースが上がりませんでした。レザノフとクルーゼンシュテルンの航海。幕府の拒絶。カラフト、サハリン。ユノナ号とアヴォス号の日本襲撃。ゴローニンの拘束など。
投稿元:
レビューを見る
この巻では物語の本筋はあまり進まず当時のロシアや日本の時代背景など物語をより楽しむための話が続いた。話が進まないため、じれったくはあったがこれはこれでありだと思った。ゴローウニンの『日本幽囚記』をものすごく読みたくなった。
投稿元:
レビューを見る
「司馬遼太郎」の歴史小説は全部読もうと考え、ブックオフで見つけて一度に購入。あらすじを読んで自分の好きな戦国、幕末ではなく、江戸後期の話であったので、ずっと積読のままであった。
しかし、読んでみて、非常に面白かった。というより、日本にこんな人物がいたのかと知ると日本に生まれてよかったと思えた。主人公の「高田屋嘉兵衛」の人としての偉大さには勇気を与えられたし、その商人哲学には強く感銘を受けた。
ストーリーとしては中盤から終盤の内容もいいが、自分としては序盤から中盤までの商人として主人公が活躍し始めるまでの展開が好きだ。この本を読んで物語の舞台である灘近辺、北方領土にも興味を持てた。
投稿元:
レビューを見る
5巻では、嘉兵衛の話を離れ、当時のロシア事情や間宮林蔵について紙面を割いている。脱線と思いきや、6巻で嘉兵衛がロシアに行くことになる背景に繋がってくるのだが。
ピョートル大帝がロシアの近代化の開祖であるが、当時、その近代化を進めたのは北欧やドイツ系の人だったりする。
エカテリーナ2世もドイツ人だ。
また、コサック、農奴などロシアの特殊性に関しての考え方は「坂の上の雲」にも繋がっている。
ロシアだけなく、欧州の近代国家について興味深い考察が散りばめられている。
『ポーランドはロシアと同じくスラブ人であるが、宗教は(ロシア正教でなく)ローマ・カトリックを国教としている。
欧州や中近東における宗教は、東アジアにおけるそれのように希薄なものではない。
「人も普遍的な思想(宗教)によって飼いならせることがなければ野獣に近く、人になりえない」という説明不要の考え方が、アーリア人やセム・ハム語族にあった。』
投稿元:
レビューを見る
この巻は、長大な前フリだと思います。高田屋嘉兵衛が全然出てこない。最後のほうに、少し出てきたと思ったら、 嘉兵衛が大きな歴史の渦に巻き込まれそうな予感を残し終了。といってしまうと簡単ですが、これから本格的に絡んでくるロシアという大国の( 嘉兵衛と同時期の )歴史的背景が緻密に描かれており、この伏線がどのように最終巻で絡んでくるのか楽しみです。
投稿元:
レビューを見る
結構時間がかかってしまった。
途中筆を殴りこむかのように、永遠とロシアの説明がはいる。
もうそれがめまいのするように情報量が多い。
少し、坂の上の雲を思い出した。
まったく終わる気配はないが、ついに最終巻へ。
投稿元:
レビューを見る
この巻は、ほぼ司馬遼太郎さんのロシアに関する歴史語りである。高田屋嘉兵衛があまりでてこず、当時の嘉兵衛の商売や暮らしの様子が分からず、物足りない。次巻に繋がる伏線と期待しよう。
投稿元:
レビューを見る
日本人にはロシアが南下し、国土を奪い取られるのではないかという恐怖が根強くある。この5巻で詳しく当時の状況がかかれている。樺太ではロシアの理由なき住民虐殺が起こる。そんな中、日本人の恐怖とは裏腹に国交を開きたいと国書持参のロシア大使が来航する。当然追い返すことになるのだが、数年後にはロシア情勢収集のため、卑怯な手を労してロシア人を牢獄につなぐなど日本は過激さをます。どうも、ロシアとの間には勘違い外交でお互いの思案の食い違いがあるらしい。正確に言葉が理解できない当時とは違い現在なら、この難局を乗り越えられるのだろうか。4,5巻は嘉兵衛の活躍より、時代背景を詳しく描写する。
投稿元:
レビューを見る
今回はロシアの事情が主で、物語はあまり先には進みません。皇帝の治める国って日本と違い特殊なんだなーって思いました。
投稿元:
レビューを見る
幕末の蝦夷地(北海道)とロシアの関係が細かく説明された1冊。
つまり、淡路出身の船乗りさんで、一代で莫大な資産を築き、今の函館の街の発展に寄与した高田屋嘉兵衛さんの物語としては、ぜんぜん進んでいません(笑)
この後、嘉兵衛さんはロシア船に捕まっちゃう予定なので(歴史は変わらないもんね!)その前提として、当時の日本とロシアの関係を説明してるんだろうな。
でも、とてもお勉強になったよ!
投稿元:
レビューを見る
読んだきっかけ:古本屋で50円で買った。
かかった時間:8/19-9/23(34日くらい)
あらすじ: ロシアは、その東部の寒冷地帯の運営を円滑にするために、日本に食料の供給を求めた。が、幕府が交易を拒絶したことから、報復の連鎖反応が始まった。ロシア船が北方の日本の漁場を襲撃すれば、幕府も千島で測量中のロシア海軍少佐を捕縛する。商人にすぎない嘉兵衛の未来にも、両国の軋轢が次第に重くのしかかってくる……。(裏表紙より)
感想:
投稿元:
レビューを見る
ほぼ一冊全て、当時のロシア事情に費やされている。
対応する日本の状況、嘉兵衛の状況・年齢は記載されているものの、4巻までの「高田屋嘉兵衛物語」とはまったく異なっている。
この巻を単独で読んでも、ほぼ問題はないであろう。
おそらくはこの先に起こる出来事をロシアの立場、鎖国可の日本の立場から理解させようという配慮からこの量を費やしたのであろうが、長かった。