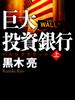大学3年生の必読書
2020/09/08 06:47
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コアラ - この投稿者のレビュー一覧を見る
投資銀行の業務が詳しく書かれている。「トップ・レフト」は出世作であり,まだまだ邦銀(著者の元職場)に対するわだかまりが垣間見られたが,本書では外資の投資銀行勤務者の生活が淡々と描かれている。そして元一流金融マン(だったのだと思う)らしくスワップなどむずかしい金融商品の説明が詳しい。金融の勉強のためにも業界に興味のある学生は読むとよい。就職してからこんなはずではなかったではすまないからだ。評者は,「やっぱ給料に惹かれて銀行に就職しなくてよかった」と思った。邦銀の理不尽,外銀の激務に較べたら評者が勤めていたなんちゃら総研なんて天国だった。
バブルが弾けたときのいきさつも詳しくて興味深い。ソロモンブラザーズがなんかやっととはきいていたが,裁定取引だったのか,ということで納得。10年くらい前まで裁定取引を主流にするファンドはとても成績がよかった。邦銀とかは理解していなかったからなのかと納得。それも今では価格差がなくなり成績が振るわない。投資先がなくて困りますね。とにかく,金融業に興味のある学生は,金融工学のむずかしい本に取り組む前に読むべし。
投稿元:
レビューを見る
読了。投資銀行の内情がよく分かる1冊。上巻は桂木が投資銀行に入ってから、苦労しながらディールをまわし成長していく過程。1980年あたりからの投資銀行およびそれを取り巻く経済環境がかなり精緻に描かれている。[2008/11/5]
投稿元:
レビューを見る
黒木亮作品はやっぱり面白い!
主人公の桂木が都銀から米国投資銀行に転職し、
最先端の金融と緊張感の中でもがきながらも
成長し成果を残していく。
男として、金融マンとして、あこがれる生き方。
自分も銀行員となったからには、彼のように
「自分のやりたいことは何か」「どう生きたいのか」
と問い続け、形のない金融というものを
自分の色にアレンジをしていきたいと思う。
新年の大切さを教えられる。
そんなかっこいい銀行マンの物語、の上巻。
投稿元:
レビューを見る
入社まであとわずかということで読んでみました。
80年代からの投資銀行を舞台にした経済小説。
IB,マーケット双方の業務が描かれているため、仕事のイメージを湧かせてくれる。
小説とはいえ、日系証券がいかに出遅れていたか・・・
上では日本がバブル崩壊まで。
投稿元:
レビューを見る
以前真山氏の作品を読んで、ビジネス小説って面白いな。と感じたので、
その他の小説で、良さそうなものがないかamazonで探したら、なかなか良い評価を
得ているので、読んでみた。
小説なので、内容をまとめて書く無粋真似はしないが、読み終わった感想としては、
かなり面白かったと言える。どの点が良かったか、それは、
1.投資銀行が行っている業務や仕事内容がありありと描かれている。
2.ある程度史実に関連づけて、リアリティが高まっている。
3.微妙に主人公が何人かいるという事。
以前映画で流行っていたマルチストーリーとまではいかないが、数人のトレーダーの
人生が重なりはせずとも描かれていて、主人公の桂木以外の竜神や藤崎という人物の
生き方や人となりに惹かれた。
しかし、投資企業の現場はこれほどまでに凄まじいものなのだろうか。
まぁ、下巻最後の辺りではクオンツという人種が増えてきて、体育会系や賭場士的な
人は減ったと描かれているので、現状はそんな感じなのか。。。
ただし、一番下っ端の激務は・・・事実だと思う。これは投資銀行だけでなく、
コンサル系もそうだろう。
また、小説内には頭の切れる人物が何人か登場し、その性格と頭の良さが描かれているが、
その凄さを見習いたいと思う。というか、見習えるというレベルのものか?という疑問が
あるが、勝手に目指すだけだし、問題はないだろう(笑)
最後に、主人公の桂木は大きな決断をするが、その心境になるには多くの事が成し遂げられ
ての事であったりする。自分も将来は、そのような決断が出来る程、心身共に成長して
いきたい。
投稿元:
レビューを見る
好きな作家の1人である黒木亮の作品。
70年代に邦銀から米国投資銀行に転職した1人の男に焦点を当て、投資銀行業界の変遷を描いた名作。
投稿元:
レビューを見る
1985年、日本の銀行に勤めていた桂木は、護送船団方式に守られたニッポン型金融に嫌気がさし、外資系の巨大投資銀行モルガン・スペンサーへ転職する。そこは、高度な投資技術を要求される代償に莫大な収入が与えられる業界だ。
そんな世界に身を置き、揉まれながらもコツコツと足場を固め、様々な案件を解決して、成長する日本人桂木。一方で、桂木と対照的な日本人として登場するソルト竜神。モルガンのライバル社ソロモンブラザーズのカリスマトレーダーだ。儲け最優先で、弱肉強食の世界を謳歌する。
そんな架空の登場人物たちに実際の歴史を体験させる経済大河小説。
桂木が転職後に起こった主な出来事は、ブラックマンデー、日経平均4万円目前、M&Aブーム、バブル崩壊、9.11テロ・・・。さすがにサブプライムローンのことは新しすぎて本作品ではカバーできず。
高度な金融用語が散りばめられ、実在の金融マンたちが匿名で登場する大長編。あまりの情報量で読むのに躊躇するが、理解できないところはとばして読み進めるべき。それでも充分、85年以降の金融・投資業界のダイナミズムを堪能できる。
この本を読むと、80〜90年代、外資系金融機関が世界を圧倒していたのは、複雑な金融商品を高額な手数料で、日本をはじめとする無知な金融機関に売りつけていたからだと分かる。それらの商品は多くのオプションを付けまくり、市場がどちらへ転ぼうとも売り手である外資が損をしないものだった。
そんな外資のしたたかさは狩猟民族ならでは。農耕民族である日本人は最近になってようやく対抗できるようになった。それは、主人公桂木のように外資で得た知識を母国へ還元しようとする愛国者によるものだ。
投稿元:
レビューを見る
用語集がついてるのはありがたいね。
最初の頃は難しくて読むの大変だったけど、だんだん面白くなってきた!
投稿元:
レビューを見る
まだ下巻読んでないけど、上巻だけのレビュー。
1980年代から2000年ぐらいまでの投資銀行の変遷がわかります。特にソロモン、ドレクセルあたりの繁栄・衰退のストーリーは「天才たちの誤算」を読んでるとかなり面白く読めると思います。
実態はどうかわからないけど、転職ストーリーやらレイオフやらもうすぐ身近に感じることがあるのかなと思いながら読んでました。
そして、結局歴史は繰り返されるということですね!!
下巻は改めてレビューします。
投稿元:
レビューを見る
黒木亮の金融小説第?段。
上下巻あるうちの上巻を読んだ雑感として、読み始めたらとんとんと進んでしまう。
上巻で特に面白かったのは、第7章。
こんな風雲児いないとは思いますが…
ただ、内容が専門用語満載で、細部までは小生も理解に及ばず悔しい思いをしています。
もうちょっと金融のこと勉強しなきゃ〜
投稿元:
レビューを見る
100年以来最大の危機の今読んでも面白いです。
バブル崩壊から最近の事柄を何人かの金融マンを通じて展開してゆく。
話は面白いです。
金融の知識がなくても丁寧に書かれており、読みやすく
読み応えもありました。
主人公の桂木の誠実な姿が読んでいても気持ちいいです。
<あまぞんより>
米投資銀行とは何か。巨額の利益を吸い上げる“金融工場”の舞台裏では何が起きているのか――。バブル経済崩壊から今日に至るまでに、米・日金融戦争の最前線で繰り広げられた攻防を描いた経済小説。国際金融マンから作家に転身したという著者ならではの取材力で、ストーリーには実在する組織や史実が巧みに織り込まれている。
主人公は、米投資銀行での出世競争を勝ち抜きながらも、ついには祖国に戻り邦銀再生に立つ桂木英一。竜神宗一は、裁定取引(アービトラージ)で巨額の利ざやを稼ぐ伝説のディーラーだ。史実と重なる企業買収劇や経済事件の顛末はもちろん、事実報道のみではうかがい知れないであろう、当事者たちの心の内をも描き出していく。
2008/12/1
投稿元:
レビューを見る
素晴らしい作品である。司馬が偉大なる歴史小説家であるように、本著者は偉大なる経済史小説家だと言える。
本書は桂木英一という名の主人公が自らの仕事をこなしていく中で近代経済、金融史に切り込んでいく小説である。小説なので当然フィクションなのだが、所々に実在の人物の名前や登場し、フィクションとは言いつつも実際の企業や金融経済史に照らし合わせたかのようなストーリーが展開する。行ってみればここ20年の近代経済史を小説として振り返るのであれば最適な本であるだろう。
資本主義という枠組みの中で個性豊かな登場人物達が織りなす物語は上下巻合わせたボリュームも忘れさせてくれる。現在の実際世界において、資本主義は金融危機を発端に崩壊の序曲を迎えているのかもしれない。本書に登場する若手インベストメントバンカーの「右から左へカネを流し、ディールをやって、シャンパンで乾杯して、そこには何も残らない」といった台詞がとても印象的であり、現在の状況を顕しているかのようだ。
投稿元:
レビューを見る
2009年5月15日に読み終わった本
http://hydrocul.seesaa.net/article/119776521.html
投稿元:
レビューを見る
金融関係の小説。面白い。デリバティブとか、ゴールドマン、とかマニアックな言葉が出てくるから、そういう言葉に抵抗がなければぜひおすすめです。
投稿元:
レビューを見る
【上下巻同一レビュー・ネタばれ含】
トップレフトとどう違うのか?と問われれば、うーん、と悩んでしまうだろう。。この小説でためになったのは、変わりつつあった外資投資銀行の姿がありのままに描かれていたこととかかなぁ。
あと、読んでいて、ナイポールの「自由の国で」を思い出させるようなタッチだと感じた。というのも、彼の帰る場所が邦銀であったこと(また、上巻の中盤か下巻の最初の方にあった、モルガン・スペンサーに勤める事への恩師の無念がる様子、そして最後の邦銀CEO就任時の恩師の祝電がそれを裏付ける。)また、外銀を渡り歩く中での降格・解雇・取引の失敗やかつての古巣の邦銀の元同僚・上司からの陰口などが、「自由の国で」で主人公が受ける暴行に似ている。著者自体、英国在住だし。パッチワーク的な部分も多いし。まぁ、とてつもなく可能性の低い推論だが。