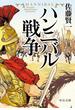絶体絶命のローマを救ったスキピオの戦術とは
2023/01/29 11:18
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:タラ子 - この投稿者のレビュー一覧を見る
紀元前3世紀の長年のローマとカルタゴの戦いを描いた物語。復讐に燃えるハンニバル率いるカルタゴ軍に若き貴公子スキピオが挑む。
この物語を読むと、敵であれどもあっぱれ!と思うところは素直に認め、そこから学ぶことの重要性が分かる。
また戦といえども憎しみにまかせ、相手を完膚無きまで打ち負かすことは得策ではないと感じた。
カンナエの戦いでは7万ものローマ兵が殺戮され、一時ローマの人口は戦前の半分になったとさえ言われていた。戦で身内を失わなかった人の方が稀で、そんな状況では人々の心に憎悪の炎が灯り、許さないと思うのは当たり前だ。
戦争では必ずこの様に憎しみが生まれる。ハンニバルの過去もそうであったが、この物語を読み、ハンニバルやスキピオの人生をすべて知った読者は、ハンニバルが選ばなかった復讐に生きない人生の方がスキピオにとってはもちろん、ハンニバルにとっても幸せだったと思うのではないだろうか。
とても面白く、あっという間に読んだが、最後のスキピオの場面が印象的で、戦の虚しさが心に残った物語だった。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:6EQUJ5 - この投稿者のレビュー一覧を見る
カルタゴの名将ハンニバルを、ローマ帝国のスキピオの視点から語る一冊。ハンニバルの戦略と猛威感じつつ、古代の歴史に思いをはせる、楽しい一冊でした。
オススメです。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:渡り鳥 - この投稿者のレビュー一覧を見る
第二次ポエニ戦争の話。ローマとカルタゴの戦いをローマのスキピオ側から描く。東では劉邦が項羽を破って漢を興した頃、西ではポエニ戦争が終結し、以後、大ローマ帝国が隆盛を誇っていく事になる。面白い事に東西で同時期に大帝国ができる事になる。第一次ポエニ戦争は、ローマの圧勝に終わるが、第二次ポエニ戦争時はカルタゴに英雄が現れる。源義経と同じで判官びいきもあり、カルタゴのハンニバルの人気は高く、ハンニバル側からのポエム戦争の書物が多いが、この本はローマ視線で。奇想天外の発想でローマ軍を翻弄するハンニバル。スペインからローマの誰もは想定していない冬のアルプスを越えてローマ目指すハンニバルに驚くカルタゴ軍。しかも象を戦闘要員として活用したり、騎兵で翻弄させたりで、ローマ軍を圧倒する。いわゆるカンナエの戦い。自らも参戦した若きスキピオは、実父や義父や叔父をカルタゴ軍に殺され、心底、カルタゴのハンニバルを恐れる。この大きな敗戦でスキピオは考える。ハンニバルを徹底して研究し,来るべきハンニバルとの戦いに備える。 この本の構成の面白い所は、スキピオは実像を持って描写するが、ハンニバルは、一度、スキピオと二人で面談する場面以外は一切、実像描写はなく、本人は本に登場しない。東野圭吾の『白夜行』と言う小説を思い出す。一組の少年少女がお互いを尊敬しあい、認め合い、少年が少女をサポートしていき、色々な犯罪に手を染めていくようなある種のラブスト-リーのような推理小説。読んいくとどう考えても二人は親密な中であり、成長していく過程で人生を共にしているが、小説には一切、二人が遭遇する場面を東野圭吾は設定していない。読者の頭の中で、そう言う風に持って行くような構成に。この『このハンニバル戦争』もハンニバルの実像は1ケ所を除いて出てこないが、スキピオの気持ちの中やローマ人たちの恐れを通じて、ハンニバルの強さが伝わってくる。
投稿元:
レビューを見る
時は紀元前三世紀。広大な版図を誇ったローマ帝国の歴史の中で、史上最大の敵とされた男がいた。古代地中海を舞台とした壮大な物語が、今、幕を開ける!
投稿元:
レビューを見る
戦記物には、人を惹きつけるものがある。
人が殺される残虐さはわかっていても、三国志やSFだと銀英伝とかに心躍らされる。
特に非凡な才を感じさせる軍略の話は、やっぱり楽しい。
ハンニバルと聞くと、あの大国ローマを脅かした天才的な将軍というイメージが浮かぶ。
冒頭は、まだ若いスキピオの目からハンニバルが語られる。
切れ者ってわけではないけど、育ちのよさからくる彼の素直さのおかげで、物語がとても近いものに感じられる。
巻末の解説によると、あの項羽と劉邦と近い時代なのだとか。
項羽と劉邦は、王同士の対決だけど、ハンニバルとスキピオは将同士の対決。その後の運命を考えると、項羽や劉邦よりも韓信に近いのか。
和平交渉という形で二人が語り合うシーン、その後の最後の戦、そして、彼らの晩年、同じ年に世を去ったこと・・・やはり、そこが心に残る。
投稿元:
レビューを見る
500頁超の大作であるが、1章ずつが寝床で読むにはちょうどいい分量で、毎晩楽しみに読んだ。
カルタゴのハンニバルが、どれほど大きな脅威をローマ帝国に与えていたかということも、よくわかった。
投稿元:
レビューを見る
ずっと前から読もうと思いながらも積んだままになっていた本。
『(第二次)ポエニ戦争』とせずに『ハンニバル戦争』としているところがポイント。ローマがカルタゴを抑え込んだ凄さではなく、ローマを長く苦しめたハンニバルの脅威を強調して描いている。ホントにもうしつこいくらいに。
物語の視点はスキピオの方。ハンニバルとの直接対決が最後の方で、しかも序盤は敗けが続くのでなかなか盛り上がらない。その辺りは仕方のない部分ではあるけれど。
ともあれ歴史物は面白い。他のも読みます。
投稿元:
レビューを見る
久々に時間を忘れて1日で読了。
凡夫だからこそ学べる、謙虚に勉強するしかないのだ。潔く余人の模倣に励めるからだ。ならば凡夫に徹しよう。偉大なる凡夫になろう。なるたけ多くを学びこの身いっぱいに先人たちの知恵を蓄えるのである。
指揮官が優れた作戦を考えれば兵士は楽ができる。
与えられた屈辱に耐えながら我らカルタゴ人は再び剣をとるまで19年もの間、苦しまなければならなかった。だから同じだけの苦しみを味合わせる。
結局のところこの世では凡夫が勝つ。選ばれた人間のひらめきとは無縁ながら、生きる力、あるいは生きようとする意志の力、その浅ましいばかりの意欲に溢れているから。凡夫として勝に執着し、最後まであきらめなかったこと。凡夫たちのよ。
投稿元:
レビューを見る
読んだ本 ハンニバル戦争 佐藤賢一 20230802
2020年に長期勤続の休暇と旅行券がもらえるってことで、パリに行こうと計画してました。気分を盛り上げるために、佐藤健一著の「フランス革命」を読み継いでたんですが、コロナでそれどころじゃない上に、「フランス革命」があんまり凄惨で。次々と登場人物がギロチンにかかっていく。読み終わる頃には、ちょっと気持ち悪くなってきて、パリに行きたくなくなってました。歴史というものに向き合うって意味では本当に面白かったんですけど。それ以来、いくつか佐藤健一の本を読んでたんですが、ナポレオンが発刊されてて、文庫化を楽しみにしてたんですが、やっと出たと思ったらめちゃくちゃ分厚いのが3冊。気軽に読み始めれない。もっと分けてよと思いつつ、あれ、「ハンニバル戦争」だと思って、買ってみました。なんか、フランス=佐藤健一、イタリア=塩野七生みたいな住み分けを個人的に持ってたんですが。
内容としては、結局スキピオの話なんですが、ローマ最大の危機と言われるハンニバルの来襲に対して、史実を交えてスキピオがいかにハンニバル=カルタゴを破ったかを描いてるんですが、史実を追うだけでなく、スキピオの成長していくさまが丁寧に描かれています。前半結構長々と、ハンニバルに蹂躙されるスキピオが書き込まれ、そこからある戦術の完成形をスキピオが追い求めるっていう結構わかりやすさもあって、おもしろかったです。スキピオの悲しい晩年が少ししか描かれてなかったのが、ちょっと残念でしたが。スキピオ像がなんとなく固まった気がします。
投稿元:
レビューを見る
ヨーロッパの歴史を題材にした小説を発表している、佐藤賢一。
長いこと、この作家さんの作品から遠ざかっていたのですが、その間に、魅力的な作品の数々を発表していることを知りました。
「久しぶりに、佐藤賢一の作品世界に触れてみよう」と思い立ち、文庫化されている作品の中から、特に時代が古いと思われるこの作品を、読んでみることにしました。
時は紀元前219年。
名門貴族の家に生まれたスキピオが17歳のシーンから、物語が始まります。
スキピオは同名で共和政ローマの最高職、執政官である父親から、出征を命じられます。
戦争の相手は、地中海を挟んでローマと対峙する、カルタゴ。
20年以上続いた戦争(第一次ポエニ戦争)で、ローマが勝利した相手ですが、19年の時を経て再び、大国となったローマに挑んできます。
そのカルタゴを率いるのが、ハンニバル。
戦地に赴いたスキピオは、ローマ軍が容易に勝てる相手と考えていたカルタゴ軍に、圧倒されてしまいます。
どこを目指して行軍しているのかも、どのような戦術でローマ軍と戦うのかもわからない、カルタゴ軍。
ハンニバル率いるカルタゴ軍の不気味さと、若きスキピオの苦戦が、描かれていきます。
自らを「凡夫」と定義するスキピオが、「天才」ハンニバルにどのように、立ち向かっていくのか。
その展開を読むのが、本書の楽しみ方だと思います。
ポエニ戦争については、ずいぶん前に読んだ『ローマ人の物語』で、おおよその流れを知っていました。
その記憶を辿りながら読んだのですが、スキピオという個人の視点で描かれていることもあり、ポエニ戦争での戦闘の過酷さ、ハンニバルという武将の怖さを、いっしょに体験するような感覚を、味わわせてもらいました。
作品の舞台は、紀元前のヨーロッパとアフリカ。
登場人物たちの名前も、多くの日本人読者には馴染みのないものが多いと思います。
そんな「遠い世界」の話ですが、スキピオをはじめとする登場人物に個性を持たせ、現代日本人が話しているような言葉で会話が進むので、理解に困ることなくすんなり、読み通すことができました。
久しぶりに読んだ佐藤賢一作品は、やっぱり面白く、読み応えがありました。
他にも未読の作品があるので、文庫化されているものを探して、読んでいきたいと思います。
.
投稿元:
レビューを見る
紀元前三世紀、地中海世界の覇権を賭けて敵対した古代ローマ帝国と北アフリカのカルタゴ。 そのカルタゴの稀代の知将ハンニバルが、ローマによるコルシカとサルディニア略奪の積年の怨念を晴らすため、アルプス山脈を超えローマに迫った!ローマの名家出身の若きスキピオは、敗走を続ける祖国ローマの存亡を賭けてハンニバルとの決戦に挑む、壮大無双な歴史小説。〝もはや戦争は地中海全域で行われ、いよいよ世界大戦の風を呈してきた。東西南北の全方位で戦わなければならなくなった。男という男が出払ったのも、全部で25軍団が動員されていたからだ。それなのに、ひとつ防衛線が崩れるや、直ちに双方向から挟み撃たれる危険と、常に背中合わせなのだ...ハンニバルには勝てない。仮に負けないでいられても、勝てない。それは今も変わりない。勝てない限り、いつまた、どのように切り返され、再びカンナエの目に遭わされないとも限らない。やはり勝つための方法を考えなければならない...スキピオは震撼した。閃きが訪れた。 「ハンニバルだ!」 兵法でも戦史でもない、最高の手本がハンニバルだ。ハンニバルに勝つには、ハンニバルに学ぶことだ!…〟
投稿元:
レビューを見る
第二次ポエニ戦争をスキピオ視点で描いた「ハンニバル戦争」。
終始、スキピオ視点で物語は進みます。ハンニバルを人物として描写されるのはザマの戦い直前。
その会談の中で、生の感情に触れたスキピオが感じた人間としてのハンニバル。それまでは戦術の天才として、軍神とまで思っていた彼が一人の人間であると知る瞬間。この変化を描くために、ハンニバルを描かずにいたのかな、と思いました。
ローマに勝利し続けるハンニバル。イタリアでの敗戦の描写。ハンニバルを学ぶことで勝利を収めてゆくスキピオ。
ザマへ至るまでの全ての描写が、ハンニバルの圧倒的な強さをローマやスキピオだけでなく、読者にも刻み込ませるものであって、とにかく彼の存在を大きく強く高く見せつけるものでした。
人間が到底達することのできない存在あるかに思えたハンニバル。会談で彼も人であると気づけなければ、勝利はなかったでのはなかろうか。そう思ってしまうほど、ハンニバルという存在の大きさを感じます。
スキピオ視点の物語であるのに、読後に残っているのはハンニバルの凄みという。
直接描かないことで、英雄を神格化に持ってゆくという形でしょうか。
漫画『ドリフターズ』でのスキピオの台詞に「ローマは100万の軍勢は恐れないが、こいつただ一人を恐れた」というものがありましたが、それも納得の存在感。
また、スキピオ視点の戦場の混乱描写がいいのです。混乱、狼狽、焦燥、絶望、とさまざまなものが次々に襲いかかってくる。緊迫感が強い。
ハンニバルとスキピオという不世出の英雄二人。ともに国家の英雄として活躍するも、政争には敗れ不遇な後半生を過ごしたというのは、何かの皮肉なのかなと思います。歴史を彩るのは天才や英雄であっても作るのは凡人であって、行き過ぎた絢爛豪華さは、忌避され排除されてしまうものなのか。
同年に亡くなったというのも、歴史の舞台から退場させられたのだ、と思ってしまいますね。
神であるかのようなハンニバルに対抗するために、研鑽を積み神に近づこうとしたスキピオ。凡人ではなくなった存在は、人の世に居場所は無くなってしまったということでしょうか。
情緒がすぎるかな。