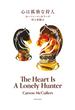村上氏の翻訳が読みやすい
2022/01/09 22:57
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ふみちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
この出口の見えてこない重苦しい作品を書き上げた時、作者はまだ、なんと20歳代前半だった。南部で生まれ育った、人生が変わることを夢見る女の子というのは、3年前に読んだ、「結婚式のメンバー」と同じだが、この息苦しささえ感じる作品は、さらに6年も前に書かれた作品だ。(作者自身は、貧困世帯で育ったミックと違って裕福な家庭で育ったようだが)、アメリカ南部での凄まじい黒人差別、貧困が描かれていて、主人公の一人、ビフはどうやら「少女=ミック」に欲望を感じるという性癖に悩んでいるようだし(ミックが大人の女への成長していく過程でそうやら、その性欲はおさまりつつあるようだが)、ブラントは共産主義者、アナーキストとして資本主義に立ち向かおうとしている、1930年代後半のアメリカ南部の闇はとことん深かったようだ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ichikawan - この投稿者のレビュー一覧を見る
多様な人物を繊細に描いたもので、マッカラーズがわずか23歳で本作を書いたというのに舌を巻く。また旧訳を読んだ時はそうは感じなかったのだが、改めて村上春樹訳で読むと、村上は確かにマッカラーズからも多く受け取っているのだということもわかる。
投稿元:
レビューを見る
本当に長い物語だった。だが、実際に読み終わってみると長いという気がしないから不思議である。
主人公シンガーとその周りにいる人々の物語で、それぞれが悩みややり場のない思いを抱えており、色々と試行錯誤するのだが、決して解決されることがなくて読んでいて切なくなった。彼らが幸せになってくれたらいいなあと思う。
しかし聾唖の男性シンガーに惹かれて一方的に話しかける人々がいるが、シンガーは話の内容をきちんと理解できていたのだろうか?
アントナプーロスの何がシンガーをあそこまで惹きつけたのだろうか?
しかしシンガーに対して周りの人々は何かしてあげることができたと思うし、シンガーに過剰に期待しすぎのような気もする。
もちろん本には書かれていない隠れている部分もあるのだろうが…。
著者が23歳でこの本を書いたというのは驚きである。写真を見たが、とても美人だ。
著者の他の作品もいつか読んでみたい。
投稿元:
レビューを見る
起伏の激しさは感じなかったが、淡々とした文章の中に、彼らの孤独とそれに抗おうとする心が見える。
寧ろ、淡々とした文章だからこそ、それが際立つのかも知れない。
ある少女が出てくるのだが、彼女には幸せになって欲しいと思う…。
中心である聾唖者が取り乱すシーン…あそこはそれまでの彼らのことを思うと、読んでいて辛かった。
今まで村上春樹作品を読んできた上で、これを手に取ったのだが…本編と訳者あとがきを読んで、これをとっておきにしていた理由が分かった気がした。
作者がこれを23歳で書いたと言うのだから、驚きである…。
投稿元:
レビューを見る
アントナプーロスはシンガーに友情を感じていたのか?言い換えると、他者にそうあって欲しい人物像を仮託させる孤独な狩人は、シンガーにも当てはまるのかどうか。初読では結論が出ず。
投稿元:
レビューを見る
あの町の住人たちの寂しさや悲しさが蔓延している世界は、今も変わらない。現代も同じだ。読後、やるせない思いがしばらく心の片隅にひっそりと居残っている。また再読したい作品。
投稿元:
レビューを見る
自分の大事に思ってきた物語が、ムラカミハルキと同じとはビックリ。そしてうんと久しぶりに読んだらば、何をそんなに後生大事に思ってきたんだったか、思い出せないことが一抹の寂しさなり。いや、そこそこ素敵で、重みのある物語ではあったけど、十代の初読後の咽び泣いた感動からは、残念ながらうんと遠くへ来てしまったみたいだ。そういう意味ではずっと気持ちを暖め続けたムラカミハルキが羨ましいし、自ら翻訳出版にまでこぎつけたことは素晴らしいと素直に思える。
投稿元:
レビューを見る
ほんと、辛かった。。
登場人物みんなとっても個性的で愛すべく人たちなんだけど、
みんなあまりにも悲しくて。
南部の、黒人たちの貧しさと、そんな人たちを雇って暮らす、また貧しい白人たち。。
聾唖の男、
人が好きなのか、孤独なカフェの店主。
アナーキストのよそ者、
人種差別に抵抗しようとする老いた黒人医師…
何度も胸が裂けるような悲しさと悔しさを感じながら、なんとか最後まで読みました。
カーソン・マッカラーズのデビュー作、なんと23歳で書き上げている。
まさにこの中に、出てくる素敵な、夢見がちな女の子ミッキーは、マッカラーズ自信を投影しているのかなと、思った。
ミッキーが、夜になるとラジオのある家の窓の下に立って音楽を聴く、ベートーヴェン交響曲第3楽章に心揺さぶられるシーンがとっても素敵だったのだけど。。彼女には幸せになってもらいたい。。
投稿元:
レビューを見る
アメリカ南部(ジョ-ジア州)の田舎町。世界大恐慌後の不安な世相、戦争の噂、貧困、黒人差別が渦巻く社会の片隅で、日々の生活に悶々としながら生きる人々の孤独と焦燥感が痛々しい。レストラン・バ—「ニュ-ヨ-ク・カフェ」に集う登場人物それぞれの苦悩が、出口の見当たらない夜の闇の中で蠢く。〝 私は聾唖者ですが 唇の動きを読んで 言われたことを理解します どうか大声を出したりしないでください 〟不幸を分かち合う聾唖の男(ジョン・シンガ-)に、つよく心を揺さぶられる。(1968年米映画「愛すれど心さびしく」の原作)
投稿元:
レビューを見る
1967年に亡くなったアメリカの女性作家、カーソン・マッカラーズの代表作。サリンジャーやフィッツジェラルドなど愛する作品を楽しみながら翻訳してきた村上春樹が「最後のとっておき」として翻訳されているが、確かに『キャッチャー・イン・ザ・ライ』や『グレート・ギャッツビー』に匹敵するくらい胸を打つ素晴らしい物語であった。
舞台は1930年代末のアメリカ南部のある小さな町。そこで静かに暮らす一人の聾唖男性に対して、4人の悩める人間は彼を頼って、ひたすら自身の悩みを語り続ける。
ー家族との関係性に悩む白人少女
ー共産主義的なアナーキズムを持って社会の変革を夢見る白人男性
ー黒人の地位向上を目指すも周囲には自身の思想が理解されないことに悩む老齢の黒人医師
ーロリコン趣味を隠しつつもその性癖に悩む白人のパブ経営者
聾唖男性は静かに彼らの唇の動きを読みつつ、彼らの悩みに聞こえない耳を傾けることで彼らを間接的に救っている。しかし、その奇妙な交流はある暴力によって急に打ち切られ、悩む4人は救いから放り出されることになる。
4人の人物造形はいずれも非常にユニークであり極めてリアルに想像することができるが、特に白人少女は”少女版ホールデン(キャッチャー・イン・ザ・ライ)”とも言うべき魅力に溢れている。
非常に不思議な物語でありながらも、聾唖男性の静かな振る舞いに心が揺さぶられる傑作。
投稿元:
レビューを見る
貧困と孤独に乾いた風が吹く町。黒人と白人の諍いは絶えず、大きな志も空虚なだけ。今日一日を生きるのに精一杯な人々、そこに佇む物言わぬ啞の静謐な視線。
悲劇は絶えずやってくるけれど、誰の人生も静かに続いていくのは、それが彼らへの、作家が託した贈りものだったんだろう。
誰もに人生があって、秘めた思いがあって、誰かに聞いて欲しくて共有したくて、その欲求はこの小説の中にいる人々に限らず現代を生きている私たちの誰にもあるはずで、人は須く孤独であり、それでも誰かと繋がっていたいと願う生き物であることを、良い小説はどれだけの歳月を経てもその普遍性を示す。
村上春樹の解説を読むまでこの作家が女性であるとは思わず、それも20代の女性の作品であることにとても驚く。感情の揺らぎに流されない落ち着いた筆致。それでいて、困難ばかりの彼らへの、深く優しい眼差し。
人生はただ生きること。それだけで貴いこと。 人は須く貴いこと。
投稿元:
レビューを見る
1930年代の南部,まだまだ黒人たちや貧しい人たちの行き場のない生活が,酒場の主人や黒人の医者,下宿屋の女の子,そして聾唖者などの語りを通して語られる.ささやかな希望が,ちょっとした楽しみが少しずつ削られるように失われていく,そんな毎日の繰り返しの中に神のような救いを一人の聾唖の白人に見つける人逹の思いが哀しい.たくさんのエピソードが散りばめられていて短編集の宝庫のような,人生の縮図のような物語.
投稿元:
レビューを見る
黒人問題。貧困。格差。差別と怒りと傷み。
80年も前に書かれた小説なのに全く同じことでアメリカは、というか、人は悩み続けているのだなあ、と。
自らの鬱屈した感情を丸ごと受け止めてほしい、認めて欲しい。批判や批評はいらない。でもそんな人はいないから啞のシンガーさんにみんなみずからのこうであってほしい他者を勝手に投影して自己満足に浸ることで孤独を癒すしかないやるせなさ。
けど、シンガーさんだって、それはおんなじで。
みんな自分のことはさておいて、周囲になんでも求めすぎだよ、まったくもう。て思いながらも、一方でその気持ちがリアルに、痛いほど「わかってしまう」わけで。
あああ、なんだか切ないなぁ。
せめてミックの最後のオーケー、は希望であってほしい。
投稿元:
レビューを見る
村上さんの作品と村上さんのお気に入りの作品はあたりまえのことながら全く違うもので、村上さんの作品は好きでも村上さんのお気に入りの作品は好きだと思わなかったのは、決しておかしいことではないと思います。
日々続く辛い日常とその出口のなさへの苛立ちが延々と描かれます。どこにも救いにない本当にしんどい作品でした。
資本論を読むのが大学生の一般教養だと思っていた若い頃に岩波の油紙の文庫を買って、つっかえつっかえ読んだことを思い出しました。剰余価値という言葉が出てきたことだけを覚えています。
投稿元:
レビューを見る
途中で挫折。
訳が村上春樹でもだめだった。
背の高い知性を感じさせる男性と太っていて食べることに興味が尽きない精神薄弱な対照的なふたりの聾唖者。
長編だし、話しは重く、淡々と続いていく感じ。
春樹氏があとがきで述べてたように、この小説が今の時代の若い人にどれだけうけいれられるかを危惧してたように、
(若くはないけど)ちょっと私には時期尚早だったのかな。
でも敬愛する春樹氏がそんなにも絶賛する小説なら、時期が熟したらまたチャレンジしてみようかな。