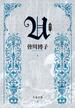0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:とめ - この投稿者のレビュー一覧を見る
オスマン帝国からUボートへの時間移動というSF的な要素。無限のような時の中で、不本意ながら軍人にさせられた男たちの不思議譚。巻末の往復書簡も興味深く拝読できる。
枯淡とは無縁の作者
2021/06/08 10:22
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Koukun - この投稿者のレビュー一覧を見る
作者皆川博子らしい「Untergrund」地下と「Unterseeboot」潜水艦を組み合わせた構成にしたかなり作りに凝った作品である。ただ頻繁に変わる視点 語り手 独白に、どちらかと言えば煩わしさを感じてしまった。これだけ優れた文章力 文体の魅力を持った作家なのだからここまで構成にこだわらなくても十分に読みごたえのある作品になったと思う。90歳を超えてもおよそ枯淡とは無縁の作者である。
投稿元:
レビューを見る
第一次大戦中、イギリスに軍に拿捕されたUボートを他のUボートが救出に向かったが失敗した…このエピソードと、オスマン帝国を繋げる世界観に圧倒されました。
デウシルメ、薄っすらとしか覚えてなかったですが、そうかそれで「これは私の戦争じゃない」。3人組でひとりだけ王宮に送り込まれたヤーノシュが、力を持てばシュテファンとミハイを護れるとメキメキと頭角表すのが哀しいです。
塩鉱…そんなことって。。同じ境遇になったヤーノシュとシュテファンだけれど、ふたりの生き方は決定的に分かたれたまま何百年も、というのも哀しかったです。ひとりは図書館に閉じこもり、もうひとりは外界に出て他人の戸籍を買いながら愛する人の子孫を護り続ける。
最期にうっ…となっていたけれど、皆川さんからはその後も容赦ないものをぶつけてこられるので心が散り散りになって終わりました。435頁の末文から436頁いっぱいまで冷静にドイツのその後が描かれます。描写が簡潔な分、かえって悲惨さが立ち昇ってくるようでした。
過不足ない…とつくづく毎回思います。皆川博子さんの頭の中どうなっているんだろう。往復書簡、お三方とも好きな作家さんだったので楽しく読みました。皆さん、皆川さんファンだけど作家さんの視点もちゃんと持たれてて。『アンダーグラウンド』も、フリオ・リャマサーレス「黄色い雨」も面白かった…「u」より前にどちらも接していたのでなんとなく嬉しい。皆川さんは本も読まれるし映画も観られるしでパワフルだなぁ…90歳超えでミステリもバリバリお書きになる。無理しないでいただきたいけど作品は読みたいので健康でいてほしいです。。
投稿元:
レビューを見る
【“幻想小説の女王”が紡ぎだす、時空を超えた長編大作】第一次世界大戦中の独軍と一七世紀初頭のオスマン帝国。時代に翻弄された三人の少年たちが時空を超えて巡り合う数奇な人生とは――。
投稿元:
レビューを見る
「U」と書いて「ウー」と読ませるが、萩尾望都「ポーの一族」からの遠いこだまとも見做せる。
1915年「U-Boot」(ウーボート)の章は、三人称。視点が寄り添う人物は、ティルピッツと、ミヒャエル。
1613年「Untergrund」(ウンターグルンド)の章は、初めは三人称と見せておいて、すぐに手記という形式……一人称が潜んでいると判明する。
また、手記は実は二人の合作であること、二つの時代の関係、書き手の熱意の不均衡、が比較的序盤で仄見えてくるが、この不均衡が中盤終盤でさらに揺らぐ。
この「語りの形式」そのものがドラマチックだから、やはり皆川博子は信用できる。
ある瞬間には「同じ獣の半身になった」と思える相手が、いったん離れるや全然別の生を……という諦念と切望と。
歴史の暴流の中で、動かず書く者と、動く者と。
現在時点と、過去と、大過去と。
歴史は歴史書の中ではちっともドラマチックではないが、その記述にドラマを幻視する作家がいる。
そしてこの作家が偶然、書き残すという人の欲望に自覚的で、現在時点、誰がどういう想いで書いているのかを曖昧にしたくない、という人なのだ。
いつどこでだれが何のために書いているのか、を明らかにしている手記は、信用できる。
信頼できない語り手であるにしても、作家のまなざしとして、信用できる。
300年をつなぐのに、岩塩鉱を置く。
「塩漬けの首級」という印象的な画や、「塩の内側に潜る」(地底、海底)→搾取された生と死が充満する棺、という、時代をゆうに超えた舞台を用意するのだから、信用できる。
というか、遠くへ、遠くへと連れて行ってくれる作者のその手腕に、ずっとこの身を任せていたい。
こんな壮大さの中に、抒情や耽美や切なさがばしばし籠められているのだから、美味しくないわけがない。
萩尾望都だけでない、SFにはまた「長命人」と「人」のギャップによる抒情があったはず。
歴史浪漫かつSFとしての皆川博子……次はこの路線で読み返してみたい。
大満足の溜め息。
本書とは全然関係ないが、つい先日「宮崎駿の雑想ノート」でQシップのことを知ったので、いろいろ関連するものだなあ、と。
投稿元:
レビューを見る
塩によって生かされて、最後は海水の中に沈む。潜水艇がふたりの棺となる。好き。
ヤーノシュがオスマンの皇帝を守り支えたなら、彼は何かをなしとげられたのか。そういう展開にならないのがいいところなんですが…ヤーノシュの自己評価ちょっと低すぎるのでは…
「双頭のバビロン」のふたりほどの絆が感じられなかったのも、ヤーノシュの自己評価のせいか。シュテファンはあんまり深く考えていなさそうな…
シュテファンがどう思っていたのか、途中から記述がなくなるから分からないけれど。
彼らの軌跡が文字として残ったのかは定かではないけれど、ミヒャエルたちの中に何かしらが受け継がれているのだろうなあ。
投稿元:
レビューを見る
第一次大戦下のドイツ。敵方の捕虜になった男の身元を確認するため、ひとりの図書館職員が潜水艇Uボートに乗せられた。彼と捕虜の男は数奇な運命に翻弄され、長い長い時を共にした〈半身〉だった。17世紀のオスマン帝国と20世紀ドイツ、両国の興亡を二重写しにして語られる長命者たちの物語。
読み終えた瞬間の感想をまとめると「何百年と生き続けても好きな人に好きだと伝えられなかった男の話」。シュテファンがそういう男だったとヤーノシュは断じるが、そのヤーノシュも内なる思いを秘めたまま何世紀もの時をやり過ごす。それでも好きな人と死ねてよかったね、と思っているところに非情なエピローグがやってくる。波音と深海の闇だけが残るラストは、皆川先生らしいさすがの斬れ味。
連綿と子をなすミハイの系譜に対し、レイプに対する自省から生殖を忌避するシュテファンと機能自体を強制的に奪われてしまったヤーノシュがいる。吸血鬼ものと異なり、この物語における長命者が性的能力を持たないという描写はないが、二人は性本能を嫌悪する気持ちによって結びつき、また遠ざかってゆく。
巻末の往復書簡で皆川先生はエドワード・ラザフォード『ロンドン』を挙げ、〈定点観測〉が初めのテーマだったと言っているが、もしかして最初は語り手をシュテファンに固定するつもりだったのではないだろうか。オスマン帝国では後宮に、ドイツでは図書館にこもるヤーノシュより、外の世界で暮らし、時代の移り変わりを見てきたシュテファン視点のほうが長命者の設定を生かした語りになったはずだ。ヤーノシュは彼自身が変わることのない〈活字の本〉だ。しかし、だからこそ彼には書かねばならない理由があったとも言える。ヤーノシュは〈本〉であり生殖能力を断たれた〈黄金の細い管〉であり、肉体を腐蝕から守る〈塩〉でもある。
正直、私には最後まで乗り切れないところもある作品で、オスマン帝国とUボート作戦との繋がりに特別な必然性は見出せなかった。ただ、何百年と死に場所を探してきた男たちが〈塩〉にもらった命を塩水=海に返すという終わりぎわの展開が美しく、またこの物語のあとにドイツがおこなう大量殺戮を予感させるラスト一文の余韻はさすがとしか言いようがない。
皆川先生は何度もドイツを舞台に戦争を描いてきたが、ここまで深い無力感を湛えた主人公に第一次大戦を代表させたことは、作品年表のなかでも重い意味を持つのではないだろうか。
投稿元:
レビューを見る
初見の作家を装丁買い。一切悔いなし。
以前に短編集『影を買う店』をちらっと読んだときに、幻想小説かぁ…ちょっと違うかもなぁ…って思ってたけど、いや全然そんなことない
同じように短編読んで離れそうになった人はぜひ長編の皆川博子をこそ読んでほしい
ドイツの潜水艦Uボートと、underground(地下)の2つのUを巡って、少年たちが「時代」や「歴史」や「戦争」…どうしようもない世界の何かに翻弄され、時を超えなお生き続けてゆくお話
彼らの身のうちに湧き、淀み、沈んでは迸る感情は強烈で、しかも彼らはそれを互いに(一部は一方通行に)何世紀もの間行き来させるのだけれど、その姿を描き切ってしまう丹念なほどの執念深さ。背すじ凍る
それを経てエピローグまで読んだときの虚脱感にも似たあの感情。
たぶん他ではそうそう味わえない、初読1回きりのそれなので、ぜひネタバレ無しのまま読み切ってほしい
投稿元:
レビューを見る
300年の時を越え、空間も超えて紡がれる二人の物語。オスマントルコ、第一次世界大戦これらをつないでいる数々の史実とそれに関わる二人。二つの物語を書いて、ぐるぐるっと混ぜて、一つにつないだ感じがして、なんとなくすわりが悪い感じがした。最終章もなんとなくとってつけた感があって、物語と今一つ有機的につながっている感じを受けなかった。読みが浅いかしら。。。