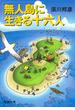- 予約購入について
-
- 「予約購入する」をクリックすると予約が完了します。
- ご予約いただいた商品は発売日にダウンロード可能となります。
- ご購入金額は、発売日にお客様のクレジットカードにご請求されます。
- 商品の発売日は変更となる可能性がございますので、予めご了承ください。
読書感想文にどうですか?日本にもあった『明らめ』て生きる男たちの物語。
2003/08/13 09:02
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:南亭骨怠 - この投稿者のレビュー一覧を見る
帯には「飲み水も食べ物もないちっちゃな島で君ならどうする?」「椎名誠氏が選ぶ漂流記ベスト20で堂々1位」とある。まず気になるのが『椎名誠氏が選ぶ漂流記ベスト20』だな。私が読んだ漂流記は,『ロビンソン漂流記』と『十五少年漂流記』。『ペリーヌ物語』というアニメの原作が『スイスのロビンソン』だったと思う。
次に読んでみたいのは『エンデュアランス号・シャクルトン』の漂流記だな。最近TVで取り上げられることが多いノンフィクションだ。
本題に入ります。
『無人島に生きる十六人』は,明治31年に太平洋上で座礁した龍睡丸の乗組員の物語だ。たどり着いた先の島が小さなさんご礁で,草は生えているものの木は一本も生えていない。これでは物語になりようがない。ところが,みんな何とか生きていくのだ。しかも,十年くらいはここで生活をして救助を待つ覚悟ができている。
悲壮感がない。無人島の生活を楽しんでいるとしか思えない。何気なく生活していたんじゃこうはいかない。無人島で生活していくことは簡単なことじゃない。遭難して無人島に流れ着いた者は少なくないようだ。ただ,その多くは絶望感から生きる気力をなくしていってしまったようだ。
この十六人は,やるべきことを考えて,どんどん行動していく。それは「アポロ13」に出てくる男たちのようだ。やるべきこと,やってもしょうがないことを明らかにして生きていく『明らめる』男たちの物語だ。
この十六人も,絶望感に襲われる可能性はあった。しかし,船長や小笠原老人などの気配りで気持ちをまとめていった。
最初に四つの決まりを作っている。
一つ,島で手に入るもので,くらしていくこと。
二つ,できない相談をいわないこと。
三つ,規則正しい生活をすること。
四つ,愉快な生活を心がけること。
何年も島で生き延びていくために,できるだけ船から持ち込んだものは使わないほうがいい。無理な希望を言ってもむなしくなるだけだ。島の生活を愉快に楽しむのがいい。そして,規則正しい生活こそが生きる希望を失わないための重要なものだったのだ。
十六人の生活は,見張りやぐらの当番,炊事,たきぎ集め,まきわり,魚とり,亀の牧場当番,塩製造,宿舎掃除整頓,万年灯などの仕事を交代で行っていた。暇にしているのが一番いけないのだ。
生活が順調に流れるようになると,学科の時間も設けている。一度学ぶ意欲が出てくれば,無人島での生活は学ぶ要素がたくさん詰まっている。学ぶ意欲はとても大きな生きる力になっているのだ。
そもそも,今にも船が沈もうとしているときに船長が出した指示の中に,「練習生と会員は,島にあがって,何年か無人島生活をして,ただ無事に帰っただけでは,日本国に対してめんもくがあるまい。かねてお前たちが望んでいた勉強をみっちりしなくてはならない。できるだけの書物を集めて,運び出すようにしろ」というものもあった。
まずは生きること,そして衣食住の確保が次に来ると思うのだが,この船長は衣食住学だった。生きる希望と学ぶ意欲を失わない,日本の海の男というのはとてつもなくすごい男達なのだ。
すてきな日本人がいますよ
2004/08/21 04:53
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Gchan - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイトルのまま、これは漂流の話だ。表紙をめくると島の地図がカラフルに描いてあって「十五少年漂流記」のような感じなのだろうかと思ったのだが、しかしこちらは実話だ。
場所がサンゴ礁というので私は勝手にグレートバリアリーフみたいなところを想像してしまって、確かに綺麗で一度行ってみたいと思うけれども、あのただなかにぽっかり島が浮かんでいて、周囲見渡す限り他の島影が見えないのだとしたら……。
変な言い方だが実にうまく繋がっていく話の運びに、初めはさすがに作り話だろうと思った。だが巻末の椎名誠さんの解説をみると記録が残っているらしい。
登場人物の中の16人は、他の漂流物にはあまり見られない日本人的な規律(漂流物は海外のものが多いので)に従ってしっかりと、海洋調査の目的を持って意気揚々と出かけていって、意気揚々と無人島に漂流し、結局最後まで意気揚々としている。暗くならない。本書の文章が最初に世にでたのは昭和23年だそうだが「ああ、おまえらって日本人!」と思ってしまう個所がいくつかあるあたり、とても新鮮だ。とはいえ逆に、私を含めた現在の日本人が果たして同じようにいられるだろうかと寂しく思ったりもする。
文章は読みやすく淡々としているが、ただ無人島というだけでない迫力を感じるのは、この話が実話に基づいていること、それから恩師の体験談を文章に起こした本書の作者もまた、海のプロだからだ。海底の状況に錨を翻弄されるさまなど実感が伴っている。多少脚色してあると考えてそれを差し引いても、世の中には想像もつかない経験をする人がいるものだ。
きっと誰も知らない冒険譚が、まだまだ沢山あるのだろうな。プロジェクトXのオープニング歌詞のままに。
世界は広いんだ。なぜか地球儀が欲しくなった。
生き延びる姿に感激。裸族、主食は海亀。遊び心は希望の源。
2003/11/18 23:46
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:3307 - この投稿者のレビュー一覧を見る
太平洋の真ん中で難破した16人を抱き留めてくれた、
無人島「本部島」の鳥瞰図を眺めるだけでも、
本書を手に取る価値はある。
地図は、見慣れた新潮文庫の扉の前に、おまけの
ポストカードのように添付されている。
「ウミガメの牧場」「土俵」「見張りやぐら」
「あざらし半島」「上陸記念井戸」
そんな言葉がちりばめられた、夢のある地図。
実際には、5年・10年待っても迎えは来ないかもしれない
絶海の孤島に、明治男16人が放り出されているのだから
「夢がある」なんて言っては失礼。
これは、過酷なサバイバルストーリー。
でも、水を確保し、カツオの刺身や
ウミガメのステーキを食べ、細かな珊瑚の砂に
包まれて眠るリズムに慣れると、「愉快」に生きるために
探求心を育てる「自然塾」に様変わりする。
珊瑚の森の花畑を見下ろし、熱帯魚の生態を観察し、
海鳥の子育てを眺め、あざらしの群と友達になる。
ギリギリの場所にいるからこそ、夢もある。
極限を生き延びた、キーワードは遊び心。
楽しくなければ駄目なんだ、笑わなければ続かない。
タフで知的な、海の男たちに万歳三唱の一冊。
「堂々たる日本版『十六人おじさん漂流記』の面白さであった。」と解説で椎名誠さん!
2015/05/20 10:37
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:佐々木 なおこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
(●^o^●)友だちからこんな本知ってる?面白いよ!とススメられて手にとった一冊。
こういう友だちからの紹介本はほんとうにうれしい。読むとほぼ大好き本になって、
次からは私が会う人会う人に「いい本あるよ~あのね~」と言うことになる。
こちら実話。明治三十一年の話です。太平洋上で帆船が遭難し、ある無人島に乗組員十六人全員が上陸した。
そこで男ばかりの十六人がどんな暮らしをしていたのか、それがつぶさに語られます。
ちょっと書き抜いてみますね。
「島でむかえる最初の朝、五月二十一日となった。」
お、まさにこの五月ではないですか!
「『島生活は、きょうからはじまるのだ。
はじめがいちばんたいせつだから、しっかり約束しておきたい。
一つ、島で手にはいるもので、くらして行く。
二つ、できない相談をいわないこと。
三つ、規則正しい生活をすること。
四つ、愉快な生活を心がけること。
さしあたって、この四つを、かたくまもろう』。
一同は、こころよくうなずいた。」
この船長の約束ごとを乗組員たちは堅く守り、
身体的にも精神的にも辛いことがたくさんあるだろう無人島生活を、助け合いながら、時には愉快に生きていったのです。
それぞれにはこの無人島で生きるための役割分担があり、それは食料の調達であったり、住まいの確保であったり…。
年長者が若い乗組員たちを励まし、若い乗組員たちも年長者を敬う。こういう日本人がいたのだな、素晴らしいなと感動することしきりでした。
水夫長の言葉も響きました。
「生きていれば、いつかきっと、この無人島から助けられるのだと、わかい人たちが気を落とさないように、どんなつらい、苦しいことがあっても、
将来を楽しみに、毎日気もちよくくらすように、私が先にたって、うでとからだのつづくかぎり、やるつもりです」
無人島生活にも少し慣れて余裕が出てくると、船長による勉強会があったり、あざらしと遊んだりすることも。
必要なものを作り出していく、たとえば海水から塩を作ったり、インキが欲しいと船長が言えば、万年灯にたまった油煙を集めて米を煮たかゆとまぜてインキのようなものを作ったり…。
「ひたいをあつめてそうだんした。」まさに生きる力をまざまざと見せてもらったようで、そのたびにすごいなと思いました。
表紙のイラストは暮らしていた無人島です。見張り櫓やカメ牧場、あざらしがいる様子も分かりますね。
巻末は椎名誠さんの熱い気持ちのほとばしる解説が。
彼は「まさに『十五少年漂流記』の向こうをはって堂々たる日本版『十六人おじさん漂流記』の面白さであった。」と最大級の絶賛でした。
ついに出た
2003/07/03 18:59
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:かずくん - この投稿者のレビュー一覧を見る
小学生の頃、母に買い与えられた某社の子供向け文庫集の中にこの本はあった。
海の厳しさ、やさしさ、人間の強さなどいろいろなものを教えられた。
成人してからダイバーになりたいと思ったのはこの本のせいだと思う。
そして、子供向けでないきちんとしたものを読みたいと探し続けて30数年、ついに手に入ることとなった。
現代人こそ必読の日本版ロビンソンクルーソーである。
これが本当に漂流記?
2003/07/01 00:14
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ヒロクマ - この投稿者のレビュー一覧を見る
自分にとって漂流記のベスト1はアルフレッド・ランシングの「エンデュアランス号漂流」だった。ところが日本にも、これに勝るとも劣らない漂流記があった!
それが今回紹介する「無人島に生きる十六人」だ。
原著は昭和23年刊。この本の存在は椎名誠氏が絶賛することによって知ってはいたが、如何せん昔の本すぎて手に入れられず、幻の1冊だった。それが今回、新潮文庫から復刊されたので、これは読まずにいられない。
読み始めたらあまりの面白さにやめられず、1日で読み切ってしまった。
明治31年、16人の乗組員を乗せた龍睡丸は、南太平洋での漁業調査のために航海に出た。ところが大しけに遭遇し、航行に大きな支障をきたす。それでも何とかハワイ島までたどりつき、現地の日系人を始めとした島民の援助により、船を修理できた。
新たな気持ちで航海に出たのもつかの間、今度はハワイ諸島上の暗礁に乗り上げ座礁。16人は何とか船から必要な物資を運び出し、近くの島へと避難する。
しかしそこは定期航路からはずれた無人島。いつ船が近くを通るか検討もつかない。また島にはわずかな植物が茂っているだけで、とうていこのままでは暮らせそうもない。果たして16人の運命はどうなるのか?
普通ならここで、どうやってこの島から脱出し、人の住む島まで行くか、ということを考えそうだが、彼らは違った。船長のもと、この島で生活し、いつになるか分からないが、助けが来ること信じ生きてゆこうと決意するのである。そのために4つの約束を交わす。
1.島で手にはいるもので、くらして行く。
2.できない相談をいわないこと。
3.規律正しい生活をすること。
4.愉快な生活を心がけること。
この約束に従い、16人はいつも前向きに、楽しく生きていく。
通りかかった船を発見するための櫓を作ったり、亀の牧場を作ったり、若い船員たちには先輩たちが海での知識や体験談を聞かせ勉強をしたりと、まるで一人前の海の男になるための合宿所のような毎日を過ごしていく。
島に棲むアザラシたちと友達になったり、流木がいっぱいの「宝島」を見つけてお喜びしたりと、微笑ましいエピソードがいっぱいで、これが本当に漂流記?という気になってくる。
南の島、という場所柄もあるのだろうが、彼らの生活に暗さはみじんもない。いつかは必ず日本に帰れる。そのときのために、海の男として恥ずかしくない毎日を過ごそう、という強い意志にあふれている。
南極と南太平洋、という気象条件の大きな違いはあるが、「エンデュアランス号漂流」と共通しているのは、とにかく毎日を愉快に過ごそう、という仲間たちの姿勢だ。極限状態で生き残るためにもっとも必要なものは、知識でも技術でもない。必ず生きて帰れる、と信じて希望を持ち続けることだ。そしてそのために仲間を信頼することだ。
昔の日本人は偉かったんだなあ、と思うと同時に、海の男たちに対するあこがれを一層強くする、必読のノンフィクションだ。
強い組織のリーダーとは
2021/11/30 23:52
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くにさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
船が遭難して無人島に流れ着いたあげく、何年かして別の船に拾われて
全員無事生還したという冒険小説である。
但し、単なる冒険小説には止まらない。
ピンチに陥ったとき、どのように組織を引っ張て行くか。
部下が支持するリーダーとは?
有名な人の書いたビジネス書よりずっと為になった。
ぜひとも映画化してほしい
2003/09/13 01:31
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:べあとりーちぇ - この投稿者のレビュー一覧を見る
すでに先輩諸氏が高評価を並べておいでなので、今さら蛇足だとか、屋上屋を架すとかいうことは重々判っている。判っているがそれでもなお読後の幸福感を書きたくなってしまう本というのも間違いなく存在し、本書はまさにそういう一冊である。
千島列島最先端の占守島(しゅむしゅじま)と内地との連絡船である龍睡丸。船にはまったく詳しくないが、76トンで二本マスト、総乗組員16名というと当時でもかなり小さな部類に入るのだろう。その小さな小さな帆船が、冬場の臨時業務のために南方の調査へでかけて遭難し、乗組員は命からがら無人島へ漂着。食べ物も火種も、水さえもほとんどない絶望的な状態にもかかわらず、16人の男たちは船長を始めとするヴェテランたちを中心によくまとまって、規律正しく紳士的に、決してへこたれずに5か月もの遭難生活を切り抜けた。誰一人欠けることなく…。
読み終えて、しみじみと裏表紙側の帯を眺めてしまった。明治32年の新聞記事。龍睡丸の乗組員が帰国した、という内容である。こういう記事が実在するということはやっぱりノンフィクションなのだろうな。でも、解説の椎名誠氏もおっしゃる通り、はいそうですかとすぐには信じられないくらい、本書はエンターテインメント小説としてもパーフェクトである。
トラブルで始まった航海。30いくつの墓標があるという無人島と「まさか自分たちも」という予感めいた会話。暗礁と遭難と決死の脱出。4つの誓い。井戸ほり、海鳥たち、海がめの牧場、草ぶどう。宝島、あざらし半島、レクリエーションと勉強の時間。救援メッセージの浮き輪と鳥の郵便屋さん。熊の胆に「鼻じろ」危機一髪。とうとう助けの的矢丸が現われるタイミングにいたるまで、まさにできすぎと言っていいくらいの完璧さ。これで面白くない訳がない。
陽気で前向きな海の男たちの暮らし振りをおいても、見どころはまだまだある。絶海の孤島から眺める朝焼けや夕焼け。真っ青な空にもくもく湧き上がる入道雲はいろいろな形に姿を変え、ぽつんと見えた黒い点はみるみる広がって命の雨を降らせる。満天の星ぼしと「龍宮城の花園」。小笠原老人の昔話。赤ちゃんあざらし…。
ページをめくりながら、後から後から美しい情景が目の前に浮かぶようだった。実際にあのような景色を目の当たりにするチャンスはとても持てないだろうから、それならせめて、誰か映画化してくれないだろうかとしみじみ思う。筆者の貧相な想像力では追いつかないような美しいシーン満載の、素晴らしい海洋冒険映画ができあがること請け合いだと思うのだが。
老練な船長や水夫長や運転士役を、緒形拳さんとか菅原文太さんとか高倉健さんとか、ああいうタイプの俳優さんに演じてもらえたらどんなに格好いいだろう(ちょっとお年が行き過ぎているだろうか)。そんな妄想に浸ってしまうような、男のロマンにあふれた一冊。絶対の自信をもってお勧めする。
一気に読みきりました
2022/03/20 20:30
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:タモさんと高田純次さんがイイです - この投稿者のレビュー一覧を見る
yahooニュースなのか何なのか、どなたかの書評を読んで興味を持って買いました。立ち読みではなく、買ってしまって大正解。実話は興味をひきますね。どこまで史実か疑問を持ったらキリがありませんが、読み物として一気に読みきりました。
生命力
2012/07/08 11:58
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:panda - この投稿者のレビュー一覧を見る
言い回しは古いし前半ははっきり言ってつまらないと思った。でも読み進める内に、無い所から作り出す16人の生命力と言うか生存力に驚かされる。お金を出せば何でも買えてしまう今だからこそ読んで欲しい一冊。
無人島で暮らす上での鉄則「愉快な生活を心がけること」
2007/07/15 22:36
7人中、7人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:栗太郎 - この投稿者のレビュー一覧を見る
明治32年、無人島に流れ着き、およそ半年を生き抜いた16人の男たちの奮闘を描いた本書は、なんと言うか、とても爽やかで痛快な物語でした。嵐で船が難破して、水すらない無人島に漂着するという、死と隣りあわせの過酷な状況でありながら、全編に暗さは微塵もありませんでした。明るく力強く、読むとムクムク元気が湧いてきます。人間って、困難の中でこんな風に生きていくこともできるんだ、という感動です。
これ、ノンフィクションなのですが、今の日本には絶対こんな男たちはいないだろうと思えてしまう、ほとんどフィクションののりでした。
無人島に上陸した16人は、まず井戸を掘りました。掘っても掘っても、なかなかきれいな水は出てきません。なんとか出てきた水は、飲むとお腹を壊してしまう代物で、みんなフラフラになりながらも井戸を掘り続けます。焚き火をしようにも燃やせる物がほとんどないし、通りかかる船を見張ろうにも遠くまで見渡せるような場所もありませんでした。
16人は力をあわせ、知恵を出しあい、一つ一つ問題をクリアしていくのですが、まずは島での生活を始めるにあたって4つの約束をします。
「一つ、島で手にはいるもので、くらして行く。
二つ、できない相談をいわないこと。
三つ、規律正しい生活をすること。
四つ、愉快な生活を心がけること。」
口で言うのは簡単でも、実行するのはとてつもなく難しいこの4つの約束を、16人は見事に守り通すのです。多少の創作は入っているにしても、にわかには信じがたいほど、立派な暮らしぶりでした。
出来すぎなのに、読んでいて白けないのは、四つめの約束があるためです。彼らは立派なだけでなく、良く学び良く遊び、愉快に日々を過ごすのです。一枚しかない服を冬のために取っておこうと、朝も夜も裸で過ごすあたり、大らかさに一役買っています。
16人の中には、老人も青年もいて、ベテランも新人もいました。それぞれが、それぞれのポジションで良い仕事をするのが、爽快です。とりわけ、年長者が良い味出しています。
例えば、無人島生活二日目の朝早く、船長、運転士、漁業長、水夫長の4人が、他の仲間たちを起こさぬようこっそりテントを抜け出して、今後のことを話しあう場面があります。船長はいわば16人の父親役であり、誰よりも重い責任を担っているのですが、そんな彼にも、支えとできる者たちがいるとわかる、良いシーンでした。他にも、若い者は「懐郷病」にかかってしまうからと、夜の見張り番を引き受ける老人や、自分の経験や知識を若い者たちに伝授するベテラン乗組員など。
対して、若者たちは向学心と冒険心、元気に溢れ、臆することなくアザラシや海鳥と仲良くなっていきます。
年長者が若者たちを導き、若者たちは自然に彼らを尊敬している。人生を生きる知恵のようなものが世代を超えて受け継がれていく、今の日本ではあまり見られない光景です。16人の天晴れな「日本男児」ぶりを読むにつれ、私たちは退化したのでは? なんて考えてしまいます。
もっとも、直前に読んだ本が、新田次郎の「八甲田山死の彷徨」で、八甲田山の悲劇は明治35年だったことを考えると、単純に昔は良かったという問題でもないのですが。
明治人の「技術」
2004/10/03 17:05
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オリオン - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本が湛えるのびやかで楽観的な明るさは、明治という時代を生き延びた男たちの「技術」に支えられている。それはたとえば、無人島生活を始めるに際して誓い合った四つの約束(島で手にはいるものでくらしていく、できない相談をいわない、規律正しい生活をする、愉快な生活を心がける)や、夜の見張りは「つい、いろいろのことを考えだして、気がよわくなってしまう心配がある」から、老巧で経験豊かな年長者が交代して当番にあたるといった知恵のうちに示されている。「ものごとは、まったく考えかた一つだ。はてしもない海と、高い空にとりかこまれた、けし粒のような小島の生活も、心のもちかたで、愉快にもなり、また心細くもなるのだ。」このリアリズムが潔い。感動はないが、いっそ清々しい。(本書の明るさは、随所に挿入されたカミガキヒロフミのシュールでファンタスティックなイラストの力によるところが大きい。)
牧歌的
2021/09/23 16:56
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:うみいぬ - この投稿者のレビュー一覧を見る
とにかく悲壮感がないです。生きてく力強さはあるけど!
すごいなー、時代なのかなー。今の世代の人だったら、どうなんだろう。多分、生きてけないでしょうねぇ。
…などなど、考えてしまいます。
でも、おそらく一番いえることはリーダー(誰とは書かれてないけど、多分船長かな?)がよかったのかな、と。信頼に足る人物だったんでしょうね。
こんな記録が残ってるなんて、面白い!楽しい!
本当、世の中、まだまだ知らないことがあります。
もっと有名になってもいい本です。椎名誠さん様々です!!
子供向けの冒険物語のよう、でも実話
2020/02/18 01:26
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Chocolat - この投稿者のレビュー一覧を見る
明治31年、日本人乗組員16人を乗せた船が座礁し、やっとなんとか島にたどり着いたけれど‥そこは無人島
という遭難記録なのに、悲壮感が全くなくて、まるで、サバイバルのお手本みたいな内容
みんなの知恵と経験が豊富で、「ヘェ〜!」な知識がいっぱいで、面白くて一気読みでした
しかし、明治の日本人は強い!