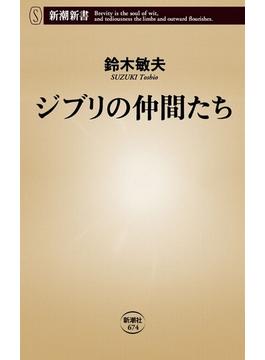- みんなの評価
 3件
3件
ジブリの仲間たち(新潮新書)
著者 鈴木敏夫
『風の谷のナウシカ』『もののけ姫』『千と千尋の神隠し』etc……ジブリはなぜ常に予想を超えるヒットを生みだし続けることができたのか。そこには作品の力に加え、プロデューサーである著者と、仲間たちの力があった。「宣伝の本質は仲間を増やすこと」という思想の下、監督と激論を交わし、企業を巻き込み、駆けずりまわり、汗まみれになって体得してきた経験則とは――。秘話満載で綴る、三〇年間の格闘の記録。
ジブリの仲間たち(新潮新書)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ジブリの仲間たち
2020/06/09 09:42
ジブリ
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Nighthawks - この投稿者のレビュー一覧を見る
ジブリが好きなら読むといいと思います。裏話的な話がいっぱいあって、読むたびに新しい発見がありますね。
ジブリの仲間たち
2018/05/30 22:45
宣伝という切り口から見たスタジオ・ジブリ
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みなとかずあき - この投稿者のレビュー一覧を見る
ある意味でいつの間にかジブリの顔になってしまったような印象のある、プロデューサー鈴木敏夫の語りおろしの1冊。鈴木氏の本はすでに何冊も出版されているけれど、これはジブリ映画を宣伝という切り口で見直したもの。随所にプロデューサーでないと知らない話が織り込まれている。
例えば、『ナウシカ』の宣伝コピーに、「人間はもういらないのか?」なんてのが候補にあったとか、当時の宣伝等の担当だった博報堂に宮崎駿の弟が勤めていたとか。「『トトロ』の最初のコピーは、「このへんないきものは、もう日本にいないのです。たぶん」だったんです。でも、宮さんが「いる」と言うので、いまの形になりました」(p.27)といったような話も出てくる。
ただし、これまでの本でも語られていることも出てくるので、ジブリ本を何冊も読んでいるとすでに知っている話もあって、新鮮味は薄い。
それでも宣伝という切り口でみているので、企業とのタイアップでは映像やキャラクターの使用料をもらわない代わりに使用方法については意見を言っていく姿勢をとり続けたことや、「宣伝費=配給収入」の法則(p.81)とか、「人間というのは3回、広告を見れば消費行動に走る」(p.139)という宣伝哲学とでも言える話が出てきて面白かったのと同時に、何だか鈴木氏の掌の上で遊ばれてしまって映画を観に行っていたのだなあといった気持ちにもなってしまった。
そんな気持ちになる一方で、やはりジブリ映画に惹かれてしまうのは、鈴木氏が「たえず考えていたのは、高畑さんや宮さんがいい映画を作れる環境を整えることです」「作るのが第一義で、ヒットするかどうかは二義的な問題」と言っているところに、偉大な作家の傍で良い作品を産み出させようとして頑張ってきた姿が見えるからだと思う。そんな姿は、プロデューサーと言うより、鈴木氏の元々の姿である編集者の姿のように思える。
ジブリの仲間たち
2016/07/29 18:09
広告本
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:七無齋 - この投稿者のレビュー一覧を見る
芸術品であり文化的作品であるもの作りをその信念と、金に換える現実路線の間でのやりくりは非常に難しい。資金稼ぎはこれでよいのか考えさせられる。