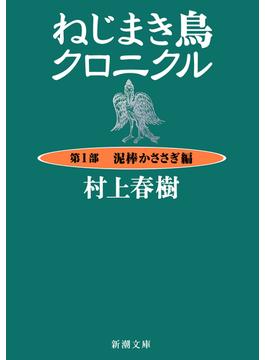- みんなの評価
 19件
19件
ねじまき鳥クロニクル
著者 村上春樹
「人が死ぬのって、素敵よね」彼女は僕のすぐ耳もとでしゃべっていたので、その言葉はあたたかい湿った息と一緒に僕の体内にそっともぐりこんできた。「どうして?」と僕は訊いた。娘はまるで封をするように僕の唇の上に指を一本置いた。「質問はしないで」と彼女は言った。「それから目も開けないでね。わかった?」僕は彼女の声と同じくらい小さくうなずいた。(本文より)
ねじまき鳥クロニクル―第3部 鳥刺し男編―(新潮文庫)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
ねじまき鳥クロニクル 改版 第3部 鳥刺し男編
2010/07/31 14:38
村上春樹の長編小説はひたひたと走るランナーのよう
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:サムシングブルー - この投稿者のレビュー一覧を見る
K・Iさんの『ねじまき鳥クロニクル』第1部から第3部までの書評を読みました。特に第3部の書評のなかの
「『1Q84』に出てくる「牛河」が出てくるのも興味深い。牛河は、『1Q84』での牛河よりももっと牛河的だ、という気がした。とくに、そのねばっこい饒舌さは一読の価値あり、だろう。」
箇所を読み、さっそく読んでみることにしました。
村上春樹の長編小説はひたひたと走るランナーのようです。ランナーは強靭な肉体を持ち、最強のメンタルで、フルマラソンのイメージトレーニングを完成させている。次第にランナーの息遣いや心臓の鼓動が私の脳細胞に侵出してきます。ページを捲る手は汗をかき、紙がしっとり濡れてくる。親指の形に濡れたあとは恐怖のしみです。
自分の思考を超える恐怖はどうしようもなく、本を閉じても脳細胞に残留している。
第1部の冒頭文「一九八四年六月から七月」、第2部の冒頭文「一九八四年七月から十月」は『1Q84』を彷彿させ、笠原メイは『ダンス・ダンス・ダンス』のユキを彷彿させます。
第3部の最終章「さよなら」の始まりは
「ねじまき鳥さんにアヒルのヒトたちを見せられなくて残念だったな」と笠原メイはいかにも残念そうに言った。(593頁)
この最終章は村上作品を好きにならずにいられない章でした。
次は、村上春樹の絵本を読んでみよう。
ねじまき鳥クロニクル 改版 第2部 予言する鳥編
2010/07/14 16:58
「僕」が求めることを決心する「第2部」
6人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:K・I - この投稿者のレビュー一覧を見る
大江健三郎さんが「再読(リ・リード)」の重要性ということをいっていて、それを本で読んでいて、再読のことはずっと頭にあった。
読む本というのは、買ってきた本、図書館から借りてきた本、そして、読み終わり本棚におさまっている本の三種類がある。
よく考えると、それらを組み合わせながら、ほとんどだいたい毎日、何かしらの本には接している、と自分のここ最近を振り返って思う。
そうしたなかで、ふと、本棚の『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』が目に入り、「再読してみるか」と思って、再読してみた。
大江さんは再読では「探索」するような読み方ができるといっている。『世界の終わりとハードボイルド・ワンダーランド』を読んだときは、鮮明に覚えている冒頭の場面。それから、進んでいく「二つの」世界、それらを読みながら、ところどころ覚えているところもあり、あるいは忘れているところもあり、「ここはああなるんだな」「次はこういう展開だな」と思いながら、再読した。
そして、それを読み終わって、次は、『ねじまき鳥クロニクル』を再読することにした。記録を読むと、ちょうど三年前に読んだようだ。
ただ、どちらかといえば僕は『ねじまき鳥クロニクル』の内容を覚えていなかった。だから、「探索」というような意識的な読み方はできなかった。それでもだからこそ逆に初めて読むように新鮮に読めた。
「第2部」は、主人公が井戸に入り、そこから出てきて、加納クレタとの関わり、それから、最終的に、「電話の女」の正体に気づく。笠原メイの「告白」もこの「第2部」だ。
上で僕は「さほど内容を覚えていなかった」と書いたが、部分的には覚えている部分もあった。そして、おそらく、また何年後か、三度読み返すであろう、ということを予感している。
その前に「第3部」を読む。新装版の文庫で読んでいるのだが、文字も大きく、カバーもかっこうよくなり、個人的にはとても気に入っている。
ねじまき鳥クロニクル 改版 第1部 泥棒かささぎ編
2005/08/30 18:57
もう、このタイトルだけで勝ちですね。だれも思いつかないでしょう。しかも、ここには第二次大戦中に日本人がされたこと、そして行ったことが克明に描かれるのです
7人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:みーちゃん - この投稿者のレビュー一覧を見る
「近所の木立からまるでねじでも巻くようなギイイッという規則的な鳥の声が聞こえた。我々はその鳥を「ねじまき鳥」と呼んでいた。クミコがそう名付けた。本当の名前も知らなければ姿も見たことが無い、毎日近所の木立にやってきては、我々の属する静かな世界のねじを巻く。そして少女との会話の中で、岡田は自分のことを「ねじまき鳥」と言い始める。」が鳥の名の由来です。
全体を通じて、クリーニング屋がポイントポイントで出てきたり、決して重要な役割を果たすのではないけれど、僕たちに家を貸してくれている裕福な叔父の話が入ってくるのが面白いです。謎の宮脇家も、時々話しに微妙な味を添えます。また、かつらメイカーのアルバイトというのも印象的です。ここで、第二巻に通じる井戸の話もでてきます。
語り手は30歳の僕、岡田亨。兄弟はいません。スパゲティを茹でているところに、見知らぬ女から奇妙な、というか性的な嫌がらせ電話がかかってくるところから話が始まります。妻のクミコは仕事先から、そんな僕のところに、出て行ったきり1週間も戻らない猫のことを心配して電話をしてきます。そう、僕は4月に働いていた法律事務所を辞めて以来、仕事を探すこともなく、のんびり家事をしながら暮らしているのです。
妻のクミコ、岡田久美子は多分28歳、雑誌の編集の仕事をしていて、僕が働かなくても何とか食べていけるくらいの収入は得ています。そして、一人で昼食を摂った僕は、ゆっくり休んだ後で、ブロック塀を乗り越え、行き止まりの路地を散歩し始めるのです。やっと家の猫ワタヤ・ノボルを探すことにしたのです。そこで出会った少女が笠原メイでした。15、6歳に見える彼女との不思議な会話。
そしてクミコがワタルの行方を捜すことを依頼した加納マルタが登場します。幼い時から未来を予言することで周囲を呆れさせ、それがもとで家を出ることを決心し世界を放浪した31歳の女性。彼女が教える五歳年下の妹クレタの存在。彼女は、亨の義兄綿谷ノボル37歳に汚されたという。
第2部「予言する鳥篇」は、岡田久美子と僕との病院での出会い、堕胎、僕の女性関係などが語られます。家から消えたクミコと、それに関して危険を予言する加納マルタ、井戸の底に降り、考えに耽る僕の危機と救出、クレタの変貌と、笠原メイの悪戯、そして綿谷ノボルの脅迫的言辞。夢の中の行為が現実と重なりながら、僕は決心をします。
第3部「鳥刺し男篇」は、ナツメグ、シナモンという親子のビジネスに顔にあざの出来てしまった僕が巻き込まれます。失踪したクミコと僕との会話がコンピュータを通じて行われ、笠原メイからの驚くべき告白がなされ、井戸の底が過去や異世界へと通じる扉となって、神話世界が展開していくのです。
と、駆け足で紹介しましたが、勿論こんな簡単な話ではありません。日本人が過去に犯した過ちが、重要な意味を持つだけではないのです。ソビエトで行われたことも含めて、歴史というものが極めて大きな役割を果たします。第1部で日本人が見せ付けられた残虐な刑のシーンがありましたが、第3部ではそれに勝るとも劣らない日本人自身が中国人に対して行った行為が描かれます。
そして、全体の話には各篇のサブタイトルが重要な意味を持っていて、それがこの話の構造と密接に関係しています。ここでも、村上春樹の小説には必ず現れる文章では軽いけれど映像にしたら騒動が巻き起こるだろうと思われる性的な、暴力的な描写を沢山見ることが出来ます。
読み返すと、張り巡らされた伏線、まそれほど緊密ではないかもしれないそれが、見えてきて、あ、これが、と腑に落ちます。