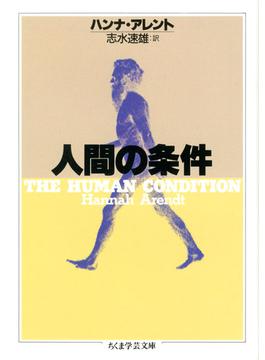- みんなの評価
 7件
7件
人間の条件
条件づけられた人間が環境に働きかける内発的な能力、すなわち「人間の条件」の最も基本的要素となる活動力は、《労働》《仕事》《活動》の三側面から考察することができよう。ところが《労働》の優位のもと、《仕事》《活動》が人間的意味を失った近代以降、現代世界の危機が用意されることになったのである。こうした「人間の条件」の変貌は、遠くギリシアのポリスに源を発する「公的領域」の喪失と、国民国家の規模にまで肥大化した「私的領域」の支配をもたらすだろう。本書は、全体主義の現実的基盤となった大衆社会の思想的系譜を明らかにしようした、アレントの主著のひとつである。
人間の条件
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
人間の条件
2020/04/11 13:40
全体主義の現実的基盤となった大衆社会の思想的系譜を明らかにしようとしたハンナ・アレントの主著です!
4人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、ドイツ出身の哲学者であり、思想家でもあったハンナ・アレントの主著の一冊です。アレントは、ユダヤ人であり、ナチズムが台頭したドイツから、アメリカ合衆国に亡命し、後に大学で教鞭をとり、主に政治哲学の分野で活躍し、全体主義を生みだす大衆社会の分析で知られる人物です。同書では、「条件づけられた人間が環境に働きかける内発的な能力、すなわち<人間の条件>の最も基本的要素となる活動力は、労働、仕事、活動の三側面から考察することができる。ところが、労働の優位のもと、仕事と活動が人間的意味を失った近代以降、現代世界の危機が用意されることになった」と主張し、全体主義の現実的基盤となった大衆社会の思想的系譜を明らかにしようと試みています。ぜひ、一度は読んでいきたい一冊です。
人間の条件
2023/03/28 21:38
学生時代
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:monsieurbutter - この投稿者のレビュー一覧を見る
頑張って読んだな~。ハイデガーと仲が良かったとか、昔も知ってたかな?まあそのことを知ろうが知るまいがこの本の価値は変わらないが。映画を観て掘り出して再読しました。
人間の条件
2001/02/27 22:23
政治的なものの復活
15人中、14人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:オリオン - この投稿者のレビュー一覧を見る
アレントの思想の根幹をなすのは、全体主義と大衆社会への徹底的な批判、そして人間の自由に立脚し、複数の人間の意識的な相互活動から織りなされる「公的なもの」による新しい社会の「始まり」の構想である。『人間の条件』は、そのような思想を体系的かつ詳細に叙述した主著の一つである。
アレントはまず、人間の基本的活動力として、労働(labor)・仕事(work)・活動(action)の三つを掲げる。それぞれ、生存のために必要な消費財の生産(労働)、有用性と耐久性をもつもの、つまり消費に抗する道具や器具、美的永続性をもつ芸術作品などの人工物の製作(仕事)、談話すなわち言語によるコミュニケーションや英雄的個人の偉業(活動)を典型とするものである。
これらのうち、アレントが重視しているのが第三の類型、すなわち言論と実践を通じて「私とはだれか」(アイデンティティ)を他者の前に明らかにしつつ、多数性の条件に羈束された人間社会への参入を果たし、人と人との関係の中から新しい価値や意味を生み出していく、人間の自由に立脚した「活動」である。その典型あるいは理想型は、いうまでもなく古代ギリシャのポリスにおける政治生活であった。
古代ギリシャ世界から抽出された「ポリス(都市空間)=公的領域」と「オイコス(家空間)=私的領域」との区別は、中世ヨーロッパにおける「教会=天上的世界」と「世俗=地上的世界」へと推移する。そして、近代になって「社会的なもの」という第三の領域が現われ、公的領域と私的領域との原理的な区別を解消してしまう。
産業と商業の勃興による「社会」の出現は、西洋近代における「労働する動物の勝利」がもたらした現象であり、その実質は国民全体にまで拡大された「オイコス」にほかならない。すなわち、社会という新しい領域の出現によって、古典的二分法によれば私的領域に属する「経済」(個体の維持にかかわる機能)が公的領域を制覇し、その結果、政治は「公共生」を喪失し、「労働」の論理(生命の必要の論理)に立脚した「家政」へと変質していった。
こうして、公的領域と私的領域は「社会的なもの」によって制覇され、近代的な意味での公私の観念が生み出されていく。やがてもたらされることとなったのが、「必要」を超える無制約の「欲望」に支配された社会である。それは、「活動」が成り立つための前提条件(人間社会の「多数性」、いいかえれば個人間の差異としての個性)を圧殺する画一主義的な大衆消費社会であり、「ついには世界の物が、すべて消費と消費による消滅の脅威に曝されるであろうという重大な危機」が支配する社会であった。
以上が、現代社会へのアレントの診断である。それでは、このような状況下にあって、いかにして「公共性」を恢復することができるのか。いいかえれば、いかにして「活動」を再構築すべきか。この点に関してアレントが示唆する処方箋は、言語を媒介とする人々の相互作用を可能ならしめる場の復活、すなわち古代ギリシャのポリスにも比肩しうる「公的空間」の創出である。
《正確にいえば、ポリスというのは、ある一定の物理的場所を占める都市=国家ではない。むしろ、それは、共に行動し、共に語ることから生まれる人々の組織である。そして、このポリスの真の空間は、共に行動し、共に語るというこの目的のために共生する人びとの間に生まれるのであって、それらの人びとが、たまたまどこにいるかということとは無関係である。「汝らのゆくところ汝らがポリスなり」という有名な言葉は単にギリシアの植民の合言葉になっただけではない。活動と言論は、それに参加する人びとの間に空間を作るのであり、その空間は、ほとんどいかなる時いかなる場所にもそれにふさわしい場所を見つけることができる。右の言葉はこのような確信を表明しているのである。》