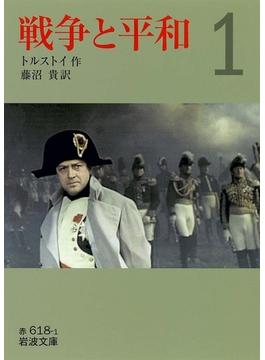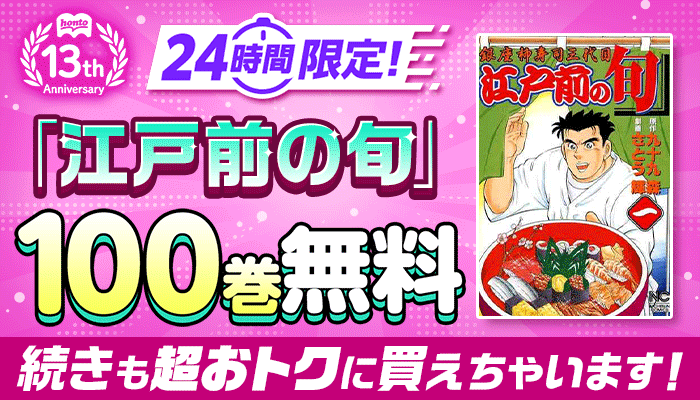- みんなの評価
 10件
10件
戦争と平和
1805年夏,ペテルブルグ.英雄か恐怖の征服者か,ナポレオンの影迫るロシア上流社会の夜会に現れた外国帰りのピエール.モスクワでは伯爵家の少女ナターシャが平和を満喫.だが青年の親友や少女の兄等は戦争への序走に就いていた.愛・嫉妬・野心・虚栄・生死――破格のスケールと人間の洞察.世界文学不朽の名作! 新訳.
戦争と平和 (六)
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
戦争と平和 6
2006/11/22 11:54
「無数の人間の営みの総和が歴史をつくる」。歴史を、人間を感じる大作だが、「全部通して読まなくても良い」と著者は言ったそうである。
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ナポレオン戦争を描いたトルストイの不朽の大作の新訳、全六巻の最終巻である。押し寄せた高波が去ってしまったかのように、疲弊したロシアの地にそれでも、静かな時間が訪れる。大きな歴史の流れから切り取られた、一つの戦争の物語。長い作品なのだが、歴史の中では一瞬でしかない時間、しかしその一瞬には多くの人の、さまざまな生きざまがあることを感じさせる、長くて短い、短くて長い物語である。
本編全四部の後には、さらにエピローグの1,2があり、エピローグ1では12年後の登場人物の姿が、エピローグ2では著者の歴史論がまとめられている。12年後の、戦争前とあまり変わらないかのように見える彼らの毎日は、「戦争がないことが平和なのだ」と語っているようである。しかし世界情勢はまだ動いていて、その数年後に起きるデカブリスト事件を予感させる情景も挿入されている。デカブリスト事件は作者がこの作品を書く契機となったと言われている。その関連性を示すためにも、このエピローグは必要だったのだろう。
「戦争と平和」という作品には、作者の歴史への想い、その中で生きる人間への想いが詰っている。それぞれの場面での情景や心理描写、著者の歴史や人生に対する考えなど、個別にとってもすばらしいものがあるのはもちろんであるが、それらがギュウギュウに詰めこまれてもまだ、微妙なバランスでまとまっている。完成した時に作者は41歳。熱も力もこめて書かれた作品であったと想像することは難しくない。 さまざまな場面での細かで鮮やかな描写を思い出すと、「無数の人間の営みの総和が歴史をつくる」というトルストイの歴史観がそこにあらためて実感されるのである。
この新訳には、登場人物の名称を簡略化・統一して表記するなどの幾つかの試みがなされていた。最終巻でも、あとがき・解説をQ&Aの形にし、ミニ写真アルバムを載せるなどの工夫がある。解りやすく、楽しく、この作品だけでなく、トルストイの全体像を与えてくれるものになっていると思う。特に「戦争と平和」執筆当時の肖像の眼光の鋭さは、当時の著者の意欲の強さを伝えているようで、ここに載せるのにふさわしく感じられた。
あとがきがわりのQ&Aで知ったのだが、トルストイはこの作品を「それぞれの部分に独立した価値があるから、全部を通読する必要はない」と言ったとか。新訳の力をかり、通読をしたのだが、そういう気楽な取りかかりかたもいいだろう。いろいろな読み方ができる、やはり大作である。
戦争と平和 4
2006/07/17 09:21
物語の中盤、トルストイの歴史論の展開が始まる
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:銀の皿 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ナポレオン戦争を描いたトルストイの不朽の大作の新訳、第四巻は第三部の1,2篇を収録。前の第三巻に収められていた第二部の後半は戦闘場面もなく、どちらかと言えば穏やかに進められて行く部分であったが、この巻に入りいよいよフランス軍はモスクワに押し寄せ、慌てふためくロシアの人々やボロジノの戦いの様子が描かれる。
物語りも半ばを過ぎたこの一巻は、ちょっと他の小説にはない特徴を現してくる。トルストイの「歴史論」である。物語の筋を進めるのでもない、歴史の展開の原因、人の意志といった事柄についての著者の考察は、第三部冒頭から始まってこの後も随所にはさまれている。著者の意見を人物に語らせたり描写で伝えるだけでは足りず、どうしても直接表に出て記さなければいられなかった作者の熱を感じるところである。しかしこのはさまれている著者の歴史論の部分から戦況の記述、登場人物の描写への移行は滑らかで、自然に融合している。トルストイの文筆家としての力はこんなところにも現れていると言ってよいだろう。登場人物の細かな心の描写、戦闘場面の詳細、ナポレオンやロシア皇帝の真にせまった言動や性格描写といった数多くのものが、「これらの一つ一つが集まって歴史となっている」という著者の論を証明しているようだ。
トルストイの描写は、この巻でも、どの一つをとっても丁寧に書き込まれ、そこだけを取り出しても読みごたえがある。ボロジノの戦いの細かな描写は、トルストイが原文に入れていたという図面などもあり、この部分だけでも戦記物として興味深い。この時代のロシアの貴族、領主と領民の関係などを記録したような場面もあり、登場人物の新しい動きもある。ボロジノの戦場に入り込んだ、戦闘には素人のピエールの様子などは、「こんなのんびりした情景があったのか」と思わず笑いそうなほどである。
トルストイはこの戦いを通じて、何を書きたかったのか。いよいよ著者が語り始め、ストーリーをこえて歴史を、人間が生きるということを読む者に考えさせていく。この先、どのように物語は、著者の考察は展開していくのか、と緊張が高まる一巻。
戦争と平和 1
2014/03/26 23:27
ナポレオンがキター!
5人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:SlowBird - この投稿者のレビュー一覧を見る
ナポレオンが攻めて来ることははっきりしている。それはロシア人にとって世界の一大事のような気がするのだが、なんとなくのんびりしているように見えるのは、宮廷の人々に緊迫感が足りないということとも少し違うようだ。元々ロシア貴族はフランスびいき、むしろフランスかぶれとでも言うような愛着があるのがまず一つ。そしてロシアというのは年中トルコやらオーストリアやらとの戦争だの内乱だのを起こしていて、それがまた首都まで及ぶようなことは滅多に無いので、ナポレオンについても小競り合いの一つになるぐらいにしか想像が及ばないのだ。
その親フランス的な人々で、またナポレオンの革新性を賞賛するような人々でも、国王の命令ならなんの疑問もなしに戦地に向かう。まるでスポーツの試合のように。しかしそれが命をかけたスポーツであることは貴族達も重々分かってはいる、ただそれでも彼らは命よりは勇敢さや名誉を重んじようという意識が強い。
その一方で、ナポレオン軍は甘くない。はるばる遠征して来て、いくらかの譲歩で満足して帰還するつもりは無く、戦う機械のようにどこまでも進軍することを使命とした、近代戦争の貌を見せ始める。
この第1巻まででは、ロシア宮廷や貴族達の内幕と戦場の過酷さが対比されて描かれているようだが、本当に対比されるのは旧来の戦争の通念の中で、新しいそれの訪れた衝撃ではなかろうか。トルストイが見たクリミア戦争の戦場で発見した、砲弾が飛び交い、大軍勢がひしめき合う中で、個人の力では進むことも退くことも出来ないという恐怖の形がここにある。
もう一つ、この戦場という空間でその才能を発揮し始める青年貴族がいる。おそらく彼は宮廷内でこ狡く立ち回るようなことはできなかったろうし、敵との戦いより味方同士の権力闘争に明け暮れるような旧来の戦場でもすぐにその場を投げ出してしまいそうだ。ただ怒涛のようなナポレオン軍を押しとどめるために必要な才能として発見される。するとこれも近代の合理化社会の生んだ一つの生き様なのだろうか。それを青年の成長と呼ぶなら、産業革命に先駆けて戦争によって近代的合理主義が生まれたという、一つの悲劇の姿のことかもしれない。