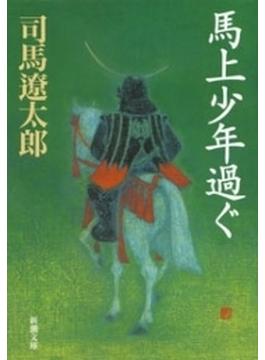紙の本
良い本です
2024/03/30 17:04
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:a - この投稿者のレビュー一覧を見る
司馬遼太郎に短編があるとはね。後の長編のプロトタイプが多いのでしょうか。表題作が良かったです。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:LR45 - この投稿者のレビュー一覧を見る
表題作の『馬上少年過ぐ』の主人公が伊達政宗だったので買って読んでみたのだが、『馬上少年過ぐ』はいまいちだった。
が、『貂の皮』と『英雄児』、『慶応長崎事件』の三つはそれを流してあまりあるくらい面白かった。
特に『貂の皮』はなんだが日本人がなくしつつあるものを思い出すような、そんな作品だと思う。
紙の本
奇妙な人生
2019/02/15 12:05
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:井沢ファン - この投稿者のレビュー一覧を見る
短編の歴史小説が7編。師弟関係を結んだ鈴木虎太郎から見た師、河合継之助の半生を描いた『英雄児』、英国水兵殺害事件にまきこまれた海援隊士の処分について述べた『慶応長崎事件』、足軽で喧嘩っ早い絵師、田崎草雲を描いた『喧嘩草雲』、伊達政宗の生涯を描いた『馬上少年過ぐ』、牢人で医師の山田重庵の奇妙な人生を描いた『重庵の転々』、兵法を身につけ立身を求めて大阪に出てきた大須賀万左衛門の話『城の怪』、さほど実績もない七本槍の一人、脇坂甚内の半生『貂の皮』。それぞれ面白く読めたが、奇妙か波乱万丈のいづれかあるいは両方の人生を送った人々の話で興味深かった。
電子書籍
佳品「重庵の転々」
2018/06/18 20:12
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:るう - この投稿者のレビュー一覧を見る
伊達政宗を取り上げた表題作は駆け足な印象。エピソードだらけの政宗なのでもう少しそれらを取り入れていただきたかった。
この中では「重庵の転々」がある藩と一人の男の数奇な運命を描ききっていて正に佳品だった。
投稿元:
レビューを見る
司馬先生の小説は果てしなく分かりやすいが、行きつく先にはいつも死が待っている。この短編集はそのむなしさがいつもより濃い気がする。『重庵の転々』が好きだ。
投稿元:
レビューを見る
タイトルの「馬上少年過ぐ」-伊達政宗を記す話-を含む、全7編で構成されている。母から疎まれながら育った政宗の悲痛が描かれ、彼の起こした行動に影響を与えていることがわかる。当時の政治とは、母の愛情すら屈折させてしまうものだったのか。子としては悲しまざるを得ないだろう。政宗に、よりフォーカスした作品を読んでみたくなる。
投稿元:
レビューを見る
全7編の短編集です。表題の作品を目当てに読んだのですが、この作品に関してだけ言えばさほど目を引く内容ではなかったかな、と。個人的には重庵の転々と貂の皮がとても好き。英雄児も結構好き。歴史の舞台の上では決して主役級ではなかった(馬上〜は主役級と言えなくもないのかな)人たちの、七者七様の人生が実に面白いです。
投稿元:
レビューを見る
伊達政宗は詞華の才能があったらしいですね。馬上少年過ぐはこれをざらーっと読むだけで伊達政宗の生涯が分かるといっても過言ではないくらいだと思う。本当に筆頭格好良い・・!
投稿元:
レビューを見る
短編集は旅行のお供に。表題作は伊達政宗が詠んだ詩から、彼の生涯をたどったものです。某国営放送の影響か、大河のキャスティングで読んでしまった。
投稿元:
レビューを見る
戦国の争乱期に遅れて僻遠の地に生れたが故に、奥羽の梟雄としての位置にとどまらざるをえなかった伊達政宗の生涯を描いた『馬上少年過ぐ』。英国水兵殺害事件にまきこまれた海援隊士の処置をめぐって、あわただしい動きを示す坂本竜馬、幕閣、英国公使らを通して、幕末の時代像の一断面を浮彫りにした『慶応長崎事件』。ほかに『英雄児』『喧嘩草雲』『重庵の転々』など全7編を収録する。
投稿元:
レビューを見る
短編集
またまた面白い人物に出会ってしまいました。
司馬遼さん、ありがとう。
「おらァ、自分がわかンねえ・・・
体の中におかしなものがいっぱい填ってやがってな、
こいつは絵にも剣にも無縁のものだよ。
いったい、何だろう」(本文より)
・・・『喧嘩草雲』のセリフが印象深い。
2008 7/3読了
投稿元:
レビューを見る
表題作の「馬上少年過ぐ」は伊達政宗の話。
なんか可哀想過ぎて叫び出したくなるゥゥ!!知ってたけどさー、想像すると悲しくて…。うわああああああ
2008.8.30 第71刷/2009.6.29 購入
2009.6.29 「馬上少年過ぐ」読了
投稿元:
レビューを見る
伊達政宗公の生涯を題材に扱った小説は多々ありますが、私は表題作の短編が一番に思い浮かびます。
政宗公の生涯を駆け足で、その詩の解説の様に描かれた編ですが、それが逆に一人の人物の姿を強烈に印象づけます。
ぶつ切りのエピソードの一つ一つが、それぞれなテンポで描かれているにも拘わらず、全体としては冒頭のシーンに帰って行く纏まり方も流石綺麗。
また、細かく描かれ過ぎない事で、考えたり調べたりする度に厚みを増して読めるのも、どこまでも私好みの短編です。
更に言えば、表紙の絵も、素晴らしい。
勿論、他の編も興味深く面白いです。
投稿元:
レビューを見る
英雄児
無隠(継之助)が一学問士から長岡藩の実権を握るようになるまで。強兵に力を入れていくが、時運ともいえるし世流ともいえるものによって負けがこみ、最後には守るべき町は自らの判断で破壊しつくされる。
この本全体に通ずる、ではどこの時代に、どこで生まれればよかったのか、という疑問をまとめた「英雄というのは、時と置き所を天が誤ると、天災のような害をすることがあるらしい。」の一文が、短いながらもずばりと心に突き刺さる。
慶応長崎事件
イギリス水兵殺害事件に巻き込まれた海援隊士、その解決をめぐって、幕府が、藩が、イギリス外交官が、坂本竜馬が、それぞれの思惑のために立ち回る。
水兵さんてこんなに嫌われていたのね。そもそも荒くれ、というイメージと、やはりよそ者阻害の意識と、どっちもあったと思うのだけど、その辺はとにかく水兵を「殺される厄介なきっかけ」と描いて終わりになっている。草の根交流の部分ではどうだったのかしら?
喧嘩草雲
喧嘩っ早い侍画家・草雲が自らの侍としての力と画家としての力のどちらもが中途半端であることに悩む。二天(剣技も画術も一流であった宮本武蔵)の鷺との出会い、妻の死、足利藩の軍師になり、草雲のかどはとれ、画師としても優れた作品を残すようになる。
このひとの女房は大変だったろうなあ。人間、誰になるか、何になるかは、簡単に決まるもんじゃないなあ。
馬上少年過ぐ
幼少時代の不遇であった伊達政宗は、その不遇さを克服せんがための発奮でか生来の知恵か、伊達家を継ぐ若き当主となる。父を見捨てるエピソードもあるが、何より印象的なのは、冒頭の正宗の読んだ歌やその茶目っ気とも言うべき神秘性の自演である。
歌がいいよね。でも司馬遼太郎のいうように、本当に自作自演だったのか? ていうか乳母すげえ乳母
伊達政宗がもっと早くに生まれていたら? もっと有利な土地に生まれていたら? よく考えれば歴史にもしもは禁物なのに、この本は冒頭からそのつもりである。
重庵の転々
土佐から伊予へ、仙台へ、医師だったはずの重庵は、自らの用心深い正義感でもって家老にまでなりあがり、危機に満ちた世界を意識して独裁的な体制改革を行う。行き過ぎた、もう死刑か、と思いきや、かつて領主を病から救った恩で、医師に戻してもらって隠匿する。まさに転々、である。
投稿元:
レビューを見る
短編集。表題作は伊達政宗。
すごく才能も力もあるのに、時代がそれを認めなくて不遇をかこつ、
みたいな話は切ないなあ。
後世の視点から見ると色々見えてしまって、もうそれじゃ古いよとか
あれをやってはいけなかったとか考えてしまうけど、一回きりのことだからなあ。
子供を戦争に出すようになったら終い、というくだりにはその通りだと思いました。