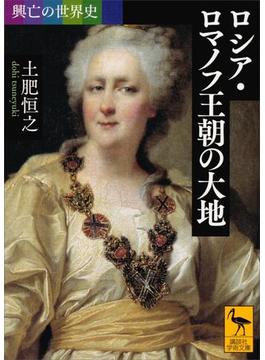ヨーロッパとアジアの間で揺れたロシアの通史です!
2019/02/02 13:29
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ちこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書は、ヨーロッパとアジアの間で揺れに揺れたロシアの通史です。ロシアでは、大改革を強行したピョートル大帝と女帝エカテリーナ二世、革命の中で銃殺されたニコライ二世一家など、非常に大きな出来事が多数起こってきました。しかし、私たちは今一つこうしたロシアの歴史については断片的にしか知りません。本書は、私たちにロシアの歴史を分かり易く、そして興味深いく教えてくれる絶好の一冊です。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:福原京だるま - この投稿者のレビュー一覧を見る
タイトルにロマノフ王朝と入ってますがその前のキエフ公国やタタールのくびきからソビエト崩壊までのロシアの通史が書かれてます。(もちろんロマノフ王朝が記述の中心ですが)
ロシア帝国の専制体制はソビエトや今のプーチン政権の底流にも流れているなぁと感じた
通史として満足。
2017/01/15 18:39
2人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:わびすけ - この投稿者のレビュー一覧を見る
ソ連関係が駆け足で物足りなかったが、ロシア史入門としては満足な一冊。シベリアはこれまでネガティブなイメージで見てきたが、ロシアの人々にとっては、夢の新天地だったというのは新鮮な視点を教えていただきました。
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ぽぽ - この投稿者のレビュー一覧を見る
ロシアのロマノフ王朝時代を知ることができます。文章は、けっこう長めになっていますが興味深く読ませていただきました。
投稿元:
レビューを見る
・ロシアとモンゴルの深いつながりが理解できた。
・広大な土地という地理的条件が歴史を作ってきたのだと感じた。日本の歴史とは全く違う足取りに驚いた。
・人口が何度も激減するさまが凄まじかった。
・ツァーリという専制的な君主が統治し、彼らによってロシアの命運が左右されていたのが面白い。日本の歴史にはそのような圧倒的な権力が存在しなかったのではないか。
・ロシアが多民族国家であるという認識が深まった。
【全体的な感想】
歴代の専制君主の人物像や思想へも記述が豊富で、統治者の視点で(当事者意識を持って)歴史を見ることができる優れた本だと感じました。
投稿元:
レビューを見る
ヨーロッパとアジアの間で、皇帝たちは揺れ続けた。民衆の期待に応えて「よきツァーリ」たらんと奮闘したロマノフ家の群像と、その継承国家・ソ連邦の七四年間を含む、広大無辺を誇る多民族国家の通史。
ロシア旅行の予習本。タイトル通り、通史とは言いつつもロマノフ王朝にかなり重点が置かれた構成ですが、面白かった!各ツァーリたちの特色や性格が分かって、歴史の流れをざっとつかむにはいい本です。途中長くて心折れそうになりましたが、、。近代史ももっと勉強したいな!観光しながらあの皇帝か~とか色々思い出して楽しめたので良かった。
投稿元:
レビューを見る
中性のロシア農民は移転の権利を持つ自由身分であったが、中小封地を持つ士族が搾取すると農民たちはより魅力的な大地主の貴族の封地に逃亡した。多数の士族の要求により逃亡農民の捜索期限が撤廃され、農奴制が確立した。
後世ロシア農民は人口増加に対して、新しい豊かな土地に移り住み旧来の粗放農業を続けることで対応した。ロシアに農業革命が生まれなかった所以である。
ピョートル大帝は変革の方向に乗り、最も強硬な案で上からの改革を断行した。教会勢力すら自らのその傘下に納めた。ツァーリ専制という独裁システムは以後のロシア史で度々登場しまた求められていく。
投稿元:
レビューを見る
ロシア。イメージが沸かない。
世界史を勉強しなかった40歳代のおっさんだと、ロシアのイメージというと、社会主義、ゴルバチョフ、チェルノブイリ、シャラポワ、ピロシキ。あ、あとマトリョーシカ。ようは散発的なもの以外に包括的なものがない。敢えて言えば、何か暗い、みたいな。
しかし、この本を読んで、おかげでロシアのイメージが少し形づくられたと思う。
講談社学術文庫はどれも値段が張るが、この興亡の世界史シリーズは本当に高い!文庫なのに1,360円!新刊本の値段と同じじゃないですか!若干買うのをためらったが、結果としては非常に面白い本だった。
印象的だった部分を挙げると、皇帝の専制、多数の農奴、オスマンとの領土争い、ヨーロッパの辺境。
皇帝という権力者とその取り巻きによって政治と金が牛耳られる構図はどこも同じなのかもしれないが、各皇帝の話は面白く読めた。特にエカテリーナ二世については事前にHuluで”エカテリーナ”を見ておりそこで見聞きした内容とオーバーラップして勉強できました。ちなみにドラマは愛人との描写が生々しく、子供と見ると大分お互い照れます笑
また農奴の解放と近代化の描写(6章)のあたりは地方の農奴の都市流入、労働力の供給、放蕩、賭事、飲酒、などまさに暗ーいロシア文学の舞台設定(というかこれが事実か)そのものでした。改めてトルストイとかドストエフスキーを読み返したくなりました。
また、社会主義への変革を鮮やかに描いた”王朝なき帝国”(9章)は激しかった。ニコライ二世一家の惨殺やレーニンの半端ない殺戮。妥協とか余地とかを許さない社会主義者の専制は読んでいて悲しくなりました。
そんな中でつらつら読んでいて感じたのは、ロシアと日本との共通性です。皇帝と天皇、ラスプーチンと東郷、農奴解放の貧民層と日本現代社会のニート、急進的社会主義者とネット右翼。単純なインスピレーションですが、日本の現象を理解するのにロシアの歴史の出来事を援用したりできそうな気がしました。
最後に纏めますと、この本は非常に面白く読めました。特に世界史初学者にはおすすめします。
本の主旨はロシア通史の描写であり、これを読んで筆者の意見を受け取るとかそういう話ではありません。しかしながら、ロシアってこんな感じの国で成り立ちなんだと理解する上では非常にいい本だと思います。願わくばもう少し価格が安いと嬉しいけど笑
投稿元:
レビューを見る
ロシアって世界の情勢に大きな影響を与えてる大国ですが、殆どその歴史を勉強したことがないのではないでしょうか?社会主義革命を起こして、世界中を革命の渦に巻き込もうとしていたのに、その理由や背景は何もわかっていない。
戦争と平和とか罪と罰とか世界的な名作を産んだ国土なのだけれど…
ロシアの歴史って面白いですね。
投稿元:
レビューを見る
ウクライナ侵攻を機に手に取った。
これまで中学校の世界史レベルにしか知らなかったロシアの歴史を概観するには、とても良かった。文章も読みやすく、楽しい。
投稿元:
レビューを見る
ヨーロッパの中世史などを読んでいたときに、なかなかロシアが出てこないのが気になっていたので読んでみた。表題のロマノフ王朝を中心にロマノフ王朝が始まる前の時代からソビエトが終わるまでを概観する。最初の疑問に対しては「タタールのくびき」が答えなのだろうと思った。
投稿元:
レビューを見る
先日読んだ『文明の本質』(ルイスダートネル著 河出書房新社)の中にニコライ2世の系譜にかかる記載があり、実は、ロシアの歴史をあまりよく知らないことに今更ながら気づき、本を探したところ、本書にであった。
本書に出会う過程で意外にも、ロシアの歴史に関する本が意外に少ないことに気づく。なぜ?
実際に数えたわけではないが、欧州、アジアの歴史本は数多くあるが、ロシアの歴史本は少ない。
その中で、本書はロシアの歴史を実に分かり易く語ってくれる読み応えのあるロシアの通史。現在のロシアを知る上でも一読すべき本だと思う。
講談社学術文庫の「興亡の世界史」シリーズに外れはない!
表紙を飾るのは、エカテリーナ2世。自信に満ちた、余裕の表情が印象的だ。
高校の世界史で、「18世紀後半、エカチェリーナ2世はピョートルの事業を受け継ぎ、南方ではクリミア半島をオスマン帝国から奪い、東方ではオホーツク海まで進出し、日本にも使節ラクスマンをおくった」と紹介されている。なんとなくやり手の女帝程度の認識しかなかった。その人が表紙になっている。
実はこの人、ロシア人ではない。ドイツ人だ。しかも、夫、ピョートル3世からクーデタで権力を奪い女帝になった。普通のドイツの貴族の娘さんが、ロシアの皇帝になったのだから凄くないかい?
だが、この人、ロマノフ朝の女帝としてロシアの近代化に大きく貢献する。在位も34年に及びピョートル大帝と肩を並べる。生涯をロシアの発展のため捧げるといえば聞こえがいいが、政治が好き、政治的能力が高かったといえると思う。
エカテリーナ2世はロマノフ朝に嫁いでから、ロシア語を覚え、ロシアの習慣に溶け込もうとする。
夫のピョートル3世はちょっと変わった人。実はこの人、生まれも育ちもドイツで、ロシアは「異国」で好きではなかったようだ。プロイセンのフリードリヒ大王の熱烈なファンで、軍隊遊びに熱中するなど、精神的にも未熟。また男性機能もなかったようだ。そのため、幸か不幸かエカテリーナ2世は数多くのの愛人がいた。その中には政治的にも深く関わった人もいるという。なんともまあという感じだが、夫婦関係は破綻。
エカテリーナ2世の後継として即位したパーヴェルは、おそらくピョートル3世とエカテリーナ2世の子ではない。ということは、以降のロマノフ朝の皇帝は、ロマノフ家の血筋ではないということになる。
エカテリーナ2世はロマノフ朝を代表する大帝として日本の世界史の教科書に載るなど歴史に名を遺した。その波乱の生涯はまさにドラマになる。
話を変えて
ロマノフ朝は、1613~1917年までの約300年ロシアを統治した。この間の皇帝は18人。
この時代の日本は、江戸時代(1603~1867年)でこの間の将軍15人でほぼ重なり、日本から遠く離れた地で起こったことでもイメージし易いが、その悲劇性は大きく異なると感じた。
300年間続いたロマノフ朝、第一次世界大戦前夜、帝政ロシアは近代化が進み、経済は好調であった。だが、第一開戦後、ロシアの社会と経済が抱える脆弱性があらわになり、結果、ロマノフ朝は���壊する。その悲劇性に儚さを感じる。
その継承国家・ソ連。自分が生まれた時、当然にしてあった大国、ソ連。ソ連と言えば思い出すことは、米国を強く刺激した1957年人類初の人口衛星「スプートニク」の打ち上げ成功。1980年モスクワオリンピックのボイコット等東西冷戦に関わることであるが、いずれにせよ米国と比肩する大国のイメージ。その大国が、僅か74年で崩壊したことを思うと、ここにも儚さを感じる。
クリミア戦争。
ロシアの南下政策は、中近東とバルカン半島に影響力を確保しようとしていたイギリス、フランス等の列強の反発を招き、1853年開戦に至る。ロシアはこの戦争で敗北するとともに、戦争中にニコライは病死する。この戦争はロシア兵が50万人が戦死した悲惨な戦争であった。