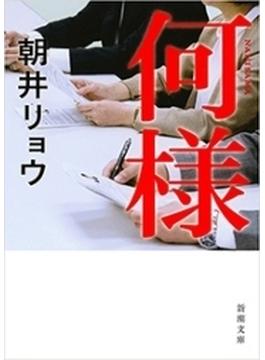1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:イシカミハサミ - この投稿者のレビュー一覧を見る
何者スピンオフ、という言い方が正しいかはわからないけれど、
かの作品に出ていた人たちの持っている物語集。
表題作「何様」は
結局どこに向かうのかピンとこなかったけれど、
そのほかはそれぞれ朝井リョウの持つ筆力が存分に出ている作品だと思う。
「何者」からのつながりを意識していると
1作目の「水曜日の南階段はきれい」はなかなか意表を突かれる。
「逆算」のおふたりはさそり座とてんびん座。
相性はとてもいいですよ。
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:おどおどさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
まだ読んでいないが、アナザーストーリーならば、こっちから読んでも良さそうですね!解説がオードリー若林さんなのも楽しみ。
どういう視線で解説してくれているのか。映画→解説→何様→何者とか色々順序変えて読んでも面白そうだ。
自分の悩みを人にいうのに勇気が必要だったのは、
2022/07/30 17:47
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:びずん - この投稿者のレビュー一覧を見る
どうしてだろうか。環境のせいか、親のせいか、人間関係のトラウマのせいか。二十歳前後の人だけの悩める心情ではない。結構多くの大人たちも、仕事をしながらも自分の存在が周囲からどうみられているのか気にしながら生きているはずだ。だけどやっぱり最後は、そういう場面で自分から逃げないで、誰かや何かのせいにしたりしないで自分のせいにしてしまえた時、とても強くなれるよ。評価される自分を恐れるな。強くなれ。
『何者』のスピンオフ短編集
2020/05/09 10:05
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:makiko - この投稿者のレビュー一覧を見る
『何者』が衝撃的だったので、『何様』も読みました。『何者』の登場人物が少しずつ関与している短編集。直視したくない人間の醜い感情を抉り出すけれど、決して冷たくない目線で書かれています。筆者は人間の醜い面に気づきつつも、それを他人事としてあげつらって非難するのではなく、自分もそうであるという自覚と謙虚さをもっておられるのかなと思いました。
長い間読めなかった
2022/11/28 15:27
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:もの - この投稿者のレビュー一覧を見る
だいぶ前に読んだ何者に衝撃を受けたのを覚えていて、こちらのスピンオフも読んでみようと思いましたが途中で負の感情に負けてしまいました。
私には共感できませんでしたがどこかにいそうな若者たちの成長に伴う痛みやどろどろとした感情が渦巻いていました。
投稿元:
レビューを見る
I LOVE IT and wonderfull
---------------------------------
https://www.targetedwebtraffic.com
投稿元:
レビューを見る
生きるとは、何者かになったつもりの自分に裏切られ続けることだ。直木賞受賞作『何者』に潜む謎がいま明かされる―。光太郎の初恋の相手とは誰なのか。理香と隆良の出会いは。社会人になったサワ先輩。烏丸ギンジの現在。瑞月の父親に起こった出来事。拓人とともにネット通販会社の面接を受けた学生のその後。就活の先にある人生の発見と考察を描く6編!
投稿元:
レビューを見る
最近何者を読んでいれば、とても入ってくる作品。1話はすごく感動したが、その他はほどほど。ただ、何者もそうだったが、人ってこんな事思ってるなっていう心境がうまく書かれているので、思わずニヤついてしまう。
投稿元:
レビューを見る
本書は6つの短編ストーリーから成り立っています。そのそれぞれは時間軸も登場人物も終わり方も違っていたので、1冊で6つの味が楽しめました。
本当に全て全く異なる結末になり、ハッピーエンドもあればバットエンドもありました。そして本書の特徴だと私が感じたのは、ハッピーエンドもバットエンドも自分の人生に起きてもおかしくないリアルな悩みだったことです。そういった意味ではホラー小説よりも「怖さ」はないですが「恐ろしさ」は高く感じました。
本書を読むにあたり「しまった!」と思ったことがありました。それは登場人物の境遇がわからなくなったことです。本書は「何者」の続編であり、本書の登場人物の境遇がわかるとより楽しめます。
最初の3編まではメインの登場人物なので伏線回収を楽しめましたが4編は瑞月の父が登場し、最後に至っては拓也の面接にいた人です。もはや最後は解説を読まないと誰が主人公になっているか、わかりませんでした。
投稿元:
レビューを見る
『何様』
普通に読み物として面白かったが、読み終わった後に、再度朝井リョウの『何者』のあらすじを確認すると、点と点が繋がってなお面白かった。特に、「逆算」というストーリーは、3年前のクリスマスにヨーロッパで読んでいた『Xmasストーリーズ』という複数の作者によるクリスマスをテーマにした短編のオムニバス小説で一度読んだことがあり、登場人物の沢渡さんが、『何者』のサワ先輩だったとわかり、合点した。
タイトルにもなっている「何様」は、就活を終えて、新卒一年目で人事となった新社会人の葛藤を描く面白いストーリーだった。自分に、人を評価するだけのものが備わっているのか、それがわからないままに、面接で人を評価することへの葛藤は、新卒二年目の自分にはわかりやすい。最後に、その葛藤が晴れる一歩となる「本気の一秒」という考え方が面白かった。葛藤を抱えながら、自分の職務を全うすることに対して、不誠実と感じていた主人公は、憧れる先輩もその葛藤に苦しみつつも、どこかで本気で成し遂げたいと思う「本気の一秒」があるから頑張れると知る。100%の誠実さ、100%そのころを成し遂げたい、自信がある状態なんてほとんどない。もやもやを抱えて、人は自分の役に向きあう。不誠実ななかで乗り越えていった無数の仕事の中にも「本気の一秒」はあった。その本気の一秒も、誠実への一歩目も、誠実のうちに入れてあげること。この考え方はある種楽天的だが、胸に響いた。
投稿元:
レビューを見る
『何者』の続編。とはいえ、同作の内容は殆ど覚えていないので、登場人物が共通していることさえ気づかず、普通に仕事モノの短編集として楽しませてもらいました。そう、本作だけでも十分楽しめた、ってこと。『何者』では確か、結構どす黒い内面まで描かれていたと思ったけど、本作はだいぶカラッとしている。同じ系統を求める向きには拍子抜けかも知らんけど、でも同じことを書いても仕方ないし、多方面からのものの見方を提示する点で、短編集ということも合わせ、本作は概ね成功しているのではないか、と。それに、ときどきハッとするような美しい描写、素敵文章に出会えるのも良い。
投稿元:
レビューを見る
「何者」と続けて読めばよかった…。
痛い、かもしれない。
でもなぜ痛くちゃいけないの?
懸命にやっていくことを、若林さんの言葉を借りて
「絶対に笑わない」
投稿元:
レビューを見る
時に目が眩むほどの眩しい青春小説を書いたかと思えば、登場人物(読者)のライフをゼロにするような話も書く朝井さん。
直木賞を受賞した『何者』のアナザーストーリーとなるこの短編集では、そんな朝井さんの表も裏も味わえると思います。
以下、印象的だった作品の感想を。
最初に収録されている「水曜日の南階段はきれい」
『何者』の中心人物だった一人、光太郎の高校時代の話です。
この光太郎『何者』では、就活の際ある業界へ就職を決めるのですが、その理由のより深いところが明らかになる短編です。
これを読み終えたときに、僕が抱いた感情は、金曜ロードショーで『耳をすませば』を観た後に近いものがありました(笑)
恋愛ものって一歩間違えると、鼻で嗤いたくなるようなものもあったりしますが、この作品の瑞々しさ、煌めきはいったい何なんだ!?
『何者』ではそんな理由で、就職を選ぶのか。と思わなくもなかったのですが、こんなことやられてたら、そりゃあその業界選ぶわなあ、と思わず納得。
でも、夕子ちゃんはいい子だけど罪な女だなあ、とも心のどこかで思ったりもします(笑)
朝井さんの毒と罠で印象的なのは「それでは二人組をつくってください」
『何者』に通じるどんでん返し! そこから明らかになるのは、登場人物の歪んだ感情であり、想像力の欠如でもあります。
こんなに登場人物をカッコ悪いというか、滑稽な状況に追い込むどんでん返しはなかなか思い浮かびません。
それでいて、人間の本質的な嫌な部分をこれでもかと照射するのは、ある意味見事というしかないです。朝井さん恐ろしや…
朝井さんのシニカルな物の見方は、ときに面白くもあります。
上記した『それでは二人組をつくってください』で描かれるテラスハウス風の番組への見方も面白いのですが、「君だけの絶対」の見方は思わず笑ってしまいました。
主人公は部活が休みだった放課後に、演劇部の劇を見に行きます。その劇は部活を通して成長する、高校生の群像劇でした。
そしてカーテンコールで「人間関係に疲れた人たちの背中を押したいと思って稽古をした」と演劇部の部長は話すのですが、それに対し主人公はこう思います。
『だけど、それを観ているのは、放課後の時間を自由に使うことができる人たち――つまり、部活でのトラブルをきっかけに成長しえない人たちばかりだった』pp219-220
……こんなことを書けるのは、朝井さんくらいしかいないのではないでしょうか(笑) あまりに身も蓋も無い…
でも、こうした見方って実は全ての創作物に、当てはまることだとも思うのです。もちろん朝井さん自身の著作にも。
だからこそこんな冷めた主人公は、最後何を思うのか、気になりました。
読者に想像を委ねる雰囲気の結末だったのですが、読み心地は決して悪くないです。その理由は、こうしたシニカルな見方も、もちろんあるのですが、それはあくまで一つの見方でしかありません。
創作��から受けとるものを、無価値だと思う人もいれば、それを心に刻み込んでくれる人もいる。また、時が経てば見方が変わることもある。
語り手はそのことを最後にうすぼんやりながらも、感覚として気がついたと思うからなのです。
そして、様々な見方があることは、創作者にとっての希望でもあるのではないでしょうか。この短編はすべての創作する人に対する、応援の話でもあるように思います。
そして表題作『何様』
これも朝井さんのシニカルな目線がうかがえます。
分かったような口を利き、就活生をふるいにかける人事部の人たち。真面目に撮影した終戦記念のドラマを、バラエティ番組でおちゃらけた後に宣伝する俳優。つい数年前まで学生だったのに、編集者になったとたん専門用語を使う、かつての友人…
それは一見すると、とんでもなくダサいことにように思ってしまいます。しかしそのダサさの意味が物語の最後に一変するのです!
100%じゃなくたって構わない。
一瞬、一秒の気持ちも認めてあげてもいい。
生きることのカッコ悪さに悩む全ての人に、読んでほしい短編だと思いました。
投稿元:
レビューを見る
何者をほとんど忘れてしまっている(というのは語弊があるんですが)ので、短編集として楽しみました。このあと何者を読み返そうかな。
いやもうほんと……安定の朝井さん……日常にあるじくじくとした、特筆するほどでもないが自分に引っかかっている瑣末な事象に対する「どうして引っかかるか」の言語化がとっても上手でっていうかなんかもうシャープでえぐるえぐる私の心を。
投稿元:
レビューを見る
帯の「何者」に潜む謎がいま明かされるという言葉が気になり購入しました。
読んでみて最後の「何様」以外は「何者」とは全く別の話と捉えたほうがいいと思います。
6篇に分かれている中で特に「何様」が面白いと感じました。就活生が社会人になると感じることがスムーズに伝わってきました。
印象的な文章
・仕事ができる能力、は、目に見えない。
・就活生のころは、自分も、例えば語学力やプレゼン能力のような、たった一言で伝わるわかりやすい能力を駆使しているのが社会人だと思っていた。だが、目に見えるわかりやすい能力を発揮する場なんて、社会人生活の中では、ほんの一瞬しかない。
社会人一年目後半や二年目になりたての仕事のことが分かって来だした人に特にお勧めできる本だと思います。