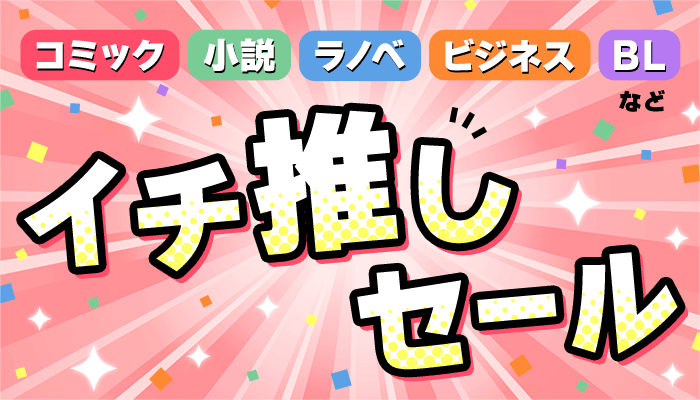- 販売開始日: 2021/04/21
- 出版社: 河出書房新社
- ISBN:978-4-309-02962-7
一度きりの大泉の話
著者 萩尾望都
12万字書き下ろし。未発表スケッチ多数収録。出会いと別れの"大泉時代"を、現在の心境もこめて綴った70年代回想録。「ちょっと暗めの部分もあるお話 ―― 日記というか記録で...
一度きりの大泉の話
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
商品説明
12万字書き下ろし。未発表スケッチ多数収録。
出会いと別れの"大泉時代"を、現在の心境もこめて綴った70年代回想録。
「ちょっと暗めの部分もあるお話 ―― 日記というか記録です。
人生にはいろんな出会いがあります。
これは私の出会った方との交友が失われた人間関係失敗談です」
――私は一切を忘れて考えないようにしてきました。考えると苦しいし、眠れず食べられず目が見えず、体調不良になるからです。忘れれば呼吸ができました。体を動かし仕事もできました。前に進めました。
これはプライベートなことなので、いろいろ聞かれたくなくて、私は田舎に引っ越した本当の理由については、編集者に対しても、友人に対しても、誰に対しても、ずっと沈黙をしてきました。ただ忘れてコツコツと仕事を続けました。そして年月が過ぎました。静かに過ぎるはずでした。
しかし今回は、その当時の大泉のこと、ずっと沈黙していた理由や、お別れした経緯などを初めてお話しようと思います。
(「前書き」より)
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
小分け商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この商品の他ラインナップ
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
むき出しの心で作品を描いていた人の話
2021/05/02 14:15
26人中、26人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:gonta - この投稿者のレビュー一覧を見る
24年組と呼ばれる少女漫画家たちの作品が大好きで、その中でも萩尾望都には思い入れが強かった。有名な大泉サロンについて、うっすらと知っていたけれどそのことに萩尾さんが言及するのか、面白そうだなと購入。
しかし前書きから衝撃を受け、その後読み進めていくと自分がふんわりとしたイメージで好きだと思っていたあの時代の漫画家たちの苦悩と衝突が描かれており、読み終わった後も大きな衝撃と混乱で頭が回らなくなった。
萩尾さんがこの本を出さなければいけなかった経緯や、萩尾さんの作品が繊細な感情がむき出しになって表現されていたこと、すべてがつらく苦しいもののように感じられた。ただ萩尾さんが数々の素晴らしい作品を発表し、読者としてそれに出会えたことに感謝しかない。
萩尾さんが漫画を愛し続けられますように、彼女の作品がこれからも人々に読まれますように。
天才と秀才
2021/05/08 18:21
20人中、20人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:タロウとハナ - この投稿者のレビュー一覧を見る
映画のアマデウスのモーツァルトとサリエリを連想しました。天才のモーツァルトが秀才のサリエリの嫉妬を理解できなかったのと同様に、天才の萩尾望都さんには、秀才の竹宮さんの嫉妬が理解できなかったのかもしれないと考えました。彼女の一部は言葉と言う毒によって殺されてしまったが、モーツァルトとは異なり彼女は、再生して作品を生み出すことが出来たのだと思いました。13歳で萩尾望都さんに出会い、救われた私は還暦を過ぎて、魂の救済が出来る作品を生み出す芸術家を天才と言うのだと思っています。
萩尾望都さんが生きている間は、萩尾望都さんの心がこれ以上傷つかない様に、周囲が静かになる事を祈り、彼女の作品の恩恵に預かりたいと思っています。
お疲れさまでした
2021/04/24 17:57
38人中、14人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:pope - この投稿者のレビュー一覧を見る
ネタばれあり。
竹宮先生から絶縁を告げられた後ここまでひどい打ちのめされ方をして心身に不調が出ていたとは・・・
萩尾さんが戦っていたのはマンガ界ではなかったから竹宮先生・増山氏と合わないのは当然だよな。
盗作疑惑を投げかけられたり、絶縁の手紙渡されたときにきちんと自分の言い分を言えれば良かったのかもしれないけど、ショックの方が大きくて何も言えなかったというのも理解できる。
少女漫画革命の使命的なものを(勝手に)背負っている竹宮先生が何で似たようなシチュエーションで描いてくれてんだよっていうところまでは20代だし若気の至りと言えるけど、その後の著作ポンと送り付けとか大泉サロンの企画の承諾は萩尾先生次第みたいな投げ方は大人のやることではないと思う。
それにしても腐女子の布教のウザさは50年前から変わらずw
どんなに月日が過ぎても
2021/05/05 18:16
12人中、12人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:はとぽ。 - この投稿者のレビュー一覧を見る
そしてどんなに才能があっても。
いや、才能があるからこそ。
テーマが似通ってしまったところに思いもしない評価がおきてしまうことがあるのかも。
そういえば、昔は「暖炉」と「11月のギムナジウム」はご本人たちは同じテーマを選んだのだと思ったことを思い出しました。
それが実は違っていたのかもと今になって思いましたが、萩尾さんが相手にそう思われた時期は解った気がしました。
なにもそこまでしなくても、と思いはしましたが、才能があって考えもしなかったことを責められたら個人の創作作家としての矜持ゆえにすべてを消してこられたのでしょうね。
かたや竹宮さんもそうなんじゃないかと思ってしまったこともなんとなくわかります。
ただの読者のわたしがあのあたりの作品を似ていると思っていましたから。
でもわたしはその当時同じテーマで描けるということがすばらしいことだと思っていましたけれども。
そうなってしまったふたり、の、どちらも感情的にわかる、大泉時代のお話しはとても興味深く読み終えました。そしてMさんがいなければまた事情は違ったのかなあとも。
それにしても今回も同時期に本が出るあたりがこれは出版社さんの都合なんでしょうか、ご本人たちのご都合なんでしょうか。
面白いことだなあと思いました。
どこまで書いてていいのかわからなくて、中途半端な感想です。
でも、わたしには必要な本でした。
萩尾望都先生の心の叫び
2021/10/29 07:12
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mako - この投稿者のレビュー一覧を見る
大好きな萩尾望都先生のご飯、という事で予約して手に入れた一冊。
読み進めて行くうちに、手が震える思いがした。
これは単なるエッセイでは無い。
萩尾望都先生が、ちをながしながらさけんでおられる、そうかんじた。
途中で読むのをやめる事ができず、一気に最後まで読み切った。
淡々とした語り口調、優しい言葉遣い、時折挟まるユーモア、その中に垣間見える黒く深い悲しみと、ある意味呪詛に近い思いが、ひしひしと伝わってくる一冊だ。
完全武装の拒絶の書
2022/09/06 11:59
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:るう - この投稿者のレビュー一覧を見る
全身を鋼鉄の鎧で包み持てるだけの武器を持って威嚇している女性の姿が目に浮かぶ一冊。
しかもその女性は泣いている。
これは萩尾望都先生と友人の決別を語った本である。
かつて友人たる竹宮惠子先生と増山法恵女史との交流は少女漫画史そのもので興味深い。
漫画を描いている事を親に反対された萩尾先生は竹宮先生による同居の提案や編集者を紹介してもらって感謝していた。
その教養を惜しみなく注いでくれた増山女史に敬意を持っていた。
そんな二人に盗作扱いされたショックはいかばかりののものか。
距離を取ろうと言われた衝撃は?
この場面、親に否定されて次は漫画仲間から否定された絶望がページに塗り込められているようだった。
時は流れ半世紀。
竹宮先生は筆を置き、増山女史は逝去した。
竹宮先生からの「もうこんなに時間が経ったのだから昔の事は水に流しましょう」という搦手からのアプローチ。
この本はそれに対する返答そのもの。
よりによって搦手から行くとは。
あんなにクレバーな竹宮先生が萩尾先生への対処に限ってことごとく地雷を踏んでいるあたりに根深いなにかが垣間見える。
この本を出版する経緯にはため息しか出ない。
世の中には善意の衣を被った傲慢な魑魅魍魎がいっぱい。
「一度きりの大泉の話」が世に出た事で萩尾先生がそんな化け物たちから開放されますように。
それを願うばかり。
賞賛と、同じだけの嫉妬と
2021/09/09 03:38
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ニックネーム - この投稿者のレビュー一覧を見る
まず、信頼する映画監督に頼んで自身をインタビューしてもらい、それをもとに一人称の語りに纏めるという形をとっている。そのためか、一貫して平易な話し言葉で綴られ、初めはその厚みにたじろぎながら、一気に読み終えてしまった。
人間、マスコミで仕事でもしていなければ、天才と近く関わる機会というのはそうない。自分もそのように生涯を終える筈が、偶々、芸術とスポーツの狭間にある分野で世界一に輝いた人間を直接知って教えられたのは、彼等は自己と戦い、そして否応なく周囲の嫉妬とも戦わざるを得ないのだということだった。世界は嫉妬で動いている。
本書が出版されたと知って、急に甦った記憶がある。80年代前半の、自分が高校生の頃、絵のうまい同級生が、萩尾望都と生年の近い少女マンガの巨匠の元にアシスタントに行った。その同級生から聞かされたのが、「萩尾望都先生は、他の作家が取り上げた素材を自分も取り上げ、その作家よりも見事な作品を生み出してしまうと煙たがられている」という話だった。
雇い主の先生なのか、アシ仲間なのか、誰が直接話したかは定かではないが、当時そういう空気が少女マンガ界にあったのだろう。
本書で萩尾望都は言う。『嫉妬という感情についてよくわからないのよ』「スポーツなどの勝負事なら、うまい人に嫉妬するのもあるでしょう。バレエや舞台のように主役が一人だけなら、ライバルに嫉妬というのもわかります。だけど創作表現の世界、漫画などはたくさん発表の場があるし、競争や勝敗はなく誰でも好きなことができると思っていたので、ピンとこなかったのです。」
萩尾望都のような天才と比べるのも烏滸がましいが、小学一年生の頃、隣家の小学二年生がピアノを習い始め、以前から習っていた私に「負かしてやる」と言った。私は母親に「かけっこでもないのに勝ち負けってあるの?」と、真顔で聞いたそうだ。生まれてこの方サンタクロースを信じたこともない、ませた子供だった私がカマトトでそんなことを言う訳もなく、まさに隣家のガキのイキりぶりが「ピンとこなかった」のだ。誰かに勝つことは自分に何の高揚ももたらさなかったし、誰かに負けたら自分の価値が損なわれるとも思わなかった。
萩尾望都は嫉妬という感情がわからないというより、マンガで人と競おうという気が無かったのではないかと思う。読者アンケートの順位という、ある種の勝敗を常に突き付けられながらも、それは発表の場を失わずに済めばいいという意味での気がかりで、そうと意識せずとも、自分の生み出すものへの揺るぎない肯定が根本にあったのではと思う。
あらゆる雑音を跳ね除けて、数々の傑作を生み出してきた作家は、何よりも大切にしてきた作品を、嘗て面と向かって剽窃だと糾弾する意味のことを言ったという同業者との間に、和解はないと本書で明言した。
そんな萩尾望都は繊細か?未熟か?こういう話は若気の至りと言うべきもので、許さないのは大人気ないか?いや、賞賛と同じだけの嫉妬から、作品を、オリジナリティを、自身を、ここまで守り続けてきたその態度を、本書を世に出して波風を立てても決然と貫き通すことを選んだ萩尾望都は、作家として天晴れだと思う。
あの作品は好き、これはさほどでも…と、ファンとまでは言えない読者だったが、作家本人に共感を覚えて、旧作を読み返したくなった。
モト先生にエールを
2022/05/14 23:10
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:こゆき - この投稿者のレビュー一覧を見る
萩尾望都先生といえば自分が生まれたときにはすでに大先生だったので、若い頃はこんなことがあって苦しんでいたとは、と衝撃を受けました。しかし大先生になっていらっしゃるゆえに、このようなことがあった、と公表しなければ今後のまんが史に影響が出るので、出版されたことは歴史的な意義があると思いました。(相手方の方の著作は読んだことが無いですけど。)
ご本人には辛いことだったと思いますが、辛い話ばかりではなく、仲良しの大先生方との楽しいお話が読めたのが良かったです!
モト先生が読者アンケートで人気を得るために、アンケート上位の木原敏江先生にコツを聞いたら、キャラのまつげと花の増量をアドバイスされたという話が好きです。「たしかに木原先生の睫毛は力強い」……いや絵柄的に無理がありませんか!?(笑)
まるで昨日の事のような語り口
2021/07/23 13:23
4人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:フカフカ - この投稿者のレビュー一覧を見る
本棚をひっくり返しながら読了。
当時の萩尾先生の気持ちがひしひしと伝わってくる内容に一喜一憂しました。 やむを得ない出版にも関わらず読み応えある作品に仕上げられた萩尾先生のプロ意識に感服します。 今までに楽しんだ作品もバックボーンを知ることで、もう一度じっくり読み返す機会が持てました。 永久に凍結したくなるほどの思い出や長年の不安があることを読者に教えてくれて感謝です。この出版をきっかけに萩尾先生が気兼ねなく創作活動に励めるように願います。
すごい
2021/04/24 00:43
5人中、4人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:はち - この投稿者のレビュー一覧を見る
一気に読みました。4時間近くかかりましたがあっという間でした。スケッチの絵、美しかったです。
難しいのは人の繋がり
2022/09/07 22:42
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:るう - この投稿者のレビュー一覧を見る
図書館でこの本を読んで衝撃を受けたので電子版を購入。
始まりはどこだったのか?
萩尾先生が福岡で漫画好きな事を両親から否定され続けたことか。
増山女史が親にピアニストになってほしいと望まれたことか。
二人共逃げ場が欲しかったことか。
女性に面と向かって「男は女よりえらいんだよ」なんて言う男がいた時代である。
窮屈な思いをしていたお二方は少年を自由の象徴として仰ぎ見た。
増山女史はそこにエロスを見て、萩尾先生は見なかった。
萩尾先生はなんでも理解してくれる双子のきょうだいが欲しいと思った。
萩尾先生が引き合わせた増山女史と竹宮先生は魂の双子となって創作に励んだ。
そこから3人の関係は壊れてしまった。なんという皮肉。
佐藤史緒先生の証言も欲しかったが、お亡くなりになったのが惜しい。
親しかった萩尾先生が佐藤先生は静かに息をひきとったそうです等伝聞口調なのに違和感を持ったが、佐藤先生は増山女史とも親しかったそうなので、それであまり踏み込まないのかもしれない。
ブレーキがかかって思うように友人の死を悼めないとしたら切ない。
ご両親についての記述。
生前のご両親は我が子に謝るという発想がそもそも無かったように思った。
そこも萩尾先生の悲しいところ。
山岸凉子先生の口寄せ?で少し救われて良かった。
この一冊で日本少女漫画史。貴重な証言だった。
覆水盆に
2021/10/15 20:53
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:saku_ai - この投稿者のレビュー一覧を見る
とても、興味深い内容でした。このように誠実に説明頂いて納得しない人はいないと思います。
人間関係は難しい
2021/06/30 10:36
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:プロビデンス - この投稿者のレビュー一覧を見る
大泉サロン、なんて知りません、私抜きでやってください、という悲痛な叫び。何度も読み返してしまった。
初めに読んだ時には、五十年前に傷ついてから立ち直ってない、と大変お気の毒に思ったが、その後ジルベールのほうや他の意見をみるにつけ、やはり、竹宮氏にも相応の耐えられない理由があったのだろう、と思うようになった。嫉妬について「ええ、萩尾さんにはわからないと思うわ」というのは、能力の高い者は低い者の気持ちがわからない、という意味ではなく、他人の感情を表情や声音から瞬時に読み取る能力が低い、という意味なのではないかと思うようになった。同居解消の理由として、排他的独占愛侵害を考えているようだが、それ以外にもポイントがあったのでは。言葉柔らかに同居解消を提案された時に、相手の「距離を置きたい」という気持ちに気付いていれば、こんなに心が破れるような事態にはならなかったのではないか。。。その傷の深さは、本当にお気の毒であった。
大泉の2年間のイベントは、この本もジルベールもほぼ同じ。しかし、心象風景が異なる。どちらも少し正しく、どちらも少し異なるのだろう。
考えさせられる話であった。
両先生のご本を先入観無しに読みました
2022/11/26 01:09
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:カンカン - この投稿者のレビュー一覧を見る
数年前、竹宮先生の「少年の名はジルベール」を読みました。
一読しただけなのですが、印象に残っていたのは、間近に萩尾先生という天才がいたことへの苦しさ。
竹宮先生も天才だと思います。(名作の数々、読んでいますし作品として好きです)それでも、他者に対する葛藤はあるんだなあ、と思いました。
そして「一度きり大泉の話」も、今日まで存在を知らず、たまたま購入して読みました。
ビックリ仰天しました。
切なかったのは、別離のあとで、萩尾先生がものすごく体調を崩されたこと。
飄々とマイペースだし、ご自身の世界をもっている先生だけれど、やっぱり上京して初めて同居し、青春のひとときを分かちあった人に、別離の宣言をされたら、こんなにもショックを受けられるのだな・・・
それだけ、かの先生のことが(当時は友達として)好きだったのだろうなあ・・・
と想い切なくなりました。
萩尾先生まったく悪くない。
でも、竹宮先生が「自分がやろうとしていたことをされてしまった」という焦りや怒りを覚えてひどい行動をしてしまった、というのも(道理はないけど気持ちとして)少し分かる。
輝かしい才能がある二人が、傷を負い、一生の別れをせざるをえなかった。そのことが切なかった。
半世紀沈黙をまもってきた萩尾先生、すごいです。
これから周りが静かになって、この出来事を封印し、心おだやかにご自身の創作に専念してくださることを祈ります。
切実な思いから書かれたエッセイ
2022/07/26 04:26
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ねむの木 - この投稿者のレビュー一覧を見る
本書を読了した今、私は二度と“24年組”や“大泉サロン”という言葉を使うことはないだろう
本書は萩尾望都さんの半生を綴ったエッセイである
同時代、同環境について語った本は他にもあり
そのどれが真実なのかなんてことは他人には藪の中なわけで
本書でもって当時の背景をどうこう検証する手段とするような著作ではないと思う
「ずっと語ってこなかったことを、一度だけ語る」
その決断をしなくてはならなくなった経緯(外圧)
いつ、どこで生まれたのか分からないけれど
私程度でも知っている有名なカテゴリー
“花の24年組”
“大泉サロン”
という言葉やそのカテゴリーに含まれる人選などが
萩尾さんの同意なく一人歩きしていったこと
そこに組み込まれることをきっちりお断りしていること
「この件について二度とお話することはありません」という
萩尾先生の決意表明
それが執筆の目的だったのではと推察する
苦しい記憶に向き合い、本書にまとめて下さったことを周囲が重く受け止めて
二度とこの件で煩わせることのないよう願う