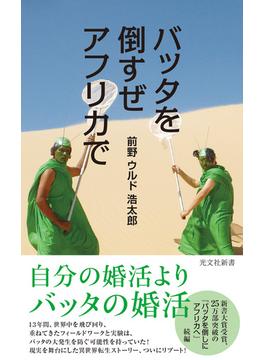バッタの研究に青春を捧げたー昆虫学者のドキュメンタリー
2024/06/23 17:05
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くにさん - この投稿者のレビュー一覧を見る
前作からの続編ということで早速購入しました。
読みながら終始私が感じていたのは、研究者がお金の心配をせずに研究に没頭できれば、短期間にもっとよい成果をあげることができるのではないか、ということである。
ほかにも苦労話を悲観的ではなく、とても面白おかしく読み進めることができました。著者の人柄によるところがおおきいのでは。
この著者がいなければ
2025/02/28 11:44
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:めんだこ - この投稿者のレビュー一覧を見る
バッタになんか一生興味を持つことなく普通に生きていたと思います。いまやこの「これ新書かよ?!」ってサイズの本を読破し、子どもたちにサバクトビバッタとゴミダマについて熱く語るような人格に変わってしまいました。前野先生ありがとう。
サバクトビバッタを愛してやまない昆虫研究者の仕事ぶり
2025/01/01 19:02
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:咲耶子 - この投稿者のレビュー一覧を見る
ウルド先生の研究について、フィールドワークのことや論文のこと、研究者たちを襲った悲劇、そして「音速の貴公子」ティジャニのこと。
いや、学術本にドライバーの事詳細に記載してどうするの?って思ったけど、彼の存在は研究に必要不可欠。学術的に必須アイテム。
夢を追い、研究を面白おかしく紹介するだけでなく、研究者たちが置かれている難しい立場、マスコミの在り方などなど問題点も取り上げられている。
娯楽感あり、知識欲も満たされ、さらに業界の問題点も明らかになる、いろいろ考えさせられる一冊。
楽しく読み切りました。
2024/08/15 14:06
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ら君 - この投稿者のレビュー一覧を見る
分厚くて重くて持ち歩いて読むのはしんどかったけど、読み切りました。
科学的な話題と研究こぼれ話の両方があり、お得です。
ティジャニさんの章が印象的でした。
世界が広がる一冊でした。
2024/08/12 19:47
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:がっきー - この投稿者のレビュー一覧を見る
『バッタを倒すぜアフリカで』は、アフリカでの研究を通じて得られた経験や学びをユーモアを交えて描いた一冊であり、読み手にとっては、異文化体験や自然科学への理解を深める良い機会となります。
著者の情熱や探究心がひしひしと伝わり、読み手に刺激を与える作品です。
一方で、専門性の高さや個人的な視点が強く感じられる部分もあるため、読み手によっては評価が分かれるかもしれません。
それでも、異なる世界を垣間見ることで、日常の視野を広げるきっかけになる一冊であることは間違いないです!
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:しゅんじ - この投稿者のレビュー一覧を見る
をを、研究が進展している。論文も受理されたんだ、良かったあ。でも今回も苦労しているなあ。若いので仕方ないけど、海外の友人に大金を任せたり高額の寄付をしたり、ハラハラしてしまう。でも結果として幸せになっているようで、素晴らしい。第三段が書けるよう希望。今度は「研究者が結婚相手に巡り会うまで」かなあ。
投稿元:
レビューを見る
最高でした!!
環境や健康に配慮したバッタ防除に結び付く世界初の発見とは、めちゃくちゃすごい!
それをこんなに解りやすく、ユーモアを交えて笑わせながら読ませるとは、恐るべし…。
前作に続き、サバクトビバッタの繁殖活動の重要な発見に至るまでを、研究のみならず、各国での暮らしや人間模様も交えながら綴られています。
ある仮説についてや、論文が国際ジャーナルに受理されるまでの長きに渡る研究の裏側。
モーリタニア、モロッコ、フランス…と、世界での奮闘とご活躍。灼熱の地でのフィールドワークは過酷すぎて、「よくぞご無事で!」という思い。
新たな事実を見つけ、明らかにすること
研究へのモチベーションの維持
研究を共にする者への心配り
逆境にあっても継続する力
不測の事態への対応力や楽しめる能力
…どれを取ってもすごいと思う。
本書は知的好奇心を満たしてくれますが、ある意味では冒険書のようでもあり、著者の人間的魅力と笑いが溢れていておもしろい。
“あとがき”を含め濃密な内容に感心しきり。
今後の更なるご活躍と続編が楽しみです。
『論文は半永久的に残り、受け継がれ、知の結晶として積み上がっていく。色んな大きさ、形、色があるだろうが、確実に折り重なり、すそ野に、高みに加えられていく。論文は研究の証となり、歴史をつくっていく』
『世界中で、毎日のように発表される多くの論文の一報一報には、研究者一人ひとりのドラマが隠されている。様々な想いが「知」に形を変え、半永久的に受け継がれていく。(中略)よそでは味わえない興奮や感動に全身が痺れ、快感に酔いしれることができるのが研究の醍醐味の一つだ。』
投稿元:
レビューを見る
相変わらず面白い
前作もそうだったが研究の裏側は興味深い
とりあえずバッタ追いかけて面白い現象に出くわし、そこから何を研究しようかと考え始めるのが意外と言うかリアルだと思った
直感的に先に知りたいことがあってそれを追いかけるのかと思ってたが、逆パターンもあるのか
確かに普通に考えて常に魅力的な問いが浮かぶことはないからそれが自然なのか
投稿元:
レビューを見る
2冊目はパワーアップしてる!ティジャニ回、最高でした。もちろん研究内容が一般人にも分かりやすく解説されてて引き込まれるし、海外の人との交流についても読むのが楽しい。
何より苦労が身を結んで本当に良かった。日々頑張って研究してる人たちになんとか貢献したい気持ちになりました。こうやって本を買って、知る事は貢献になるでしょうか。とりあえず、周りの人にはこの本いいよってお薦めしました。
投稿元:
レビューを見る
standing on the shoulders of Giants(巨人の肩の上に立つ)を体現した著者。巨人たちへの感謝と、未来の博士に向けられたメッセージに心を打たれた。ウルドの肩の上に立て!
投稿元:
レビューを見る
4・17→4・19
まえがき
第1章モーリタニア編ーバッタに賭けるー
会心の目撃/バッタ大発生の謎を解くために/違和感の正体/失望の朝/新発見のきっかけ/充電タイム/緊急野外調査/灼熱の台地/データをとらないと研究者として死ぬ/
第2章バッタ学の始まりー
第3章アメリカ編ータッチダウンを決めるを決めるまでー
第4章再びモーリタニア編ーバッタ襲来ー
第5章モロッコ編ーラボを立ち上げ実験をー
第6章フランス編ー男女間のいざこざー
第7章ティジャニ
第8章日本編ー考察力に切れ味を
第9章災厄と魂の論文執筆
第10章結実のとき
あとがき 名前とお礼と挨拶と
参考・引用文献
投稿元:
レビューを見る
エッセイ的なおもしろさはもちろんのこと、研究者として大切なことを学べる書。面白いのでサクサク読めるが、バッタの写真が多数掲載されているので、虫嫌いは気をつけて!
p.484 論文の書き方を指南した教科書は世にたくさん出回っているため、本書では詳しく取り扱わない。その代わり、学校で勉強した教科・科目がいかに論文執筆に役立つか、なんだったら、義務教育は論文を書くためのものだったのかと、感動を覚えた点について記す。
国語:論文は文章力が求められる。論理展開、話の流れに加え、得られた結果がいかに重要であるかをうまくアピールする圧倒的な筆致を有する者は、論文を制することができる。加えて、先行研究を知るために論文を読む必要があるため、読解力は必要不可実である。
実き・早の未適言言としての英蓄ができなければ、醤文を書けないし、読めないし、やってられない。英語が苦手だから理系に進み、研究が楽しくなってきたらあら不思議、下手したら文系よりも英語が必要となる。
社会(地理・歴史・公民):先人が発表した過去の論文を網羅し、取り扱う研究テーマの歴史を知るときに役立つ。また、多くの人々が関心を持つことを把握するバランス感覚も、社会の動向を知ることで得られる。異国で生活するときや外国人と話すときに、相手の国のことを知っていると大変喜んでくれる。
数学:得られたデータを統計解析する際に、基本的な演算(足し算、引き算、掛け算、割り算)
が求められる。一方、高度な数学力が必須となるモデル・シミュレーション使いも存在する。
私は基本的な演算を駆使し、なんとかやっている。
美術:得られた結果を視覚化する際、円グラフ、棒グラフ、散布図など、最も直感的に理解理科:実験する際のアプローチ方法は研究者によって異なる。物理的な計算や、化学分析、生物一般(行動観察や測定)、遺伝子解析、分子生物学など、調査方法に研究者の色が出る。しやすいグラフを導き出す美的センスが求められる。白黒(モノクロ)が基本ではあるが、孤独相は緑色、群生相は黒色で表すなど、カラフルに色分けすることで、説明文を読まずとも読者の直観的な理解を手助けすることができる。グラフの見せ方も重要だ。イラストが一つ入っているだけで、わかりやすくなるし、なんだかなごむ。プレゼンする際のデザインがオシャレだったり、わかりやすかったりするとすごく良い(研究者が手掛けた魅せるプレゼン資料作成ノウハウがぎっしり:高橋佑磨・片山なつ著『伝わるデザインの基本」技術評論社)。
遺伝子や分子を扱う際には、その道の作法が必要だ。私は大変不慣れのため、解説は他を当たられたし。
体育:研究は体力勝負になる。長時間、論文と向き合うためには健康が必。知力、体力、気力の三点が揃ってようやく前に進める。
図工:論文執筆の前段階である実験で、実験道具を工夫する際に大活躍。
倫理:人のデータをパクったり、データを捏造したり、誰かを傷つけたりなど、してはいけないことを把握するために倫理観は絶対に必要。とくに生命を扱う場合、倫理的配慮が不可
穴だし、採集禁止エリアから虫を捕獲してくる���ど違法行為をしてデータをとることは許されない。社会のルールの範囲内で研究をする必要があることを自覚する上で、倫理感は必気である。
家庭科:生活力が身に付き、世界のどこでも生きていけるようになる。
道徳:人に優しくできる。
投稿元:
レビューを見る
『バッタを倒しにアフリカへ』後の研究はどうなったのか気になっていたので続編が読めて嬉しい。
論文発表までの実験研究過程がユニークに綴られていてその間の困難も悲壮感がなくて軽やかに楽しく読ませてくれる文才が凄い。面白かった!
10年間続けた研究への情熱も伝わってきて著者の言う通り、最後はハッピーエンドなのも良かった。
今後も気になるのでまた本を出してほしいと願う。
投稿元:
レビューを見る
ヤバい。
もし自分が10代前半くらいのときにこの本があって読んでしまっていたら、分もわきまえずに人生の道を踏み違え、バッタ博士をめざそうとしたかもしれない
ヤバい、ヤバい。それくらいヤバい
凡人の想像を超える困難に、凡人の想像を超える努力で打ち克ってきたであろう著者が、極めて明るく語る名著
投稿元:
レビューを見る
著者の前野ウルド浩太郎博士が、アフリカの研究体験記を書籍に纏めている。
著者自身の体験談が大変面白く書かれているだけでなく、研究するためにどのようなことに困ってどう乗り越えたかを事細かに記載していて、臨場感持って楽しく読めた。
体験記がコミカルに描かれていて、とても面白かった。