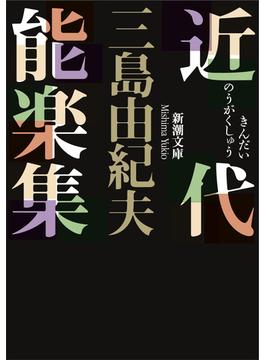「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
収録作品一覧
| 邯鄲 | 7-56 | |
|---|---|---|
| 綾の鼓 | 57-92 | |
| 卒塔婆小町 | 93-118 |
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
青春時代の特権とは?
2006/10/14 05:46
5人中、5人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:くにたち蟄居日記 - この投稿者のレビュー一覧を見る
高校時代の校内行事に演劇コンクールがあった。学年8クラスを4チームにわけて 4ヶ月程度稽古をした上で コンクールで出来映えを競うものである。「青春時代」だけに 演劇だけでは終わらず 恋愛やら人生論やら 青臭いもので満ち満ちてしまうのはしょうがない。高校の夏休みは そんなもので費えてしまうのが 23年前の日々だった。
*
そんなコンクールで取り上げられたのが 本作の「邯鄲」であり それを見ていて 三島の演劇に興味を感じ 本作を手にとった。*
基本的には各作品ともに一時間程度の一幕ものであり 切れ味のよさは抜群である。題材を能にとりながら 上手に現代に翻案する手際は際立っており 題材のテーマと (当時の)現代の精神の融合には舌を巻く。三島は演劇に その才能が最大に有ったと聞いたことがあるが なるほどと思わせるものがある。
*
1980年代初頭の高校生には ちょっと難しかったはずである。41歳になった小生は 今はそう思う。但し あの頃はそうは思わなかった。難しいことに 分かった顔をして立ち向かうのも 青春時代の特権である。
紙の本
いいですね
2023/04/30 20:09
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:a - この投稿者のレビュー一覧を見る
能の筋を三島由紀夫が現代劇の脚本に焼き直したものです。単なる現代語訳ではなく、三島なりの解釈によって、変えてある作品もあります。
紙の本
近代能楽集
2021/12/07 07:32
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:雄ヤギ - この投稿者のレビュー一覧を見る
現代を舞台に能を翻案したもの。個人的には「弱法師」がよかった。
盲目の少年を生みの親と育ての親が取り合うが、双方共に少年に振り回される。少年は空襲で失明し、空襲で聞いた言葉にならない声(悲鳴)を人間の本当の声と悟り、その本当の声しか聞きたくないと言う。普通空襲のような悲惨な目に会うとそれがトラウマになって目を背けたくなると思うが、あえてそれしか聞きたくないという点が普通と違っている点だろうと思う。解説にもあるとおり、誰からも愛される少年が誰よりも孤独だというのがまた良い・
紙の本
能の普遍性を現代モノに翻案する三島ならではの戯曲集
2006/11/26 22:43
6人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ドン・キホーテ - この投稿者のレビュー一覧を見る
能楽に造詣の深い三島由紀夫がまとめた8編の戯曲集である。戯曲集といっても能楽に原作を求めて、その原作の味を生かした戯曲である。原作とは、邯鄲、綾の鼓、卒塔婆小町、葵上(あおいのうえ)、班女(はんじょ)、道成寺(どうじょうじ)、熊野(ゆや)、弱法師(よろぼし)の8編である。
これらの作品は一つを除いて実際に上演されたことがあるという。海外でも上演されて好評を得たそうである。能楽の芝居としての筋書きは、オペラなどでもそうであるが、それほど複雑なものはなく、むしろ簡潔で分かりやすい。ただし、そのまま受け入れられる分かりやすさではない。
幽玄こそが観阿弥、世阿弥が追究したテーマであるので、登場人物には霊がよく登場するし、そのために面を付けてくるわけである。どの作品も原作の香りが漂う傑作であると思う。けっして原作そのものを現代風にアレンジしただけではないし、それを目的ともしていない。
むしろ、全く別の作品であるが、原作の香りの濃淡はあるものの、読み手としてはその香りをどの程度嗅げるかが楽しみの一つであろう。現代劇ではあるが、昭和31年に発表されたものなので、それ自体が相当な古さを感じさせる。現代風というよりは昔風の懐かしさのある時代背景を感じさせるのである。
巻末に三島本人の昭和31年当時のメモとドナルド・キーンの昭和43年当時の解説が掲載されている。これも随分興味深い解説である。三島本人の解説によると、この戯曲の端緒となったのは、郡虎彦氏の鉄輪、道成寺、清姫の戯曲に影響を受けたからだとしている。郡氏は能の時代をそのままにして、近代的な物語を作ったが、三島自身は、能の自由な時間的、空間的処理を生かし、主題を際立たせて現代に生かしたとその意図を語っている。キーンの解説もいつもながらその含蓄の深さには驚かされる。
私にとっては、実に収穫の大きい一冊であった。