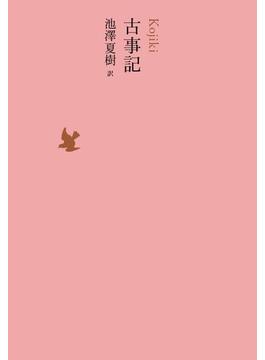古事記を読むなら、この一冊がダントツでおススメです。
2020/05/30 23:13
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:タオミチル - この投稿者のレビュー一覧を見る
ご近所の神社に祀られている神さまが登場していたり、実は、国内旅行に出るときに日本の神さまをめぐるガイドブックになったりもする。「古事記」はどんな風にでも読める物語だと思う。個人的には、ファンタジーとして読んで楽しんだりもしてきた。何冊か現代語訳を読んできたけど、池澤夏樹翻訳のこの一冊が、本格的なのに、読みやすい。というより、しんそこ面白かった。古事記を読んでみたいんだけどという人には、この一冊がいちばんのおススメ。
神話を神話として楽しめる時代
2015/08/11 09:54
3人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:Sancho - この投稿者のレビュー一覧を見る
国威発揚のためではなく、反日のためでもなく、国に伝わる神話・伝承を文学として楽しめる。落ち着いた良い時代になったものです。定番の伝承や天皇家の系譜に関する記述もさることながら、歌謡の翻訳が秀逸。リズム感があって先人の息吹を感じることが出来ます。
ホトホトうんざりだよ!
2018/08/30 14:53
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ROVA - この投稿者のレビュー一覧を見る
・・・すいません、読んでる間ずっと言いたかったんです(笑)
池澤さんの全集を世界&日本問わず順不同でちょっとずつ齧ってます。
古事記の月報に大好きな京極さんがいると知って勇気を出して(?)手に取りました。
いやはや、この歴史的作品をちゃんと頭に入れながら最後まで読めたのは初めてです。
挫けそうになっても脚注を見ると池澤さんのツッコミ満載で
楽しく読み進めることが出来ました。池澤さんありがとう。
内容だけ考えると時代背景を鑑みてもしょーもない作品ですが(あくまで私見)
解説を読んで太さん(で良いの?)の苦労を考えると
本当に大事にしたくなる作品でもあります。いや当たり前ですが。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ないものねだり - この投稿者のレビュー一覧を見る
「古事記」は現存する日本最古の書物とされる。原本は全て漢字で書かれている。特定の読み方をする。現代の出版物は「それそのもの」では、ない。
投稿元:
レビューを見る
第1回配本 第1巻 11月14日刊行開始
【新訳】原文の力を活かしたスケールの大きい池澤古事記の誕生!(帯装画:鴻池朋子 月報:内田樹、京極夏彦)
世界の創成と神々の誕生から国の形ができあがるまでを描く最初の日本文学。神話と歌謡と系図からなる錯綜のテクストを今の我々が読める形に。日本最古の文学作品を作家・池澤夏樹が新訳する。原文の力のある文体を生かしたストレートで斬新な訳が特徴。読みやすさを追求し、工夫を凝らした組みと詳細な脚注を付け、画期的な池澤古事記の誕生!
投稿元:
レビューを見る
日本最古の文学作品を作家・池澤夏樹が新訳する。原文の力のある文体を生かしたストレートで斬新な訳が特徴。読みやすさを追求し、工夫を凝らした組みと詳細な脚注を付け、画期的な池澤古事記の誕生!
投稿元:
レビューを見る
もっと時間をかけてじっくり味わいたかったのだけれど読みやすいのだもの。順序は逆だけど勾玉の世界へ。仕方ないので次巻が出るまでしばし何度か味わいたいと思います。
投稿元:
レビューを見る
点が線に繋がりました。
系譜の羅列にはなかなか苦戦したけど、
解説にもあった通りその当時から一文字一文字に意味があったのが凄い。
逆にやっつけ感がひどいのもあって、実に人間臭い。
共感したのは、日本書紀との違い。
正史であるとしたいならば、フォーカスをあてる必要のない敗者が、躍るような唄と一緒にいきいきと、まさしく生きていた。
読後に思うのは、三浦先生の授業本当にもっと真剣に受けとけば良かった…。
なんて勿体ない事してたんだろう…。
投稿元:
レビューを見る
面白い。。
古事記に関しては以前にこの本の解題として最後に
書かれている三浦佑之氏の書籍いらいですが。現代語訳
とはいえ、古事記をそのまま読めたことが、面白いと
思いました。
日本の神様はとっても人間臭いというか?ぶっとんでいて、天皇は女性ばかり追い求めていて。。
簡単に敵をほろぼしてしまうし。。でもその敗れた側
に対してのシンパシーを感じているところとか
とても面白く。やはり日本って、西洋・中国とは違うなあと思います。
また、この池澤直樹氏の個人編集とされる日本文学全集
は今後の配本を見ると、古典なり名作が現代語訳などで
、現代の著作者によって復活するというもので、
わくわくするものが多く。これは読みたいと思います。
たとえば。。
折口信夫の万葉集。江国香織の更級日記。
角田光代の源氏物語。内田樹の徒然草
いとうせいこうの曽根崎心中
とかとか。。。
投稿元:
レビューを見る
伝承児童文学の授業で、AT分類による色々な話型をやって、世界の各地域別の特徴をみたりした。その記憶が残っているうちに、最初のほうに出てくる逃走譚なんかを読んでみたい。
投稿元:
レビューを見る
建国記念の日。
脚注が充実しているからか、あっさりしてて読み進めやすいのがありがたい。
脚注も、よく読むと遊び心が…(笑)
楽しめます。
古事記で好きなのは、やはり倭建命の部分ととスサノオの暴挙かな。
多神教の神様は人間臭いというより、人間以上に無茶苦茶で面白いね。
投稿元:
レビューを見る
上巻の国生みから中巻の途中まではとてもスペクタクルで楽しかった。歴代天皇の話になってからは苦痛だった。しかし、今までなんとなくしか知らなかった話をなぞることが出来て有意義だった。
投稿元:
レビューを見る
何回も読んできた古事記、
池澤夏樹訳、
大変読み易く、最後まで通読できた。
持統天皇が政権を確立して、神話的な権威で補強、権力保持のためのツールの一つとして、日本語による文学を採用した。
参考文献に、西宮一民先生の古事記があり、皇学館での講義を思い出した。
投稿元:
レビューを見る
日本人に生まれたのだからと思って手に取った、我々日本人のルーツ。
初めての古事記。
脚注をこまこま読んでたせいか最初はなかなか内容が頭に入ってこず苦戦し、間があいてそれまで読んだ内容を忘れてしまったのをきっかけにざーっと読み返したら、流れが生まれて面白くなった。
やっぱり、神話の世界を描いた上巻が個人的にはおもしろい。ぶっとんだことが淡々と書いてあって。
中巻では神話の世界と地続きで歴史上の人物が出てくるので、歴代天皇たちまで神話の世界の実在しない人かのような気持ちに…。
下巻はTHE権力争い、という感じ。
下知識の足りない私にとって、時代背景や奥行きを知る手助けを大いにしてくれた脚注も、なんとも興味深く、ありがたい存在。(先に書いたように、まとめて読むやり方が私には合っていた)
他のを読んでいないので比べようがないのですが、とっつきやすく、大変読みやすい現代語訳なのではないかと思います。
わかりやすく書かれていることで、古代の話と思えないくらいの不思議な親近感。
登場人物たちの人間臭さよ。
あと、名前が雑な人とか性的描写とかがあからさまだったり、展開が早かったりして笑える。
敗者の物語がこうして残っているのはすごいことだなと思う。
最後の解説がまた、なんともよいです。
プレスト。
投稿元:
レビューを見る
まず驚いたのは、イザナキとイザナミが「性交をしてみよう」という場面。なんとも開放的な奔放な感じがしました。次に、スサノオの乱暴振り。「神殿に糞をまき散らした」のだそうです。いやはや神様の所業とは思えません。オホナムヂは神々のだまし討ちにあい、大木に挟まれ殺されます。とにかく3巻を通して、殺したり殺されたりの話がこれでもかというくらいに出てきます。それと、ホトもしばしば出てきます。おおらかでスケールの大きなお話でした。