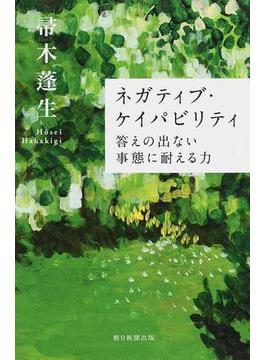「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
読割 50
紙の本
ネガティブ・ケイパビリティ答えの出ない事態に耐える力 (朝日選書)
著者 帚木蓬生 (著)
ネガティブ・ケイパビリティとは、どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力のこと。小説家であり、臨床40年の精神科医である帚木蓬生が、この「負の力」を...
ネガティブ・ケイパビリティ答えの出ない事態に耐える力 (朝日選書)
ネガティブ・ケイパビリティ 答えの出ない事態に耐える力
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
ネガティブ・ケイパビリティとは、どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力のこと。小説家であり、臨床40年の精神科医である帚木蓬生が、この「負の力」を多角的に分析する。【「TRC MARC」の商品解説】
多くの受賞歴をもつ小説家であり、臨床40年の精神科医が悩める現代人に最も必要と考えるのは「共感する」ことだ。この共感が成熟する過程で伴走し、容易に答えの出ない事態に耐えうる能力がネガティブ・ケイパビリティである。
古くは詩人のキーツがシェイクスピアに備わっていると発見した「負の力」は、第二次世界大戦に従軍した精神科医ビオンにより再発見され、著者の臨床の現場で腑に落ちる治療を支えている。昨今は教育、医療、介護の現場でも注目されている。セラピー犬の「心くん」の分かる仕組みからマニュアルに慣れた脳の限界、現代教育で重視されるポジティブ・ケイパビリティの偏り、希望する脳とプラセボ効果との関係……せっかちな見せかけの解決ではなく、共感の土台にある負の力がひらく、発展的な深い理解へ。【本の内容】
著者紹介
帚木蓬生
- 略歴
- 〈帚木蓬生〉1947年生まれ。九州大学医学部卒業。作家、精神科医。通谷メンタルクリニックを開業。「蛍の航跡」と「蠅の帝国」で日本医療小説大賞、「逃亡」で柴田錬三郎賞を受賞。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
電子書籍
人間の善性、無限の可能性を引き出す哲学。 読む前と読む後で、物事への取り組み、考え方を大きく、そして深く、強くしていける渾身の書。
2021/09/24 07:23
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mitu - この投稿者のレビュー一覧を見る
「ネガティブ・ケイパビリティ(負の能力もしくは陰性能力)とは、『どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」をさします。
あるいは、『性急に証明や理由を求めずに、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力』を意味します」
「私自身、この能力を知って以来、生きるすべも、精神科医という職業生活も、作家としての制作行為も、ずいぶん楽になりました。いわば、ふんばる力がついたのです。それほどこの能力は底力を持っています」
(「はじめに」より)
精神科医であり、作家である著者が、その根底の哲学を縦横無尽に語り尽くす。
すぐに結論を求められる社会。
白か黒かを決めたがる安易な態度。
問題の解決ばかりに目を向けて、その奥底にある真実に向き合うことのできない薄っぺらさ。
未知のウィルスとの闘いに右往左往する2021年。
先の見えない闘いの中で、誰かを攻撃することで憂さを晴らす浅はかな態度。
そういう現代だからこそ、不確かな状況に耐えうる力。
相手の苦しみに簡単な答えを出すのではなく、寄り添い、同苦し、共感していく姿勢。
人間の善性、無限の可能性を引き出す哲学。
読む前と読む後で、物事への取り組み、考え方を大きく、そして深く、強くしていける渾身の書。
紙の本
性急に解を求めないこと
2022/09/15 15:19
1人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:nekodanshaku - この投稿者のレビュー一覧を見る
どうにも答えの出ない、対処のしようがない事態に、せっかちに解を出さずに耐える能力を、negative capabilityという。課題が山積みとなり、複雑に絡み合う現代社会において、素早く快刀乱麻に切れ味よく、解を見つけることは、良いことではない。保留の状態で、思考を停止した状態で、持ちこたえる能力を育むことにより、時間の助けを借りて、よい社会を生むことが期待される。答えのない事態に耐える力は、子どもたちにも持ってほしい。
紙の本
人間の善性、無限の可能性を引き出す哲学。 読む前と読む後で、物事への取り組み、考え方を大きく、そして深く、強くしていける渾身の書。
2022/09/08 15:21
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:mitu - この投稿者のレビュー一覧を見る
「ネガティブ・ケイパビリティ(負の能力もしくは陰性能力)とは、『どうにも答えの出ない、どうにも対処しようのない事態に耐える能力」をさします。
あるいは、『性急に証明や理由を求めずに、不確実さや不思議さ、懐疑の中にいることができる能力』を意味します」
「私自身、この能力を知って以来、生きるすべも、精神科医という職業生活も、作家としての制作行為も、ずいぶん楽になりました。いわば、ふんばる力がついたのです。それほどこの能力は底力を持っています」
(「はじめに」より)
精神科医であり、作家である著者が、その根底の哲学を縦横無尽に語り尽くす。
すぐに結論を求められる社会。
白か黒かを決めたがる安易な態度。
問題の解決ばかりに目を向けて、その奥底にある真実に向き合うことのできない薄っぺらさ。
未知のウィルスとの闘いに右往左往する2021年。
先の見えない闘いの中で、誰かを攻撃することで憂さを晴らす浅はかな態度。
そういう現代だからこそ、不確かな状況に耐えうる力。
相手の苦しみに簡単な答えを出すのではなく、寄り添い、同苦し、共感していく姿勢。
人間の善性、無限の可能性を引き出す哲学。
読む前と読む後で、物事への取り組み、考え方を大きく、そして深く、強くしていける渾身の書。
紙の本
答えの出ない状況を生きる。
2017/10/31 12:52
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:名取の姫小松 - この投稿者のレビュー一覧を見る
この作者の本を読むのは初めて。医者や学者の文章ではない、触りのやさしい文章。何を説明しようとしているか、やさしく導いている。
電子書籍
持ちこたえていれば、いつか、そんな日が来ます。
2024/04/05 22:06
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:sachi - この投稿者のレビュー一覧を見る
この作品を読んで、もう少しゆっくり生きたいと思いました。
若いころにはきっと出会わなかった、今の年齢だから出会ったのだと思います。
仕事で悩んでいた時に読めたのも良かったです。
第九章の「学習速度の差は自然」の節が心に残りました。
著者の帚木先生がマルセイユで生活していた時の、お子さんの小学校のお話。
「学習の速度が遅い者は、その学年を何度でも繰り返す。考えてみれば、これが当然のやり方」。
私もそんな学校に通いたかったです…。嫌なのに無理やり通い、無理やり授業やテストを受けていたので。
締めくくりの「どうにもならないように見える問題も、持ちこたえていくうちに、落ち着くところに落ち着き、解決していく。人間には底知れぬ「知恵」が備わっていますから、持ちこたえていれば、いつか、そんな日が来ます。」
“いつか、そんな日が来ます”が好きです。
紙の本
少し期待外れだった。
2017/07/30 16:57
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たまがわ - この投稿者のレビュー一覧を見る
率直にいうと、期待外れだった。
主題である、「ネガティブ・ケイパビリティ」についての話は意外と少ない。
ボリュームが多いのは、「ネガティブ・ケイパビリティ」について言及している作家の生涯についてとか、
シェイクスピアや源氏物語の話、その他いろいろ。
精神科医である著者の、患者への対応についての実例の話は面白かったし、
プラセボ(偽薬)効果についての話も結構長く、これはとても興味深く面白かった。
紙の本
イメージと違った
2024/01/05 20:12
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ごんざ - この投稿者のレビュー一覧を見る
答えの出ない事態に耐える力を手に入れるための具体的な、科学的な方法を期待したがそういったことはあまり書かれていない。
そういった事態を経験した著名人の生涯、エピソードが主な内容。
「プラセボ」「祈祷師」あたりの話は面白い。