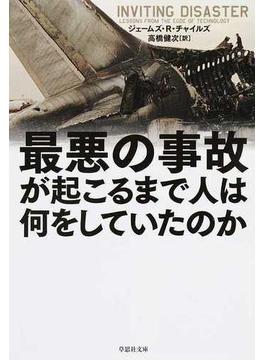「honto 本の通販ストア」サービス終了及び外部通販ストア連携開始のお知らせ
詳細はこちらをご確認ください。
読割 50
紙の本
最悪の事故が起こるまで人は何をしていたのか (草思社文庫)
著者 ジェームズ・R.チャイルズ (著),高橋 健次 (訳)
原子力発電所、ジャンボ機、高層ビル…。巨大システムが暴走を始めたとき、制御室で人びとは何をするのか、何ができるのか。50余りの事例を紹介しつつ、巨大事故のメカニズムと人的...
最悪の事故が起こるまで人は何をしていたのか (草思社文庫)
最悪の事故が起こるまで人は何をしていたのか
ワンステップ購入とは ワンステップ購入とは
このセットに含まれる商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
商品説明
原子力発電所、ジャンボ機、高層ビル…。巨大システムが暴走を始めたとき、制御室で人びとは何をするのか、何ができるのか。50余りの事例を紹介しつつ、巨大事故のメカニズムと人的・組織的要因に迫る。【「TRC MARC」の商品解説】
現代における最も危険な場所の一つが巨大システムの制御室である。原子力発電所、ジャンボ機、爆薬工場、化学プラント、核ミサイル基地……技術発展に伴い、システムはより大きく高エネルギーになり、人員はより少なくて済むよう設計されたが、事故が起これば被害は甚大になる。巨大システムが暴走を始めたとき、制御室で人びとは何をするのか、何ができるのか。最悪の事故を起こすシステムと、その手前で押さえ込むシステムとの違いは何か。50余りの事例を紹介しつつ、巨大事故のメカニズムと人的・組織的原因に迫る。【商品解説】
著者紹介
ジェームズ・R.チャイルズ
- 略歴
- 米国の技術評論家。1955年生まれ。ハーバード大学卒業、テキサス大学ロースクール修了。科学技術と産業、社会との関係を考察する記事を雑誌に掲載している。寄稿先は「スミソニアン」「エア・アンド・スペース」「オーデュポン」など。ミネソタ州ミネアポリス在住。
あわせて読みたい本
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
この著者・アーティストの他の商品
前へ戻る
- 対象はありません
次に進む
紙の本
小さなミスが、大事故につながるまで
2018/08/11 21:14
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:たまがわ - この投稿者のレビュー一覧を見る
原題は、
"INVITING DISASTER: Lessons from Edge of Technology"
膨大な数の重大事故の検証集。
アポロ宇宙船やら潜水艦やら原子力発電所やら、
飛行機墜落事故、工場爆発、船舶火災、熱気球、自動車…。
「序章」で著者は、
『わたしは、人間のミスとマシンの不調が結びついた災難を中心に検討することにした。
ニアミスですんだり、多少の損害はあったが大惨事にいたる寸前ですんだものもある。』という。
本書内では、ある一つの事故について考証しているうちに別の事故に言及したり、
また最初の事故についての記述が終わったのかどうかはっきりしないままに、
別の事故についての詳しい記述が始まったりと、
とにかく膨大な量の過去の事故について、ひたすら紹介と考察が続いていく。
教訓は、とにかく高濃度酸素は何でもすぐに燃やしてしまうから危険とか、
水と電気の接触による事故は、より重大な事故に結びつくとか、
NASAや納入業者は、打ち上げ期日や納入期限に追われると
小さな不具合を無視するようになるとか、
24時間勤務のシフト制では、情報の引継ぎが重要とか、色々、多数。
もちろん、リスクを扱う組織はこうしたほうがいいとか、
小さな問題に直面した個人としてこういう行動もありうる、などの提言もある。
著者が強調するのが、今日システムはより巨大化し、ハイパワーになっているために、
ほんの小さなミスが災害の引き金を引いてしまうことがある、ということだ。
本書の実例でも、小さな不具合やミスが、システム全体の破局につながるというケースが
多く紹介されている。
そもそも、システム自体が元からかなり危険度の高い、
脆弱なものだと感じるケースもある。
少なくともスリーマイルアイランド原発事故当時(1979年)の原発は、
危険だらけの代物なのではないかという印象を、本書を読んで持った。
当時、何が起きているのか現場の誰も分からない大混乱のさなかに、
技術者のひとりが、問題を起こしている二号炉の担当ではなかったブライアン・メーラーを
制御室に一本しかない電話で自宅から呼び出して、
そして彼がある問題に気付かなければ、どんなことになっていたかわからないという。
またこの原発事故の二年前にも、オハイオ州のデビス・ベッシ原子力発電所一号機で、
惨事寸前のニアミスが起きていた。
著者はいう。
『 本書で訴えたいことのひとつはこうだ。
われわれは凶暴化することもあるマシンにかこまれて暮らしているのだが、
そうしたわれわれの世界においては、いまや平凡なミスが
莫大な被害を招きかねないことを認める必要があるし、
その結果として、より高度の警戒がもとめられるばかりでなく、
家庭や小企業のレベルまでもが高度の警戒をしなければいけないように
なりつつあることを知る必要がある、ということである。
たとえば、惨事につながる連鎖は、飛行機の機体の洗浄を担当する会社からも生じうるし、
マンションのガス管のそばで作業する人からも生じうる。』
紙の本
訳者にあっぱれ!
2017/09/11 18:40
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:飛行白秋男 - この投稿者のレビュー一覧を見る
内容はもちろん読みごたえがありますが、複雑な事故の状況が
手に取るようにわかる。
訳者の高橋健次さまの技量にあっぱれです。
紙の本
事故を防止したいと思う方は必読
2020/03/08 10:46
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:KazT - この投稿者のレビュー一覧を見る
歴史上の事故やごく最近(2000年)までの人が引き起こした重大な事故の事例を60件近く取り上げ、解説しています。訳者のあとがきにも書かれていますが、著者は事故を引き起こすような人為的ミスを防ぐには、事前にマシンの欠陥を見抜くこと、マシンの言いなりにならないこと、つねに第二の方策を考えておくことが、たいせつだと語ります。
本書では様々な事故例とともに心理学者の実験データなど、人がミスを起こす理由も多く示されます。多くの人は「自分だけはうまくやれる」という幻想を抱いており、「無知が自信過剰を生む」ことが実験データとして示され、チャールズ・ダーウィンの言葉「知識よりも無知の方が自信を生むことが多い」が引用されています。
あらゆる事故を防止したいと思う方にはぜひ本書を読んで知識を得てもらいたいと思う一冊です。
紙の本
大事故の裏側
2023/10/22 23:10
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:ブラウン - この投稿者のレビュー一覧を見る
微に入り細を穿ちながら大事故の起こる過程を説明している。専門的な解説が多いので、ライトな読み物というよりは、リスクマネジメントに携わる人が見識を深めるために読む本といった印象。