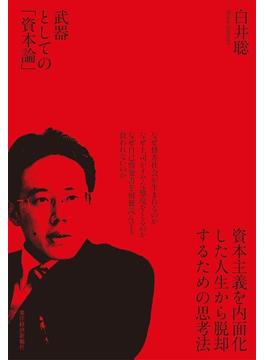資本主義の仕組みの理解と近代史のおさらいに!分かり易い!
2020/05/03 22:12
9人中、6人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:neoaco - この投稿者のレビュー一覧を見る
いや、参りました!資本主義の仕組みを様々な文献を参考に
ここまでわかりやすく、本質を書き表せるとは…。感動いたしました!
私のような素人でも、今後の社会の行く末が占えるのでは?とすら
思える程の、わかりやすく、論理に飛躍の少ない名著です!
全てにおいてそうなのでしょうが、社会制度にも絶対的正しさは存在せず、相対的なものなのだと言うことも、確認できました。
人間の価値からの見直しと再出発の武器として
2022/02/07 09:52
2人中、2人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:魚太郎 - この投稿者のレビュー一覧を見る
資本制の延命のために新自由主義が唱えられたのは、20世紀末から21世紀初頭にかけてである。今立ち止まって振り返れば、これが実は巧妙な「上からの階級闘争」であり、気がついてみたら「下の」階級から利潤が上位へ簒奪されていた。下の階級はぼんやりしているうちに、階級闘争で敗北していたのである。それが現在の格差社会だ。所得税率の累進性がゆるゆるに緩和されたまま惰性に流れていたり、非正規雇用が拡大して労働分配率が下がっているのがよい例である。そしてなぜか、この状況が平穏なのだ。新自由主義の帰結に多くの人が馴らされてしまい、あたかも洗脳されたかのように声をあげない。魂が馴化されてしまったのだと著者は述べ、「人間の価値を信じ」て「意思よりももっと基礎的な感性に遡る必要がある」と言う。そこからもう一度始めるために、武器として「資本論」を使ってほしいという趣旨。本書はそのための入門書という位置づけだが、これから膨大な「資本論」に取り組んでみようとする人は多くはないかもしれない。しかしこの本が、暗黒の未来に向けた道標となることは間違いない。
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:怪人 - この投稿者のレビュー一覧を見る
マルクスの資本論は約半世紀前の学生時代に読もうとして結局読まず終いに終わった。半世紀後の今日、改めてこの資本論を解説してくれるこの本は新鮮に映った。読みやすい文章に加え、多くの話題が盛り込まれており読み物としても興味深い。感謝したい。著者の新自由主義に対する見解に同意する。
3人中、3人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:コアラ - この投稿者のレビュー一覧を見る
今まで読んだ「資本論」入門の中で一番読みやすくわかりやすい。著者の主張がだいぶ入っているようでオーソドックスなものかどうかはわからないが…。階級闘争が「うまいものを食う」ことだという結論には笑ってしまった。評者もネオリベやグローバリズムには反対だが,だからといってではどうするべきかがわからない。著者もわかっていないのではないか。というかわかっている人はいないのではないか。はっきりしていることは共産主義という名前のファシズムでないことだ。
マルクスを通して現実をみる
2020/09/17 23:27
1人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:せきた - この投稿者のレビュー一覧を見る
マルクスの暴力革命論はともかく、資本主義の分析については傾聴に値するということがよく分かった。
働くとはつまり、共同体生存のための共同作業ということだが、そのツールとしての資本制がもつ、価値の膨張欲求を制御することは大変に困難。いずれ手段が目的化し、人間が商品の価値に奉仕するという危険を孕む。
技術が進歩すればいずれ人間は働かなくてよくなるわけはない。生産性の向上はその実、労働ダンピングであり、労働価値の低下を目指すと言っていることと同じ、との言説はとりわけショッキングだ。
人間の安全や生存を保障する仕組みを生み出すのは、思っているほど基本原理とはいえず、やはり政治的な意思形成が必要だ。現実にある危機の実感をもつ人がこの本を読んで1人でも増えたらよいと思う。
彼ももう気付いているのだと思う。だからこそ、こんな名前の本を書くのだろう。
2021/03/28 21:53
3人中、1人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
投稿者:FA - この投稿者のレビュー一覧を見る
この本を読むために、先に佐々木隆治著『マルクス資本論』を読んで準備した。というのは、この本は恐らく『マルクス資本論』についての解説はないだろうと思ったからである。彼がユーミンに対して無礼を働いた後であったことも大きかった。それに、大学時代も共産主義に対して全く関心がなかったので、知識も持ち合わせていなかったことも大きな理由だった。
さて、内容だが、エッセイ本としても出来が悪い。自分の浅智恵で政権批判をしているだけ。大学で講義しているのに知性が感じられない。彼は本当に武器だと思っているのだろうか。彼のような人物が、大学で職を得ようと思ったら、確かに武器かもしれない。
でも、一般の日本人にとって『マルクス資本論』は自分に無関係な墓標。誰も顧みない。彼ももう気付いているのだと思う。だからこそ、こんな名前の本を書くのだろう。本当に売れているのかな。トンデモ本です。時間の無駄です。止めた方がよろしい。
投稿元:
レビューを見る
これまでサラリーマンとして生活を送っている中で漠然と感じていた疑問の正体をわかりやすく解説してもらった気がする。
終盤に、行き詰まった現状を打破するためにまずは社会生活を送るために最低限必要な豊かさの水準を素直にケチらず再設定すべしというような記述があったが、そこはいまいち腑に落ちなかった。それよりは、個々人が可能な範囲で自給自足を楽しみながら取り組むことが、資本主義に依存しない社会をつくる上で必要なんじゃないかと思う。
それと印象的だったのは、資本主義が教育をダメにしているという主旨の主張。確かに、学生が客の自覚を持ったり、教員が学生や保護者に阿ることは良くないことだが、教育機関が教育の質を向上させる上で競合との差別化をモチベーションとすることも重要なのではないかと思われる。
師弟がともに学ぶ関係なら良いのか?
継続して模索したい。
投稿元:
レビューを見る
現代の閉塞状況、労働者の過重労働や非正規雇用問題の拠って来る由縁と著者が考えている現代の資本主義、特に新自由主義の跋扈に対して、「資本論」から何を読み取ることができるかを、シャープに解き明かしている。
マルクスが「資本論」を書いたのは、当然その時点での経済社会状況を念頭に置いてのものだったが、社会主義崩壊後の資本主義独り勝ちの現代において顕在化する問題に、資本主義批判の書である資本論の射程は深く届いている。本書により資本論に再チャレンジしたいと、改めて思ったところである。
投稿元:
レビューを見る
以前勤務していた米国では、講演やプレゼンテーションの最後に「何か質問は?」と問われて、聴衆から手が挙がらないことはまずない。必ず質問が出る。Q&Aの時間もはじめから十分に取ってあって、講演者は出来る限りの回答を示す。もちろん愚問もあるけれど、質問によって新たな論点や視点が生まれて「この講演者は次回からこのネタを取り入れそうだな」と思わせるような場面も多々あった。
一方の日本。まずもって手が挙がらない。そもそもQ&Aの時間を取っていないし、講演者側から「質問は受け付けたくない」という要望が出される場面を見たこともある。
いまの資本主義に限界があることを示唆して、労働者が立ち上がる必要性を「階級闘争」というほぼ死語である言葉を敢えて持ち出してまで主張する本書を読みながら頭に浮かんだのは、この日米の差異。
象徴的なのはサンダース旋風。この旋風のユニークな点は、サンダース個人の政治家としての資質に拠っていることではなく、若者を中心とした社会的活動の声を上述の講演者よろしくサンダースがうまく吸収して自身の論点を拡充することによって支持を広げたことにある。そして、この動きはサンダースという政治家を介した「階級闘争」と言えるように思う。もちろん、この闘争もまだ道半ばなので、今後どうなるかは分からないが、少なくとも闘争の芽は確実にある。翻って、質問を受け付けず、旧態依然とした首相交代劇を繰り広げる日本。著者が指摘する「階級闘争」が進むまでには相当な時間がかかるのでは。そんな思いが強く残った。
投稿元:
レビューを見る
1990年以降にフランシス・フクヤマが展開した
「歴史の終わり」議論では、冷戦終了に伴い達成された資本主義こそが、自由と理性が実現されていく過程=人間の歴史において人類が到達した最終段階だとされた。本書は、その歴史の終わり以降の世界において到来した新自由主義的なグローバリゼーション世界がいかに完遂され、どのような問題を今なお孕んでいるのかについて、マルクスが記した「資本論」の入門書の形で紐解きながら「新自由主義の打倒」の手がかりを掴む内容となっている。
新自由主義とは富の逆再配分であり、資本家階級からの階級闘争だという話は、気付いてはいたもののはっきりとは認識できていなかったと感じた。ピケティ以降により意識的に見つめられるようになった現実に広がる格差の問題と地続きの話であり、200年前にそれを思考していたマルクスの偉大さを知り、現代もなお読まれ続けているその理由に触れることができた。
※※以下メモ
■奴隷制の痕跡
近代社会は自由平等人権を掲げ、かつてのような人の支配を根本的に否定し、人格の尊厳を確立したと言われている。ただし、それは建前上の話であり、資本による労働者の支配という現実がある限り、私たちの社会は奴隷制の痕跡を残している。むしろ一続きになっている。
■奴隷制-封建制-資本制
封建制では他人のための労働と自分のための労働が分かれている。奴隷制に比べると人格的な独立性が高まっている。資本制では必要労働時間と剰余労働時間とが不可分に混ざっている。資本家のための労働も、自分のためと錯覚される。
■工場法
これをしなければ資本が搾取する相手である労働者がいなくなるので法律を定めた。資本主義は自己規制が必要であり、現在の働き方改革もそれ。しかし当時とは「必要性」の基準が変わり今では16時間も労働者を働かせることが出来なくなった。
■必要性=賃金の生存費説
労働者の賃金水準は、労働者自身が生きて、労働者階級が再生産されるのに必要な費用に落ち着く。搾取されすぎて死ぬほどには低くなく、金持ちになって働かなくて済むようになるほどは高くない。しかし、必要の定義は人それぞれ&文化によって違う。デフレマインドになると自己評価が低くなり、別に吉野家松屋でいいよとなる。悟り世代。
■資本主義発生の条件
一定の資本が将来の資本家のもとに積み上がっていないと資本主義は始まらない。さらに、資本家の元に生産手段だけでなく「生産手段を持っていない労働者」が存在しなければならない。彼らは身分制から解放されていて、職業選択の自由がなければならない。彼らを「はじまりの労働者」と呼ぶが、現代資本主義における派遣・日雇い・非正規雇用など労働者のあり方はこの「はじまりの労働者」に近付いている。
■「はじまりの労働者」の作り方
封建社会においては、前近代社会においては、人間は土地と結びついていた。自分で自分の生産手段を持っていて、自給自足をしており、どう働くかが決まっていた。
資本主義をスタートさせるためには、その彼らを、どう働くかを労働者自身で決められないようにする必要が��った。つまりは、生産手段と労働者の分離。 封建社会とそのベースである農村共同体の解体を行い、他人が作った商品を買って、それを消費して生きるようにさせる。それは、社会の生活手段と生産手段を資本に転化する過程であり、直接生産者を賃金労働者に転化もする過程であった。
■技術革新について
技術革新は人間を幸せにする目的で行われているのではない。特別剰余価値の獲得のため。しかし、競争相手も必死に走るため、こちらも必死に走らないと負けてしまう。しかも、みんなが必死だから大した差はつかず、大した特別剰余価値も手に入らず、疲弊することになる。
労働の価値は下がり続け、同じ生活をするために長い時間働かなくてはならなくなった。剰余価値を生産する手段がなくなってきている。資本の側は労働者に長時間労働を強いたり、人件費をカットするといった形で無理に剰余価値を生産しようとする。そこに様々な歪みが生まれてきた。
寿司職人が独立するまで15年という話がある。技能の上達に個人差があることは分かっている。この仕組みは職人の価値の低落を防ぐためのものだったのではないか?どんどん弟子を独立させると過当競争になる。要するにこれは生産の統制と考えるべきもの。統制されていると生産力は低位の状態に押しとどめられる。それを解き放ったのが近代社会、近代資本制社会。果たして生産力を際限なく上げていくことが人間の幸福に結びつくのだろうか。値段が下がれば、その製品の社会的価値が低落したことになる。となると、生産従事者の労働価値の低下となる。環境負荷の問題もある。
■フォーディズム
資本主義vs社会主義というイデオロギー対立の時代。国内の勤労大衆が総じて貧しく購買力が小さいと市場を国外に求め、それが世界戦争へとつながるリスクが高まっていた。階級格差を緩和し、労働者階級を富裕化して中流階級化するため、比較的高い賃金を払って労働者を消費者に変えようとした。資本主義制も自らの正当性を弁証する必要性もあった。
■フォーディズムで与えた権利の剥奪
新自由主義が目指したのが過去に与えた労働者権利の剥奪。しかも、新自由主義が変えたのは社会の仕組みだけではなく、人間の魂・センス・感性をも変えた。ネオリベの価値観は人は資本にとって役に立つスキルや力を身につけてはじめて価値が出てくるという考え方。資本の側は、何もスキルがなくて他の人と違いがないんじゃ賃金下げられて当たり前でしょ、もっと頑張らなくちゃと言ってくる。
投稿元:
レビューを見る
資本家ではなく労働者であるなら絶対に読んでおいた方が良い本だと思った。必要がどこにあるかは上下するが飼い慣らされた家畜のようになってしまわないように人生に感動出来るように支配から自由でありたいと思う。
投稿元:
レビューを見る
今、本当に求めていた本。本当にありがたい。
全てが商品になる。対価が投じた資源を上回る場合、特に大量に捌ける場合、何でも商品になる。大量なほど効率が上がるから、値段も質も下げても儲かる方が良い。ニッチを見つけて商品化することをイノベーションと呼んでいる。なんでも商品化されると無縁な社会に至る。商品たる労働者の自己評価も商品としての評価になる。
最後の贅沢な食事のところも良かった。感性の復権。感覚的な満足、つまり富と商品を分けないといけない。
もう一度読もう。
投稿元:
レビューを見る
まず真っ赤な装調に圧倒される。現代の新自由主義を見るのに「資本論」は決して古くはなく、改めてマルクスがそこまで現代の状況を読んでいたことを平易な言葉で解説された著者にも感心した。資本主義が終わるのは歴史的必然性ではあるが、これまでの延長線上での階級闘争で変わるわけではない。特に現在のように人間の生存が脅かされるような状況こそ変革の契機はあるが、逆の可能性もある。頭を使い、過去の経験から学び、賢くなることが必要である。一方、私たちの考えも「包摂」されているので常に自己点検は必要である。
投稿元:
レビューを見る
来年度から「労働者」として社会に出ていく身として、資本主義とは何なのか?ということについて学んでみたいと思い、読み始めました。以下に学んだことと疑問点を述べますが、至らない点がございましたらご指摘いただければ幸いです。
【学んだこと】
・「資本論」とは資本主義全体のことを指すのではなく、マルクスの著書「資本論」のことであること。
・マルクスの資本論においては、ブルジョア民主主義である古典派経済学者のアダムスミス等とは異なる視点を有していること。具体的には、アダムスミスは資本主義を超歴史的なモノとして捉えるが、マルクスは富と商品を別々のものとして考え、資本主義には始まりがあり、終わりがあると考えた。
・剰余価値を生み出すことができるのは、労働価値のみであること。そして労働価値によって剰余価値を生み出すことができる理由は、労働力の使用価値>労働力の交換価値であるから。
・イノベーションによってもたらされる剰余価値は期限付きの(模倣可能な)特別剰余価値であるから、結局は労働分配率の削減による剰余価値の創出に帰結すること。
・資本主義の発展の肝は、安い労働力にしかないということ。
・剰余価値の更なる創出には、必要労働時間の削減・剰余労働時間の拡大が必要であり、それは同時に労働者が搾取されることを意味する。
・相対的剰余価値の生産が行き詰ると、戦争が発生する可能性が高まること。戦争はそれ自体が需要を生み、戦争後には巨大な復興需要が生じる。
【疑問点】
・「イノベーションによって獲得される剰余価値が一時的であり、結局は安い労働力でしか(労働者が搾取されることでしか)剰余価値は創出されない」という主張に疑問を持った。GAFAMのような巨大IT企業や、P&G、コカ・コーラといった企業が、最終的に安い労働力でしか優位性を示せなくなるという未来が想像できない。また、GAFAMが得た剰余価値は、安い労働力の搾取によるものではなく、イノベーションによるものであると考えるし、P&Gやコカ・コーラが優位性を維持できているのは、マーケティングに多額の資金を割けること、規模のメリットによるものも大きい。そういった参入障壁は、果たして一時的かと言われれば、そうではないように感じる。
投稿元:
レビューを見る
【薄々感じている資本体制】
あらゆるモノ、コトが商品化されていく世界、それが資本体制です。
一度商品化されるとそれを提供する側は、利潤を高めるため、無駄を削ぎ落とし効率的に生産しようとします。
もう一つの利潤を高める方法として、労働者を長時間働かせることがありますが、現代ではこれは国際的にできないので生産性を上げるしかありません。
ただ、生産性の上昇が労働者の給料上昇につながるわけではありません。(多少は上がるでしょうが、微々たるものです)それにもかかわらず、労働者はPDCAを回して、生産性を上げようとします。資本側にうまく啓蒙されています。
会社が潰れたらあなた方労働者は困るでしょ。働くところがなくなったら、どうやって暮らしていくのですか?という論法です。
あらゆるモノ、コトが商品化されていく中、何を買うにもするにもお金が必要になってきます。お金を得るため労働者は労働力という商品を提供し買い取ってもらいます。しかし、これが等価交換になっていません。資本の増加分も労働者側が提供しています。つまり、労働者がもらう給料以上に労働力を資本側に提供しているということです。
労働者側にもヒエラルキーがうまくつくられています。
資本側としては、資本の歯車として単純に労働を提供して資本を増やしてもらえばそれでいいのですが、それだけでは資本を増やす分まで働くのは割に合わないと考える労働者も出てきます。そこで、役職という褒美、ヒエラルキーを与えることによって、積極的に資本を増やす活動をする労働者には役職を与えヒエラルキーの上位へ移動させます。これもよくできたシステムです。
なぜ、労働者は労働力を提供しないと食うに困るのか?
労働力の提供以外何も持っていないからです。
完全なフリーな状態なのです。労働力を自由に使える状態なのです。身分制度が無くて自由に仕事を選択できるようになった自由人であり、逆に労働力として大多数を占める存在になってしまいました。圧倒的にフリーな労働者が増えすぎたのです。
資本体制は資本を増えすことだけが目的のため、労働者を豊かにすることは目的ではありません。年貢ではないですが、生かさず殺さずの給料が労働者には与えられるのです。労働者の給料は実際に稼いだお金ではなく、労働者が生きていくことができ、健康的に労働力を再生できる最低レベルに落ち着くのです。そして、モチベーションをあげるために役職ヒエラルキーを設けているのです。
しかも、生産性向上という本来、資本側が担う業務も、役職を与えられた労働者自ら行うようになっているのです。資本を増やす、利潤を高める一つの方法である生産性を上げることも労働者側で実施しているのです。
当たり前にように労働者側で行っていますが、本来、資本を増やす作業であるため、資本側がコントロールして生産性を上げる方策をとらなければならないことですが、完全に洗脳され、労働者側で実施することになっています。
そろそろこの不条理なシステムに反旗を翻してもいいのではないでしょうか。