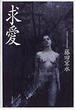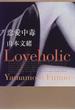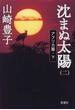澤木凛さんのレビュー一覧
投稿者:澤木凛
2001/03/31 15:34
難しい「経済学」を明快に解説、これから経済学部を目指そうとする高校生も楽しく読める一冊
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
少し前にどこかの経済大学の募集広告(大学も広告をしないと入ってくれないような時代になった)に「経済の語源は『経国済民』からきている」なんていうのがあったけど、国を運営して民を救うなんてかなり大変なことで経済学てなものがなかなかうまくいかないのはある意味当然と思っていた。経済学者が自分たちのことを「いいかげんだ」といってブラックジョークにするのはよくある話で、そういう意味でも「経済学=当たらない天気予報」みたいなところは皆常々感じているんじゃないだろうか。
この本はそんな経済の広くみんなに紹介しようと言うとてつもないコンセプトを持っている。しかもずっとベストセラーの上位にランクインされていたのだから、当初の目的は十分に達成したといえるだろう。この本は広告プランナーの佐藤雅彦氏がエコノミストの竹中平蔵氏に質問して議論するという構成で出来ていて、まあボクらが普段よくわからないなぁとか思っているようなことを率直に聞いてくれていて、素人にもわかりやすい構成。経済っていうよくわけの分からないものを初めからあきらめるのではなくて「なんだ、そういうことなのか」と思えるようになればしめたもの、少しずつ幅を広げていけばいい。
といってもこうした本は一度読んでしまうと、「はい、それまで」みたいなところがあるから本当は毎週ちょっとづつ読めるようなものがいい。日経の経済教室は少し(いやかなり)難しすぎて市井の人々には敷居が高すぎる。こういう企画も新聞紙上とかで取り入れて欲しいものだ。そういう意味ではこの本のきっかけとなった対談は「月刊プレイボーイ」だとか。さすがに「月刊プレイボーイ」、単にエッチなグラビアを載せているだけではない(もちろん、それも大切だが…笑)というところを示してくれている。週刊はともかく、月刊の方は昔からそういう「心意気」みたいなところがあって高校時代に国語教師から「おまえら、プレイボーイを読め、そこに社会が広がっている」と言われたことを思い出す。少年よ、プレイボーイを読め、か。なかなかいいフレーズだ。
話はそれたけど、この本、なかなか面白いです。経済ってそんなに難しいばかりではないんだな、と思えれば十分でしょう。これから経済学部を目指そうという高校生にも十分にわかる明快な一冊。ちょっと興味のある人には一読をすすめます。
2001/03/31 15:20
語は流行語の最終形、そこにはその時代が確実に反映されているから面白い。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この本、いまや誰もつかわなくなった死語について年ごとに記してあるのだが、「ああ、こんな言葉もあったっけ」と思わせるところがよい。例えば「フィーバーする」「なめ猫」「三語族」「浮沈空母」「ニャンニャンする」…等々、そんなのあったなぁと思うようなものが沢山お目にかかれる。この中で最近のものはまだわずかに使われているものもあり、だんだん死語になっていくのだろうなぁというのもわかる(実際、99年まで書かれていて「これだけ、ずーっとやってくると、わかりますね。あ、これは死語になる、というのが。」と小林氏も書かれているように予想も入っています)。
つまり死語というのは流行語の裏返しでないといけないわけで、一世を風靡した言葉がその後使われなくなるからこそ、死語を形成するわけで世間に一度は評価されないといけないわけです。そのあたりが難しい(だからボクがこの本を買ったのは死語辞典としてではなく、流行語辞典として購入しています)。言葉は時代をきちんと反映させるので時代が見えて楽しいと言うこともあります。
言葉遊びは「たかが言葉遊び、されど言葉遊び」の部分が大きいと思います。知らないと言い切ってしまった段階でその言葉を使う人々とのコミュニケーションを自ら放棄してしまうことになるのです。「へぇ、そんな風に使っているんだ」と興味をもったり、「昔はこんな言葉があったのか」と言葉に対する探求心を持ち続けることは人間に対する興味・探求につながっていくのではないでしょうか。
言葉に敏感にありたい人、ふと昔の自分を見てみたい人(流行語、死語はその当時の自分を思い出させるに十分な触媒です)、是非一読してみてはいかがでしょうか?
2001/03/31 15:17
身近なことに科学のメスをいれてみると・・・サイエンスライターの実力発揮の一冊。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
サブタイトルが「見慣れたものに隠れた科学」となっていて、本の主旨は「普段の生活にこんな科学が隠れているよ」というもの。書いているイングラムはサイエンスライターという肩書きをもっていて、母国カナダではサイエンス番組の司会もやっているそうです。しかし、なにが凄いって「カナダサイエンスライター協会賞」とかとっているところ。サイエンスライター協会なんてカナダにはあるというのも凄い。日本ではサイエンスライターなるものは職業として存在しないからね。前々から言っているように、そういう部分が日本では遅れているなぁと痛感します。
さて、実際の内容は軽めのコラムがずらりと並んでいます。一つのコラムはそう数頁で読むのに10分くらい、内容もそれほど難しいことは書いてなくて本当に身近にある自然現象を取り上げたものばかりです。「思わず舌をだすのはどんなときか」「コーヒーを出来るだけ冷まさない方法は」「まばたきのわけは?」「あくびはどうしてうつるのか」「虫はなんのために群れて飛ぶのか」等々が科学的なアプローチでいかに解明されるか書かれています。
我々が普段何気なく接しているものや事象にももちろん科学的な根拠やしくみが存在します。それを疑問に思って解明しようとする人々が沢山、この世界には存在するのです。そうか、こういうしくみになっていたのか!と我々は物事の真実を知ったときに喜びを感じます。それは幼い頃に満たされた好奇心と全く同じもののはずです。幼い頃、我々の周囲は未知なる物事で一杯でした。ちょっとした毎日が冒険の連続でもありました。それが背が伸びて大人になるにつれて「ありふれた毎日」へと変化していったのです。もちろん、毎日が驚きの連続というのは結構くたびれる生活かもしれません。しかし、ドキドキ、ワクワク、不思議なことを解明する喜びがない世界はもっと寂しいものです。我々の中に眠っている好奇心という名のエンジンに再びスイッチを入れてみるのもいいことです。そのときのガソリンにはこういった本が最適なのかもしれませんね。
紙の本美女入門 Part2
2001/03/26 20:42
林真理子女史が書くからこそ真実がある「美女」学の秘話。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
林真理子女史に対しては世論はどうとらえているのだろうか。一般的にブス/デブの代名詞として扱われているのか、それとも単なるブランド好きとして見られているのだろうか。いや、文学としてとりあげるなら「官能小説に走ってしまった女流作家」ということになるのか。まあ、どれもあたっているようであたっていないようで…。
私は彼女は日本人の典型である、と思う。いや、正確には「少し古い日本人の」という方が正しいか。彼女は基本的にまじめな人である。そして田舎から出てきて都会というものに一生懸命紛れ込もうと努力した。都会で認められ、賞ももらい、故郷に錦を飾った。でも根っこは田舎の普通の娘さんなのだ。お嬢でもなければ、都会育ちでもない。芸能人大好きなミーハーだし、ハイソな人々にあこがれもあるが、気後れしてしまう。しかし、彼女はあえてその中に踏み込んでいこうとする。その世界を知ってみたいとする。こんな世界もあるのね、と友達(つまり一般の人々)に知らせようとする。自分だけが知っているからちょっと自慢げになったりもする。いつでも背伸びしてハイソな世界に入っていたい、その背伸び感覚が彼女の持ち味だろう。
もちろん、本当にハイソな人々は努力なんてしなくても美女だったりするし、努力しているところを人に見せようなんて考えもしない。私はこんなに努力しているんだ、でもダメなのねぇ、というのが林真理子女史が旧日本人たる象徴的な事実である。まあいずれにしてもこの本は肩をはらずに読むことは出来る。そして、林さんも頑張っているのねぇ、私もちょっとはダイエットでもしてみよう、と思ったらそれで十分なのだろう。この本を読んで林真理子女史を本当に鬱陶しいと感じる人もいるだろうな、その人はきっと彼女と同じ感性を持っている人だと思う。案外多かったりするのかもしれない。全く無関心でいられる人が本当のハイソな人に違いない。
紙の本大学崩壊
2001/03/26 20:41
大学崩壊、この言葉の裏にある真実を読み始めよう。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この本、帯には「発売直後より各紙誌絶賛!」と大げさにかいてあるけど、まあ大学というところに在籍していたらよくわかる話ばかりだ(というか、大学院に在籍しないと見えてこないかな)。でも、世間的にはそれが象牙の塔という全く見えない世界故に新鮮だったのかもしれない。
大学の教授がいかに人間的にたいしたことないか、私も大学にはいってすぐに痛感した。ものすごく視野が狭い人々が沢山いる。ここ以外では生きていけないんじゃないかと思う人が本当に沢山いた。彼らはある意味で子供のまま歳を重ねているのだ。政治屋(研究せずに学内人事に一生懸命の教授)は沢山いるし、政治屋のせいで大学がくだらないところになっているのもきっとかなり正しいだろう。ただ、それは今まで日本のどこの大学でも見えたことだ。一企業でも上司の顔色ばかりみている人間の方が出世したりするのはよくある。それが最近は実力主義に徐々に変わりつつある。組織というものがオープンになり、自由競争がかなり入ってきたからだろう。大学の組織もオープンにすればきっと変わっていくに違いない。
この本では学生の学力低下もかなり深刻に取り扱っていた。実際、分数の計算ができない、なんてよく言われるけど、それ以外の部分も大変な状態になっている。ただし、これは学生だけが悪いのではなくて日本人全体のレベルがダウンしていることに起因するのではないか。全て意味で日本人のレベルがダウンしている。典型的なのは日本のリーダをみればいい、原敬、田中角栄、現在の首相と比べれば日本人のレベルダウンがわかる気がする。学生のレベルあげるために何をしなければならないか、この本の中では共通一次のように五教科受験を義務づけよと語っている。
負の要因は沢山ある。生徒の数が減って勉強しなくても大学に入れるようになり、大学が生徒にこびる時代になっている。文部省は義務教育の週休二日を導入し、ゆとりの教育という名の下に勉強時間を減らす。これで日本の教育が復活するはずがない。そういうこれからの「教育」に対する議論を始めるきっかけにこの本は十分なる。実態を知る一つのものさしに読んでみるのもいい。
紙の本おまえは世界の王様か!
2001/03/26 20:38
読書王時代の自分に苦笑、ハラダ氏のタイムトラベル書評。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この本、少し変わったタイトルがついているが、王様とは実は原田氏自身のことを指していっている。いや、正確に言うと二十年前の二十歳の時の原田氏のことをさして四十歳の氏が言っているのである。
ことの発端は氏が実家に帰ったときに母上から「あんたが昔かいてたカードが沢山出てきたよ」というところから始まる。氏は二十歳くらいの時に読書記録を京大式カードに書きつづっていたのだ。それが二十年の時を経て発見された。読んでみると、実に偉そうなことが書き記してある。今の氏をして「お前は世界の王様か」と言わしめるばかりの感想文なのである。これを取り上げて笑ってみよう、というのがこの本はスタートしている。実に楽しい構成で、読んでいてなかなか愉快である。
この手の本を面白くなるかそうでないかの境目は何だろうか。これは「書いている本人が楽しんで書いているかどうか」という部分が大きいと思う。本人が「これはむちゃくちゃ面白い!」と思って書いているとやはり読む方もそれに引きずりこまれていく。逆に本人が楽しめないものは読者も夢中になれない。この本では昔の自分との対話が楽しいであろう。昔の自分の日記を読むと「こんなこと考えていたんだ」とか「むちゃくちゃ言っているなぁ」とかがあって、しかもそのことをいくらでも批判しても誰も怒らない(当たり前だけど)。昔の自分との距離があいていればあいているほど、そのギャップが大きくなって面白い。ちょうど昔の自分が書いた日記をみて笑ってしまうのと似ている。
推奨の一冊、小難しいことは一切無し、すっきり読める。しかし、なんといっても偉大なのは「若さ」か。これだけの読書を毎日飽きることなく続け、それを記録として残しているところにこの本の最大の素晴らしさがある。若い頃のインプットがきっと原田氏を「かっちょいい」オヤジにしたのだろう。この本を読んで自分も「もっと精進しないと」と思ったらそれで十分読む価値はあったといえる。
紙の本絶版
2001/03/25 20:23
ヲタクの道も奥が深い。極めた三人の究極のオタク談義の最終章。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
岡田斗司夫・田中公平・山本弘の3氏の究極のオタク対談の第三弾がこの本である。前の二冊は「封印」、「回収」の両方ともサブカルチャーの極みという内容であったが、最後に出てきた本作も十分に濃い内容になっている。
さて、三冊目も前の二冊と同じように濃ゆい。ギャルゲーの話ではトキメモのキャラクタが実は絵的には全然個性的ではないと言う話が書いてあり、フィギュアにしたら区別がたいしてつかなかったらしい。それをみたとあるモデラは「全然、区別がつかないな。赤く塗るか」といったとか(笑)さあ、この文章を読んで爆笑した貴方、貴方は立派なオタクです。この本をすぐに読んで十分に堪能できるはずです。
こうやってオタク談義をしている三人だが、彼らも実はかなりの才能の持ち主。田中氏は「サクラ大戦」の主題歌テイゲキを作っている売れっ子作曲だ。「田中公平なんて知らない」という人はほとんどだが、この田中氏、かなりの数のアニメ、ゲームの主題歌を作曲し、音楽もつけている。ゲーム業界は必ずCDになるから、芸能界で売れない作曲家よりも収入はいいし、やりがいもあるという。では、誰でも出来るのかといえば、氏は一笑に付すのだ。「才能がないとこの世界でやっていけない。アニメだからといってバカにはできない」
かくいう氏も東京芸大を出ているし、そのあたりの「○○○音楽学院」なんていう専門学校で少しやったくらいでは無理だという。ゲームやアニメの音楽業界で生きていこうと思ったらかなりの実力がいる、らしい。たしかに劇場用の音楽つけると何百万というギャラなわけだし、オーケストラの譜面に書き下すのはちょいちょいとできるかというと、そりゃ大変なわけ。
しかし、これらだけのオタクな三人が集まって語っているのは「我々よりもっと凄い奴は絶対にいる。そいつらは表に出てこないだけだ」というのには脱帽。そうだな、ホンモノはいるに違いない。きっとK1とかに出てこないようなとんでもない殺し屋というか格闘家がどこぞの山奥にいるみたいなものだろう。道を極めるとはそういう世俗と切るところからありか、んんん、オタクの道も奥が深い(感嘆)。
紙の本暗室
2001/03/25 20:19
暗室とは光を定着させるために闇で処理する場所、そこには人の闇も潜んでいる。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
日の当たる部分がまぶしいのはあたらない部分の暗さがあるからだ。黒い部分があるからこそ白の部分が際だつ。同じ白さでも隣にある色がもっと白いか、もっと黒いかで見え方が変わってくる。闇があるから光がまぶしい。その闇には一体、なにが潜んでいるのか。
この本の構成は非常にわかりやすい。題名の通り、全くの暗闇である暗室を描くことで、光に照らされた部分を切り出そうとしている。彼が描きたかったのは普段日があたることのない「陰」の部分だ。小説は自分の周囲にあった話をモチーフに7つの短編から描かれている。全てが写真に関わる人々の話であり、彼らの共通項として存在しているのは暗室だ。現実の断片を切り取る写真、それは撮っただけでは切り取ったことにならない。一度暗室という一切光を遮断した闇の世界で「処理」して初めて白日にさらされる。写真という現実を達成させる瞬間が闇であること、それ自体がきわめて暗喩的である。
この作品に出てくる人々はどこか心に闇を抱えている。いや、全ての人が心に闇を抱えているのだろう。それを暗室という真っ暗の世界が引き出してしまう。普段はけっして出てこない闇の部分。それはひどく醜い形をしているし、奇怪でもある。ただ、それを描くことで初めて人間の光の当たっている部分がまぶしく見えるのだ。小林氏はそういう人間の陰の部分を「写真」と「暗室」という二つの視点で切り取っている。実にわかりやすく、それでいていろいろ考えさせられる。
闇をもたない人間は薄ぺっらに見える。写真と同じでコントラストが小さいと単調になってしまうからだ。だが、度を超すとそこにうつる姿はコントラストの強すぎて不自然さを残してしまう。すべてのものが強く隈取りされたような歪なものとして目に映る。闇の部分を描くことは非常に難しい。それを出すことで明るい部分は強調されるが、あまりにも出しすぎると見る方は目を背けてしまう。この作品集が全体的に暗い感じで仕上がっているのは、あえて闇の部分を切り取ったために全体の明度を抑えたからだろう。これ以上のコントラストは異形になる。それがわかっているのは氏が写真家だからだろうか。
2001/03/25 01:02
趣味の色の強い短編に隠された森思想の秘密。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
森博嗣氏の短編集、載っている作品は犀川・萌絵シリーズ有り、Vシリーズの小鳥遊くんと萌絵ちゃんの競演有りで、かなりファンサービスあふれる作品群だ。
といっても、短編集はア・ラ・カルトというか、一つくらいはずれてもいいだろうという余裕のせいか、趣味の世界に走った特異作品もある。今回もこれは理系でないとわからないだろう(「どちらもAから始まるのに自由(gとu)の差で、一番と二番にわけられるものはなに?」といったなぞなぞ)というものやチェスをしらないと落ちすらわからないものもあった。作品を楽しむには勉強するべしということである。
その中で個人的に興味深かったのは理想の模型屋の話。これはミステリィというより寓話に近いもので、模型好きの少年が自分の理想の模型ショップを妄想するという話。まさしく森氏が小さな頃の自分の世界をそのまま話にしたものだ。模型好きの少年は最初は簡単なプロモデルからその世界に入っていく。模型の世界は奥が深い、動力付きのものに進み、そのうち自分でそれらを作っていく楽しみがわかっていく。それは一朝一夕で達成されるものではなく、何年も模型を作り続けて初めてその世界観というか奥深さがわかっていくのだ。主人公の少年は自分の理想の模型屋さんを想像する。あらやるパーツが揃っていて格安で売っている店だ(もちろん、そんな店はない)。そしてある時夢の中でその店に遭遇する。こんなに安くていいの?とびっくりする少年に店主は「君のように本当に模型好きの子供にはその値段でいいんだよ」という。
そしてその店でもう一人の少年と出会う、自分には格安で売ってくれた店主ももう一人の少年には厳しい。いや、もう一人の少年は価値もわからず、ものすごく手の込んだモデルの値段を聞くと、「これは売り物ではないんだ」と言わんばかりに値段をいう店主、そこで彼ははたと気がつく。極めていって初めてわかる世界があるということを。店に並んでいるものは模型の世界を極めた者にとっては価値がわかり、「これは格安だ」とわかるが、そうでない人々にとってはただの高価なものに過ぎない。なにも知らない少年がそこで買うことのできるものはただのプロペラだけかもしれない。しかしそのプロペラから始めていって、時間がたって初めて買うことを許されるものがある。それは単にお金を持っていれば買えるものではない。キャリアを積んで初めて買うことが許されるものなのだ。
寓話はそのまま森氏の模型感というか趣味に関する思いに通じているだろう。モノはお金を出せば確かに手にはいるが、本当の一品は人を選ぶ。趣味の世界もそうだ、ずっと続けていてある時初めて目の前がパッとひらけるときがあるのだ。野球観戦も観劇も美術鑑賞も、読書も漫画を読むこともドラマをみることもそういった全ての趣味は同じだ。わかるようになるには段階が必要なのだ。その瞬間のために我々は惜しげもなく時間や金をつぎ込む。それが趣味というものであり、生きると言うこと事なのではないか、そんなことをふと考えさせられる一冊である。
紙の本「捨てる!」技術
2001/03/25 00:41
ストックとフローをわけて考えることから整理法は始まる
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
一時期話題となったこの本、あっという間に読んでしまえる量で極端に言えば一つのことしか書かれていない。つまり、エッセンスとして書かれていることは「ストックとフローにわけて考える」ということだけだ。
昔と違って情報の単価は低くなり、簡単に手にはいるようになった。それによって情報を保管することよりも廃棄することが実は大きなテーマになっている、というのがそもそもの主旨だ。そしてその情報を捨てる上で重要な見極めが「情報をどの段階で捨てるのか」ということになる。
見た途端捨てれるものも沢山あるし、ある程度判断すれば捨てれるものもある。最終的には情報はほとんど捨ててしまう。どの段階で捨てるかがミソなのだ。大切なのは一次情報である。それを加工して出来る二次情報は重要度が低い。簡単に引き出せる(他で保管してある)情報も捨てることが出来る。となると最終的に捨てることが出来ないのは自分が作り出した情報ではないか。確かに自分が作り出したものはどこにも保管されない、自分で保管するしかない。本は捨ててもいいが、日記は捨てることが出来ない。
また情報はフローとして扱うものとストックとして扱うものがある。処理していく中でこれは重要だと判断されるとストックとして「保管」される。一度ストックしたものはなかなか廃棄されないからストックに行く前に捨てなければならない。フローの中で捨てる技術を見いだすことが大切だ。確かにボクの生活や仕事の中でもフローの中に捨てるべきものは沢山ある。簡単に言えばファイルとして格納された書類はまず捨てられることはないが、机の上に乱雑に置かれている書類は捨てられるべきものであふれている。これを早く判断して捨てれば、情報のアクセスが速くなる、ということだろう。
著者は究極の廃棄術はアウトプットすることだと言っている。大量に集めた資料やデータもそのまま放っておくとなんら使い道がない。ストックする意味があるのはその情報が使えなければならない。そういう意味では使える情報だけが意味がある。報告書にする、本にする、論文にする、そういう形でまとまったものをストックして初めて意味をもつ。これはまさしく「真実」だろう。結局アウトプットの過程にあるものがフローである。フローの情報をいかに管理し、素早くアウトプットし、エッセンスだけをストックする。これが究極の情報を捨てる技術、簡単にして困難、だからこそこの手の本が売れる。本当に出来るかどうかは、是非一読して実践してもらうしかない。
紙の本求愛
2001/03/25 00:37
特殊な出会い、特別な二人、そこに宿る男女の心の機微。
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この物語はリハビリ中のプロ野球のエースと偶然出会ったピアニストの恋愛話だ。男は野球選手、しかももうベテランとよばれてもいいくらいの抑えのエースだ。しかし開幕戦で死球を肘に受けて去年は一年間棒に振っている。今年はようやくリハビリをしている最中である。もしかしたら今年一年ではまだ投げられないかもしれない、そんな不安の中、チームの通訳をやっている男から「女房のピアノのレッスンをうけてくれないか」という誘いを受ける。その男の女房は一流のピアニストだったが指の怪我が元で昔のようには弾けなくなってしまっているらしい。分野が違うが一流の人間がリハビリをやっているのはきっといい心の支えになるという。それ二人の出会いとなった。
全く異なった環境で育った二人はいつしか心を引かれ合っていく。それはともに自分を支えてきたものを失おうとしている共有感からくるものなのか、それとも何かが彼らを導いたからなのか。やがて二人は周囲の反対を押し切って一緒に暮らしはじめる。一向に指が思うように動かない彼女に対して、男は少しずつあのマウンドへ向かって進みはじめる。心の微妙な葛藤を繰り返しながら二人は運命の道を一直線に進んでいく。
ラストは一気に話が展開する。このラストをよしとすると否とするかは読者によって大きく分かれるだろう。私はなんとなく納得してしまった。そう感じてしまう必然性がそれまでに描き込まれているからだろうか。はっきりとして陰影が映って初めて光がまぶしく見える。秋の夜にしっとりとくる作品である。
2000/11/19 15:41
濁りきった組織を建て直すことが出来るか、新展開の会長室篇スタート
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
御巣鷹山の惨事で国民航空の危機管理が政治的問題としてあがるようになり、時の総理大臣の命を受け、一人の男が会長として派遣される。関西の大手紡績会社の会長である国見である。墜落事故を生んだ航空会社の闇の部分を白日にさらし安全運行と健全経営の為に、彼は必死の覚悟で会社内の不正をただそうとする。会長室篇の幕開けである。
もちろん、今まで会社の不正に立ち向かったが故に海外勤務をたらい回しにあってきた主人公恩地も会長室部長として会社の更正に参加する。二人の義侠心あふれる男の手によって国民航空はその悪しき呪縛から解き放たれることが出来るのだろうか。分裂した組合の統一と、安全巡航のための様々な改革、事故遺族の補償問題。彼らは大きな組織の陰に隠れている様々な問題に一つ一つ立ち向かう。
起承転結でいえば、「転」の部分にあたる第四巻では、恩地と国見の獅子奮闘の活躍が記される。果たして国民航空は義士たちの手によって変わっていけるのだろうか。遠くにうっすらと見えている暗雲が徐々に近づいている中、男達の熱い戦いが始まろうとしている。
2000/10/30 19:47
キラリと光る野口節健在、ITが怖くて今の時代を生きていけるか!
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
東京大学先端研で教授を勤める野口悠紀雄氏のエッセイである。野口氏は「超」整理法で有名になったが、なんといっても独自の視野で経済を切りとり、自分のスタンスで世の中の流れを読む。東京大学工学部から大蔵省という経歴が物語るとおり、理系と文系の両方の視野で物事を見ること出来る数少ないオピニオンリーダーである。その氏が「週刊ダイヤモンド」に連載中のエッセイをまとめたものであるが、さすがに第5集ともなると安定感も出てきて、落ち着いて読めるものに仕上がっている。
内容はIT化が進む現代日本社会の中で氏が感じる矛盾点を指摘し、新しい考え方を提案したものだ。独自の視点は、長く続く連載だけに「またこの話か」と思う点もいくつかあるけれども、その反面「こういう考え方もあるのか」と気がつかされることも多い。野口氏のエッセイをずっと読み続けている読者にとっては少し物足りないかもしれないが、全く読んでいない人にはきっと発見や驚きであふれていることだろう。文章もそれほど難しくなく、それでいて理知的な展開で読んでいてすっきりと理解できるのも氏の明晰さゆえである。
氏のエッセイをずっと読んでいる私にとってはマンネリよりも「ああ、こういう考え方もあるのか」と感心させられる話の印象が強かった。つまり「氏の提案している発想法」の前に脱帽させられたのだ。特に「東京は5分で独立できる」という発想、着眼点には非常に感嘆した。この章だけでも一読は価値は十分にあると思う。
IT時代到来で若者はそれほどやっきにならないが、中年層には大きな重石となってのしかかってきている。50代は半ばあきらめ、40代はもろにプレッシャーを感じ、30代ですらどことなく不安を覚えている。本当にそんなことが起きるのか、そしてもし起きたとしたらその潮流に自分は対応できるのか。その不安は簡単には解消できないが、少なくともこの本にはその重石をもちあげる「てこ」の使い方が示してある。こういう風につき合ってみてはどうか、とオピニオンリーダーがアドバイスを送ってくれる。ITに踊らされることはないが、逃げ出さずに向き合うためにはどうすればいいか、それ知るにはうってつけの一冊である。
紙の本恋愛中毒
2000/10/30 19:41
理系の男諸君、君の自分勝手で妻を不幸にしていないかい?
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
一人の女性が「恋愛」というとてつもなく大きなものに飲み込まれていく様を描いているのだが、実に話の展開が上手だ。最初の導入部分でとまどいを感じたまま、気がつくと一人の女性の異常な感情の世界に引き込まれていく。最初から身構えさえないような構成になっているのだ。知らず知らずのうちに我々はその女性の世界観にはまっていく。気がつくと逃げ道はない。もしかしたら恋愛中毒とはそんな状態のことなのかもしれない。
一人の女性を追い込んでいったものは彼女の育った環境であったり、彼女の思いこみの激しい性格にあったりして複数の原因があるのだが、絶対に切り離せないのが彼女の別れた夫の存在である。この夫、彼女がいうところの「理系の男」である。この「理系の夫」は自分の価値観で物事を判断し、それと同じ価値観を妻にも求めようとする。そしてそのことが当然であると思っている。彼女も最初はその夫にこたえることが自分の愛だと思っていた。しかし、生活を続ける間に徐々に二人のあいだにひびがはいっていく。そしてある時、ついにはじけてしまう。
夫との離婚はこの物語のいわば陰のテーマで物語の表層にはあまり浮かび上がってこない。だが、この「理系の夫」とのことが原因で彼女の「恋愛中毒」が始まっていったのだ。彼女は自分をどんどん追い込んでいってしまう。それが中毒、そしてとめどもなくその道を突き進んだ果てに待っているもの、それがこの小説の最後(ラスト)だ。彼女を追い込んだのは彼女自身に他ならない、ただその引き金は間違いなく夫の存在である。
「理系の男」と書かれているのは一般論だろう。しかし、理系の男である私にはその指摘が痛いようにわかる。自分勝手に世の中を、自分の家庭を見据えてしまう部分をたしかに「理系の男」は持っているのだ。世の「理系の男」諸君、君はここ書かれたようなことをしていないかい?君の自分勝手でこういう女性をつくりだしていないかい?この作品、「理系の男」にはある意味でものすごくリアルなホラーなのかもしれない。
2000/10/24 22:37
数奇な運命に振り回される主人公、先に待つものは一体何なのか
0人中、0人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
第一巻でテヘランに飛ばされた主人公・恩地はテヘランへの就航便開設に参加し、その後度重なる会社側の圧迫に屈せず、ケニア・ナイロビに飛ばされる。第二巻でも主人公は不遇にさらされるが、どんな状況にあっても自分を律し、屈しない主人公はある意味異常なほどだ。一つは主人公が「狩猟」という趣味に逃げ込んでいたことで救われたかもしれない。しかし、それは一つ踏み外せば自分を危険にさらす行為であり、精神の破綻を引き替えにしたものでもあった。
第二巻では国外で暮らす実に多彩な人々の生活・歴史をも伝聞の形式で語っている。イギリス人と国際結婚しナイロビで暮らす日本女性の数奇な人生、奴隷商人につかまったが嵐で船が転覆し奇跡的に助かった祖父の話をするナイロビの使用人の父、海外で生き抜く主人公の目を通して様々な人々の歴史・人生が浮き上がる。多くの人々が交錯するこの巻で著者は人生の儚さ、不思議さと訴えようとしているのだろうか。著者の意図は私には見えてこない、ただ、そういう伝聞を通じて主人公の身に何が起こっても不思議ではない、そういう雰囲気だけは確実に伝わってくる。
全体を通じて読者をグングンと引き込むストーリー展開は一巻から続いている。だが、強いて言えば主人公の内面の葛藤があまり見えてこないのが少し物足りない部分もある。あまりにも早いストーリー展開と物語の広げ方にとまどいを感じつつ、話は御簾鷹山篇へと展開していく。確かに続きを読まざるを得ない。