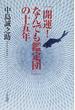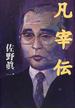和田浦海岸さんのレビュー一覧
投稿者:和田浦海岸
2009/08/11 18:05
神棚・仏壇。
11人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この本を読んだら、家にある神棚や仏壇を思いました。
以下、思いつくままに。余談から。
司馬遼太郎著「この国のかたち」に「ポンペの神社」という文があります。
「十数年前、私が四国の善通寺に行ったとき、そこの国立病院の名誉院長だったこの人にはじめて会った。『私の生家の庭に、ポンペ神社という祠(ほこら)がありまして』といわれた話は、わすれがたい。幼少のころ、荒瀬(進)さんは、毎朝庭に出てその祠をおがまされた。あるとき祖母君に問うと、『ポンペ先生をお祀りしてある』という。オランダ人・・ポンペは、江戸幕府がヨーロッパから正式に招聘した最初にして最後の医学教官だった。・・・安政四年に開講した。・・三期生になって・・百二人という多さだった。三田尻での代々の医家にうまれた荒瀬幾造青年の名は、その百二人のなかに入っている。武士待遇の藩医でなく、庶民身分の町医であるかのようだった。惜しくも幾造は、早世した。
ただ、帰国してめとった妻に、ポンペ先生の人柄と学問がいかにすばらしかったかということをこまごまと語った。それだけでなく、ポンペ先生の恩は忘れられないとして、庭に一祠をたてて朝夕拝んでいたのである。
右のことについて、私はかつて書いたことがある。人間の親切(この場合、ポンペの熱心な講義と学生への応対)というものが、幾造の妻に伝わり、さらには孫の進氏にまで伝わったことに感じ入って『胡蝶の夢』という作品を書いた。・・・・・・・・・・・
唐突だが、右の祠に対する未亡人やその孫の感情と儀礼こそ、古来、神道(しんとう)とよばれるものの一形態ではないか。」
「栗林忠道 硫黄島からの手紙」(文藝春秋)に、昭和二十年一月二十一日の手紙があります。そこから、
「遺骨は帰らぬだろうから、墓地についての問題はほんとの後まわしでよいです。もし霊魂があるとしたら御身はじめ子供達の身辺に宿るのだから、居宅に祭って呉れれば十分です(それに靖国神社もあるのだから)。それではどうか呉々も大切にして出来るだけ長生きをして下さい。長い間、ほんとによく仕えて呉れて難有(ありがたく)思っています。この上共子供達の事よくよく頼みます。 良人より 妻へ 」
この栗林忠道氏についての本を書いたのが、梯久美子氏でした。
その梯(かけはし)氏が、今度「昭和二十年夏、僕は兵士だった」を出された。五人の昭和二十年の回想をインタビューしてまとめられたものです。
その「まえがき」に、こんなエピソードが書き込まれておりました。
「平成19年の春、ある雑誌の記事が目にとまった。俳人・金子兜太(とうた)氏のインタビューである。健康法を問われ、当時87歳の金子氏は、毎朝、立禅をしています、と答えていた。立禅というのは彼の造語で、座禅を組む代わりに立ったまま瞑想するのだそうだ。しかし、どうしても邪念が浮かぶ。そこで、忘れられない死者の顔と名前を、ひとりずつ思い浮かべていくのだという。この人は、こんなふうに死者とつきあっているのか。そう思った。金子氏は戦時中、海軍主計中尉としてトラック島に赴いている。日本の将兵の多くが、おもに飢えのために死んだ島だ。やせ衰えて死んでいった人たちの、小さくなった木の葉のような顔が目にこびりついて離れないと、記事の中で語っていた。」
こうして、この本に登場するのは、金子兜太・大塚初重・三國連太郎・水木しげる・池田武邦。ただのインタビューと違って梯久美子氏は、その戦時中の関連する背景まで記述しておりました。金子兜太氏の文には、同じトラック島にいた梅澤博氏が出てきます。
「朝、仏壇に水をあげるとき、梅澤氏はかならず埋葬した人たちのことを思う時間を持つという。『われわれが思い出すときだけ、かれらは内地に帰ってこられる―――そんな気がするんです。もうあの人たちのことを知っている人間も少なくなりました。生きている限り、わたしが覚えていてやらなくては』」(p26~27)
金子兜太氏が復員船で帰国する昭和21年11月のことも書かれておりました。
「日本から迎えにきた駆逐艦が島を離れるとき、甲板の上から、米軍の爆撃で岩肌がむきだしになったトロモン山が見えた。そのふもとには、戦没者の墓碑がある。このとき金子氏は、こんな句を作っている。
水脈の果(はて)炎天の墓碑を置きて去る
みずからが『人生の転機といえる二つの句のうちの一つ』と言う句である。
甲板の上で金子氏は、墓碑に見られているように思ったという。死者が最後の一瞬まで自分たちを見送ろうとしている、と。」
この梯氏の本には五人が登場するのでした。
その五人を読みおわると、自然と、五人の戦争を思うのでした。すると、「美しい花がある、花の美しさというものはない」という言葉が浮かぶのでした。戦争の悲惨というものはない。ここには、五人の兵士の悲惨さがある。その悲惨をかかえながら、戦後を生きた強さが、たんたんと語られているのでした。
2008/09/20 12:49
「いい仕事してますね」と語る鑑定士・中島誠之助のうしろ姿。
12人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
中島誠之助著「『開運!なんでも鑑定団』の十五年」を読みました。
各雑誌に掲載された文をまとめた一冊。それで、ちょっと読み通すのに時間がかかりました。けれど、読後感の手ごたえは十分。注文原稿でも、手をぬかずに、一回一回丁寧に書かれているため、思わず『いい仕事してますね』と声をかけたくなります。
この本をどう紹介すればよいのでしょう。
テレビ番組『開運!なんでも鑑定団』の初回から登場している鑑定士中島誠之助です。その鑑定が、もしもいい加減だったとしたら、あの番組はどうなるか。と思ってみればよいかもしれません。たとえば、私はテレビ番組「水戸黄門」を思いうかべます。毎回ドラマがあり、最後にカクさん、スケさんが印籠を出して、この紋所が見えないかと提示する。その印籠がニセモノで、そもそも水戸ご老公さまもクワセモノだったなら、どうでしょう。現実的な話です。
そんなことを思う、その参考になりそうな箇所が本文にありました。
鑑定書を紹介しているくだり。
「『鑑定書が付いています』と言われた場合、その事実が真贋の判定にとってはマイナス要因の一つとなります。それは(すべての鑑定書がいい加減な代物であるとはいえませんが)品物に添えられている鑑定書の多くが、信憑性に欠けるものだからです。・・・鑑定書を付けることにより、評価と信頼が跳ね上がるからです。そこにニセ判定の付け込むスキが生じます。程度の低いニセモノほど、かえって仰々しい鑑定書が添付されています。真贋かまわずに片っ端から鑑定書や箱書を乱発した学者や画家もいました。彼らは酒代が欲しかったのですね。」(p76~78)
ここに出てくる鑑定書というのを、鑑定士と言葉をかえてよいかもしれません?
さまざまな鑑定書があるように、さまざまな鑑定士もいるはずで。そして、そういうスキが生じないように、いま現在、ここに中島誠之助が重要な位置を占めているのだなあ、と思ってみるのです。
「美術鑑定の展望」という6ページほどの短文があります。
はじまりは、こうでした。
「美術品を鑑定するようになって四十年以上になる。とはいうものの、そのほとんどは人に鑑定を依頼されたのではなく、自分が入手しようとしている品物の真贋を鑑定してきたことにほかならない。そのために鑑定をあやまれば、即自己の金銭的な損失につながってくる。・・」
そしてこうもあります。
「困ったことに美術品を売り買いするプロたちも、鑑定を依頼された時に真贋をはっきりと回答しないことが多い。彼らは鑑定料を貰おうなどとは決して考えてはいないが、見せられた品物がニセモノだった場合に、真実を告げたがために敬遠され、商売のポイントを一点失うことをおそれるのだ。かりに見せられた物がホンモノであった場合でも、廉価で引き取れば商売として利益が上がるために、あいまいな鑑定結果しかいわないものだ。これはプロとして当たり前のことで、その道何十年苦労して磨き上げてきた鑑定眼を、そうそうたやすく素人に提供するわけにはいかないのだ。・・・・私は自分個人の範囲の中では、決して真贋の判定を公表していない。・・・そこで考えて欲しいのだ。私がレギュラーを務めているテレビ番組『開運!なんでも鑑定団』の素晴らしさを。だれも教えてくれない真贋の真実を、ずばりと腹蔵なく判定するのは、あの番組をおいてほかにはないのだ。私はプロを返上し、番組の中では真実の追求に邁進している。・・」(p94~99)
ちょくちょくと、テレビをつけては、そそくさとチャンネルを移動して、雑読ならぬ、雑見している私ですが、鑑定団の番組は、意外と見ていたことに気づきます。その魅力のありかをこの本は教えてくれています。「いい仕事してますね」と語る男のうしろ姿をご覧になりたければ。これは、またとない一冊となっております。読み始めると、読者対象がちがう雑誌に掲載された短文の集成でとまどうのですが、なあに、読み終ってみれば、さまざな方向から、中島誠之助を浮き彫りにしてくれている、貴重な一冊。
2007/06/20 01:48
「好きです」と本・人を語りはじめる新鮮さ。
11人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
高島俊男著「座右の名文」(文春新書)が魅力です。
「好きです」と、本・人を語り始める鮮やかさ、すばらしさ。
こりゃ紹介するにこしたことはないでしょう。
「ぼくは内藤湖南がすきです。頭のいい人であり、学問ができる人であり、また書いたものはみなおもしろい」(p88)
「ぼくは津田左右吉が大すきです。すきということでは斎藤茂吉と双璧といえる。ただこの二人、性格がまるでちがう」(p135)
「元来ぼくは、柳田國男の文章とはあまり相性がよくない。しかし、『遠野物語』だけは別だ。近代文語文の最もすぐれた文章であり、卓越した文学作品であると思っている。手もとには、なんべんも読みかえしてぼろぼろになった『遠野物語』がある」(p159)
こうして柳田國男の『遠野物語』をとりあげたかと思えば、寺田寅彦では「この人の書いたものはどれを読んでもおもしろい」(p191)とあります。「もし、日本の文学者のなかでだれが一番すきか、と問われたら、ウームとしばし考えて『斎藤茂吉』とこたえるでしょうね、多分。茂吉のなにがすきなのか、といえば、その人物がすきなのである」(p199)
さてさて、この新書の核は「まえがき」にあり。
この10㌻ほどの「まえがき」を、丁寧に読めばそれでOK。
その「核」を種として、育った新書。桃栗は三年ですが、この新書は三年半。
いきさつを知りたい方は「あとがき」に詳細が語られております。
ことほどさように、「まえがき」「あとがき」がしめる位置の確かさ。
その確かさに、楽しみが充満している醍醐味があるのです。
それを、ちょびちょびと削っては紹介するのがもったいない。
勿体ないけれども、ここで終らせるにはしのびない。
ということで「まえがき」のエッセンス、
これだけは読んでのお楽しみとしておきましょう。
ちょいとぶつ切りに紹介するのはしのびない。
新井白石についてでは「『西洋紀聞』という本がある。白石がのこした多くの書物のなかでも最もおもしろい、感動的なものだ」(p24)
本居宣長の最後では「もちろんぼくも、宣長の思想に共鳴するものではない。しかし『玉勝間』という書物、これは・・宣長が年をとって、学問が熟して、まことにおだやかな、常識的な、たいがいのところは筋のとおったことが書いてあって、たいへんにおもしろい。そのへんが、ぼくはすきなのである」(p58)
この新井白石・本居宣長の二人は、つながっていっしょに読んでみると興味深いのでした。
また森鴎外を語るのに向田邦子の文からはじめております。ここの家族との接し方が夏目漱石の家庭への伏線になっておりました。幸田露伴の箇所はまるで高島俊男ご自身を解剖してゆくような雰囲気がただよいます。
そういえば「あとがき」は、「この本は、ぼくにとって初めての、しゃべってつくった本である」とはじまっておりました。そこにこんな箇所がありました。
「2004年いっぱい、ぼくが東京へ行くたびに五反田のアパートへ来てもらって、二人を相手に、しゃべりにしゃべった。録音はどんどんたまったが、これがどうにも文章にまとまるしろものではなかったらしい。たとえば露伴についてしゃべるとなると、話を聞いてくれる人がいるのをいいことに、露伴に関することならなんでもかんでも、とりとめもなく野放図にしゃべったからである。・・録音は、しゃべるにかけたと同じだけの時間をかけて聞くよりしょうがない。そのしゃべりの内容は、脈絡なく、あっちへとんだりこっちへとんだりである。・・結局一年あまりしゃべって、録音の山ができて、計画は挫折してしまった。しばらくはそれっきりになっていたところ・・・」(p220)
今回はこれくらいにしておきます。
というか、この魅力ある新書の紹介は、ここで挫折。
紙の本詩のこころを読む
2006/02/21 18:46
自分の詩を載せない。という詩人のいさぎよさ。
12人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
2006年2月19日に、詩人茨木のり子さんが自宅で亡くなっておられたという死亡記事が20日新聞に載りました。79歳でした。詩人が消えてしまわれた。言葉だけを残して。
そこで、あらためて皆さんに読んで欲しい茨木のり子の一冊はと思うと、詩集ではなくて私にはこの本が思い浮かびました。
この「詩のこころを読む」が岩波ジュニア新書に登場して(1979年)、翌年すぐに向井敏が魅力ある書評をします。
その書評の最後は
「現代詩案内として、また現代詞華集として得がたい一冊。
体裁こそジュニア向けだが、人生経験を積んだ大人にこそ
むしろふさわしい。」と締めくくられておりました。
以前、2002年の高校国語教科書掲載一覧を覗いていたら、茨木さんの名前が19箇所もひろえました。よく知られた詩ばかりでしたが、変わったところでは、学校図書「国語Ⅰ」が、詩「言いたくない言葉」をとりあげておりました。
じつは茨木さんのこの新書「詩のこころを読む」には、ご自身の詩を載せておられません。そのいさぎよさに気づいた童話屋の田中和雄さんは、「おんなことば」という茨木さんの詩の詞華集を編み(1994年)、それから「ポケット詩集」(1998年)に茨木さんの詩を3つ載せました。ちなみに3つの詩は「聴く力」「汲む」「自分の感受性くらい」です。田中さんの「おんなことば」のあとがきと「ポケット詩集」のまえがきの言葉は、どちらも「詩のこころを読む」の「はしがき」の言葉からバトンを受取った走者のようにつながって読むことができます。
詞華集といえば、「教科書でおぼえた名詩」文春ネスコ編(1997年)がありました。この本、解説・説明のたぐいが、ないのです。それはまるで詩の門前が、きれいに掃き清められてでもいるかのようです。表紙の写真には臨海学校の海で、丸坊主の子どもたちが、海の家の黒いタイヤチューブの大きな浮き輪に10人ほどでつかまってカメラに向って笑っています(田沼武能・写真)。本の最初に島崎藤村の言葉を、序にかえてでは、丸山薫の詩「学校遠望」を置いています。今年教科書一覧で茨木さんの「わたしが一番きれいだったとき」が中学で二冊(東京書籍2年・三省堂2年)。高校で四冊(三省堂国語Ⅰ・教育出版Ⅰ・筑摩書房Ⅱ・第一学習社Ⅱ)とりあげておりました。なぜだろうと思って、この文春ネスコの本をひらくと、与謝野晶子の「君死にたまふことなかれ」の次に「わたしが一番きれいだったとき」が並べられてありました。
さて、茨木さんの詩「言いたくない言葉」は、
ふつう詞華集ではお目にかかれません。ここに引用します。
「心の底に 強い圧力をかけて
蔵ってある言葉
声に出せば
文字に記せば
たちまちに色褪せるだろう
・・・・・・・
人に伝えようとすれば
あまりに平凡すぎて
けっして伝わってはゆかないだろう
その人の気圧のなかでしか
生きられぬ言葉もある
・・・」
この詩のなかの
「たちまちに色褪せるだろう」言葉を、現代詩として造型した詩人たち。
その詩たちを茨木さんはこの本で掬い上げておられます。
そう、自分の詩は一切取り上げないいさぎよさでもって、
その詩たちは、取上げられ、語られています。
もう四半世紀前(27年前)のこの本が、今どのように読まれるのか、古くて新しい本をあらためて、この機会に、ここに紹介してみようと思います。
紙の本紙つぶて 自作自注最終版
2005/12/19 23:47
何度も、何回でも聞いていたい。本読み人への応援歌。
12人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
昭和53年刊行の「完本・紙つぶて」(455編)に、改めてそれぞれ一篇ごとに新稿を書き加えた本です。見開きの片㌻に旧稿。もう片方の㌻に新稿が並んで943ページ。とりあえず、私は新稿だけを読みました。旧稿と新稿との関係は、短歌の自歌自註。連歌俳諧の付合(つけあい)の気分を、この書評コラムで実演してみせます。
付きすぎもせず、離れすぎもしない。その間合いが、まるで詩の改行のように私には見えます。
ご自身はこう語ります。
「書評や書物随筆の醍醐味は、取り上げた一冊にこだわらず、
それに関連する読書の話題を、適宜に繰り出す手法にある」(p421)
最後には
人名索引・書物索引がしっかり頼もしく並びます。
たとえば、今年(2005年)岩波書店の「新日本古典文学大系」全100巻・別巻5が11月に完結しておりました。それじゃあ、その大系を取りあげた箇所はというと、4箇所でした。紹介がてら、ひとつ引用しながら始めます。
「古典文芸の読解とは、時を隔てた昔の作品が、当時の読者によってどのように面白がられたのかを照らしだす作業であり、さらには、その作品を現代のわれわれがより深く感じとれる道筋をしつらえる努力であると、中村幸彦先生から教わったものである。」
こうはじめて、おもむろに新日本古典文学体系を語るのです。
(ちなみに人名索引では「中村幸彦」が38箇所並びます。
この箇所だけでも拾い読みして気持ちいい充実感を味わえます。)
さて、
「安東次男の『芭蕉七部集評釈』正続は、俳諧の歌仙がこれほど人間臭く奥行き豊かに読みとりうるのかと、読みかえすごとに興を深める絶品である。・・・ところで新日本古典文学大系『芭蕉七部集』の校注を担当した白井悌三および上野洋三は、七部集の参考文献のリストから安東次男の著作を削り、そういうものが世に存するとは認めないという姿勢を示した。ちなみに上野洋三は芭蕉自筆本『奥の細道』を鑑定し、その然らざるゆえんを以て増田孝に叩かれた。」(p699)
それで、安東次男について知りたくなったら。
すぐに、検索できるようになっております。
「芭蕉七部集の注釈と言えば、まず幸田露伴の仕事が挙げられ・・
露伴が句をあしらう時の方法は、底知れぬ博学宏識を以て縦横に解する面白さにある。・・ところが芭蕉の俳風が次第に変って、殊に画期的な『猿蓑』に至ると、露伴流の博識が句解の役に立たなくなる。露伴評釈が興趣をそそるのは、『冬の日』、『春の日』、『あら野』『ひさご』、この四つの巻に尽きるのではないか。そのあとを継ぐかのごとく、殊に『猿蓑』を中心として蕉風に参入したのは安東次男であろう。・・・」(p315)
それでは、この「紙のつぶて」が他とどう違うのか。
それに触れた箇所は、丸谷才一・山崎正和・木村尚三郎と、
その三人の鼎談書評を取り上げた場面でした。
「この鼎談書評が名企画による見事な完成品であること言うまでもないけれど、実際に取りあげた本が文芸およびその周辺に偏りすぎ、この時代に大きな顔をしていた経済の本が、ほとんど視野に入っていないこともまた事実である。・・・鼎談書評三冊目は一刀両断の試し斬りに偏っているので、そこへ経済書を投げこめば、ほかの本との比較が楽しめたであろうにと思ったのである。」(p683)
そんなことを語ったかと思うと、
「平成16年の大河ドラマ『新選組!』のとっぱしから、近藤勇と坂本竜馬が交友親しく談笑したので、多くの人が度肝をぬかれたけれど」(p877)といった話題まで「それらがいったい何の役に立つかを見抜く眼力」(p441)
そういう谷沢永一の眼力を堪能する醍醐味が詰まっての「自作自注最終版」。
2005/07/21 00:03
歴史家と哲学者。
11人中、11人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
八木秀次さんは語ります。
「・・そういう人々は自らに連なる歴史という実感に乏しいんでしょうね。どこか【第三者の歴史】という感覚でいる。アイデンティティの喪失であり、自らの都合のいいように歴史を取捨選択しようとしている。私たちが背負っていくのは『人類史』という抽象的なものではなく、『日本人の歴史』です。その根幹には、先人に対する慰霊がなければならない。・・」(p153)
渡部昇一さんは語ります。
「日本文明がシナ文明と決定的に異なるところは何か。私は前に述べた言葉(古代文学に漢語がほとんど入っていない)と神道、つまり神社だと考えています。神道は体系だった教義を持ちませんが、象徴的に示すものとして樹木との関わりがあります。『日本書紀』に、こんな話があります。須佐之男命が高天原を追い払われ、韓の国へ行く。しかし木がないから嫌だといって戻ってくる。息子の五十猛命(いたけるのみこと)は木の種をたくさん持っていたが、韓の国に植えずに持ち帰って、九州や紀伊国に植えた。だから紀州を『木の国』という。ちなみに紀州は五十猛命を祀っている神社があります。・・キリスト教を含めて世界の宗教はたいがい木を伐り払って宗教施設を建てている。日本では木を伐らず、森や林の中に神社を建てる。この木を伐らないということは、神道の際立った特色だと思います。明治神宮も伊勢神宮も森の中にあります。それが神道の原型だからでしょう。面白いのは、東京の神宮の森は明治神宮とともに生まれたということです。つまり神社のために東京という大都市の真ん中に森をつくったわけです。明治の日本人は西欧文明を取り入れながら、木を伐らずに森をつくろうとした。・・これは他国にはありません。明らかに外国の文明の影響を受けていない日本の重要な要素は神道なのです。さらに言えば、日本文明がシナ文明に対峙するとき、最も有効だったのが神道です。
・・靖国神社をなぜ政治的な取引に供せないか、これで自明でしょう。靖国問題で譲歩することは、日本文明の放棄を意味し、日本は総崩れになりかねない。現在の中国政府もそのへんを歴史的に感じているからこそ・・、執拗に譲歩を迫ってくるのです。」(p169〜172)
さて、高橋哲哉著「靖国問題」(ちくま新書)で、高橋氏は「はじめに」で、ご自身を「哲学者」と自称しておりました。以下引用。
「私は歴史家ではなく、哲学者の端くれである。靖国問題がどのようなものであるかを知るためには、その歴史を知らなければならないが、本書の中心テーマはそこにはない・・・」。
どうやら、歴史を都合よく切り貼りしての論理を弄んだ新書であると高橋哲哉氏の内容を想像するわけです(ちょいと、読み進むことが出来ませんでした)。どうやら高橋哲哉氏の言葉をかりて語るとするなら・・・私は哲学者ではなく、日本人の端くれである。靖国問題がどのようなものであるかを知るためには、その歴史を知らなければならないが、私の知りたいと思う中心テーマは新書「靖国問題」のそこにはない・・・。
自称哲学者が哲学に馴染んでいるあいだに、
英語学者で歴史家でもない
渡部昇一氏は日本の探求の手を緩めずに、その根幹を尋ねるのでした。
科学者の寺田寅彦が芭蕉の俳諧を書いた文に
「俳諧の本質を説くことは、日本の詩全体の本質を説くことであり、やがてはまた日本人の宗教と哲学をも説くことになるであろう」とありました。
やがては説かれるであろう「日本人の宗教と哲学」を
どこの馬の骨ともしれない自称哲学者が、ふりまわす
「論理的に明らかにする」言葉には見出し難いと私は断定いたします。
紙の本江戸時代語辞典
2009/04/05 09:43
なんともミーハーな書評紹介。
11人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
まったくもって、ミーハーな私であります。
この本。とても私には手が出せない金額であります。
その癖して、なんとも開いて見たい誘惑に駆られます。
というのも、魅力ある書評を読んだからなのでした。
それではと、ミーハーなわたくしは、どう考えたか。
魅力のある、書評を取り上げるという変則ワザ。
つまりはね。書評の紹介なのであります。
やっぱりね。いいものは、書評でもいいのであります。
それに、私に手が出なくても、他の方は別かもしれません(笑)。
ということで、はじめます。
はじまり。はじまり。
2009年3月30日のコラム産経抄はこうはじまっておりました。
「国文学者の尾形仂(つとむ)さんは戦後まもなく、昼食の握り飯を包んでいた新聞で、恩師の訃報を知った。恩師とは、近世文学研究の大家、頴原退蔵博士だ。戦前に東京文理科大学の学生だったころ、俳文学の指導を受けていた。尾形さんは卒業後海軍へ入り、当時は土木の仕事に就いていた。・・・・」
ところで、頴原退蔵(えばらたいぞう)博士というのは、いったいどのような方なのでしょう。 私は未読。そういえば、林望氏の文に、登場しておりました。 その箇所を引用。
「私は学者の世界に長くいたけれども、学者たちが書く文章は、ほんとうに下手くそなのが多い。それも気取りに気取って、生半可で・・・私は学者先生の書く学術論文というもは、ほんとうに読みたくない。なかには、戦前の古典学者池田亀鑑(きかん)博士や、近世文学の頴原退蔵博士のように、高度な内容を分かり易く面白く書ける先生もいたけれど、それは例外で、現代ではほとんどそういう人は見かけなくなった。・・・」(p125~126・「日本語は死にかかっている」NTT出版)
話をもどして、産経抄。
尾形さんは遺族にお悔やみの手紙を送ったことが縁となり、頴原氏の次女、雅子さんと結婚することになったそうであります。学究生活へと戻る。その続きを引用してみます。
「頴原氏にはやり残した大きな仕事があった。江戸時代の言葉を網羅した辞典の完成だ。昭和10年ごろから、用例を集めてカード作りを始め、その数は10万枚に達していた。【江戸語辞典執筆半ばに父逝きて用例カード空しく遺りぬ】。雅子さんは自らの歌集『夜の泉』のなかで、父の無念をうたっている。やがて夫婦は静かに年輪を重ねていった。・・・尾形さんの脳裏から、義父の辞典のことが離れることはなかったようだ。古希(70歳)を迎えたのを機に、教え子たちに呼びかけ、完成をめざした。【用例の乏しき中より語意を汲むと腐心の夫に父が重なる】。そんな夫を見守ってきた雅子さんは、辞典の完成を見ることなく、平成18年に79歳で亡くなった。『江戸時代語辞典』(角川学芸出版)が、「構想70年」と銘打たれて刊行されたのは、昨年11月のことだ。【妻雅子に対し、やっと約束を果たすことができた】。辞典の前書きの欄外に、小さな文字で記した尾形さんは26日、雅子さんの待つ浄土に旅立った。89歳だった。天寿を全うするとは、このことをいうのだろう。」
その日の産経抄の、ほとんどを引用してしまいました。
ところで、尾形仂ご夫婦をむすびつけたところの「握り飯を包んでいた新聞に」という箇所に私は興味を持ちました。 そういえば、お祭りなどの屋台で、焼きソバは、その昔は新聞紙の切ったのが皿の代わりになってました(笑)。
終戦直後のようすは、どうだったのか。
「幸田文台所帖」(平凡社)にこんな箇所がありました。
「戦争のおにぎりは、新聞紙のおにぎりだ。木の葉ならばいさぎよいものを、新聞でじかに包んだおにぎりには、紙のケバがくっついて活字のあとがしみていた。印刷のおにぎり、文字のめしである。それをたべてしまうのだった。印刷おにぎりを超満員の列車の便所の扉に押しつけられながらしみじみ眺めていて、同行のある出版社の青年は『無条件か、―――」とわんぐり食いついた。・・・・」(p36)
むろん推測なのですが、尾形仂氏の戦後を決定する「昼食の握り飯を包んでいた新聞」というのも、そんな感じだったのではないでしょうか。
紙の本凡宰伝
2008/05/06 09:56
二日つづけてこの本がbk1で取り上げられてたので、三日目は私(何やら、読書会みたいです)。
13人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この本が、二日続けてbk1の新着書評で取り上げられておりました。
それじゃ。私も、だいぶ前に書いたのですが、載せてみましょ。
そうそう。何だかbk1上で読書会でもしているように。
月刊雑誌文藝春秋の2005年12月号。
そこにある、特集「消える日本語」が楽しかった。
ついつい26名の短文を読んじゃいました。
そこでの、出久根達郎氏は「おてんと様」という題で、こうはじまっておりました。
島根県松江のラフカディオ・ハーンは、朝陽がのぼる頃に、あちこちから拍手(かしわで)を打つ音がするのを聞くのでした。「明治23年のことであった。『お天道(てんと)様』信仰は、この頃、松江だけでなく、全国で当り前に行なわれていたと思われる。一日の、最初の挨拶みたいなものだったろう。太陽に今日の無事を祈って、それぞれの稼業を始めるのであった」
茨城県から上京した出久根さんは
「東京に住んだのは昭和34年だが、その当時、毎朝、陽を拝む人は、まだ見られた。老人が多かった。江戸のなごりをとどめる下町だったからか。拍手を鳴らす人はなく、静かに拝礼していた」
そして、年表を調べ、昭和37年に『スモッグ』が流行語となり、この年の12月は、14日間も東京の空はスモッグにおおわれた。と確認した出久根さんは「おてんと様という言葉が、遣われなくなったのは、この頃からではあるまいか」としております。
印象深い箇所は上京する出久根さんに母親が
「『おてんと様に顔向けできないような真似だけは、しないでおくれ』と言った。おてんと様は何事もお見通しだからね、とも言った」
とあります。
ああそうだ。ということで思い出したのが、今回紹介の本でした。
思い浮かんだのはこの箇所です。
「小渕さんはとにかく早起きなんです。六時くらいには起きてましたね。そして必ず太陽に向かって拝んでました。・・小渕は海外に行くといまでも、太陽を拝んでいる。太陽が出る東の方角がわからないときには四方八方に向かい拍手を打つ。」
そしてインタビューに答える小渕首相の言葉が続きます。
「太陽は親父が拝んでいたのを、見よう見まねで子どもの頃はじめた。自分の運命を考えてみても、天地宇宙、人知の及ばざることは多いと思う。べつに総理大臣になったから偉いなんて、おれは全然思ってないんだ。・・ただこれだけの重責を負った以上は果さなければならない。これまでを振り返ってもずいぶん転機があった。それは自分でこしらえたものじゃない。そう思って、毎日、太陽に向かって手を合わせるという素朴な気持ちなんだ。・・・」
なぜ、小渕恵三氏の本が思い浮かんだのかなあ。
そういえば、
最近、曽野綾子著「『受ける』より『与える』ほうが幸いである」(大和書房)という本を手にとりました。 最初の方をめくると2000年10月号の雑誌に掲載されたことのある 教育改革国民会議「第一分科会報告」が、あらためて掲載されておりました。題して「学校で道徳を教えるのにためらう必要があろうか・・日本人へ」。
ちなみに、この教育改革国民会議を開催したのは小渕首相でした。
中央公論2000年3月号に「司馬さんに教わったこと」と題して、
司馬遼太郎の奥さん福田みどりさんと小渕恵三氏が対談をしておりました。
そこには、こんな箇所。
「僕はいま、教育改革国民会議というのを開こうとしているんですよ。いままでのこういう会議では、政府が人を選んで、その人たちに案を出してもらっていました。僕は逆に、『野に遺賢なからしむべし』で、いろいろな百五十人余の人に手紙を出して意見を求め、そのうえで会議を進めようと思っている。しかし、最後にお願いしたい人となると、司馬さんなんだ。しかし、いらっしゃらない。」
そして、ご存じのように小渕氏は2000年4月2日緊急入院。5月14日に亡くなっておられます。そういえば、今年も5月5日の子どもの日が過ぎて、もうすぐ小渕恵三元首相が亡くなった5月14日が来るのでした。
紙の本直筆で読む「坊っちやん」
2007/10/25 09:44
「読みにくいかも知れないが、是でも一生懸命に書いたのだから、どうぞ仕舞まで読んでくれ」とは清から坊っちゃんへの手紙。
10人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
この夏目漱石の直筆原稿は、読み甲斐がありますよ。
原稿用紙の枡目ごとに、きちんと、ひと文字づつ書きこまれており、草書の、のたくってくっついているくずし字ではありません。丁寧な文字なのです。ですが、平仮名が変体仮名なので、最初は何とも違和感があります。
この<直筆で読む「坊ちゃん」>には、最初に秋山豊氏の文があり、次に漱石の原稿。最後に夏目房之介の文が載っております。
最初の秋山豊さんの文には、実際に通読する際の読みにくさを解消するための手引きとしても書かれており、急がば回れという気持ちでまずは読まれるとよいのでした。
私は「変体仮名早見表」(p63)を何度も参考にして読み進みました。秋山氏いわく「変体仮名や漢字の崩し方、仮名遣いなどは、はじめのうちこそ困難を感じるだろうけれども、二、三頁読み進めれば次第に慣れて、さほど困難は感じなくなると思う」(p13)と書かれております。
最後にある、夏目房之介さんの「読めなかった祖父の直筆原稿」では、
「残念ながら孫の僕には、それをストレスなく読みこなすリテラシーはない。我慢して数ページ読んだが、すぐ挫折してしまった。印刷された小説は何度か読んでいるから、なんとか読めるかと思ったが、いかんせん『面白くない』のだ。まあ、面白がらせる字を書いているのではなく、読みやすく書いたのだろうから当たり前である」(p369)とあります。
じつは、私はお孫さんの夏目房之介さんが「挫折してしまった」と書いているのを読んで俄然、読む気になりました(笑)。
というのも、最初は字面を追うのがやっと。内容を楽しんではいなかったのですが、原稿用紙13枚目の四国へと旅立つころから、にわかに文字を追うのが苦痛ではなくなりました。ということは、20ページぐらい読んでからやっとエンジンがかかってきたようなわけです。それもこれも、房之介さんの「挫折」が励みになりました。
さて、このようにして読んで来るとですね。
清から坊ちゃんへの手紙が、印象に残るのです。
たとえばこんな箇所。
「今時の御嬢さんの様に読み書きが達者でないものだから、こんなまづい字でも、かくのによっぽど骨が折れる。甥に代筆を頼もうと思ったが、折角あげるのに自分で書かなくっちゃ、坊っちやんに済まないと思って、わざわざ下た書きを一返して、それから清書をした。清書をするには二日で済んだが、下た書きをするには四日かかつた。読みにくいかも知れないが、是でも一生懸命に書いたのだから、どうぞ仕舞迄読んでくれ。と云ふ冒頭で四尺ばかり何やら蚊やら認めてある。成程読みにくい。字がまづい・・・おれは焦つ勝ちな性分だから、こんな長くて、分りにくい手紙は五円やるから読んでくれと頼まれても断はるのだが、此時ばからは真面目になつて、始から終迄読み通した。読み通した事は事実だが、読む方に骨が折れて、意味がつながらないから、又・・・・」
さて、ここで庭が登場します。
「又頭から読みなおして見た。部屋のなかは少し暗くなって、前の時より見にくくなったから、とうとう椽鼻へ出て腰をかけながら丁寧に拝見した。すると初秋の風が芭蕉の葉を動かして、素肌に吹きつけた帰りに、読みかけた手紙を庭の方へなびかしたから、仕舞ぎわには四尺あまりの半布がさらりさらりと鳴って、手を放すと、向ふの生垣迄飛んで行きそうだ。おれはそんな事には構って居られない。・・・」
もう一か所、庭が登場します。清へと手紙を書こうとして書けない。ながなが書けない理由を並べる箇所でした。
「・・庭は十坪程の平庭で、是と云ふ植木もない。只一本の蜜柑があって・・・」
おっと、話がそれてしまいました。
この秋の11月18日まで、江戸東京博物館にて特別展「文豪・夏目漱石」が開かれているそうです。直筆原稿や写真など資料が豊富。見どころの一つは東北大学所蔵の「漱石文庫」が並んでいる「展示されている蔵書の約400冊はロンドン留学時代に購入した洋書だ。シェークスピアなどの文学作品や評論が中心だが、中にはジョーク集やマナー集も」(読売新聞10月8日文化欄から)。ということで博物館へ出かけられるのも面白いでしょうが、ここはひとつ居ながらに「坊っちゃん」の草稿写真版全文を読めるありがたさ。
丸谷才一は新聞連載「袖のボタン」で、外国では普通単行本になった時点から百年と計るのだそうです。『坊っちゃん』がホトトギスに掲載されてから百年が、去年でした。ところがもうけもので、今年も『坊っちゃん』百年を祝えるたのしみが続きます。そんな二度目の楽しみに際して、思いもしなかった最高のプレゼント。
最後に、この新書の後記では、さりげなくこう終っておりました。
「『坊っちやん』が単行本に収められてから、ちょうど100年・・・この節目の年に、新書版という小著ながらも、『坊っちやん』の直筆原稿、及び漱石肉筆の魅力を、今の時代のより多くの読者に引き継げたことを、ここに報告します。」
拍手。
紙の本私家版・ユダヤ文化論
2006/07/22 14:35
さっそく買って読みました(笑)。
11人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
最近はもっぱら、書評を眺めて、そこから本を選び、買います。
さて、今回紹介の本はというと、予告篇が長かったなあ。
季刊「考える人」に3回にわたって、この本が取り上げられていたのです。紹介者は養老孟司さんでした。
2006年冬号の連載「万物流転⑮」が「ユダヤ問題」と題して、
内田樹(たつる)氏のこの本を語って、
「連載の初回から思わず釣り込まれてしまった」とはじまっておりました。
2006年春号・夏号では養老孟司・内田樹対談を前編・後編と分けて掲載しており、どちらも楽しく読みました。 楽しく読んだのですが、肝腎な話題になっている本が、それこそ、いまだ刊行されていなかった。
それが、この7月20日に新書で発売になりました。
内容は硬いのですよ。「ユダヤ問題」「シオン賢者の議定書」「ペニー・ガム法」などと出てくるのですが、その間をすいすいと繋いでゆく語りかけがよくこなれている。というか、魚がスイスイと障害物を避けて泳いでゆくような、自在な論の進め方です。
こんな箇所があります。
「彼が善意であることも無私無欲であることも頭脳明晰であることも彼が致命的な政治的失策を犯すことを防げなかった。この痛切な事実からこそ私たちは始めるべきではないか。そこから始めて、善意や無私や知力とは無関係のところで活発に機能しているある種の『政治的傾向』を解明することを優先的に配慮すべきではないか。私はそのように考えている」(p105)
さて、内田樹さんの泳ぎ方はというと、
「読者にとってはまことに迷惑なテクスト戦略であるが、『私にわかっていること』だけをいくら巧みにつぎはぎしても、ユダヤ人問題に私は接近することができない。・・・ユダヤ人問題を30年近く研究してきてそのことだけは骨身にしみてわかった。・・ユダヤ人問題というのは、『私の理解を絶したこと』を『私に理解できること』に落とし込まず、その異他性を保持したまま・・次の受け手に手渡すというかたちでした扱えないものなのである。・・・いかなる政治学的・社会学的提言をもってしてもユダヤ人問題の最終的解決に私たちは至り着くことができない。これが私の立場である。」(p162)
さて、季刊雑誌の養老・内田対談は、というと未発表部分を含めて新潮社より単行本になる予定なのだそうです。
新書を読んで、対談を読むというのも楽しめます。
私など、予告編にあたる対談を読まなかったら、この新書買わなかっただろうなあ。そう思うと対談のよさを感じます。
ちなみに新書のあとがきに
「もとになったのは2004年度後期の神戸女学院大学での講義ノートである」なんて言葉があり、その次には
「三回の担当時間が終わってレポートを集めたら、『ユダヤ人が世界を支配しているとはこの授業を聞くまでは知りませんでした』というようなことを書いている学生が散見され。これは困ったことになった」とあります。
うんうん。そういう困ったことがおきないためにも、養老孟司・内田樹の対談は出版されるほうがいいですね。と思ったりします。新書と対談と両方いっしょに読めば楽しさの厚みが何倍にもふくらむのでした。
紙の本日本を虐げる人々 偽りの歴史で国を売る徒輩を名指しで糺す
2006/06/01 23:50
社会主義から学ぶべきものは何か。
12人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
池田潔著「自由と規律」(岩波新書)がありますね。
最近その本のレビューを2つ読みました。そしたら、
私が連想したのは池田清著「海軍と日本」(中公新書)なのです。
そう、池田潔と池田清というキヨシの連想でした。
司馬遼太郎の、街道をゆく42「三浦半島記」がありますネ。
そこにこんな箇所があります。
「余談ながら、
【比較躾(しつけ)学】ともいうべき貴重な経験をした学者がいる。池田清氏である。1925年、鹿児島県うまれ・・江田島の海軍兵学校を出、中尉のときに敗戦をむかえた。戦後、七高から東大法学部を出、一時期、大阪市大法学部で教えた。その大阪時代(昭和40年代)奇縁を得て、英国のオックスフォード大学に研究留学した。寄宿舎に入った。三、四人が同室で、室での起居のマナーが、パブリックスクールそのままだった。同室の若い学生たちが、日本からきた老学生の身ごなしのよさにおどろいた。同室のイギリス人学生たちはふしぎに思ったらしい。『われわれでも、ここでのマナーは厄介なのに、君はその日からやっている。どういうわけだ』いわれてみて、すでに四十代になっていた池田清教授は、自分が経た江田島の海軍兵学校での起居のマナーとそっくりであることに気づいた」
こうして
司馬さんの余談は旧海軍の話に入ってゆくのでした。
(ちなみに司馬遼太郎さんは1923年生まれで陸軍)
ここから、池田清氏の「海軍と日本」を話します。
そこでは、海軍にひそむ体質的欠陥が遠慮なく指摘されております。
「短剣と白手袋に象徴されるスマートな清潔さの奥に潜む、このずるさと無責任さとひよわさには、明治以来の日本の知識人一般と相通ずるものがあるように思われる」とはじめに語っております。
たとえば、昭和17年8月8日の第一次ソロモン海戦をとりあげて、「ここには、まる二日にわたる七段がかりの執念深い追撃線という日本海海戦の戦訓はまったく忘れられており・・異常なまでの淡白さと性急さがうかがわれる。当時、南東太平洋方面最高指揮官のハルゼー大将は、この海戦の直後、『日本人は勝ったと思うと引き揚げていく。決して追撃して来はせんから心配するな』と・・語ったという」(p46)
だいぶ「余談」の
寄り道をしすぎたでしょうか。
今回紹介する鼎談本は、少しずつ題名を変えてこれで3冊目。渡部昇一氏は「私は、大切なことは何度でも繰り返し主張すべきだと思っています」(p32)と語ります。
私は、ここで鼎談を読みなさいとは薦めるわけではありません。ですが、「淡白さと性急さ」を持つ日本知識人一般の側にたって、愚直に繰り返している渡部昇一氏の主張を嘲ってはならない。
と申し上げたいのです。そういう嘲笑に含まれる「ずるさと無責任さとひよわさ」をもうすこし自覚しようではありませんか。
渡部氏はこうも語っております。
「私はこれまで何度も繰り返し述べてきましたが、『朝日新聞』やNHKがこの事実を取り上げるまで何度でも述べたいと考えているのが、1951年5月3日に米上院軍事外交合同委員会で・・マッカーサーが語った次のような一節です」(p149)
この一節は、渡部氏の読者なら先刻ご承知のことでありますし、まだ確認しておらなければ、注意が必要な、受け止めるべき問題なのです。
渡部氏は最後に
「かつてハイエク教授がこう呟いていたのを思い出します。
『社会主義者からわれわれは学ぶものは何もないと思っていたが、たった一つあった。それは彼らが、繰り返し語ることだ』われわれも彼らに倣って、繰り返し語ることにしましょう」
こういう学び方が、体質的欠陥への一番の処方箋じゃないでしょうか。そう私は思ったわけです。
紙の本氷川清話
2005/11/14 00:30
こんなところで、勝海舟。
10人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
最近、NHKで浜口梧陵を紹介するアンコール番組を見ました。
戦前の尋常科小学国語読本に「稲むらの火」として掲載された人物です。
その実話の主人公が浜口梧陵。
1854年の安政南海地震津波での村人を救う臨機応変の対処。
その大津波の後の村の復興として堤防建設への献身。
昭和9年に編集・発行されたその人の伝記を、現代語訳して
和歌山県広川町が配布しており、注文すると簡単に手に入ります。
送料共に1000円もかかりません。その人となりを知るには、まず広川町のHPを開いてご覧になってはいかがでしょう。
という話とは別に、浜口梧陵小伝にはこんな箇所がありました。
「梧陵は・・佐久間象山、勝海舟等の先覚者のもとで兵学及び砲術を研究し、勤王家と知られた有田の先輩、菊地海荘とも交流し、一層、尊王攘夷と開国との得失を深く研究した。梧陵と海舟との交際は、彼が象山を訪問した後間もなく始まったので、嘉永三、四年の頃と思われる。文政六年に生れた海舟は・・まだ世に認められず貧困であったため、経済的に梧陵に頼るところが多かった」とあります。
そういえば、
「氷川清話」の最初の方に「渋田利右衛門のこと」という箇所があります。
それは、読書家ならずとも一読忘れられない箇所でした。
貧乏をしていた頃の海舟が、書物商の店先でもって、立って書物を読むことにしていたそうです。店主が、貧乏を承知でいろいろと親切にしてくれ、北海道の商人渋田にその海舟の話をしたそうです。ある日海舟の家に来る。(以下は直接「氷川清話」から)
「渋田は自分でおれの家へやってきた。そのころおれの貧乏といったら非常なもので、畳といえば破れたのが三枚ばかりしかないし、天井といえばみんな薪(たきぎ)にたいてしまって、板一枚も残っていなかったのだけれども、渋田はべつだん気にもかけずに・・帰りがけになって、懐から二百両の金を出して、『これはわずかだが書物でも買ってくれ』といった。」
「それからというものは双方絶えず音信を通じていたが、おれがいよいよ長崎へ修業にいくことになると、・・渋田は『万一、私が死んであなたの頼りになる人がなくなっては』といって、二、三人の人を紹介してくれたが、その一人は嘉納治右衛門、これは治五郎(柔道・講道館の開祖)の親に当たるので、灘の酒屋をしていたのだ。いま一人は伊勢の竹川竹斎という医者で、その地方では屈指の金持ちで、蔵書も数百巻あった。それからいま一人は日本橋の浜口、国会議員をしている浜口の本家であった。すべてこれらの人はそれぞれ一種の人物で、さすがに渋田の眼識は高いものだと、おれはあとで悟った。」
ここに出てくる浜口が、どうやら浜口梧陵のような気がします。
広川町の広八幡神社境内には、勝海舟の題字並びに撰文の浜口梧陵碑があるそうです。残念ながら、そこには若き日のエピソードは刻まれてはおりませんでした。思わぬところで勝海舟の後姿をみたような気分になり。「氷川清話」の印象的な箇所とともに並べて書いておきます。
紙の本いろんな色のインクで
2005/10/28 02:38
書評集というのは時にはゴミの山に見えたり、宝の山に見えたりします。
10人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
本とのつきあい方には、まだまだ未開発の発想がありますね。
たとえば、珍しい新刊の余白ページをちぎって、隣りの人の質問に答えるメモがわりにしたりする。そんな本とのつきあい方もあるわけです。丸谷さんはどうか?
部厚い本のハードカバーがはずされ、五冊分ぐらいにバラバラに破いて置いてある。
「ーーなんでこんなに破いたんですか」という質問に
丸谷才一さんは答えております。
「これは寝ころんで読むために。・・ベッドで寝ころんで読むときも、机に向かうときでも、破いてやると、とても楽なんですよ、特にA5判の本は。僕は破いて読むし、色鉛筆その他で書きこむし、・・・本はみな、実用品なんです。」
こうして
破り読みから、エキスを抽出したような書評本が、今回紹介する本です。
魅力ある書評がつまっているのです。ですが、いけません。
普通の読者が見ると、本の残骸の山に見える時がある。
さまざまに破り落書きされた紙の束にしか見えない時がある。
読者は残酷ですから、そうなったら宝の山も、ゴミの山に見えてる。
だいたい書評の山をまとめて一冊にしてあるわけです。
見る人によっては、ゴミの山にしか見えないわけです。
たとえばです。新明解国語辞典で「読書」の項目を引くと、
「・・寝ころがって漫画本を見たり電車の中で週刊誌を読んだりすることは、勝義の読書には含まれない」とあります。
寝ころんで、しかも本を破いて読む人の書評なんか読めますか?
それにです。丸谷才一なんて名は、小学校・中学校・高校の国語教科書のどこを探してもその人の文章など載っていないじゃありませんか。そんな人の書評を読んでもしかたないじゃないか。
つまりですね。国語教科書でしか本に接しない若い人にとっては丸谷才一なんて存在しないのです。その存在しない人が書いた書評の山なんで、ちり紙交換にだしてもいいようなゴミの山にしか見られない。この本のお終いの方にある五人で選んだという近代日本の百冊リスト。これなんて教科書に載っている近代日本文学史のリストにないものばかりで、おまけに現在入手困難な本を並べている。こんなのは大学の試験にも出てこない本ばかり並べて悦にいっているだけじゃないか。とまあこんな風に見ることも可能なのであります。
コツコツと書きためた書評が、新聞紙の回収に並べられる時というのは、まあ、こんな感じでしょうか。
その回収にまわされる前に、
ちょいとこれだけでも聞いてください。
というように本の最初に談話が載せてあります。
一箇所だけ引用しましょう。
「書評というのは、ひとりの本好きが、本好きの友だちに出す手紙みたいなものです。・・友だちなんだから手紙以前に友好関係が確立しているわけです。好みもわかるし、気質もわかる。何よりも、相手を信用している。ところが書評というものはたんに文章だけで友好関係、つまり信頼感を確立しなきゃならない。それは大変なことなんですよ。その親しくて信頼できる関係、それをただ文章だけでつくる能力があるのが書評の専門家です。その書評家の文章を初めて読むのであっても、おや、この人はいい文章を書く、考え方がしっかりしている、しゃれたことをいう、こういう人のすすめる本なら一つ読んでみようか、という気にさせる、それがほんものの書評家なんですね。・・・」
ところで、
ほんものの書評家といえば、
2005年10月23日毎日新聞に鹿島茂の書評が載りました。
それが書評のお手本のような文なのでした。読み逃したのですか。
残念だなあ、これが単行本になるには、すくなくとも半年は待たなけりゃならないだろうなあ。ひょっとして本にはならないかもしれない。その書評の題は「至芸の語り口、全読書人に贈る書評集」とありました。
紙の本日本財団9年半の日々
2005/07/11 22:39
「あしながおじさん」の後編を楽しんだような読後感。
10人中、10人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
「小さい時に、生きるのが辛いほど家庭的に不幸な日がありました」と語る曽野綾子さんが、大人になって、ひょんな機会から日本財団の会長になります。その当時は財団の悪評がすごかった。
ところが「その時、さんざん悪口書いた記者何人かに、後年会いました。根拠があったら改めて教えてもらおうと思って。でもそれだけの裏づけはなかった。皆、空気で書いていたのね」(p18)
そういう悪評のためもあって
「会長になる時に私が出した唯一の条件は、『無給である』ということでした」。それを日本財団に申し入れたら、笑われます。
「財団では、株式会社の定款(ていかん)に当たる『寄付行為』の24条に、会長はもともと無給であることが明記されているんだそうです。つまり、前会長の笹川良一さんも無給だった。」「言うまでもなく、ボーナスもありません。自由になる交際費の枠など一円もない。財団からもらう現金は、出張した時の五千六百円の日当だけ。日本財団の食堂で食べるランチの定食は一番高いのが三百五十円です。」(p21)
こうして語られてゆく会長職の9年半を読んで、私に思い浮かんできたのが、ジーン・ウェブスター作「あしながおじさん」でした。まるで主人公のジュディ・アボットが大人になって、ひょんなことからご自身が「あしながおじさん」役になることに決まった物語を読んでいるような錯覚を抱いたのです。そのように読ませる筆力で、最後まで楽しめること(「あしながおじさん」を楽しんだ人なら)請け合いです。
もうひとつ。
私に思い浮かんだ新聞記事がありましたので、それを書いてみます。
新潟県中越地震のボランティアで、後発のあるリーダーが仮説トイレの汚れがひどく。町内の二百十ヵ所あったトイレを掃除する人がいなかった。というところに目をつけます。隣県からのボランティアの日帰りバスを運行して支援活動をするのに、そのリーダーは「トイレを掃除してくれる人はいませんか」と呼びかけます。手を挙げる人は数人・・・(産経新聞2005年4月10日・社会面)。
この記事が思い出されたのは、曽野綾子さんが「会長就任の辞」の要約を、本文中に引用されていたからでした。その挨拶は1995年12月12日。まず第一にあげておられた言葉はというと、
「奉仕とは、ギリシャ語で『デイアコニア』といいまして・・・『コニア』というのは塵とか芥とかいう意味です。つまり、汚いことを通して奉仕することだけが本物です。歌を歌ってあげたり、お花を飾ってあげるのは奉仕ではなく、うんこ、おしっこの世話をしてあげるのが奉仕である、とうのです。」このように曽野さんは職員の皆さんへとお願いをしておりました。
私は本の内容を語りすぎたでしょうか?
いいえ、「あしながおじさん」のなかで、いろいろな問題が起きるように、会長就任してからが、さまざまな問題がおこってくるのです。それは読んでのお楽しみ。楽しみながら日本財団の姿を、あなたは知ることになります。はたして悪評を書いた記者は、この本を読むでしょうか?忙しくて読む暇もないかなあ。
2008/03/13 09:28
いつもおまえがぼんやりと立ってたな。
9人中、9人の方がこのレビューが役に立ったと投票しています。
ゲゲゲの鬼太郎・悪魔くんを書いた水木しげる氏の夫人が、本を書きました。昨日。その本を読み、そして気分よく熟睡しました。
妖怪をはじめとするパンドラの箱をひっくりかえしたような水木作品を、正面から取り押えようとする作品論があるとすれば、この本は、袖から、そして水木しげるの背中ごしに語る人物論になっております。もちろん後ろからですから、水木氏の手もとなど見えないのですが、それがかえって筋の通った、力(りき)みの無いすがすがしさを読者に提供してくれております。
本の最後の方にこうありました。
「以前、富士山の小屋に行ったときに、水木に聞いたことがありました。
水木は小首をかしげた後に、空を見上げ、ポツリといいました。
『よかったんじゃないか、おまえで、いつもぼんやりしていて』
『ぼんやり? 私、ぼんやりしてる?』
『とんでもなく、ぼんやりだ』
『そうかなあ』
『ああ。横を見ると、いつもおまえがぼんやりと立ってたな』
そういって、にやりと笑うと、右手で私の背中をバシッと叩きました。」(p238)
装丁が素晴らしくてね。
もし、本屋にあったなら、手に取ってみてください。
と、つい薦めたくなる一冊。