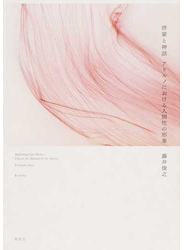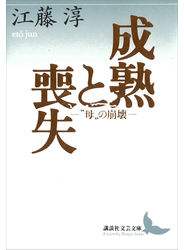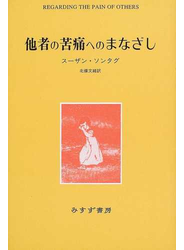ブックキュレーター哲学読書室
ブックキュレーター哲学読書室
ナルシシズムの時代に自らを省みることの困難について
SNSなどのインターネットメディアを介して、誰もが手軽に自らを虚構の中に演出することのできる時代。増殖する匿名のナルシシズムに埋もれて、思考の原理としての「省察」は窒息し始めています。こうした現代の自画像をそれと見抜くための4冊+1(拙著)を紹介します。【選者:藤井俊之(ふじい・としゆき:1979-:京都大学人文科学研究所助教)】
- 79
- お気に入り
- 5674
- 閲覧数
-

啓蒙と神話 アドルノにおける人間性の形象
藤井 俊之(著)
「理性」とは原初状態を反復する「自己保存の原理」である。『啓蒙の弁証法』のこの定義に基づいてアドルノは、自己の反復に充足するナルシシズムを理性の狂気と考えました。本書は、彼の理性批判を、その芸術論に現れる感性的諸形象へと接続することで、神話(元型)の反復を逃れる「逸脱」への道筋を照らしだしています。
-

詩的自叙伝 行為としての詩学
寺山 修司(著)
「故郷喪失の文学」(小林秀雄)の系譜に連なる寺山の思想の核心。そこには常に自己イメージの破壊の問題が存在します。民衆のわらべ唄に「虚構原則の人さらい」を聴きとる彼の想像力は、いま在る現実を過去に遡って書き換えようとするアクチュアルな文学実践を求めていました。本書は、それを理解するに格好の詩論集です。
-

ウィトゲンシュタインの講義 ケンブリッジ1932−1935年 アリス・アンブローズとマーガレット・マクドナルドのノートより
ウィトゲンシュタイン(述) , アリス・アンブローズ(編) , 野矢 茂樹(訳)
自己の同一性を根底から疑ってかかるヴィトゲンシュタインの講義録。アドルノの著作では批判的にしか言及されない人物ですが、あらゆる記号からその実体性を剥ぎ取り、さらに「私」の自己イメージまで解体してゆくその議論は一聴に値します。『この身体を指すことと私を指すこととは、やはり別のことなのである』(167頁)。
-
理想(不在)の「母」を求める男たちと、己の自然(母性)を殺害することで近代に乗り遅れまいとする女たち。それぞれに自己イメージを母によって規定されたまま、「父(倫理)」なき自然状態を生きる日本人の実相を「第三の新人」の諸作品に読み取る1967年初版の傑作評論。日本型ナルシシズム入門と呼べる一冊です。
-

他者の苦痛へのまなざし
スーザン・ソンタグ(著) , 北条 文緒(訳)
戦場で撮影された一枚の屍体写真。それを前にして「われわれ」は怒りを、悲しみを、あるいは喜びを覚えもする。しかし、その「われわれ」とは何か。ソンタグの写真論がフォーカスするのは、写真を前にナルシスティックな同胞意識を強めるこの「われわれ」です。冒頭から読むのではなく結論部の強烈な断言から、是非。
![]()
ブックキュレーター
哲学読書室知の更新へと向かう終わりなき対話のための、人文書編集者と若手研究者の連携による開放アカウント。コーディネーターは小林浩(月曜社取締役)が務めます。アイコンはエティエンヌ・ルイ・ブレ(1728-1799)による有名な「ニュートン記念堂」より。
ブックツリーとは?
ブックツリーは、本に精通したブックキュレーターが独自のテーマで集めた数千の本を、あなたの"関心・興味"や"気分"に沿って紹介するサービスです。
会員登録を行い、丸善・ジュンク堂・文教堂を含む提携書店やhontoでの購入、ほしい本・Myブックツリーに追加等を行うことで、思いがけない本が次々と提案されます。
Facebook、Twitterから人気・話題のブックツリーをチェックしませんか?
テーマ募集中!
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを募集中です。あなたのリクエスト通りのブックツリーが現れるかも?
テーマ応募フォーム
こんなテーマでブックツリーを作ってほしいというあなたのリクエストを入力してください。
ご応募ありがとうございました。
このテーマにおける、あなたの”6冊目の本”は?
※投稿された内容は、このページの「みんなのコメント」に掲載されます。
コメントを入力するにはログインが必要です